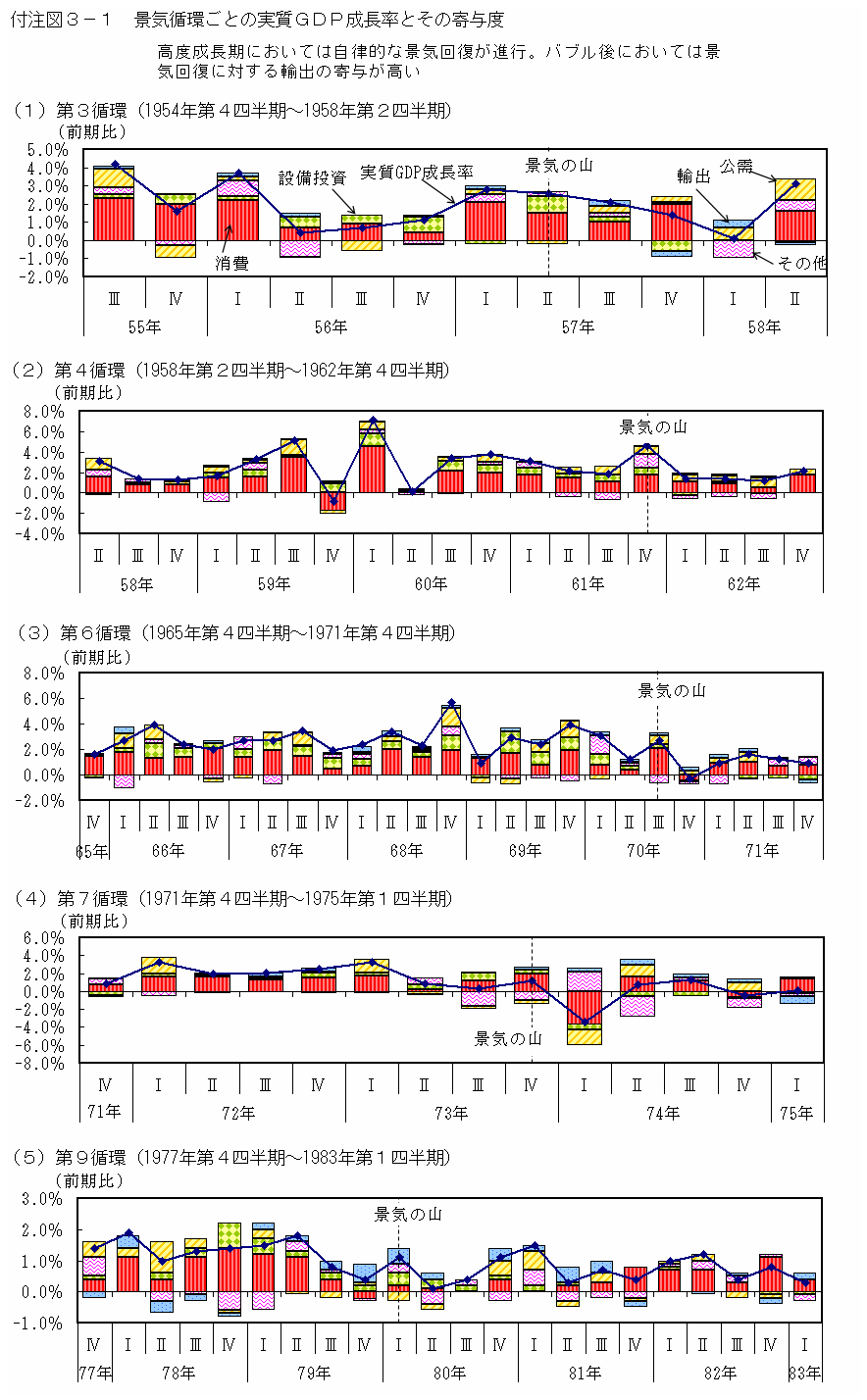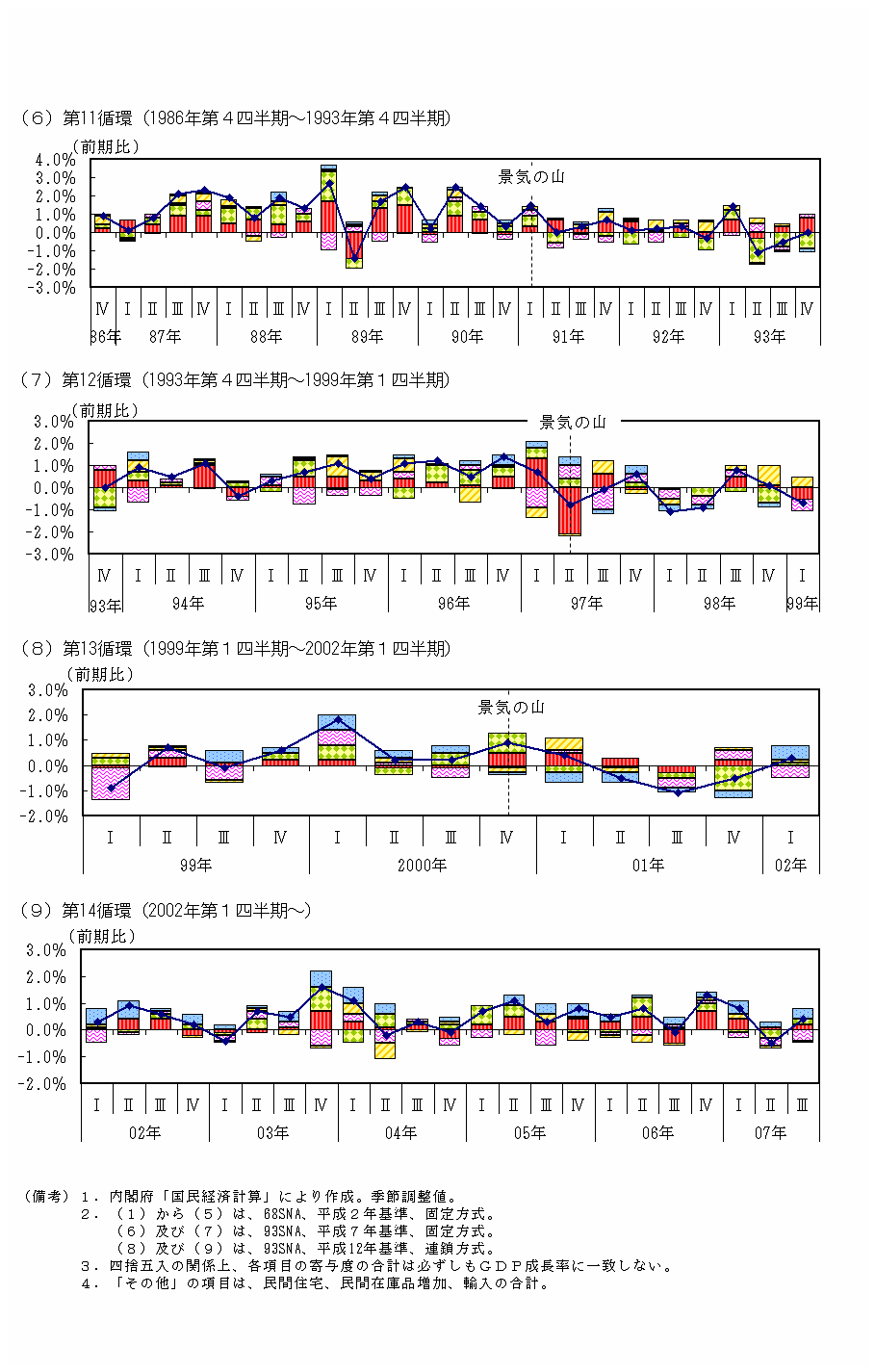付注3-1 過去の主な景気循環のパターン
(i)第3循環(1954年11月~1958年6月)
(景気拡張期:1954年11~1957年6月、景気後退期:1957年6月~1958年6月)
第3循環における景気回復は「神武景気」と呼ばれ、白黒テレビ、洗濯機、冷蔵庫といった新製品や新技術が次々と登場し、それを具体化するための設備投資が増加した。こうした企業部門の活発化はやがて家計部門へと波及し、所得と消費が著しく増加した。しかし、好況が長引くにつれて輸入が増加し、国際収支が大幅赤字を続けたことから、「国際収支の天井」が制約となって1957年半ばから政府は金融引締め政策に乗り出し、それが起因となって生産や輸入が急減し、景気は後退局面へと入っていった(付注図3-1(1))。
(ii)第4循環(1958年6月~1962年10月)
(景気拡張期:1958年6月~1961年12月、景気後退期:1961年12月~1962年10月)
「神武景気」後の調整期間を経て金融引締めが解除されると、再び景気は回復し始め、1961年後半にかけて息の長い大型景気となった。この期間の景気回復は「岩戸景気」と呼ばれている。「岩戸景気」では、「神武景気」と同様に新技術に支えられた設備投資が盛り上がるとともに、消費の伸びも高まる中で景気回復が進んだ。さらに、池田内閣が策定した所得倍増計画がさらに投資マインドを高め、景気は急速に盛り上がっていった。こうした好況は輸入の急増を通じて国際収支を悪化させ、再び「国際収支の天井」が制約となって金融引締め政策への転換が図られ、景気は後退局面入りすることとなった(付注図3-1(2))。
(iii)第6循環(1965年10月~1971年12月)
(景気拡張期:1965年10月~1970年7月、景気後退期:1970年7月~1971年12月)
大型の企業倒産が相次いだいわゆる「40年不況」における調整が終了した後、日本経済は景気拡張期間57ヵ月という大型景気を経験することとなる。この期間の景気回復は、「神武景気」、「岩戸景気」を上回るという意味で「いざなぎ景気」と呼ばれている。「いざなぎ景気」においては、需要刺激策と輸出の増加によって景気が回復に向かい、それに誘引される形で設備投資が増加していった。「いざなぎ景気」の特徴としては、製造業の国際競争力が高まる中で、海外経済の景気回復を受けて輸出は高い伸びを続けたことである。この結果、それまでの景気拡張期のように景気回復が進むと輸入が急増し、国際収支は悪化するという現象は起きず、むしろ好況期にも国際収支の黒字が累積する状況が出現した。しかしながら、次第に需給逼迫による物価上昇圧力が高まったため、インフレ抑制の観点から財政金融政策は引締めへと転換し、こうして長く続いた景気回復も後退に転じることとなった(付注図3-1(3))。
(iv)第7循環(1971年12月~1975年3月)
(景気拡張期:1971年12月~1973年11月、景気後退期:1973年11月~1975年3月)
1971年12月に為替レートがそれまでの360円から308円に切り上げられたが、円切上げ当初こそは輸出落込みにより一時的に成長率が鈍ったものの、金利引下げや積極財政といった需要刺激策により次第に景気は回復へと向かっていった。その後、「日本列島改造論」に刺激されて地価が高騰し、これに加えて、第一次石油危機の発生により原油価格が上昇したことから、いわゆる「狂乱物価」といわれる物価高騰が発生した。これに対処するため需要抑制策が取られ、これを契機に景気は後退局面へと進んでいった(付注図3-1図(4))。
(v)第9循環(1977年10月~1983年2月)
(景気拡張期:1977年10月~1980年2月、景気後退期:1980年2月~1983年2月)
第一次石油危機後、企業の減量経営が進行したことから再び設備投資が増加し、さらに、日本を世界経済の牽引役として期待する「機関車論」に基づいて公共投資が拡大したことを受けて、ようやく景気は本格的な回復に向かって動き始めた。しかしながら、そうした動きが進んでいたところへ、イラン革命に端を発して第二次石油危機が発生した。第二次石油危機時には危機直後からすばやい対応策を取ったことが功を奏して第一次石油危機時ほどには物価が上昇することはなかったが、インフレ対策のために金融引締め策が取られ、その後は長期に渡る緩慢な景気後退が進行した(付注図3-1図(5))。
(vi)第11循環(1986年11月~1993年10月)
(景気拡張期:1986年11月~1991年2月、景気後退期:1991年2月~1993年10月)
「プラザ合意」後に円高が急速に進んだ結果、輸出産業が大きな打撃を受け、日本経済は「円高不況」と呼ばれる景気後退に見舞われた。この不況に対処するために政府は積極的な財政政策を行った。また、日本銀行は段階的に金利を引下げ、金利水準は極めて低い水準となった。これを受けて、低金利下で設備投資と住宅投資が大きく盛り上がるとともに、大型耐久消費財や高額商品の需要が伸長するなど個人消費は大きく伸び、「いざなぎ景気」に次いで長い回復期間を記録することとなった。こうした中で、地価と株価が異常な高騰を示すいわゆる「バブル」が発生し、資産インフレを抑制するために、金融引締めに転じたことで資産価格は大きく下落し、その後の長期低迷へと繋がっていく(付注図3-1図(6))。
(vii)第12循環(1993年10月~1999年1月)
(景気拡張期:1993年10月~1997年5月、景気後退期:1997年5月~1999年1月)
バブル崩壊後の長い調整局面を経た後、積極的な財政政策と金利引下げに支えられて回復テンポは極めて緩慢であったものの景気は徐々に上向いていった。こうした動きは次第に自律的回復過程へと移行しつつあったが、アジア通貨危機による輸出減少や金融機関の破たんによる金融システム不安への高まりなどの影響から景況感は厳しさを増し、景気回復の循環が断ち切られ景気は後退へと向かった(付注図3-1(7))。
(viii)第13循環(1999年1月~2002年1月)
(景気拡張期:1999年1月~2000年11月、景気後退期:2000年11月~2002年1月)
第13循環における景気拡張局面では、消費が伸び悩み設備投資の回復が脆弱な中で、世界的なIT関連需要の増大によって輸出の増加し、これが景気回復に対して大きな役割を果たした。一方で、不良債権問題や企業の過剰債務問題の長期化が経済の活性化を阻害し、第12循環の景気拡張期と同様にその回復テンポは緩やかなものとなった。その後、2000年末になると世界的なITバブル崩壊により輸出が急減し、景気は後退局面入りすることとなった(付注図3-1図(8))。