第2章 インドの発展の特徴と課題(第1節)
第1節 貿易構造と人口動態からみたインドの経済成長の特徴
本節においては貿易構造と人口動態からみたインドの経済成長の特徴を確認する。貿易面からみると、中国やASEANが「世界の工場」としての道をたどってきたのに対し、グローバル・バリュー・チェーン(GVC)へのインドの参画は途上であり、中国から機械製品等を輸入する関係が近年更に強まっていることが確認できる。また、人口動態からみると、先行の新興国が終えている「人口ボーナス」をインドは引き続き享受しており、生産年齢人口比率は2030年頃にピークを迎えるものの、その後の同比率の低下は緩やかなものにとどまると見込まれていることの含意について検討する。
1.インド経済の位置付け
(人口規模に比して、経済規模は発展途上)
まず最初に、インドと中国について、人口や経済の基礎的な統計を比較することで外形的な特徴を確認しよう。国連の人口推計166によると、インドの人口は2021年時点で14.08億人(世界人口の17.8%)に達し、中国の14.26億人(同18.0%)とおおむね同規模となっている(第2-1-1図)。なお、ASEAN167の人口は6.74億人(同8.5%)であり、中国やインドの半分程度にとどまる。また、インドの人口は2023年までに中国を上回り世界最多となる見込みである(第2-1-2表)168。
このように中国、インドの人口はそれぞれ世界の2割弱を占めるものの、GDPについては、2022年時点で中国の世界シェアは18.1%であるのに対し、インドは3.4%にとどまり、GDPシェアでみるプレゼンスはまだ高くない(第2-1-3図)。なお、ASEANは3.6%であり、インドはおおむねASEANと同規模となっている。
IMFは、インドのGDPは2022年に英国を上回り世界5位となり(市場レートベース)、今後も着実に経済規模が拡大する見込みとしている(第2-1-4図)169。しかしながら、インドは一人当たりGDPでみると経済発展は途上である。OECDの長期推計170によれば、インドの一人当たり実質GDP(2015年価格)は2060年時点でもOECD平均との差は埋まらず、世界平均及びG20途上国平均を下回る状況が続く見込みとなっている(第2-1-5図)。
2003年のいわゆる「BRICSレポート171」以来、インドの発展可能性は指摘されて久しいものの、これまでの実績はかつて期待されていたような高成長パスからはやや下回って推移している172。政府目標としている製造業のGDP構成比の引上げも順調には進んでおらず173、インドへの外資企業の進出や直接投資の引上げも道半ばであること(2章2節参照)等を踏まえると、可能性と同時に解決が容易ではない課題の存在が示唆されている。2022年8月のインド独立75周年記念式典において、モディ首相は「25年後(2047年)までに先進国入りを目指す」との決意を表明したところ、同目標の達成には成長の加速が必要となる。
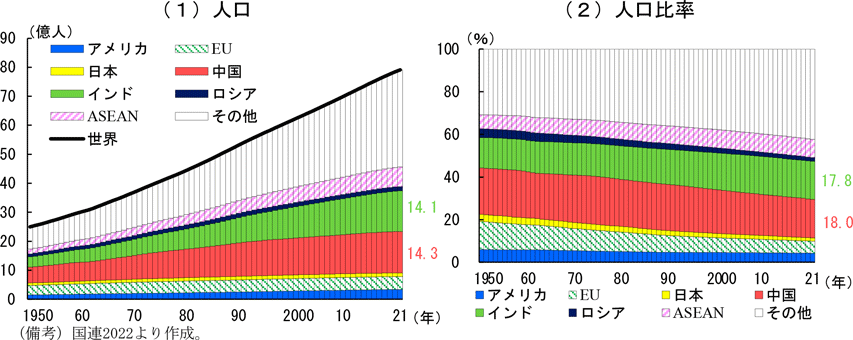
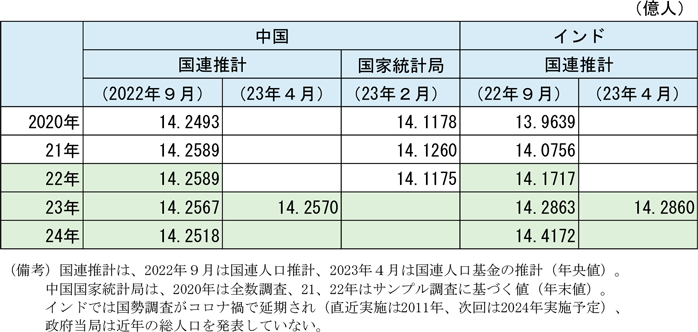
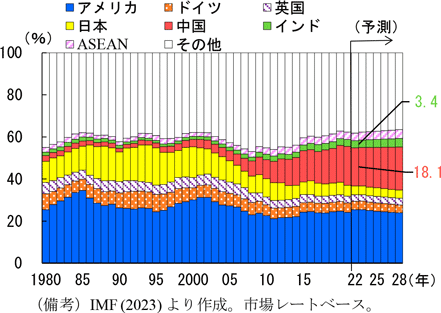
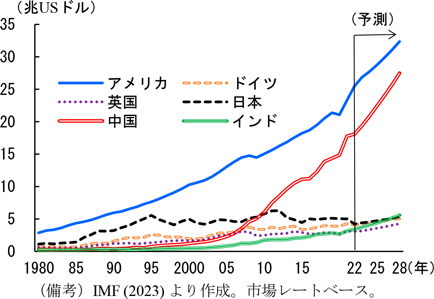
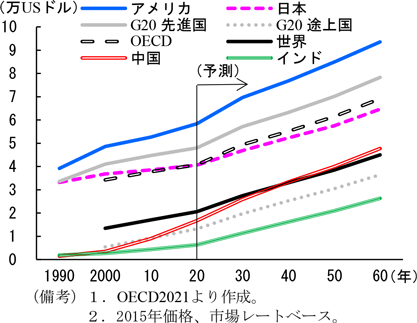
(人口規模に比して、世界財貿易に占めるインドのシェアは小さい)
インドのこれまでの発展の遅れの一つの背景には、輸出の伸び悩みがあるとみられる。世界の財輸出全体に対する各国の構成比をみると、2022年時点で、中国の14.6%、ASEANの7.9%に対し、インドは1.8%にとどまっている(第2-1-6図)。
一方、輸入の世界シェアは、2022年時点でインドは2.6%と、中国の9.3%、ASEANの7.9%には劣るものの、輸出に比べるとその差は縮小する(第2-1-7図)。
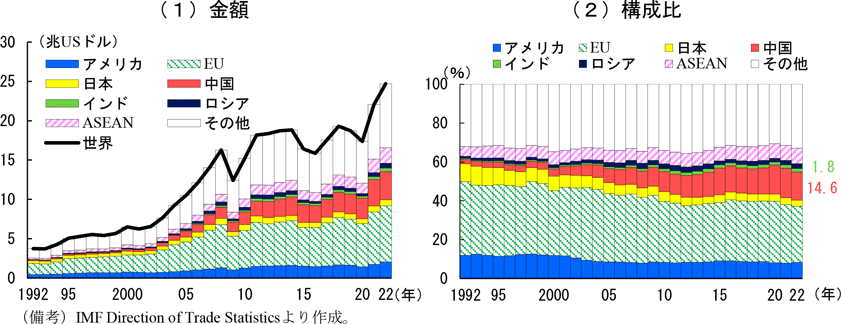
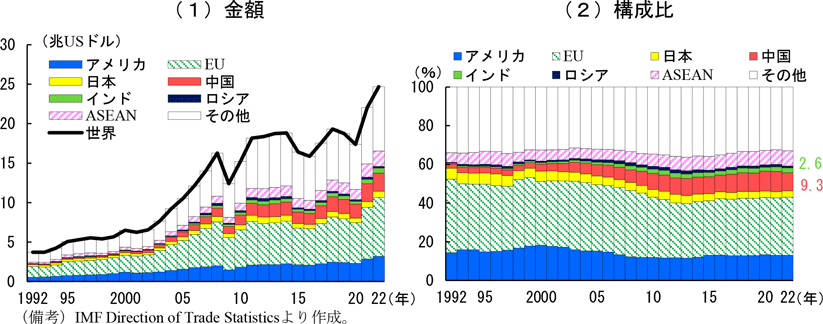
(輸出先をみると、中国に比べて先進国やアジア向けのシェアが低い)
各国・地域の財輸出の規模と輸出相手国の金額及び構成比をみると、中国とASEANは金額及び構成比ともに相互に増やし、輸出規模全体を拡大させてきた。他方、インドは貿易自由化が1991年7月に始まり174、この30年間で対中・対ASEAN輸出は金額面は増やすことができたものの、構成比においては2000年代半ば以降はおおむね横ばいにとどまっている。また、2000年代の中国、インドの輸出先構成比をみると、中国は米、欧向けの輸出比率が高まったが、インドは同比率が低下した。インドは中国に比べ、先進国向けの財輸出が少なく、結果としてその他の国々への輸出比率が高まったとみられる175。なお、近年は、中国の欧米向け輸出比率は対米貿易摩擦の影響もある中で横ばいとなる一方、インドの欧米向け輸出比率は上昇に転じており、傾向に変化がみられている(第2-1-8図、第2-1-9図、第2-1-10図)。
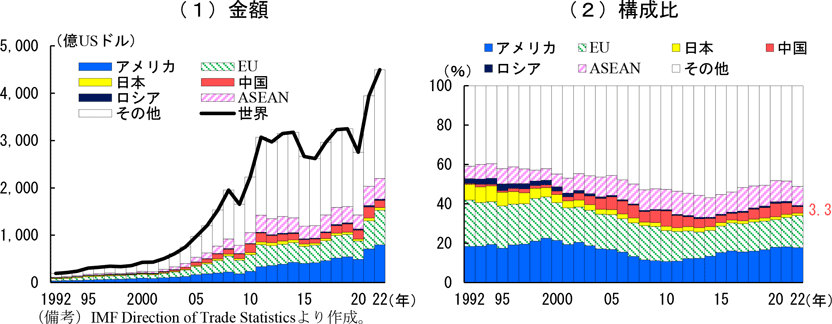
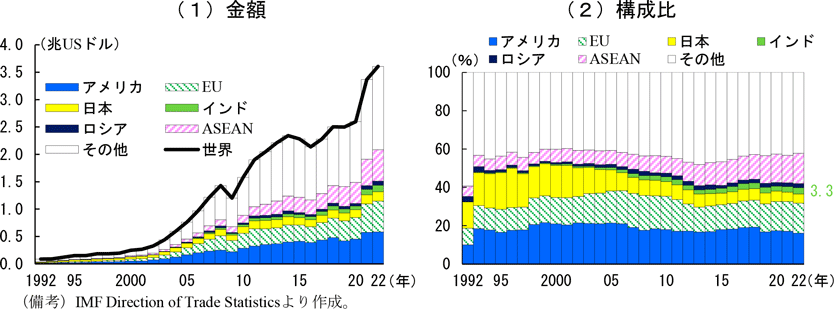
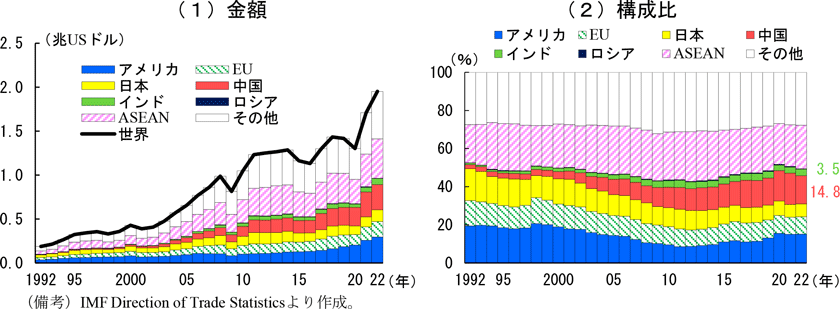
Box.経済成長には内需の増加に加えて輸出を伸ばすことが重要
インド、中国及びタイの経済成長における内需・外需の寄与をみると、おおむね内需の拡大により経済成長を促進する中で、輸出を伸ばし経済成長を達成していることが分かる(図1)。高い成長を実現するためには、自国の成長力に加え、貿易を通じて他国の成長力を適切に取り込むことが重要であると考えられる。
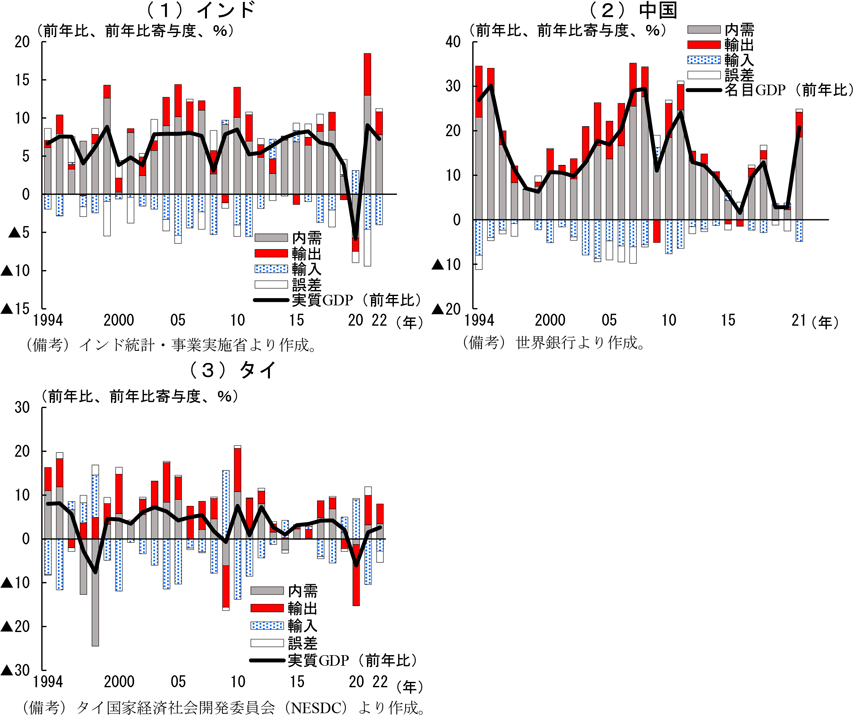
(輸入先をみると、ASEANやアメリカ同様に中国のウェイトが高まっている)
次にアメリカ、中国、ASEAN及びインドの財輸入における各国のシェアを確認する。アメリカの2022年の輸入におけるシェアはインドが2.5%、中国が18.2%、ASEANが9.2%となっている(第2-1-11図)。2018年の比率(インド2.1%、中国19.5%、ASEAN6.6%)と比べると、米中摩擦を受けて中国のシェアが低下する中で、受け皿としてのASEANのシェア上昇がみられるが、インドのシェアはほぼ横ばい程度にとどまり、貿易拡大の機会には必ずしもつながっていない。
また、中国の2022年の輸入に占めるインドのシェアは0.7%にとどまり、ASEAN(12.6%)との差が顕著である(第2-1-12図)。ASEANの2022年の輸入に占めるシェアでは、インドの2.2%に対し、中国は29.3%に及んでいる(第2-1-13図)。
一方でインドは、中国からの輸入が18.4%を占めている(第2-1-14図)。このように中国、インド両国間の貿易は、輸入においてはインドの中国に対する一方向的な関係となっていることが分かる。
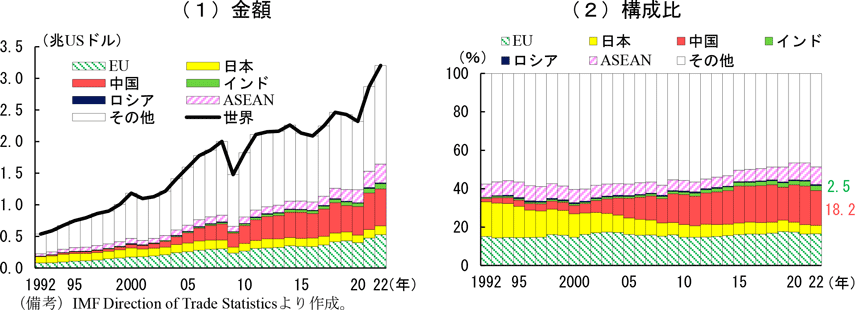
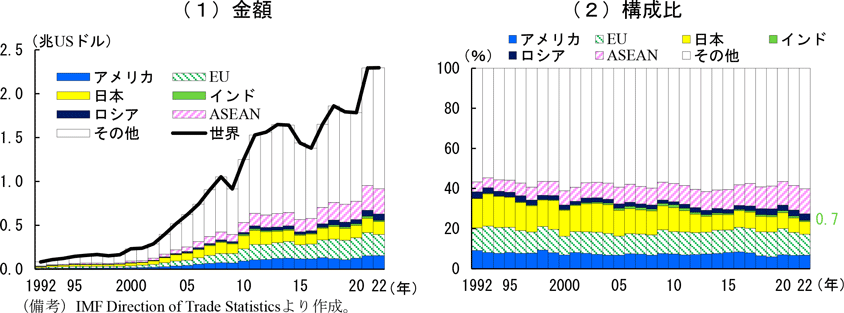
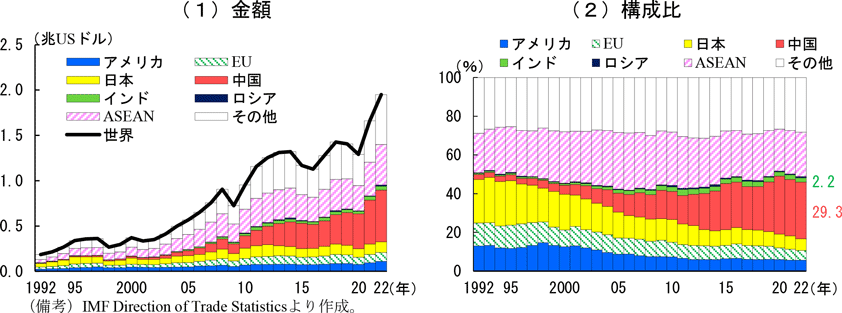
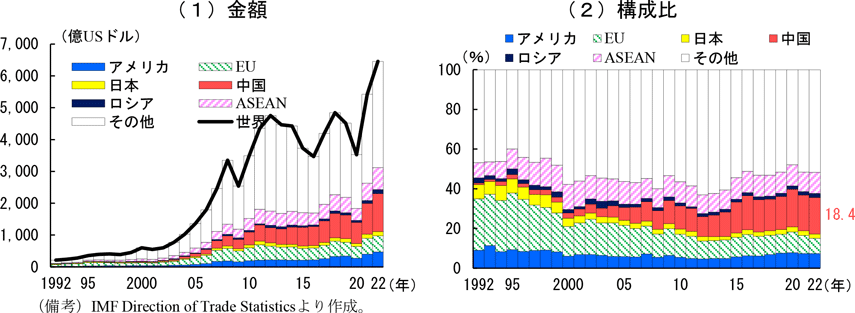
2.グローバル・バリュー・チェーン(GVC)からみた輸出の特徴
(輸出規模の違いの背景には製造業シェアの伸び悩み)
このように、世界各国に対する輸出規模は、中国、インド両国で好対照となっているが、どのような背景があるだろうか。両国の産業別構成比(3部門)をみると、GDPに占める第二次産業比率176が、インドは28.5%、中国は39.9%と構成比が10%以上差が開いており、インドは中国に比べ工業化に遅れがみられる(第2-1-15図)。さらに、部門別構成比(10部門)をみると、製造業のシェアはインドは15.8%と、中国の27.7%に比べ低い。インドは、製造業のシェアを2025年までに25%に引き上げることを目指しているものの177、これまでのところ順調には進んでいない。
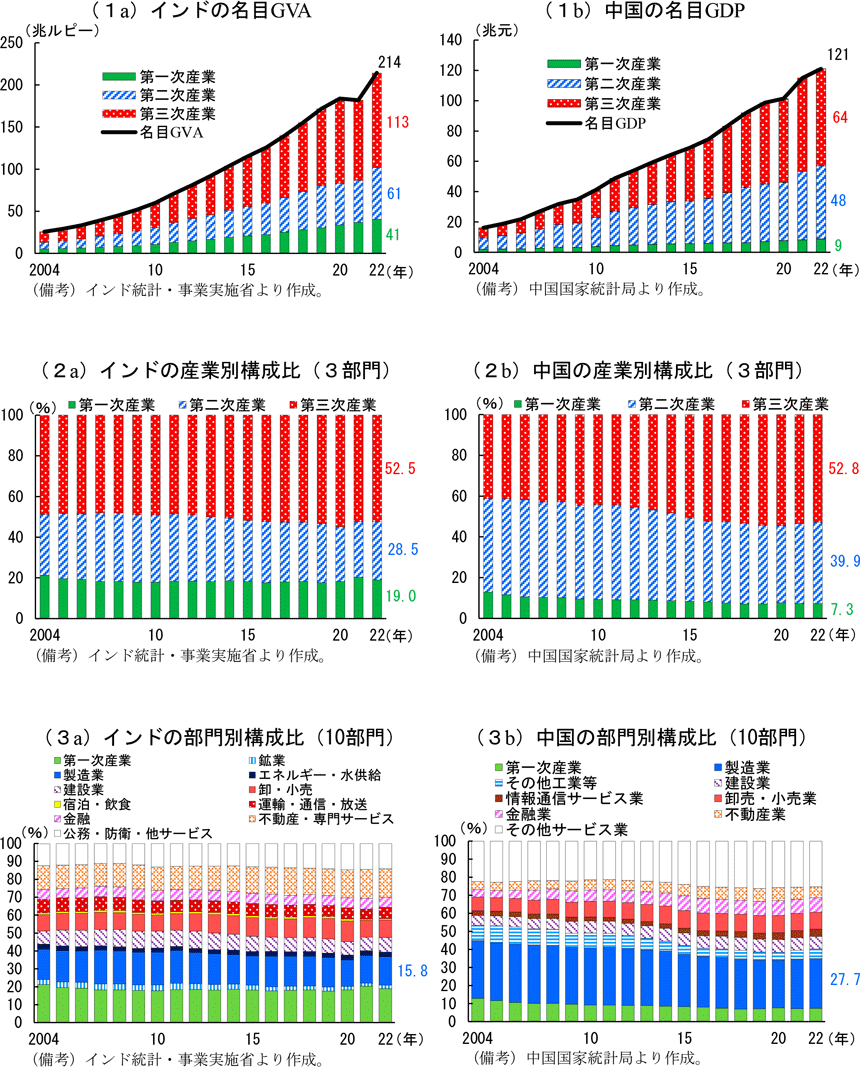
インドの製造業部門の伸び悩みの傾向は、就業者の構成比でもみられる。まず、インドの就業者比率は、2010年時点でも農業が54.7%と依然高い178。製造業の就業者比率は11.6%と、中国(19.2%)やタイ(14.1%)に比べ低い。また、インドの1960年の水準と比較しても2ポイントの上昇にとどまっており、工業化のペースが緩慢であることが表れている。なお、インドで製造業よりも発展が進んでいるとされるサービス業の就業者比率も、中国やタイに比べて低い(第2-1-16図)。こうした就業者の農業部門における滞留は、マクロ経済の生産性の改善を停滞させる可能性があり、農業改革とそれによる雇用の流動化を進めていく必要性が示唆されている(後掲第2-1-35図)。
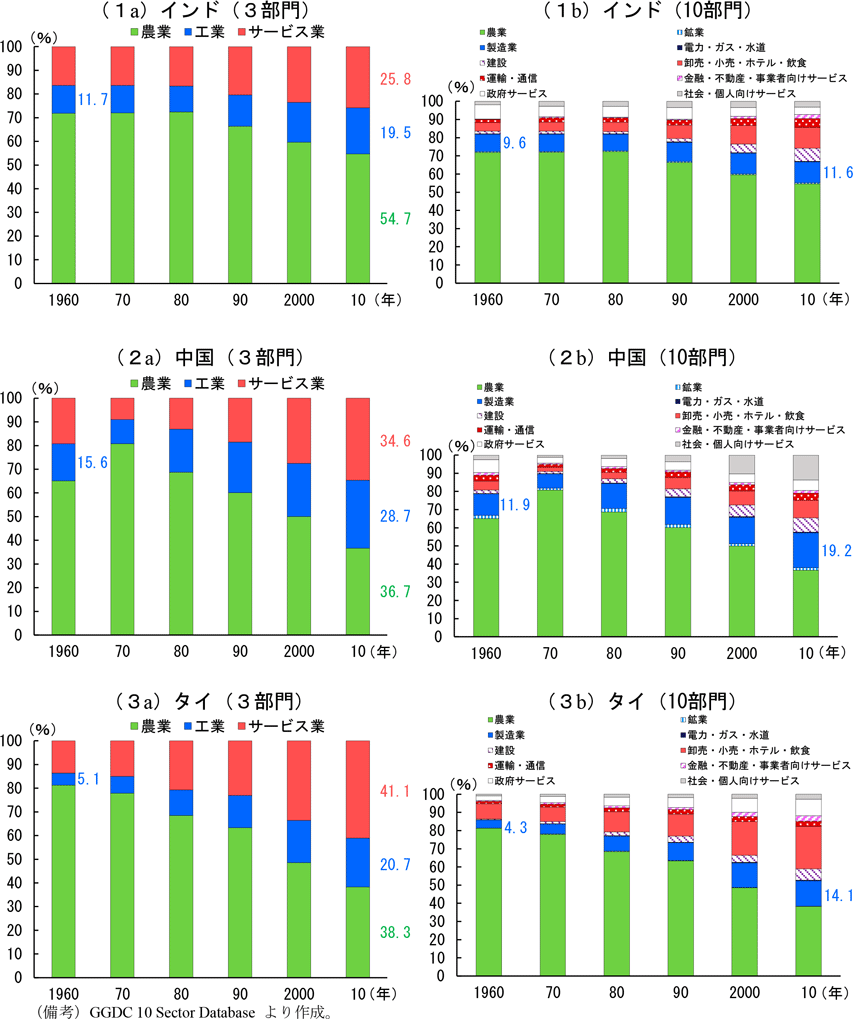
(輸出品目別にみると、機械製品へのシフトが緩慢)
以上のような製造業の停滞を背景として、世界におけるインドの輸出シェアも伸び悩んでいるが、輸出品目にはどのような特徴がみられるだろうか。
フランス国際経済予測研究センター(CEPII)の貿易データベース(BACI)を用いて、HSコード6桁ベース(約5,000品目)でインドの輸出品目を業種ごとに分類すると、2001年、2011年、2021年の3時点において、以下の傾向が確認できる(第2-1-17図)。
(i)食料、鉱物、金属製品179等、一次産品の比率が約50%に及んでいる(2001年44.1%、2021年50.5%)。
(ii)衣料品・靴等の軽工業製品のシェアは過去20年間で低下している(2001年30.1%、2021年11.8%)。
(iii)化学工業製品、輸送機器のシェアは高まっている(2001年13.4%、2021年21.1%)。一方で機械・電気機器のシェアはわずかにしか上昇していない(2001年7.7%、2021年11.2%)。
(iv)こうした傾向は、対中国で更に顕著となっている。機械・電気機器のシェアは2021年時点で8.9%と、2001年(2.2%)に比べれば上昇しているものの、低水準にとどまっている。
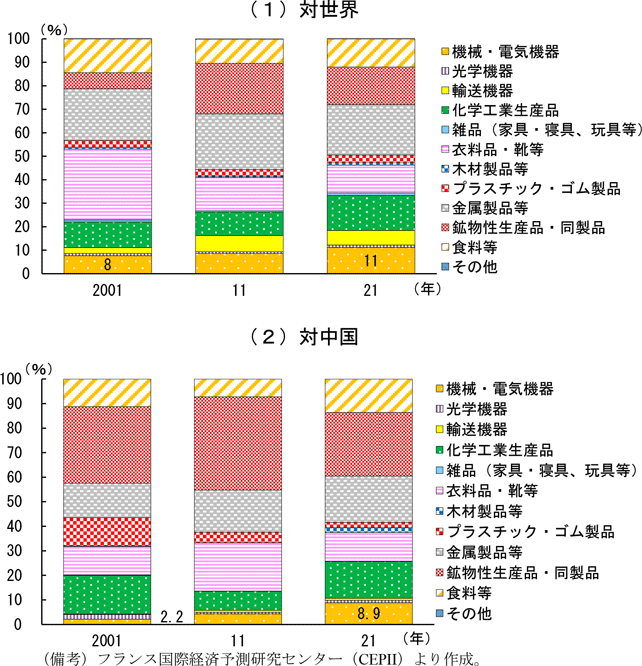
(輸出品の要素集約度別にみると、資本集約財への重点シフトが緩慢)
また、輸出品目を集約財別の5分類((1)資本集約的(高スキル)財、(2)資本集約的(中スキル)財、(3)資本集約的(低スキル)財、(4)資源集約的財、(5)労働集約的財)に分類すると、以下の特徴が確認できる(第2-1-18図)。
(i)インドの輸出品目は、近年、資本集約的財の比率が上昇している。ただし2021年時点で45.3%(うち高スキルが23.4%)と、中国(75.3%、うち高スキル42.6%)やベトナム(62.5%、うち高スキル46.8%)に比べると低水準となっている。
(ii)資源集約的財の比率は、依然として高い。
(iii)労働集約的財の比率は、過去10年で横ばいとなっている。
以上より、インドの輸出品目の資本集約財への重点シフトは中国及びベトナムに後れを取っていると考えられる180。
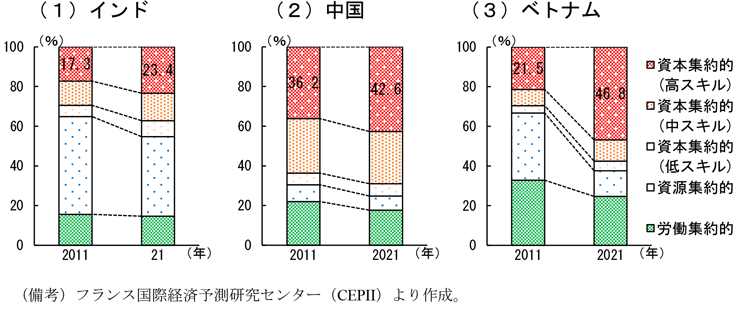
(GVC上、インドは部品・原材料、アウトソーシング等の前方参画率が高め)
こうした輸出品目の構成(強みと弱み)の中で、インドは国境をまたぐ製造過程(GVC)にどのように参画しているだろうか。アジア開発銀行(ADB)が推計したGVCへの前方参画率(部品・原材料等の上流工程)、後方参画率(組立等の下流工程)の2010年→2015年→2020年の推移をみると、以下の特徴が確認される(第2-1-19図)。
(i)製造業(低技術)、製造業(中・高技術)双方において、インドはASEAN諸国に比して後方参画率が低水準となっており、下流の組立工程においてはASEAN諸国のような強みを発揮できていない181。
(ii)他方、サービス業においてはインドは上流工程の比率が高く、IT技術を活かしたビジネス・アウトソーシング業の強みが発揮されているが、2015~2020年にかけては後方参画率が上昇している182。
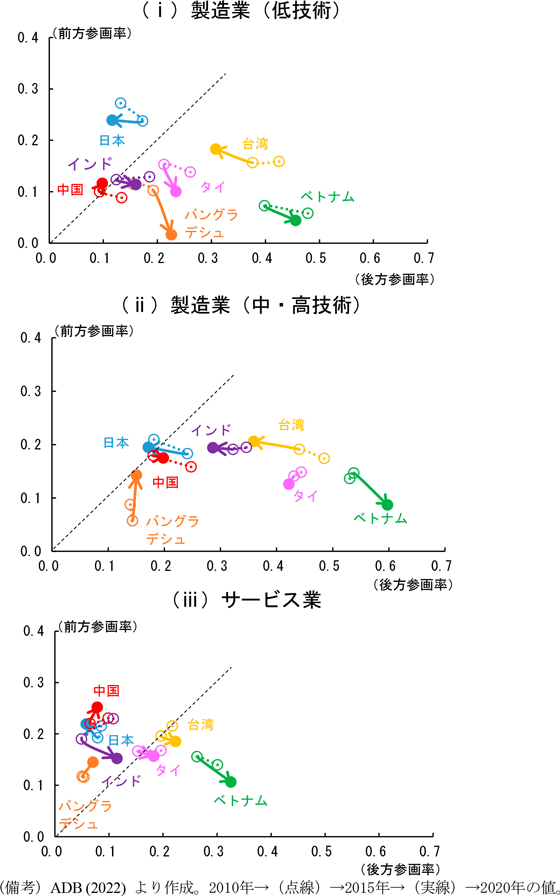
3.ウェイトが高まる中国からの輸入の特徴
(中国からの輸入ウェイトが近年更に上昇)
ここまでインドの輸出品目についてみてきたが、輸入品目についてはどのような特徴がみられるだろうか。輸出品目と同様に、HSコード6桁ベース(約5,000品目)で輸入品目を整理すると、輸入先の特定国への集中が進んでいる状況が確認できる(第2-1-20図)。ある品目の輸入額の50%以上を特定国から輸入している品目(集中的供給財)の数は、2001年時点では、1位の中国(284品目、全体の5.7%相当)、2位のアメリカ(258品目、5.2%)、3位のドイツ(149品目、3.0%)の上位3か国の中で大きな差はなかったが、2011年には中国の比率が大きく上昇し(978品目、21.0%)、中国への依存が大幅に高まった。さらに、2021年には中国の比率が更に上昇しており(1,288品目、27.9%)、中国からの輸入ウェイトが高まっていることが確認できる。
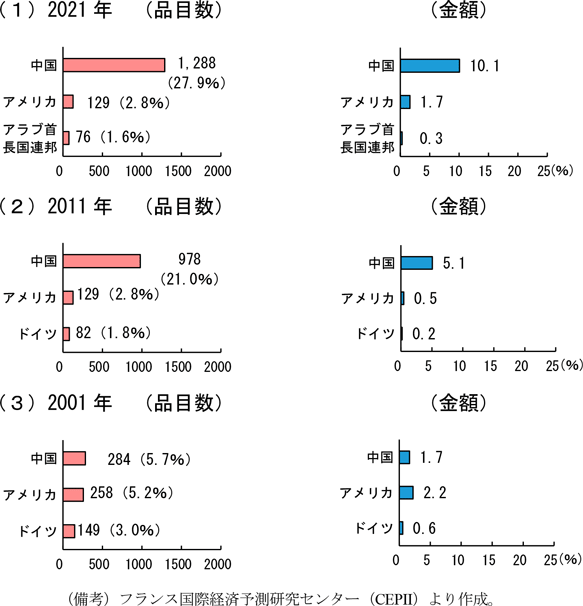
(輸入品目別にみると、機械・電気機器の輸入が増加)
インドの輸入はどのような品目で中国への集中がみられるのだろうか。まず、インドの輸入全体(対世界)の過去20年の傾向をみると、輸出品目と同様に、鉱物・金属関連の製品が5割程度を占めている(第2-1-21図)。機械・電気機器のシェアは2割程度で横ばいとなっている。次に、インドの対中輸入を確認すると、過去20年で鉱物・金属関連の製品の比率は低下する一方、機械・電気機器のシェアが大幅に高まっている(2001年22%、2011年42%、2021年49%)。2001年時点では対世界、対中国で同程度であったことを踏まえると、インドは機械・電気機器の輸入で中国への集中を急速に高めたことが分かる183。
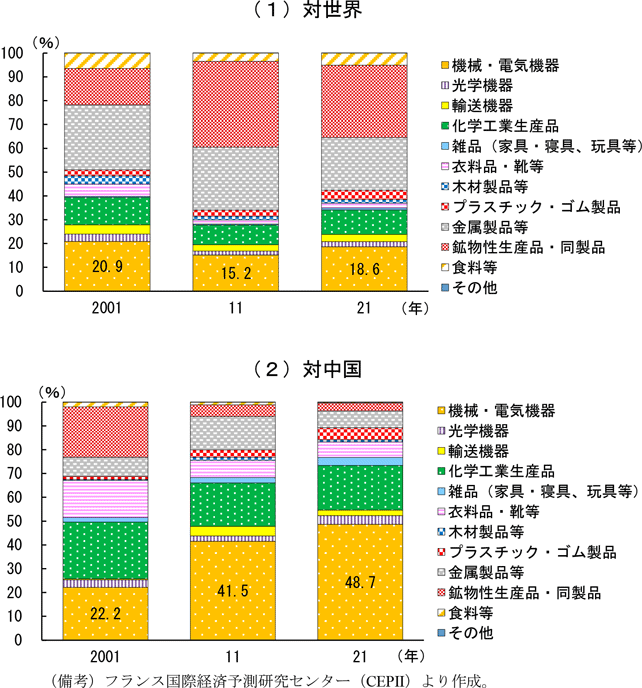
(輸入品を要素集約度別にみると、資本集約財が増加)
インドの輸入品目の集約財分類をみると、全体(対世界)では資源集約財が大宗を占める状況が続いている一方で、対中国では資源集約財のシェアは過去20年低下を続けており、代えて資本集約財(高スキル、中スキル)のシェアが大幅に高まっている(第2-1-22図)。
インドの輸出品目においては、対中国では依然として資源集約財が多く、資本集約財(高スキル、中スキル、低スキル計)のシェアは、2021年時点で37.0%(うち高スキル23.1%)と、2001年時点の39.4%(うち高スキル30.9%)と同程度にとどまっており、対世界(2021年時点で45.3%(うち高スキル23.4%))と比べても低い(第2-1-23図)。
以上から、インドは製造業を中心とする資本集約財について、輸入面では中国への集中が高まっており、輸出面では(対世界ではシェアが高まっているものの)対中国ではシェアを高められていないことが分かる。
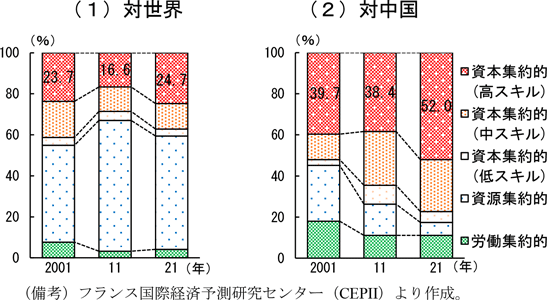
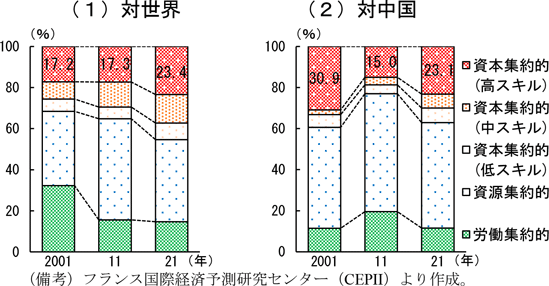
4.インドの将来人口推計からみる成長の可能性
ここまでインドの貿易構造を概観してきたが、中国にみられたような貿易を梃子にして、豊富な労働力を活かしたダイナミックな生産構造の変化と成長はみられなかった。もっとも、貿易を梃子にした成長といっても、製造業に限らずサービス業も含め、生産活動の基礎になるのは労働力であり、今後の中長期的な成長には人口動態が重要となる。インドではどのような特徴がみられるのであろうか。以下では、中国との比較をしつつ、成長と人口の関係を整理しよう。
(中国とインドの成長率水準は逆転)
まず、インドと中国の長期的な成長率を比較すると、1980年から2010年までの間、インドの成長率は中国の成長率を下回る状況が続いた(第2-1-24図)。2010年代は、中国の成長率の低下傾向もあり、中国、インド両国の成長率はおおむね同程度で推移した。2020年以降は、感染症拡大の影響等により両国の成長率は大幅に変動したが、2022年の成長率はインドは2000年代以降の平均的な成長率と同程度の7.2%184となった一方で、中国は成長率が感染症拡大前よりも低下し3.0%となった。IMFは、2023~2028年の成長率については、インドが横ばい傾向で推移する中で中国の成長率は低下し続けることから、インドが中国を上回る状況が続くと予測している。
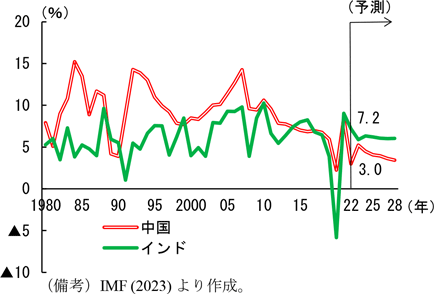
ただし、両国の経済規模には依然として大きな差があり、2022年時点の名目GDP(市場レートベース)で、インドは3.4兆ドルと、中国(18.1兆ドル)の18.7%相当にとどまる(第2-1-25図)。IMFの予測によれば、今後インドの成長率が中国を上回るとしても、経済規模のキャッチアップは緩慢なものとなり、2028年時点でインドの経済規模は中国の20.3%相当にとどまる見込みである。
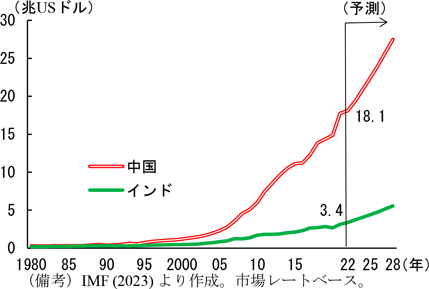
また一人当たりGDPでは、インドは2022年時点で0.24万ドルと、中国(1.28万ドル)の18.6%相当にとどまる(第2-1-26図)。IMFの予測では、今後インドの成長率が中国を上回るとしても、中国で人口減少、インドで人口増加が続く中で、一人当たりGDPのキャッチアップはより緩慢なものとなり、2028年時点でもインドは中国の19.0%相当にとどまると見込まれている。
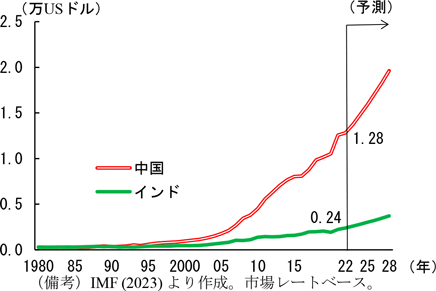
中国、インド両国の成長率と一人当たりGDPの分布(いわゆる「収れんチャート」)をみると、両国ともに、GDP成長率の高まりに応じて一人当たりGDPが高まるが、一定の時期からはGDP成長率が徐々に低下していく逆U字型の分布がみられる(第2-1-27図)。インドの一人当たりGDPは、2022年時点では約15年前の中国と同水準となっている。過去15年間、中国においては一人当たりGDPが高まる一方で、成長率については傾向的な低下が観測されている。インドにおいては、「人口ボーナス」を引き続き享受しており、生産年齢人口比率は2030年頃にピークを迎えるものの、その後の同比率の低下は緩やかなものにとどまると見込まれているが(後述)、中国と類似の軌跡を歩むかどうか、詳しくみていこう。
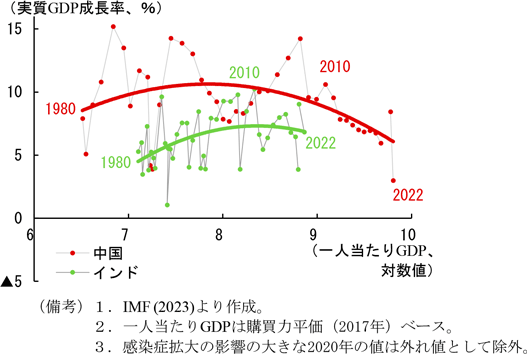
(中国、インド両国の発展パターンは資本投入主導の点で共通)
次に、経済成長の特徴を比較するため、成長会計の手法を用いて成長率を労働投入・資本投入・全要素生産性(TFP)の寄与に分解する(第2-1-28図)。インドでは、労働投入の寄与は1980年代に最も高かったが、1990年代半ばから縮小傾向となっており、人口ボーナスが続いているにもかかわらず、2010年代も労働投入の寄与は低水準にとどまっている。代わって資本投入の寄与は1990~2000年代後半まで安定的に高まり、2010年代は低下傾向となっている。TFPは、2015年前後に大きく伸びたが、2019年にかけて縮小した。このように、インドの発展形態は、(i)資本投入の寄与が大きい、(ii)労働投入の寄与が比較的小さい、といった点で、中国と共通している。
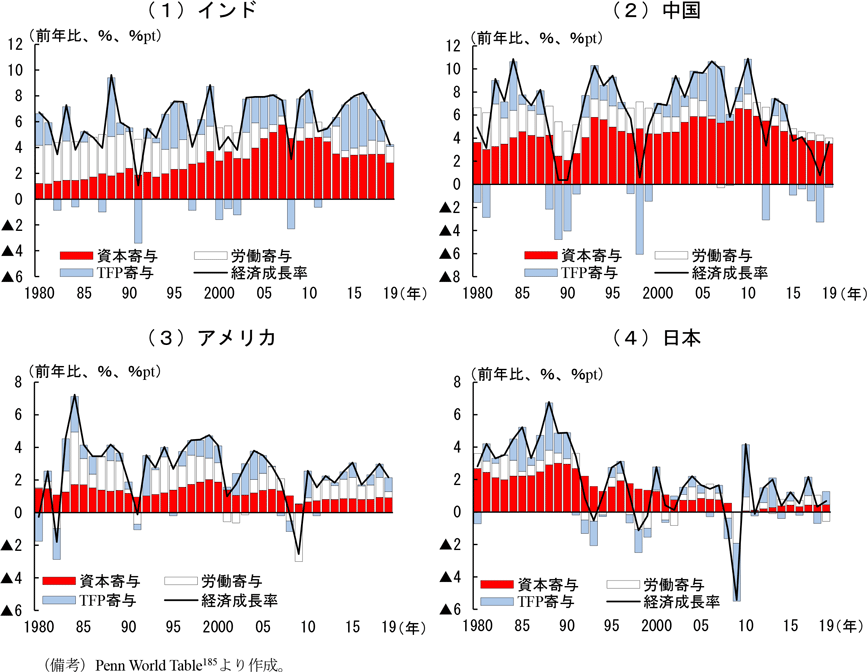
(インドでは、生産年齢人口の増加が継続)
人口が14億人強で並んだ中国、インド両国だが、人口動態の局面としては大きな違いがある。合計特殊出生率は、両国ともに低下しているが、2021年時点では、インドは2.03と、人口置換水準(中長期的な人口規模の維持に必要な出生率:2.07)をわずかに下回る程度にとどまる一方、中国は1.16と極めて低水準となっている(第2-1-29図)。
また、国連の2019年時点の見通し186と比べた場合、インドはわずかな下方修正であったが、中国については大幅な下方修正が行われた。中国においては今後大幅な出生率の反転が起こらない限りは人口減少が加速することが見込まれているが、インドにおいては当面は人口の増加が続く見込みである。
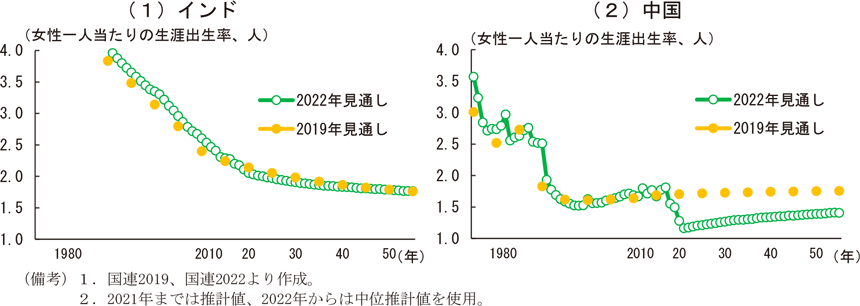
上記の出生率を前提として、国連2022は、インドの総人口は2063年(16.97億人)、生産年齢人口(15~59歳)は2044年(9.75億人)にピークを迎えると予測し、生産年齢人口比率は2029年にピーク(64.8%)となった後、緩やかに低下していく見込みとしている(第2-1-30図)。なお、中国については、総人口は2021年(14.26億人)、生産年齢人口は2011年(9.28億人)、生産年齢人口比率は2007年(69.2%)にピークとなっている。
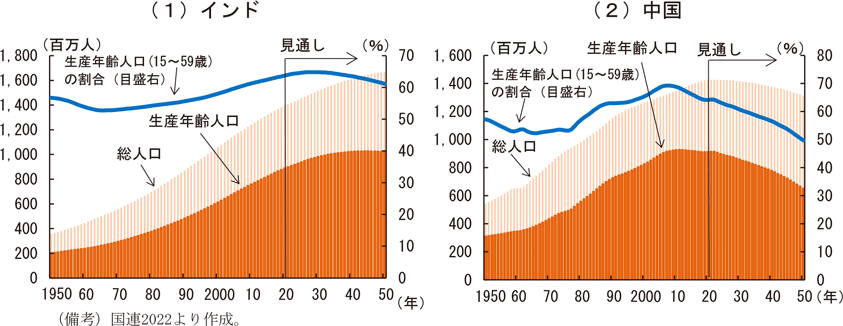
人口ピラミッドの形状で比べると、インドと中国には大きな差がみられている(第2-1-31図)。2022年時点で14.2億人程度でほぼ並んだ総人口は、国連予測では2050年時点でインド16.7億人、中国13.1億人、2100年時点でインド15.3億人、7.7億人となっており、中国では高齢化から人口減少への動きが急速に進行することとなる。こうした人口動態の局面の差異は、中長期的な成長率に影響するものとみられる。
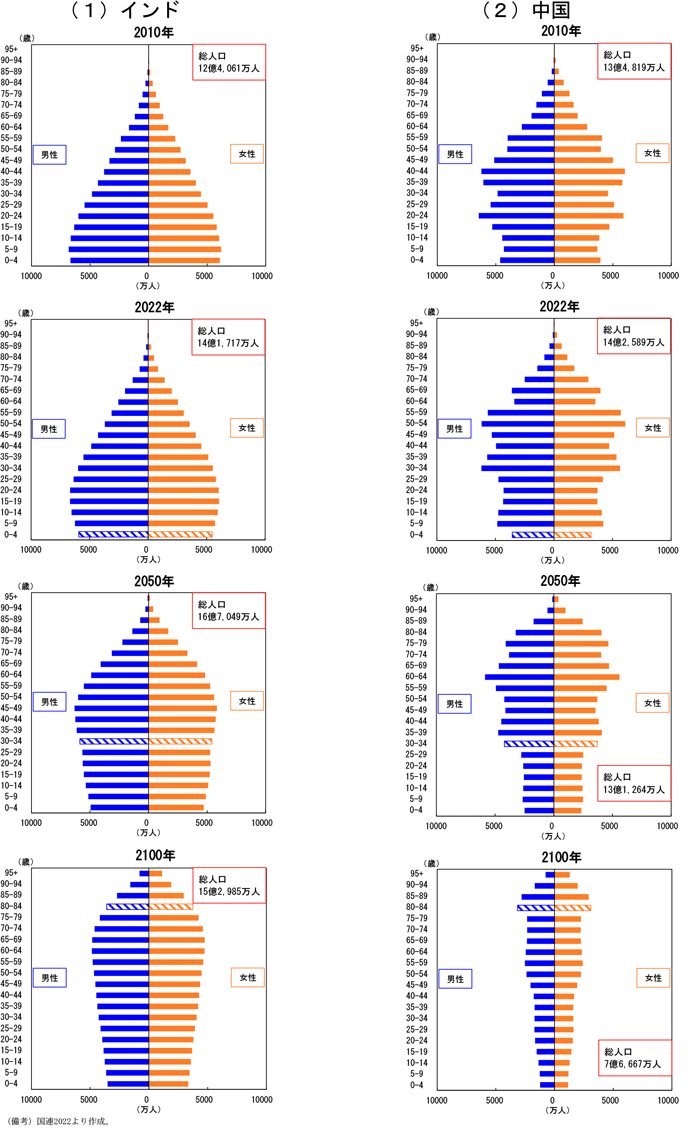
(インドの生産年齢人口比率のピークは2030年頃の見込み)
人口面から、インドの成長余地を探るため、いわゆる「人口ボーナス」と呼ばれる生産年齢人口比率が高まる期間に着目しよう。同期間には経済成長が促進される傾向がある187。中国において生産年齢人口比率と経済成長率(後方5年移動平均値)を比較すると、生産年齢人口比率がピークとなった2007年以降は、経済成長率の低下傾向が顕著となっている(第2-1-32図(1))。機械的に中国の経験を踏まえると、インドの生産年齢人口比率は2030年頃がピークを迎えるため、その先には成長率への低下圧力が生じるかもしれない(第2-1-32図(2))。
ただし、その低下程度については、従属人口比率の中身に着目する必要がある。つまり、生産年齢人口比率の低下要因が、急速な高齢化によるものであれば成長率への下押しは強いが、若年人口比率も高い中での緩やかな高齢化によるものであれば、それほど大きな下押しにはならないかもしれないということである。
そこで、従属人口比率と成長率を比較すると、中国においては、従属人口比率の低下とともに高度成長を果たしたが、2007年に30.8%(うち若年19.1%、高齢11.6%)を底として反転した後は、急速に従属人口比率が上昇しており、特に高齢人口比率が高まる中で、経済成長の鈍化がみられている(第2-1-33図(1)、第2-1-34表)。
対して、インドでは、国連予測によれば、従属人口比率は2029年に35.2%(うち若年22.6%、高齢12.6%)を底として反転が見込まれるが、その後の従属人口比率の上昇と高齢化の進行は緩やかとなる見込みとなっている(第2-1-33図(2)、第2-1-34表)。このため、成長への人口動態の制約は中国と比べて相対的に小さい可能性がある。
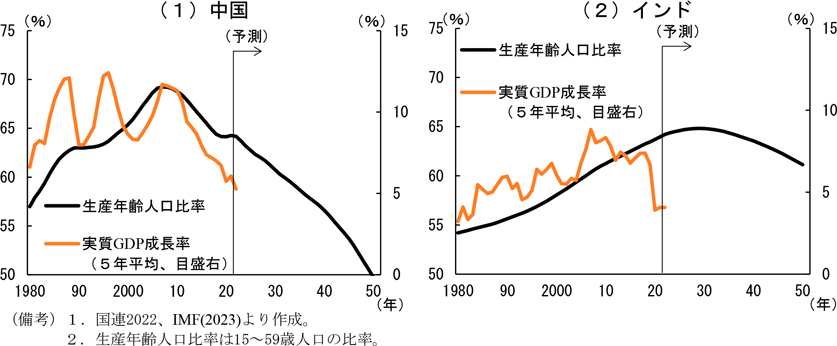
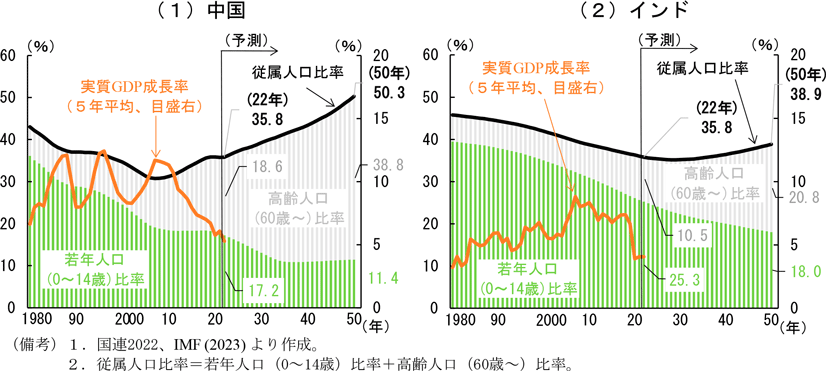
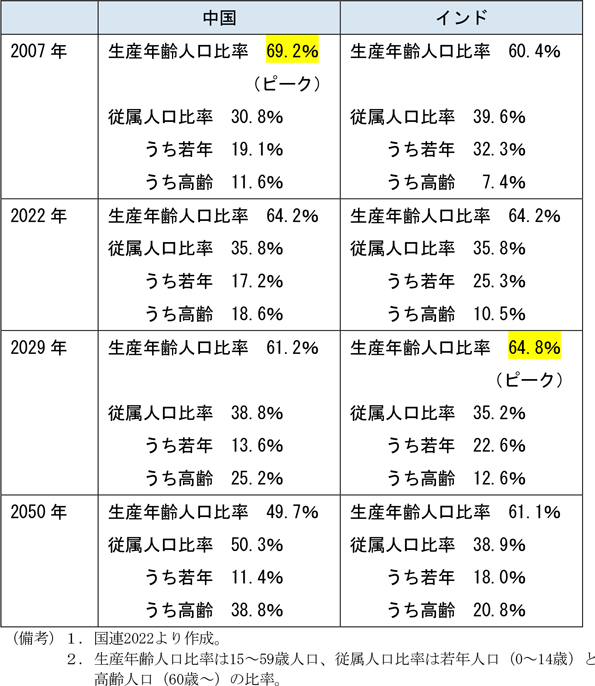
(近年の労働生産性の改善には、労働再配置の寄与が上昇)
人口要因に加え、経済成長の源泉は生産性である。中国、インドの労働生産性はどのような状況だろうか。OECD (2018) は、Nordhaus (2001) に基づき、タイの労働生産性の成長率を、(1)産業内部での生産性上昇(「内部効果」)、(2)産業間の労働移動による生産性上昇(「労働再配置効果」)への分解を行っている188。
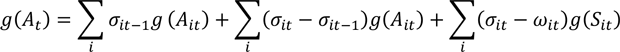
g(∙)は変化率、Atはマクロの労働生産性、Ait、σit、ωit、Sitはそれぞれ、産業iの労働生産性、名目付加価値額シェア、労働投入量シェア、労働投入量を表す189。上記の式において、第一項が内部効果(個別産業の生産性変動)、第二項(産業間のシェア変動)と第三項(労働移動)の合計が労働再配置効果を表す。
この枠組を用いて、1976年~2019年190のデータから労働生産性成長率の要因分解を行うと、以下の特徴がみられる(第2-1-35図)。
(i)中国においては、2015年まで労働生産性の上昇が続いた。内訳としては、内部効果の寄与が徐々に高まっている。労働再配置効果は、1995年までは大きかったものの、近年では縮小がみられる。
(ii)インドにおいては、労働生産性の伸び率が中国に比べ低い。労働再配置効果は、1995年頃までは寄与が極めて小さく、1996年以降はシェアの緩やかな上昇がみられる。内部効果は、2006~2015年に大きく上昇した。
(iii)タイにおいては、労働再配置効果の寄与が大きい状況が2015年まで続いた。2016年以降は、労働再配置効果が縮小する一方で、内部効果の高まりがみられる。
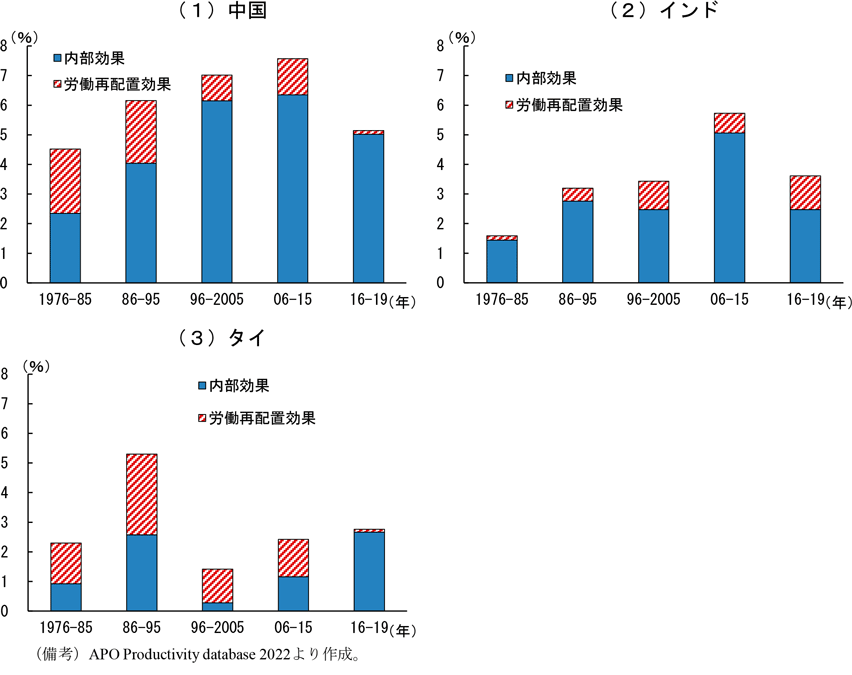
中国やタイにおける労働再配置効果の低下は、過去に比べて都市化(農村部から都市部への労働移動)の勢いに減速がみられつつあることが関係しているとみられる。インドにおける労働再配置効果の上昇は、1990年代以降、IT産業を中心とした労働生産性が相対的に高いサービス産業へ労働力の流入が進んだことの影響が示唆されている191。各国においては、人口ボーナスによる成長効果が徐々にはく落していく中で、労働参加率の上昇や各産業固有の生産性上昇に加え、生産性のより高い産業への労働移動の重要性が高まっており、インドはその双方を推進していく時期にあると言える。インドでは製造業・サービス業等の高生産性部門への労働再配置は緩やかながらも進展しているが、農業部門の就業者が4割を超えている。また、各産業の生産性上昇率は中国の方が高く、インドは引き続き生産性を高めていく必要があり、識字率の向上192からICT専門人材の育成までを含むヒトへの投資(教育投資)が重要である。

