第1章 景気の持ち直しとウクライナ情勢等による物価上昇(第1節)
第1節 世界経済の動向
2022年前半の世界経済は、新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)による影響が緩和され、欧米主要国では実質GDPが感染拡大前の水準をおおむね上回って推移するなど、持ち直しが続いている。一方、昨年来の世界同時的な景気回復等による物価上昇が、ウクライナ情勢の緊迫化を受けた国際商品市況の高騰等の下で一段と進行し、さらに中国における感染再拡大を受けた防疫措置の動向によるサプライチェーンの不確実性の高まりや、各国での金融引締めの進展等を背景に、世界経済の先行きは不確実性が高まっている。
本節では、22年前半の世界経済の動向(持ち直しの進展、物価上昇の進行、先行きの不確実性の高まり)を、ウクライナ情勢や中国の防疫措置の影響、各国の財政・金融政策等の動向を交えて概観し、今後の見通し及び下方リスクについて考察する。
1.景気の持ち直しの進展
(経済活動の進展)
先進国では、実質GDPが21年末時点でアメリカとユーロ圏で感染拡大前の水準を上回り、英国でもほぼ同水準まで持ち直していた(第1-1-1図)。22年第1四半期は、アメリカは貿易や在庫投資の動向により7四半期ぶりのマイナス成長となったが、個人消費や設備投資といった内需は拡大が続いた(第1-1-2図)。ユーロ圏と英国では、いずれも個人消費は足踏みがみられたものの、在庫投資等の増加によりプラス成長が継続し、英国は実質GDPが感染拡大前の水準を初めて上回った。
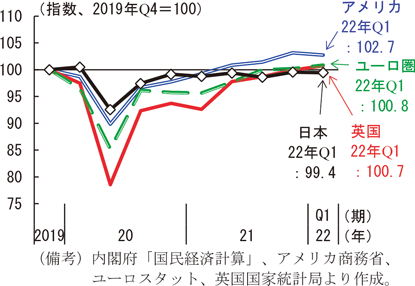
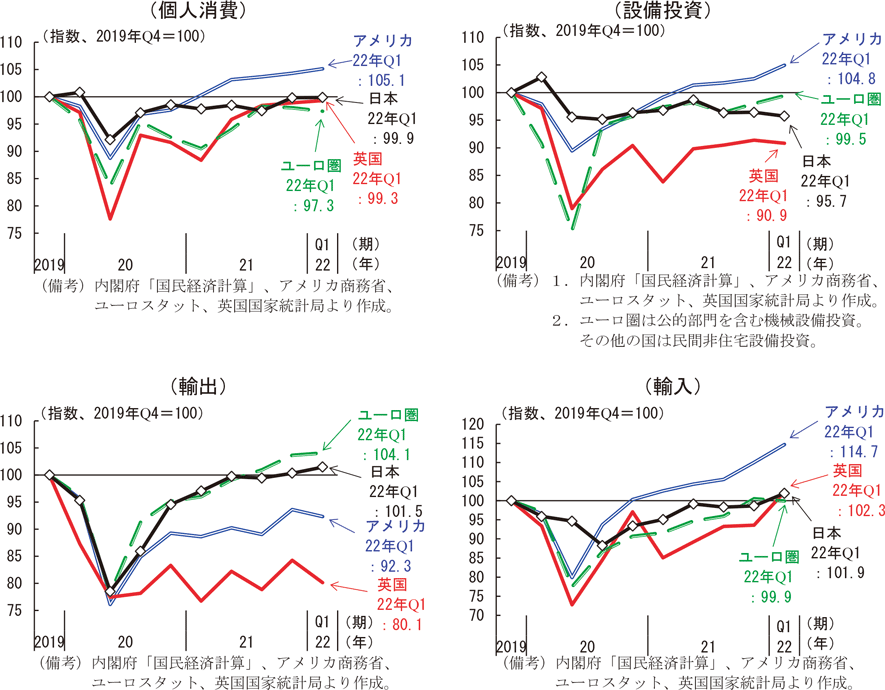
雇用情勢も改善が続いている。主要国の失業率をみると、ユーロ圏と英国で感染拡大前(20年2月)の水準を下回り、アメリカも22年春までに感染拡大前とほぼ同水準まで低下した後、足下まで同水準を維持している(第1-1-3図)。
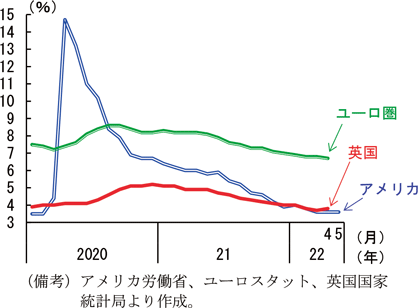
新興国に目を向けると、中国では、21年後半に環境規制の強化を受けた電力供給不足や生産抑制、不動産開発規制強化を受けた不動産市場の冷え込み等により景気の回復テンポが鈍化していたところ、22年初頭には持ち直しの動きがみられたが、感染再拡大により一部地方の経済活動が抑制されたことで、第2四半期からは持ち直しの動きに足踏みがみられている。その他の主な新興国では、いずれも第1四半期の実質GDP成長率が、インドで前年比+4.1%、ブラジルで同+1.7%、南アフリカで同+3.0%となった(第1-1-4図)。
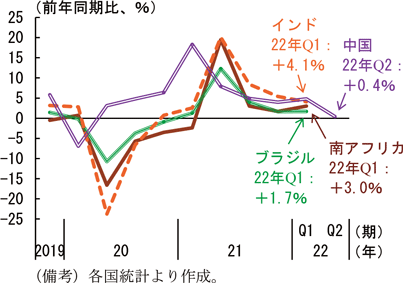
(感染動向等)
感染症について、欧米では、21年末から22年初旬にかけてオミクロン変異株の影響で急速な感染再拡大がみられた(第1-1-5図)。昨年来のワクチン接種の進展等を背景に、重症者数は以前の感染拡大期よりも相対的に低水準に収まったが、欧州では一時的に制限措置が実施され、消費の抑制等につながった(第1-1-6図、第1-1-7図)。アメリカでは、以前の感染拡大期のような制限措置は実施されなかったものの、飲食・宿泊等をはじめとする一部サービス部門では1月に消費の一時的な減少がみられた。その後、欧米主要国の感染者数や重症者数は大きく水準を下げて推移した。
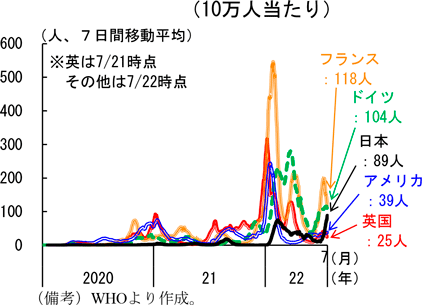
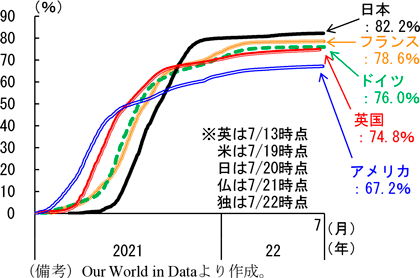
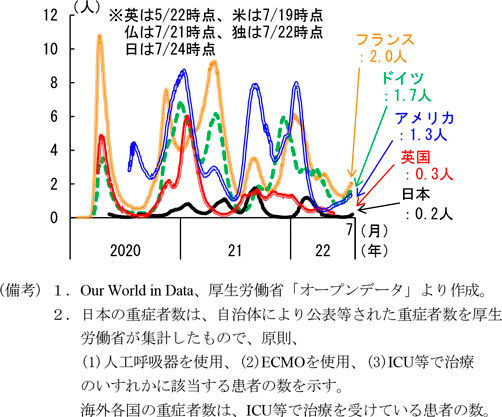
オミクロン株による感染再拡大は新興国でもみられた。このうち中国では、春節(1月31日~2月6日)後頃より感染者数が急増し、一部地域で厳格な移動制限や休業措置が実施された(第1-1-8図)。中国では従来、「ダイナミックゼロ」コロナ(中文では「動態清零」)の方針の下、第一階層の理想状態として感染者数ゼロの実現が重視されてきた。本年はオミクロン株の感染が拡大する中、第二階層として感染を早期に抑制し感染者数を減少させる方針をより重視し、感染対策と経済活動の両立を図ることとされた中で、広東省深セン市等の都市では制限措置を早期に解除する動きがみられた。上海市や北京市等の大都市では、感染の抑制に長期間を要し、経済活動の抑制が続いたが、6月初旬には制限が解除され、社会経済活動の正常化が進められている(本節4項参照)。
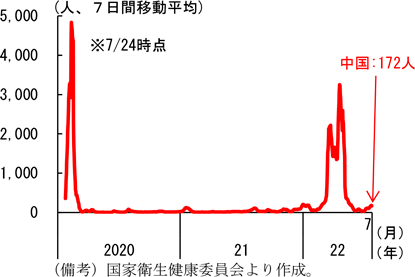
2.ウクライナ情勢
(1)世界経済への影響(波及経路別の確認)
14年のウクライナの親露政権崩壊やロシアによるクリミア半島併合等を経て、ロシアとウクライナの関係は近年緊張状態が続いており、特に昨年頃からは、ウクライナがNATO(北大西洋条約機構)への接近姿勢を強めたことなどを背景に、緊張感が一層高まっていた。こうした中でロシアは、22年2月21日にウクライナの一部であるドネツク州及びルハンスク州の独立を承認する大統領令に署名するなどし、さらに24日にはウクライナへの軍事行動を開始した。以降、7月現在もロシアによる侵略行為が続いており、アメリカやEU等の主要先進国によるロシアへの各種制裁措置と、ロシア側からは特定の財の輸出制限や欧州のエネルギー関連企業への輸出停止等の対抗策が相次いで発動されている(第1-1-9表、第1-1-10表)。以下では、ウクライナ情勢の世界経済への影響について、(i)国際商品市況の高騰、(ii)金融資本市場の変動、(iii)国際貿易の鈍化、(iv)ロシア経済の減速、の4つの波及経路別に確認する。
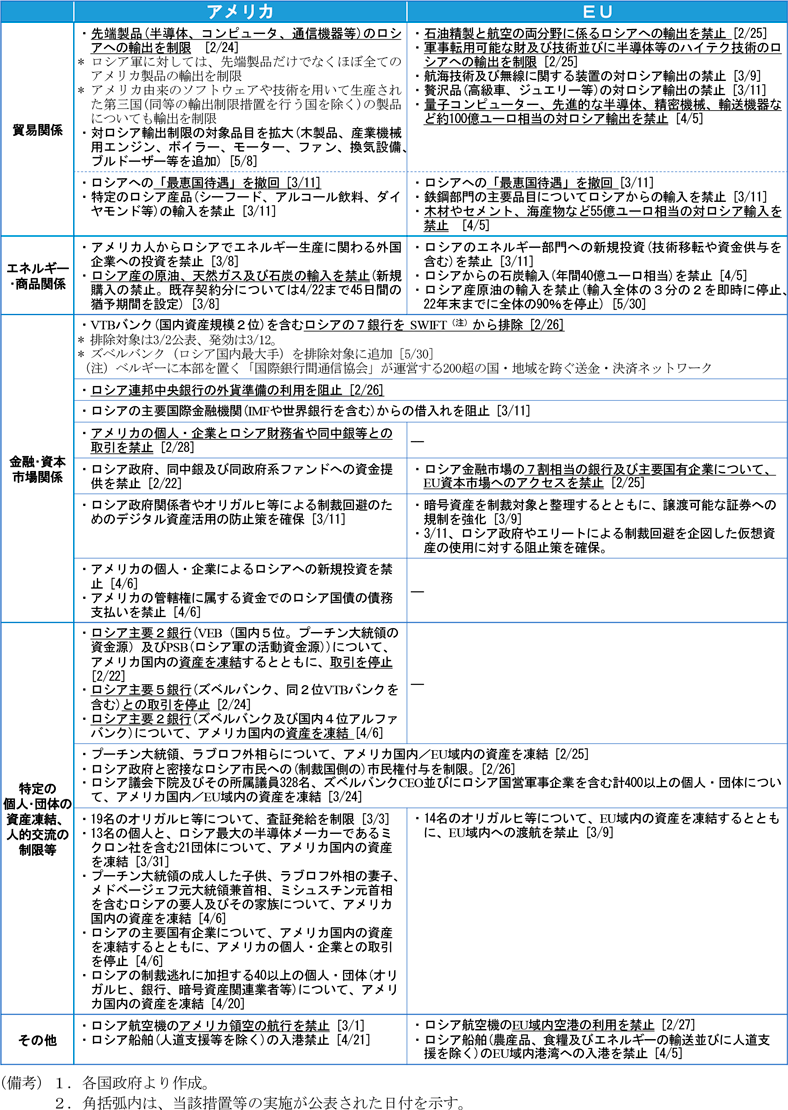
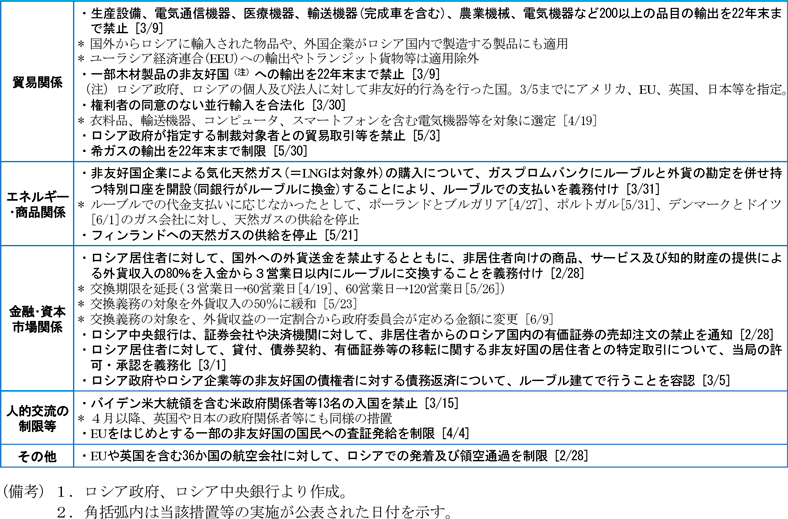
(i)国際商品市況の高騰
ロシアとウクライナは、経済規模では、世界経済に占める割合は必ずしも大きくない。世界のGDPに占める割合は、ロシア1.8%(21年時点)、ウクライナ0.2%(20年時点)であり、世界の貿易総額に占める割合は、ロシア2.2%(21年時点)、ウクライナ0.3%(21年時点)となっている(第1-1-11図)。
他方、両国は、エネルギーや穀物等の一次産品や、希少金属の輸出において重要な位置を占めている。代表的な品目の国際商品輸出のシェア(20年時点)をみると、ロシアは、原油で12.3%(世界2位)、天然ガスで19.1%(1位)、小麦で17.0%(1位)、とうもろこしで1.0%(12位)、パラジウムで26.7%(1位)を占める。ウクライナは、とうもろこしで12.8%(4位)、小麦で8.4%(5位)となっている(第1-1-12図)。
21年夏以降、感染症の影響が世界的に緩和され、景気の持ち直しが進み需要が高まる中で、国際商品市況は総じて上昇傾向にあった。22年2月24日にロシアのウクライナ侵攻が開始されてからは、戦争の影響による両国からの輸出の減少や、経済制裁措置及び対抗策による両国の主要輸出品目の供給減が見込まれる中、関連品目の価格は更に大幅に上昇し、3月上旬にピークとなった。その後は、戦況が長期化の様相を呈する中で、足下ではロシアのウクライナ侵攻前の水準まで低下するものもみられる一方、天然ガスは6月中旬以降再び大きく上昇するなど、不安定な推移となっている(第1-1-13図)。
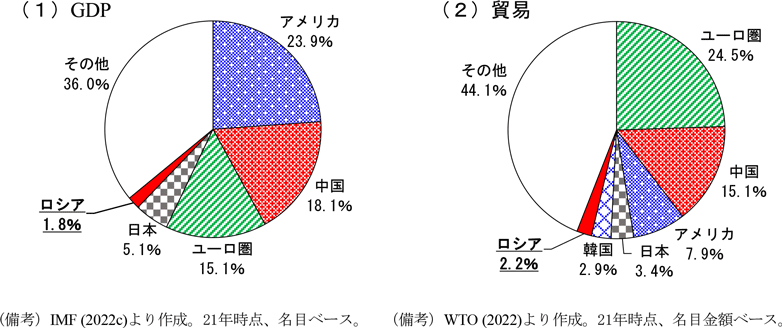
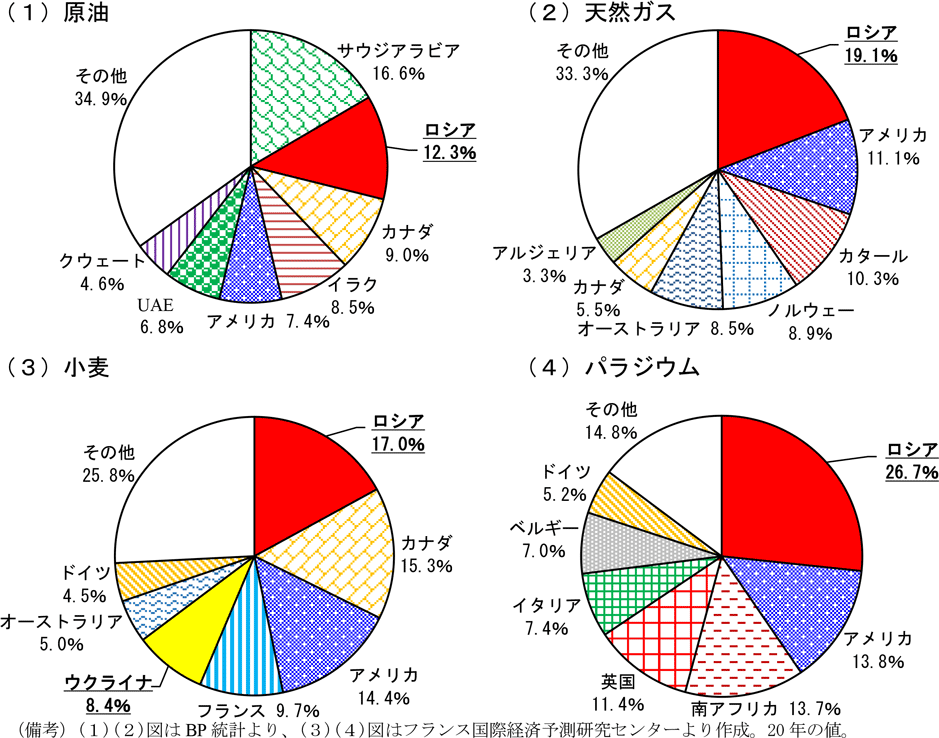
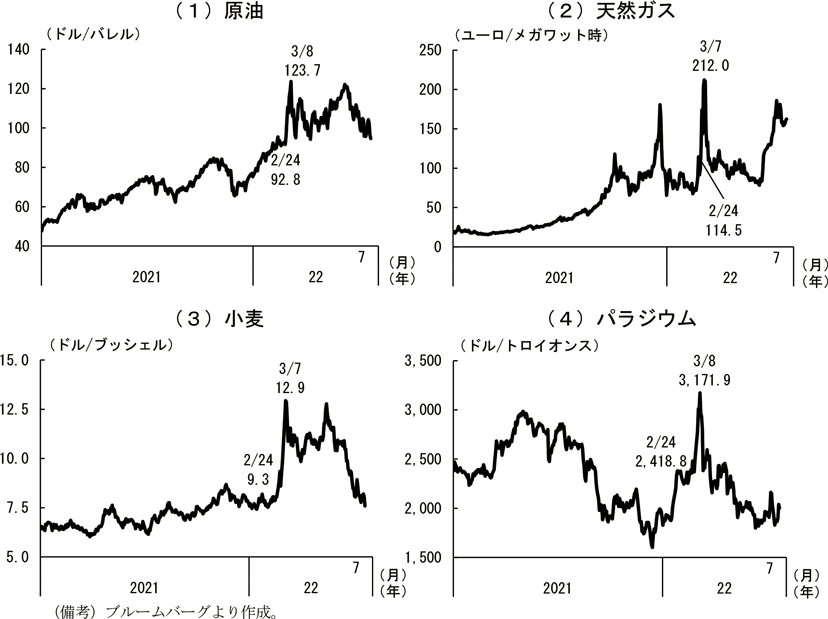
世界の多くの国々が、農産品輸入でロシア・ウクライナ両国に依存する中で(例えば小麦は、40か国近くが輸入の3割以上を両国に依存1)、農産品の供給不安に伴う商品価格の上昇は、世界的な物価上昇のみならず、食料安全保障に影響している。World Bank(2022)は、ロシアによるウクライナ侵攻は農産品の商品価格を顕著に上昇させており、食料安全保障を悪化させているとした。加えて、一部の農産品輸出国が輸出制限等の保護主義的な政策を実施したことで、農産品価格の上昇や変動の拡大につながったと指摘している。OECD(2022)は、アフリカ、中東、中央アジアの低所得国が、穀物等の国内生産比率が低く、ロシアとウクライナからの輸入に依存する比率が高い傾向があり、食料安全保障の懸念が大きいと指摘している2(第1-1-14図)。FAO(2022)は、ロシアとウクライナの小麦等の輸出減少3を想定すると、22年度4に栄養不足人口が760~1,310万人増加する見込みであり、さらに深刻な輸出減少が継続する場合5には、23年に栄養不足人口が1,900万人近く増加する見込みとしている。
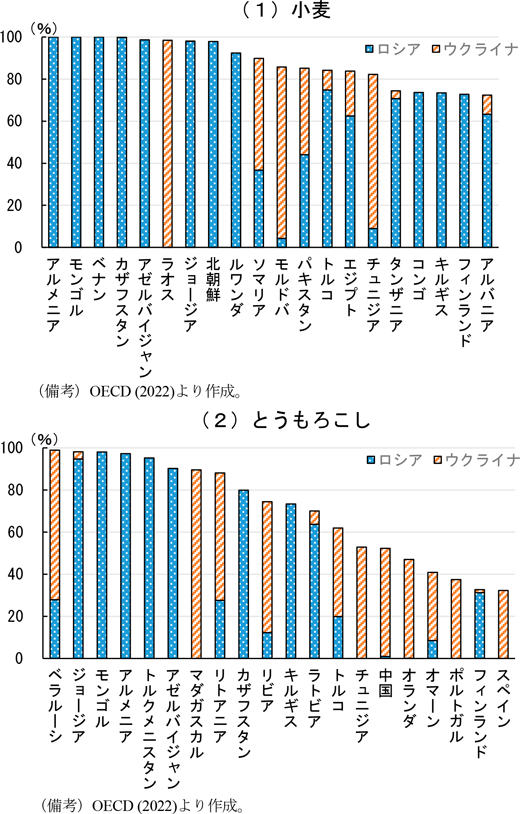
(ii)金融資本市場の変動
株式市場の動向をみると、22年2月から3月にかけて、アメリカ、ドイツ、日本の株価指数は総じて下落傾向となった(後掲第1-1-55図)。22年初を基準点とするグラフをみると、特にドイツが大きく下落しているが、背景にはドイツはロシアとのエネルギー関連の取引が多いことがあると考えられる。
市場のボラティリティを表すVIX指数6をみると、ウクライナ侵攻の2月下旬にかけて、不確実性の高まりを反映して大幅に上昇し、過去1年で最も高い水準となった(後掲第1-1-56図)。
(iii)国際貿易の鈍化
ウクライナ情勢により、グローバル・サプライチェーンを介する供給制約の悪化等を通じて世界の貿易や生産を下押しする可能性が考えられる。世界の財貿易量の推移をみると、21年10月から12月にかけての増加傾向の後、22年に入り増勢が鈍化している(後掲第1-1-51図)。世界の鉱工業生産については、22年2月までの増加傾向が3月には反転し、4月も減少が継続した(後掲第1-1-52図)。ウクライナ情勢が世界の財貿易量に及ぼす影響は、今後更に顕在化してくる可能性もあり、注視が必要である。
海上輸送の運賃の動向を表すバルチック海運指数をみると、21年下旬から22年初にかけて低下傾向であったが、3月に急上昇し、5月にかけて再び水準が高まった(後掲第1-1-53図(1))。また、空運指数も高水準で推移している(後掲第1-1-53図(2))。輸送コストの上昇は、今後、貿易量の下押し要因として影響が生じ得る。また、貿易財への価格転嫁が進むことを通じて、各国の物価上昇の追加圧力となることが懸念される。
(iv)ロシア経済の減速
(ロシアの金融市場の動向)
ロシアの通貨ルーブルは、ウクライナ侵攻開始(2月24日)前後から大幅な減価が始まった(第1-1-15図)。年初来、対米ドルで最も減価が進んだ3月7日時点では、減価が加速する前の2月16日の水準に比べ約45.8%安となった。特に、2月26日には、主要先進国により、ロシアの一部銀行のSWIFTからの排除や、ロシア連邦中央銀行の外貨準備の利用阻止が発表されたところ7、週明けの2月28日には前週末から2割程度の減価が進んだ。同日、ロシア中央銀行及び財務省は資本規制を導入し、ロシア居住者に対し、国外への外貨送金を禁止するとともに、非居住者向けの商品・サービス及び知的財産の提供による外貨収益の80%を、入金から3営業日以内にルーブルに交換することを義務付けた8。こうした規制の効果もあり、ルーブルの為替水準は調整が進み、5月以降は侵攻開始前の水準を回復し、7月にかけて更に水準を高めている。
ロシアの外貨準備高は、クリミア侵攻時の13~14年に減少した後、15~21年は増加傾向が続き、21年末時点で6,300億ドルに達していたが、22年2月以降は減少している(第1-1-16図)。なお、欧米等各国による制裁(ロシア中央銀行の外貨準備の利用阻止)を受け、大半が凍結されたとみられている9。
ロシアの株式指数(RTSI)は、ウクライナ侵攻が開始された2月24日に急落し、2月28日~3月23日には株式市場での取引が停止された(第1-1-17図)。その後は6月末にかけて上昇傾向で推移したものの、7月は再び水準を落としている。
ロシア国債の信用リスク(デフォルトリスク)に関する市場の見方を示すCDS保証料率をみると、3月に入り急上昇し、その後は大きな変動を伴いつつ高水準で推移している(第1-1-18図)。上述のとおり、欧米諸国の制裁によりロシア中央銀行は外貨準備の大半の利用ができない状態が続いている。3月以降、アメリカ財務省の特例措置等によって、外貨準備を使った国債の利払い等を実施してきたものの、こうした特例措置が終了すれば債務不履行となる可能性があることが指摘されている。アメリカ財務省は5月24日、制裁免除の特例措置は延長せず、25日に失効すると発表した。6月、世界の主要金融機関で構成するクレジットデリバティブ決定委員会(CDDC)は、4月4日が償還日であったドル建てロシア国債について、一部債務の支払の不履行(デフォルト)があったと認定した10。
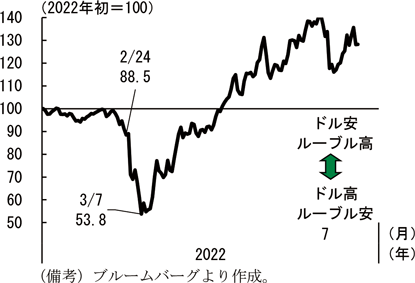
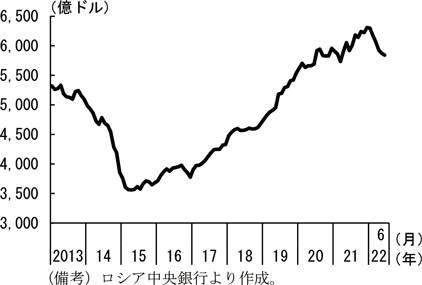
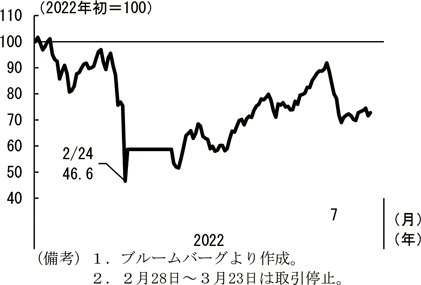
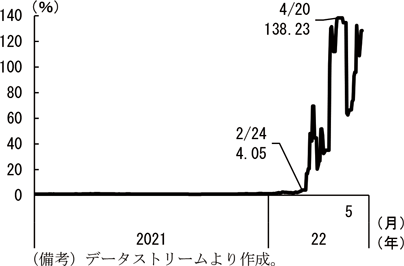
(ロシアのマクロ経済指標の動向)
ロシア中央銀行は、主要先進国からの経済制裁によるルーブルの急速な減価と物価上昇に対応するため、2月28日、主要政策金利(1週間入札レポ金利)を従来の9.5%から20.0%まで大幅に引き上げた(同日適用)(第1-1-19図)。その後、為替水準の回復傾向と経済の下支えの必要性等を勘案し、4月8日に17.0%(4月11日から適用)、4月29日に14.0%(5月4日から適用)、5月26日に11.0%(5月27日から適用)、6月10日に9.5%(6月14日から適用)と相次いで引下げを発表している。
ロシアの消費者物価上昇率は、6月は前年同月比+15.9%と高い上昇率となっている(第1-1-20図)。また、生産者物価上昇率は、4月に前年同月比+31.5%(前月比+6.3%)と大幅に高まり、5月も前年同月比+19.3%(前月比-6.9%)と高水準で推移している。
ロシアの実質経済成長率をみると、22年1~3月期は前年同期比+3.5%となり、前期(21年10~12月期:+5.0%)に比べると減速したものの、プラス成長を維持した(第1-1-21図)。
直近の月次経済指標においては、3月まではプラス成長を維持したものの、4、5月はマイナスが続いた11。ロシア経済は、主要国の経済制裁を受け、ルーブルの急落等を通じた急激な停滞は当面回避した可能性があるが、物価上昇の継続や禁輸措置による実体経済への影響は、今後更に顕在化していくとみられる。ロシア中央銀行のナビウリナ総裁は、6月10日付の声明で、「物価上昇は顕著に鈍化しており」「年末には14~17%程度になる見込み」、「主な不確実性は第一に石油禁輸措置のインパクトであり、ロシア産石油の輸出が急減すれば、貿易収支の収縮からインフレ圧力とルーブルの減価が起こり得る。どの程度他の輸出先に振り向けられるか、輸出数量の減少を価格上昇で相殺できるかにかかっている」、「我々はスタグフレーションリスクを回避せねばならない」等と述べた12。
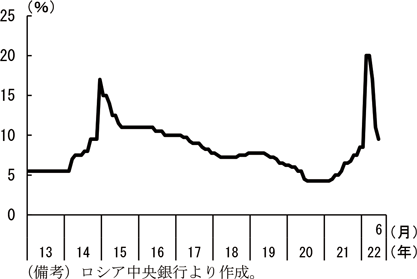
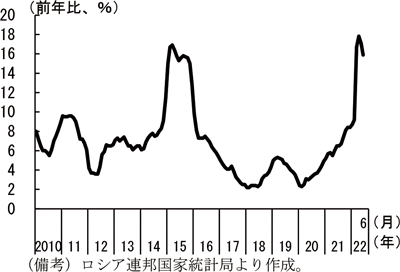
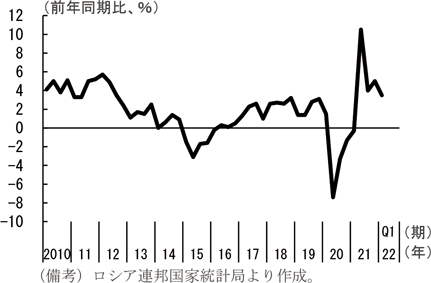
(各国の対ロシア貿易の動向)
(ア)アメリカ
アメリカの財貿易に占めるロシアのシェア(21年)は、輸出で0.4%、輸入で1.0%にとどまっている(第1-1-22図)。直近の動向をみると、アメリカからロシアへの財輸出(名目ベース)は3月に大幅に減少し、4月も同様の状況が続いた(第1-1-23図)。一方、財輸入(同)は、鉱物性燃料・油等の大幅な増加を受けて、3月には全体としても前月から増加した13が、4月には減少に転じた。ロシア産の原油、天然ガス及び石炭の輸入禁止措置が4月末以降に本格的に適用されたことから、今後は影響が更に顕在化してくるものとみられる。
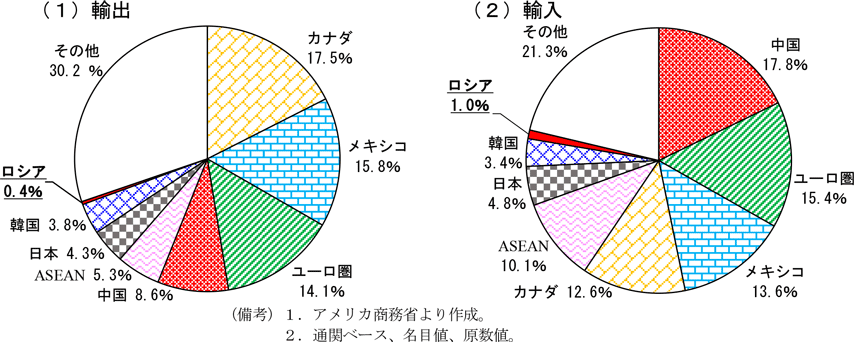
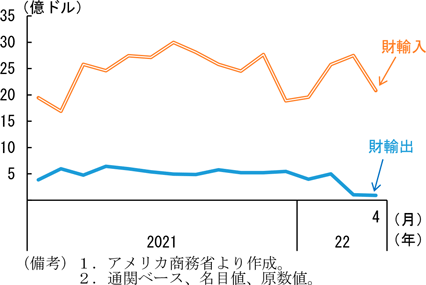
(イ)ユーロ圏
ユーロ圏の財貿易に占めるロシアのシェア(21年)は、輸出で1.5%、輸入で2.9%となっている(第1-1-24図)。ユーロ圏の輸出をみると、3月は前月比+1.0%、4月は同+1.5%と、4か月連続で前月を上回ったが、国別では、3月から続くロシア向けの落ち込み14を、アメリカ、英国、その他向けが補う形となった(第1-1-25図(1))。財別では、ウクライナ侵攻後の供給混乱による自動車工場の生産調整が欧州各地で報じられる中、機械類・輸送機器が3、4月と大きく落ち込んだ15一方、鉱物性燃料は好調であった16。
ユーロ圏の輸入は、昨年央より堅調で足下も好調(3月:前月比+3.2%、4月:同+7.1%)であったが、対ロシアは3月に前月比+0.1%、4月は同-0.5%となった(第1-1-25図(2))。ロシアからの輸入の大部分は燃料であることから、3月は価格上昇の効果で増加したものの、4月は輸入数量の減少の影響が上回りマイナスに転じたものとみられる。今後は、EUの対ロシア輸入禁止措置の影響が徐々に強まる中で、輸入は数量減少と価格上昇の両要因を反映して推移するものとみられる。
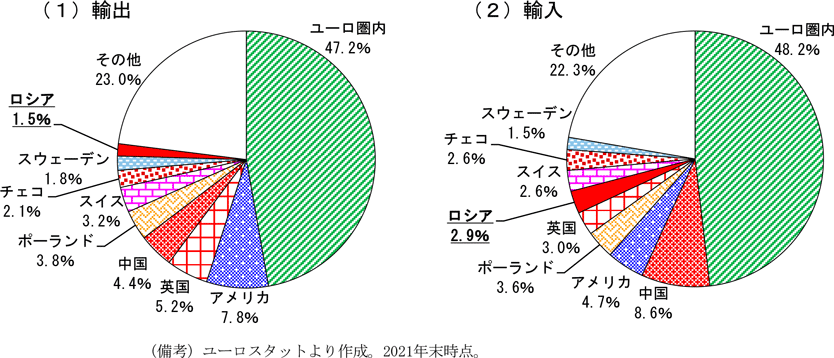
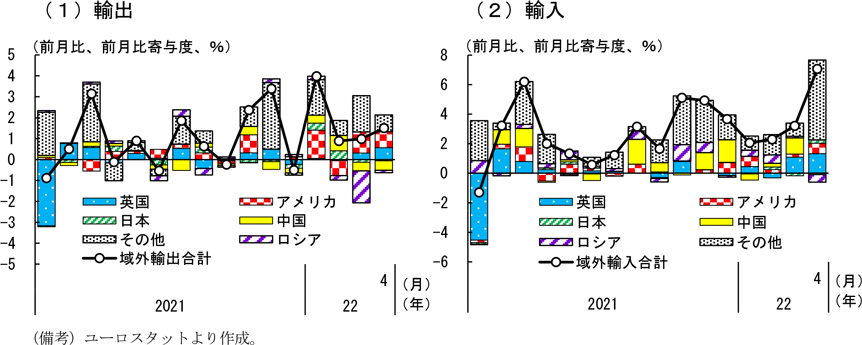
(ウ)中国
中国の財貿易に占めるロシアのシェア(21年)は、輸出で2.0%、輸入で0.8%となっている。また、中国の対ロシア貿易の構成比をみると、特に輸入においては鉱物性製品が高いシェア(21年時点で72.7%)となっている(第1-1-26図)。直近の5月の動向をみると、中国からロシアへの財輸出は前年比で減少が続く一方、財輸入は5月にもプラス成長を続けており、鉱物性製品の寄与が大きいことが分かる(第1-1-27図)。中国は対ロシア制裁の禁輸措置を行っていないことから、鉱物性製品を主体とした輸入の増加傾向が続く可能性がある。
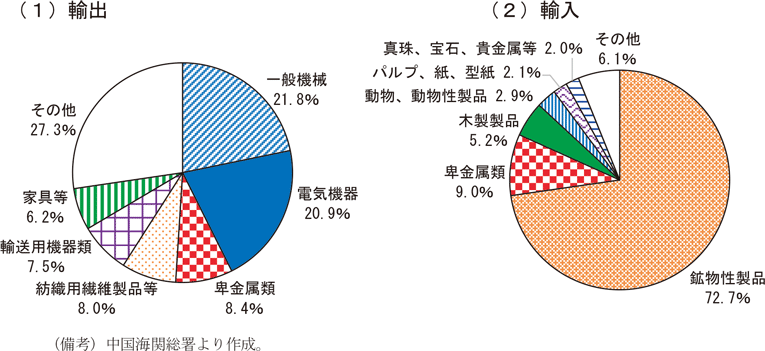
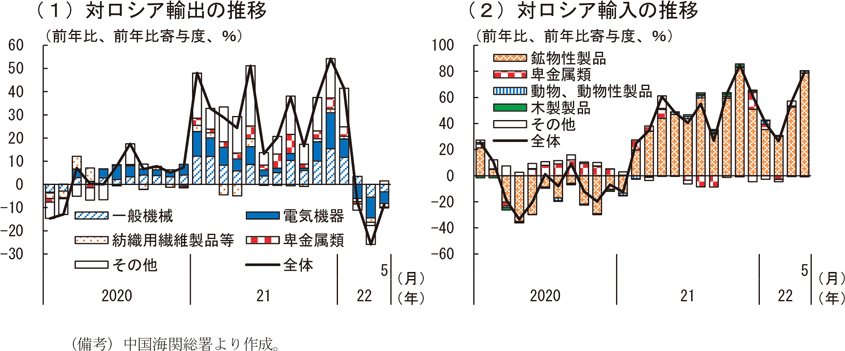
(2)各国のエネルギー関連政策等
先述のとおり、ロシアはこれまで、世界の原油や石油製品、天然ガス等の供給において大きなシェアを占めていた。このため、ウクライナ情勢を受けてロシア産のエネルギーの使用が困難になったことで、世界全体として当面のエネルギー供給の安定化が急務となった。また、特にエネルギー供給の多くをロシアに依存する欧州諸国では、代替供給源の確保を含む中長期的なエネルギー戦略の見直しも必要となった(第1-1-28図)。以下では、ウクライナ情勢下における各国のエネルギー関連政策等の動向を概観する。
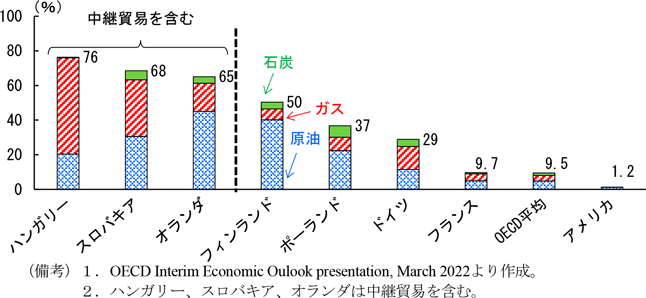
(当面のエネルギー供給の安定化)
ウクライナ情勢の緊迫化によりロシア産の原油及び石油製品の使用が難しくなったことを受け、国際エネルギー機関(IEA)加盟国は3月1日、当面の石油供給の安定を図るため各国の戦略的石油備蓄17から計6,000万バレル余りを協調的に放出することを合意した。その後、4月1日には同じくIEA加盟国の合計で1億2,000万バレルの追加放出を行うことが合意され、アメリカの別途放出分18を合わせて、向こう6か月の間に計3億バレル超の石油供給が各国の備蓄から賄われることとなった19(第1-1-29表)。
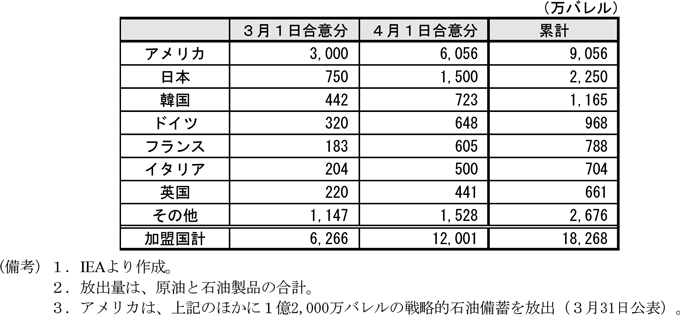
(中長期のエネルギー戦略の見直し)
ウクライナ情勢の緊迫化を受け、特にロシアへのエネルギー依存度が高い欧州では、代替供給の確保を含め中長期的なエネルギー戦略の見直しの必要性が認識され、対応が検討された。EUに関しては、欧州委員会が3月8日に、天然ガスのロシア依存脱却に向けた「REPowerEU」計画を公表した。同計画は、液化天然ガス等についてロシア以外からの輸入を増やすとともに、バイオメタンや再生可能水素の生産及び輸入を拡大することで、ガス供給源を多様化すること等を取組の柱とし、30年より相当前にロシア産化石燃料への依存の段階的な削減を目指すとしている。欧州委員会は、21年に策定された2030年温室効果ガス削減目標達成に向けた政策パッケージ「Fit for 55」に基づく取組と本方針に基づく取組を合わせることで、22年末までにEUのロシアのガスに対する需要を3分の2削減することができると見込んでいる。
欧州委員会は、同計画に関して原子力の活用の可能性及び必要性を指摘しており、各国で原子力を活用する動きがみられている20。具体的には、3月にはフィンランドで原子力発電所の稼働予定期間の延長が決定され、ベルギーでも25年に予定していた脱原子力発電を10年先送り、35年まで運転を継続する方針が決定された。このほか、いずれも2月時点で、フランスで原子炉の新設、ポーランドで原子力発電所の新規稼働の計画がそれぞれ公表されている。
英国は、3月8日にロシアへの制裁としてロシアからの石油輸入を22年末までに段階的に停止することを表明していたが、4月6日に公表したエネルギー安全保障戦略で、石油に加えて石炭と天然ガスの輸入停止に向けた道筋を示した21。同戦略では、当面の国内の石油・ガス生産を支援しながら、風力、原子力、太陽光及び水素の導入を加速し、30年までに電力の95%を低炭素化する方針も示されている。
ドイツは、ショルツ政権発足に当たり、再生可能エネルギーが電力消費に占める比率を30年には80%(21年は42%)とするなどのエネルギー戦略の方針を示していたが、4月6日に公表した新エネルギー戦略「イースターパッケージ」で、陸上発電や太陽光発電設備の増強などを通じ、同比率を30年に80%、さらに35年にはほぼ100%に引き上げるなどの目標を明示した。
(アメリカのエネルギー増産に向けた動き)
3月25日の米・EU両首脳の共同声明により、アメリカからEUへの液化天然ガス(LNG)供給を22年内に150億立方メートル、30年までに500億立方メートル追加することが合意されるなど、EUの対ロシア依存脱却に向けては、アメリカが代替供給源として重要な役割を果たすことが期待される。
アメリカでは、2010年代の前後半それぞれにおいて、原油価格が緩やかな上昇基調で推移する中で、シェールオイルを中心に原油の増産が進んだ。一方、足下では、環境に関する議論が高まる中で、大幅な価格上昇が続いているにもかかわらず、シェールを含む原油産出量は感染拡大前より依然低い水準にとどまっている(第1-1-30図)。アメリカ政府は、原油の増産が遅れている背景として、石油企業が連邦政府公有地の採掘権の多くを活用していないことを挙げ、企業に増産を呼びかけるとともに、3月末には未使用の採掘権を有する企業に対して金銭の支払いを求める措置を検討するよう議会に要請している。天然ガスについては、感染拡大前の水準を持ち直して増産が続いているが、EUへの供給拡大に向けては、アメリカとEUの双方でLNG基地を整備する必要性も指摘されている。
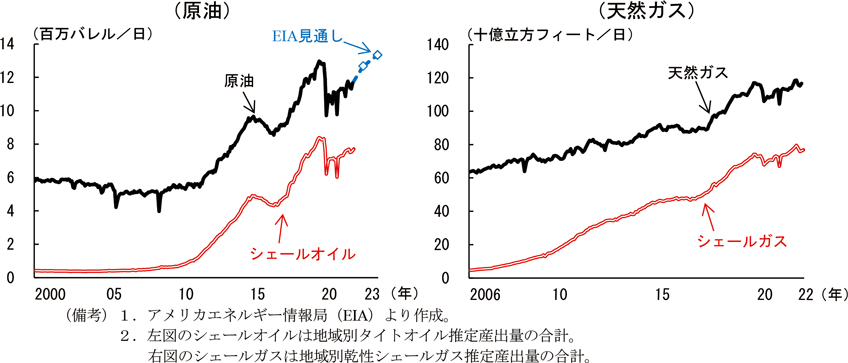
(3)国際機関による影響試算
ウクライナ情勢による不確実性の高まりを受けて、国際機関等は、その影響試算を行っている。OECD(2022)は3月、侵攻開始後2週間で起きた原材料価格の上昇と金融市場へのショック22が1年間持続するとの前提の下、侵攻後1年間で世界の実質GDP成長率を1%ポイント超押し下げ、消費者物価上昇率を約2.5%ポイント押し上げると試算した(第1-1-31図)。欧州は、ロシアとのビジネスやエネルギー面で深いつながりがあることや、他地域よりガス価格の上昇が顕著であることから、相対的に大きな影響を受けるとした(ユーロ圏の成長率は1.4%ポイント程度押下げ)。アジア太平洋州や米州の先進国は、ロシアとの貿易や投資面でつながりは小さいが、世界的な需要減少と物価上昇の影響を受けるとした(アメリカの成長率は0.9%ポイント程度押下げ)。また、物価上昇への対応として、侵攻後1年間で主要先進国では1%ポイント超、主要新興国では1.5%ポイントの政策金利の引上げが行われるとした。
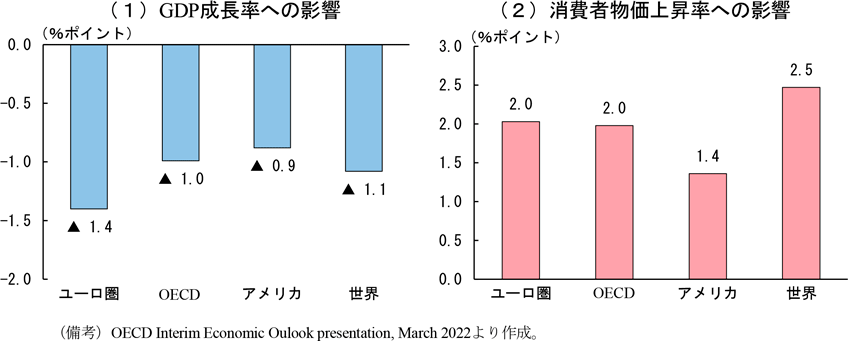
IMF(2022c)は4月、ウクライナ情勢の影響を受け、世界の実質GDP成長率を、22年は3.6%(22年1月時点の見通しから0.8%ポイントの下方修正)とした。また、世界の消費者物価上昇率は、ウクライナ情勢に起因する原材料価格の高騰23により高水準で推移し、22年は先進国で5.7%(同1.8%ポイント上方修正)、新興国・途上国で8.7%(同2.8%ポイント上方修正)とした。各国の経済成長率については、欧州(ユーロ圏)はエネルギー高騰と自動車産業等の供給制約の影響を受けて22年は2.8%(同1.1%ポイント下方修正)、アメリカは早期の金融引締めとウクライナ情勢に起因する貿易相手国の経済状況の悪化を反映して22年は3.7%(同0.3%ポイント下方修正)とした。さらに、リスク要因として、(i)ウクライナ情勢、(ii)中国の防疫措置の動向、(iii)金融引締めの動向、(iv)各国の財政状況等を挙げ、下方リスクが大きいとした24。
World Bank(2022)は6月、原油、天然ガス及び石炭等のエネルギー価格の見通しを引き上げたことにより、22年の世界の経済成長率が0.5%ポイント押し下げられ、23年には更に0.3%ポイント低下するとの見通しを示した。同見通しでは、こうした影響は特に、EU諸国を始めとする先進国で大きいことが示唆されている。
3.世界的な物価上昇の進行と各国の対応
(1)世界的な物価上昇の進行
21年以降、世界同時的な景気の持ち直しの下、需要の回復が続き、原材料・部品等や労働者の不足などもあり、先進国と新興国の双方で物価上昇がみられてきた。22年前半は、ここにウクライナ情勢を受けた国際商品市況の高騰等の影響が加わり、各国で物価上昇が一段と進行している。G20諸国の消費者物価上昇率(中央値)の推移をみると、先進国、新興国とも22年以降に上昇率が一段と高まっている(第1-1-32図)。
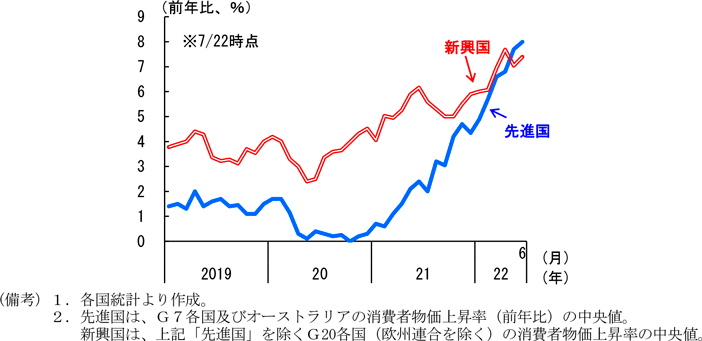
このうち欧米主要国について、直近(22年6月分)の消費者物価上昇率(前年同月比)をみると、アメリカが+9.1%(うちエネルギーの寄与度は+3.0%ポイント)、ユーロ圏が+8.6%(同+4.2%ポイント)、英国が+9.4%(同+4.7%ポイント25)と、いずれも高い水準となっている(第1-1-33図)。これをロシアによるウクライナ侵攻開始前(22年1月26)と比較すると、アメリカで+1.6%ポイント(うちエネルギー+1.3%ポイント)、ユーロ圏で+3.5%ポイント(同+1.4%ポイント)、英国で+3.9%ポイント(同+2.2%ポイント)となり、ウクライナ情勢下での物価の伸び幅とエネルギーの寄与度の増加幅は、いずれもアメリカにおいて相対的に小さく、英国において相対的に大きくなっている。また、21年後半以降、サービス部門等の労働市場で需給のひっ迫やサービス消費の回復、加えて住宅価格上昇を反映した家賃の上昇など、物価上昇のすそ野の拡がりがみられている27。
ウクライナ情勢に起因するエネルギー・食料品価格高騰は、各国経済にとっての新たな供給ショックとなって物価上昇を加速させており、特にロシアとの経済・貿易関係の強い国々・地域においてその傾向が顕著となっている28。
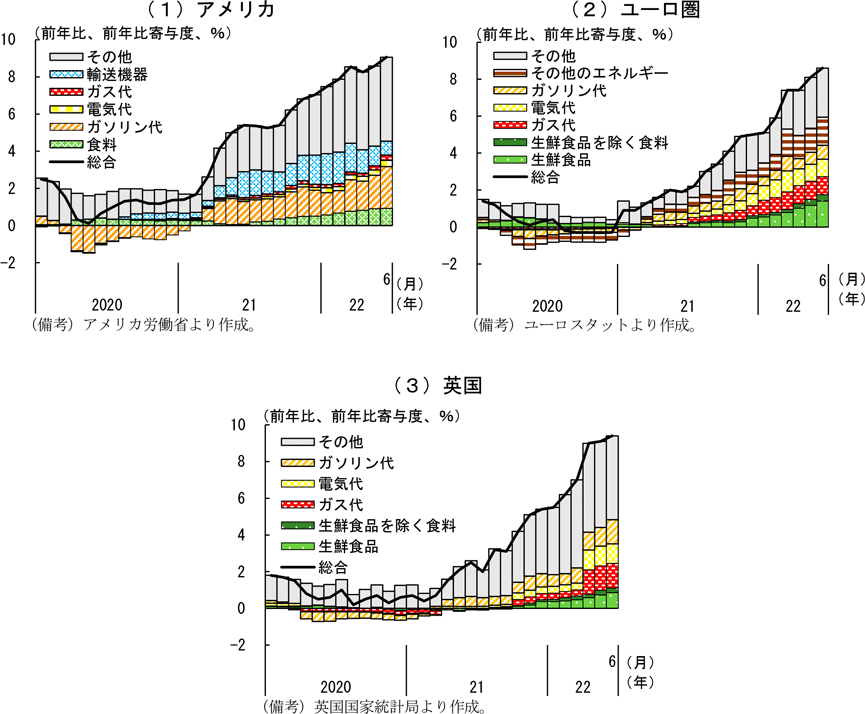
(2)各国政府の対応
ウクライナ情勢等による物価上昇の一段の進行を受けて、ロシアへのエネルギー依存度が高く、地理的にもつながりのある欧州各国を中心に、4月末までに原油価格等の高騰を受けた物価抑制策や幅広い家計及び企業を対象とした各種支援策、所定の要件を満たす中小企業等や生活困窮者等への重点支援策が打ち出された(第1-1-34表)。
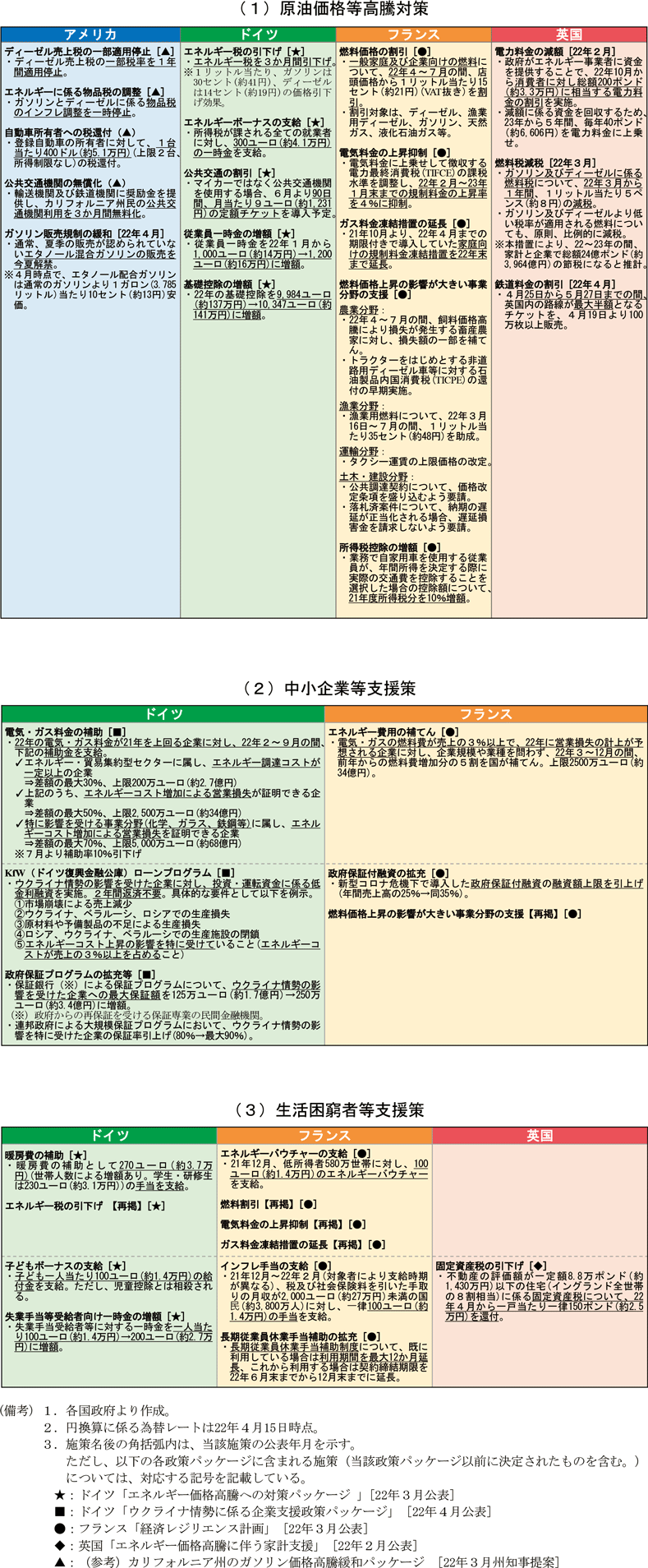
(3)金融引締めの進展
21年以降、景気の持ち直しや物価上昇等を背景に各国で金融緩和の縮小や金融引締めが進められてきたが、22年前半はこうした動きに一段の進展がみられた。G20諸国の各月の政策金利変更回数をみると、新興国は21年前半から複数の国が利上げを行っていたが、同年後半、さらに22年前半と、利上げを行う国が一段と多くなってきた。先進国は、21年末から利上げがみられるようになり、22年春以降利上げを行う国が増えてきている。(第1-1-35図)。
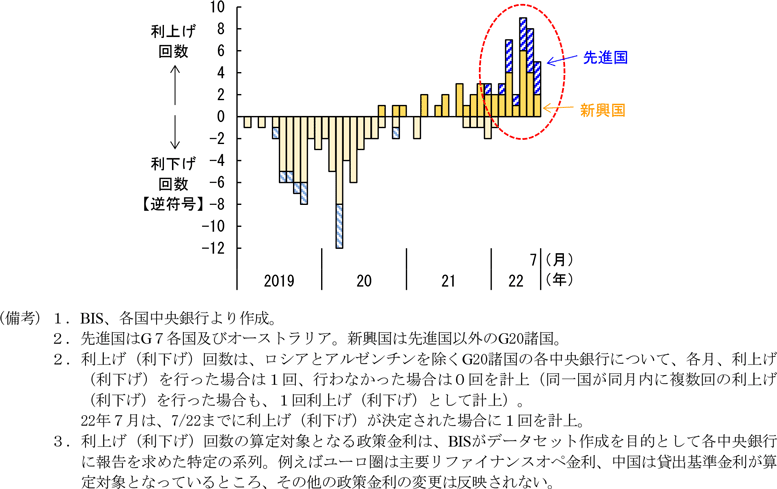
アメリカでは、消費者物価上昇率が約40年ぶりの高水準となる中、3月に利上げが開始された。連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長は、連邦公開市場委員会(FOMC)5月会合後の記者会見で、「金融政策は需要面に働きかけるものであり、供給面のショックに対しては真に効果を持たないため、我々が石油価格や国際商品価格、食料価格等に対して影響を与えることはできない」とした上で、「目下、労働市場や製品市場では供給を上回る需要が発生しており、こうした需要面に対して、我々の為すべきことがある」と述べ29、アメリカにおける物価上昇が、ウクライナ情勢の影響に加えて需要の過熱にも起因していることを強調した。
欧州中央銀行(ECB)のラガルド総裁も、2月に欧州議会で行われたスピーチで、「金融政策によって、ガスパイプラインを満たし、港湾の停滞を解消し、あるいはより多くの貨物ドライバーを訓練することはできない」と述べた30。ユーロ圏では、昨年末に実質GDPが感染拡大前の水準を上回った後、春以降はオミクロン株による感染再拡大も抑制的となったことで経済活動の再開が一層進展し、サービス部門を含め消費需要が一段と高まった31。さらに、失業率の持続的な低下により労働需給の引締まりが強まるなど、22年前半を通じて需要面の価格上昇圧力の高まりがみられる中32、7月に利上げが決定された。
IMF(2022c)による先進国のGDPギャップの推移及び今後の見通しをみると、利上げが進められている国では、GDPギャップが感染拡大以前の水準に近付き、あるいは上回っている傾向がうかがえる(第1-1-36図、第1-1-37表)。
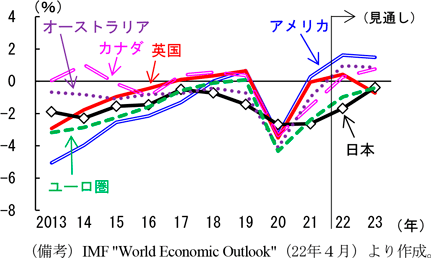
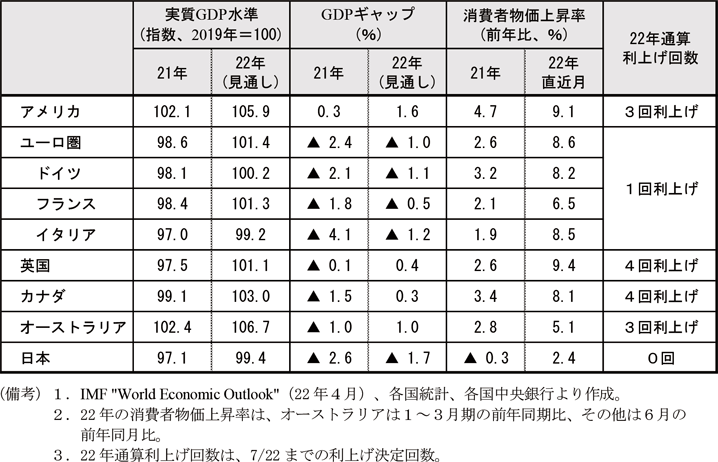
以下、欧米主要国の金融引締めの進展状況について具体的に確認する(第1-1-38表)。
(アメリカ)
FRBは、雇用の改善の進展と物価動向を踏まえ、21年11月から量的緩和の縮小(テーパリング)に着手していたが、当初の予定を早め、22年3月にテーパリングを完了すると、その後まもなくの開催となったFOMC3月会合で、感染拡大後初めてのフェデラル・ファンド・レート(FF金利)の誘導目標範囲の0.25%ポイント引上げを決定し、20年3月から続いていた事実上のゼロ金利政策(FF金利の誘導目標範囲:0.00~0.25%)の解除に踏み切った。続く5月会合では、ウクライナ情勢が更なる物価上昇圧力になっていることなどを背景に、2000年5月以来となる0.50%ポイントの利上げと、6月から保有資産の削減を開始することを決定し、パウエル議長が会合後の記者会見で、次回(6月)及び次々回(7月)の会合でも0.50%ポイントの利上げを行う可能性に言及した。迎えた6月会合では、5月の消費者物価上昇率が予想に反して再び上昇したことなどを受けて、利上げ幅を94年11月以来となる0.75%ポイントに拡大し、7月会合の見通しについても、パウエル議長は0.50%ポイント又は0.75%ポイントの利上げを行う可能性が高いと述べた。6月会合で示されたFOMC参加者の22年末の政策金利の見通しは、全参加者の中央値で3.4%、最低値でも3.1%と、7月会合後も速いペースで利上げが進められる想定となっているほか、保有資産の削減に関しても9月から上限額の引上げが予定されており、金融引締めは今後更に進展していく見込みとなっている。
(ユーロ圏)
ECBは、感染拡大以降、従来の資産購入プログラム(APP:Asset purchase programmes)と「パンデミック緊急購入プログラム」(PEPP:Pandemic emergency purchase programme)により資産購入を進めてきたところ、資金調達環境と物価上昇見通しに対する評価を踏まえ、21年第4四半期からPEPPによる購入を縮小し、22年3月をもって終了した。APPについては、PEPP終了に伴う変動を緩和するため、22年第2四半期に購入ペースが一時引き上げられたが、4月の政策理事会で第3四半期にはAPPによる購入も終了する方向性が示され、続く6月の理事会で、7月1日に終了することが正式に決定された。6月の理事会では、20年以降ゼロ水準での据え置きが続いている主要政策金利について、(i)次回(7月)の理事会で0.25%ポイント引き上げる方針であること、(ii)その次(9月)以降の理事会でも持続的に引き上げることを想定しており、中期インフレ見通しが現状維持か悪化となる場合には、大幅な利上げが適当と考えていることが示された。迎えた7月理事会では、インフレリスクの一層の高まりや、金融政策を効果的に波及させるための新たな仕組み(TPI:Transmission Protection Instrument)33の導入を受けて、利上げ幅が当初の予定から拡大され、0.50%ポイントの利上げが決定された。利上げは11年以来11年ぶりであり、これにより、14年に導入されたマイナス金利政策が終了した。
(英国)
イングランド銀行(BOE)は、21年12月の金融政策委員会で、労働市場の引締まりが続く中で、国内のコストや物価に対する圧力がより持続的になる兆しがあることを踏まえ、政策金利であるバンク・レートの引上げを決定したが、その後の会合でも相次いで引上げを決定し、6月会合での引上げによりバンク・レートは1.25%となった。また、2月会合以降、再投資の中止により保有資産の削減も進められている。今後については、6月会合時点で、持続的なインフレ圧力の兆候に対して警戒を怠らず、必要になれば強力な対応を取る方針が示された。8月会合以降には保有国債の売却についても議論される予定であるなど、年後半以降に更なる進展が見込まれる。
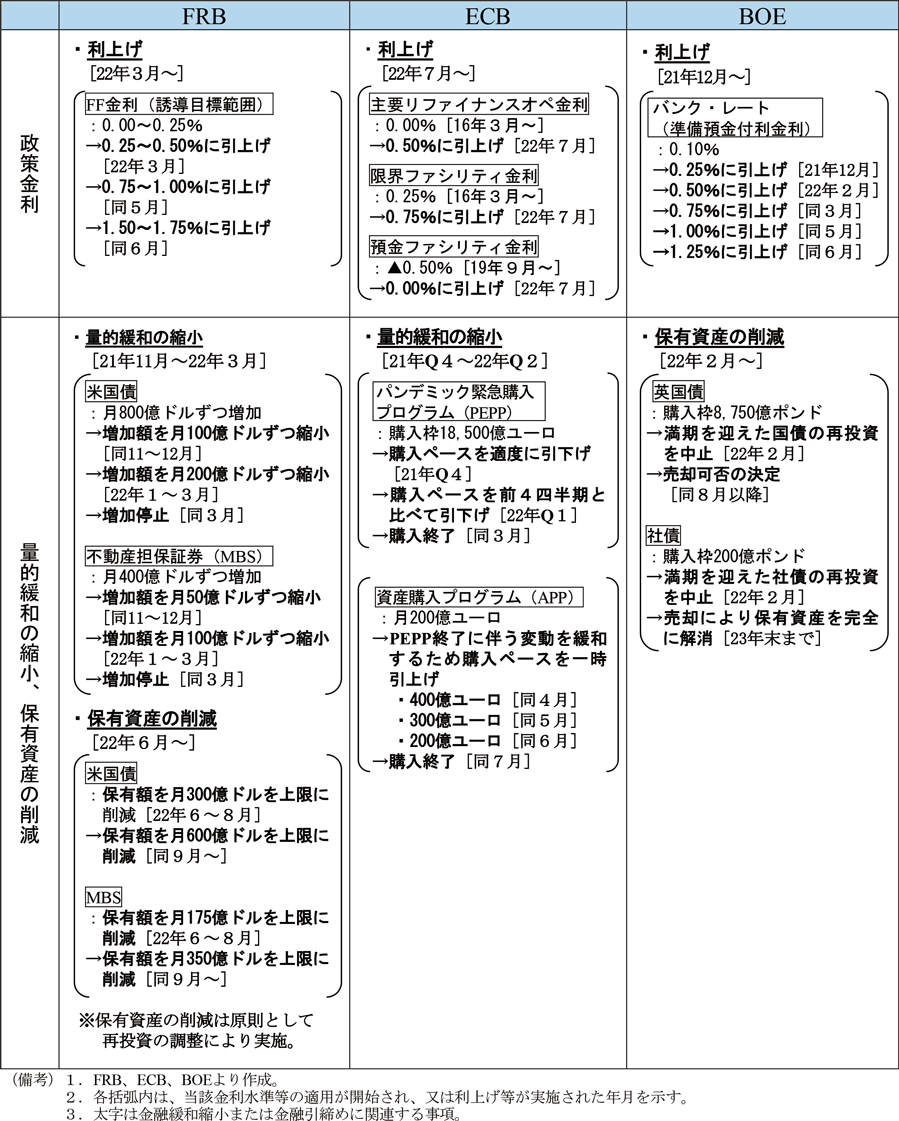
Box.アメリカにおける金融引締めのペース(前回引締めとの比較)
FRBは、22年3月にFF金利の誘導目標範囲の引上げを、同6月には保有資産の削減を開始し、本格的な金融引締めに着手した。今般の金融引締めの進め方について、パウエルFRB議長は従前から前回(2010年代後半)の引締め34よりも速いペースで進める方針を示唆していたところ、実際に5月会合までに決定された今般の引締めのスケジュール及び内容を前回と比較すると、前回よりも顕著に速いペースで引締めが進められていることが分かる(図1)。
具体的には、スケジュールの面では、前回はテーパリング終了から利上げ開始までに1年余り、そこから保有資産の削減開始まで更に2年弱の期間を設けていたが、今回はテーパリング終了から保有資産の削減開始まで約3か月と、格段に短い期間で進められている。また、保有資産の削減額についても、各月の米国債とMBSの削減上限額を比較すると、前回は月当たり100億ドルから削減を開始、その後同500億ドルまで削減上限を引上げとなっていたが、今回は同475億ドルから開始、3か月後には950億ドルに引上げ予定となっており、前回を大きく上回っている。
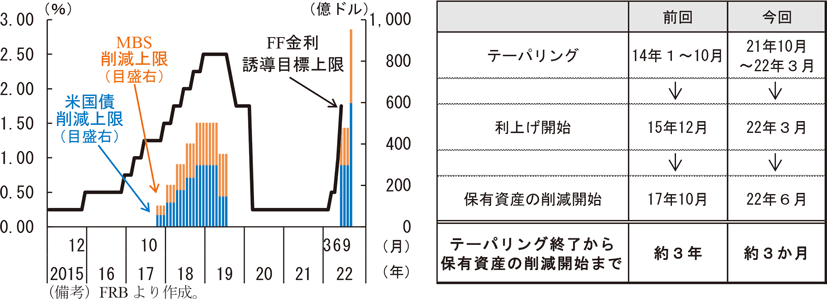
なお、感染拡大後の金融緩和により、5月末時点のFRBの保有資産は前回の引締め開始時の約2倍に拡大しているが、保有資産の削減上限(当初額)とFRBの保有資産全体額の比率でみても、前回(17年10月最終週)が0.22%、今回(22年5月最終週)が0.53%と、今回のほうが倍以上の削減比率となっている。
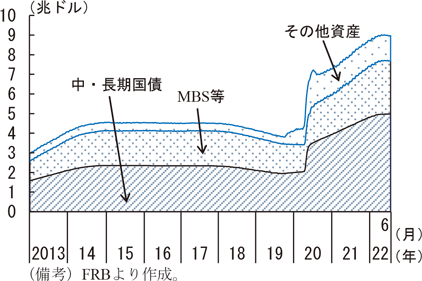
4.中国の厳格な防疫措置の動向と影響
(1)中国国内の動向
(「ゼロコロナ」の下で実現してきた感染者数の抑制と経済成長)
中国では、20年初頭の感染拡大以来、湖北省武漢市の都市封鎖を始めとして、厳格な移動制限や休業措置により感染者数を大幅に減少させ、ゼロに近い水準を保つことを理想としてきた(いわゆる「ゼロコロナ」政策)。こうした政策は、短期的には経済活動を大きく抑制するものの、一たび感染の抑え込みに成功すれば、生産・消費活動を平時に近い水準までV字回復させることが可能となり、中国経済は20年中にも尻上がりに成長率を高める「前低後高」型の成長となった。その後も感染者が出た団地をピンポイントで封鎖する等の措置を継続する中で、21年を通じて感染者数は低水準で推移し、21年通年の実質経済成長率は前年比8.1%増と、同年の目標「6%以上」を大きく上回った35。
(感染の再拡大と「ダイナミックゼロ」の方針による対処)
本年は春節の連休36以降、感染者数が徐々に増加した。全人代が閉幕した3月11日以降急増し、3月17日には3,507人に達した37。同日、習近平総書記は、「ダイナミックゼロ」の方針を堅持して速やかに感染拡大を食い止め、最小の代償で最大の防疫効果を実現し、経済社会への影響を最小限にすることを指示した。職責を果たさず感染を制御不能にした場合、関係者を直ちに調査・処分するとした38。
感染の急拡大を受け、各地の幹部が厳しい処分を受ける中、東北部の吉林省長春市、南部の広東省深セン市・東カン市、北京近郊の河北省廊坊市・唐山市等の都市が相次いで、市内全域・広域で厳格な移動制限・休業措置等39を導入した(第1-1-39表)。
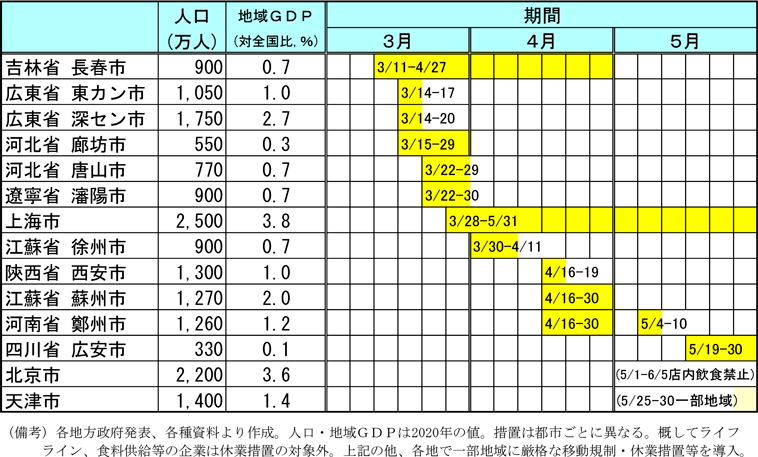
これらの都市は、人口面でも経済面でも大規模な都市が多く、マクロ経済やサプライチェーンへの影響が危惧される中で、防疫措置の運用にも変化が見られた。例えば深セン市・東カン市では、新規感染者数が完全なゼロになっていない段階から、「ダイナミックゼロ」を達成したとして、社会経済活動の回復に踏み切っており、厳格な移動制限は比較的短期間で終了した。他方長春市では、感染者数が高止まりしたため、厳格な移動制限の期間が長期化した。4月中旬以降は新規感染者が隔離環境のみから検出される「社会面ダイナミックゼロ40」を達成し、4月下旬に全域の封鎖を解除した。
3月下旬にかけて、上海市でも感染者数が無症状者を中心に拡大した。市当局は、上海市は国家経済発展の特別な地位を占める地域であるため、いわゆる都市封鎖には適さず、団地単位などピンポイントの封鎖管理にとどめる方針を強調していた。しかし感染者数の更なる急増を受けて方針転換を迫られ、4月1日からは全域での移動制限・休業措置を続けることとなった。4月11日からは、全市民PCR検査結果に基づき3区分で差別化した防疫措置を実施した41。
経済規模が中国最大で、物流の中心である上海市において、こうした厳しい措置が長期間続いたことは、中国経済に対する顕著な下押し圧力となった。4月の上海市の鉱工業生産は62.6%減と大幅なマイナスとなった(第1-1-40図)。また、上海港でコンテナ取扱量が大きく落ち込んだことで、各国との貿易が滞ることとなった(第1-1-41図)。
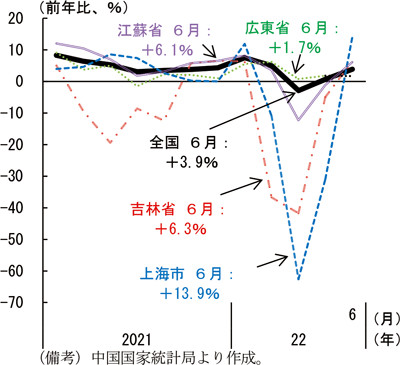
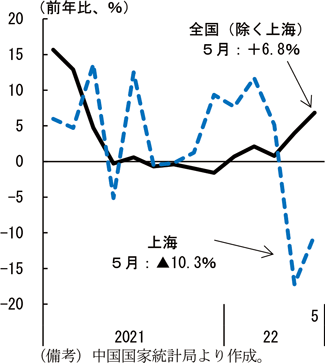
さらに、北京市でも、新規感染者の増加傾向を踏まえて、4月25日~30日に、ほぼ全市民を対象とした大規模なPCR検査を3度実施した。一部地域を管理区画、防疫区画に指定し、感染者の出た団地を個別に封鎖するに留められたが、対象地域は徐々に拡大した。5月1日からは市内全域で店内飲食が禁止となり、6月5日まで継続された。
こうした厳格な移動制限が課される中で、旅行も大幅に減少し、観光収入は、4月の清明節連休42は前年比30.9%減(19年比60.8%減)、5月の労働節連休43は前年比42.9%減(19年比66.0%減)、6月の端午節連休44は前年比12.2%減(19年比34.4%減)となった。
(景気刺激策の導入)
本年は、昨年来の景気の下押し圧力45に直面する中で、安定成長に向けて年初から景気下支え策が活発に打ち出されていたが、感染急拡大により各地の封鎖措置が長期化する事態を受けて、4月以降、政府各部門・各地方はさらに頻度を高め、様々な景気刺激策を導入した(第1-1-42表)。5月25日に李克強総理は、「3月、特に4月以来、雇用、工業生産、電力消費、貨物輸送等の指標が顕著に低下しており、一部方面での困難は、20年の感染症の衝撃の際に比べても一定程度大きい」と危機感を示した。5月31日、国務院は「経済安定政策パッケージ(6分野33項目の措置)」を発表した(第1-1-43表)。
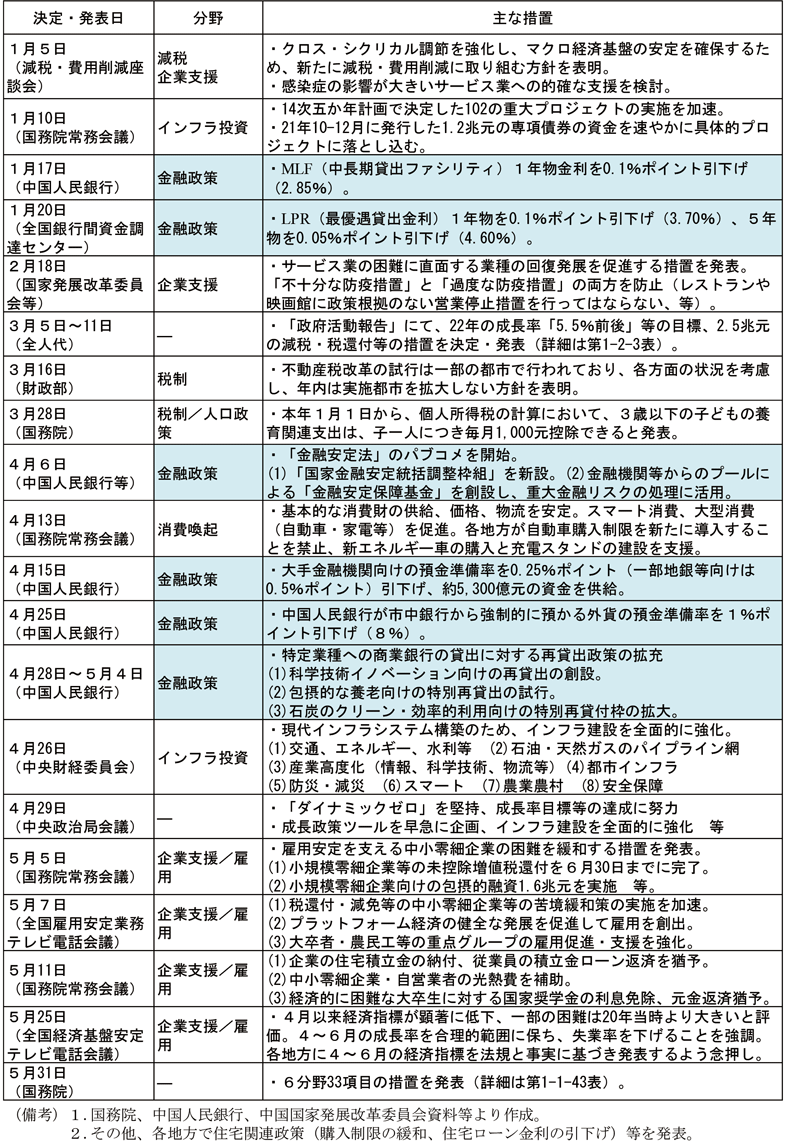
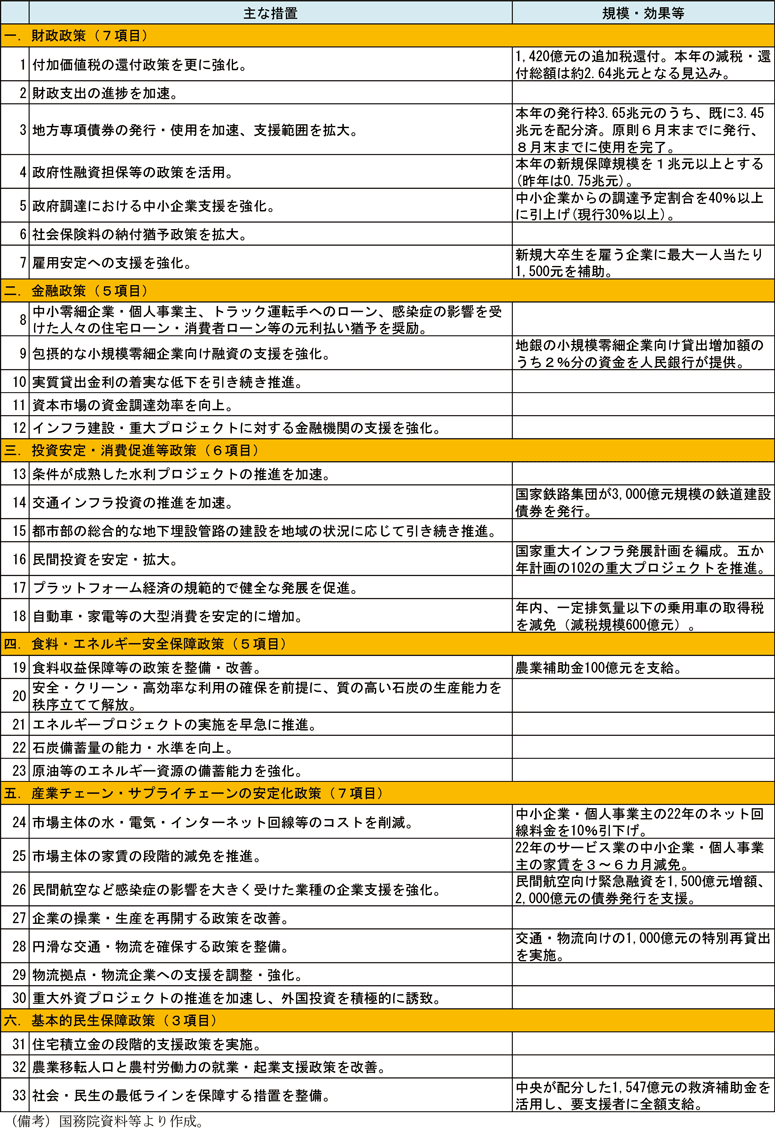
(中国経済が直面する試練)
本年の中国経済は、昨年までとは異なり、ゼロコロナの達成が著しく困難な感染再拡大の試練に直面し、封鎖措置を長期化させつつ景気下支え策を打ち出すという、言わばブレーキとアクセルを同時に踏まざるを得ない状況になったものと整理される。本年感染が広がったオミクロン株は、その感染力の高さから、都市封鎖ほどの厳しい措置によっても感染の完全な収束が困難であり、短期間経済の痛みを甘受してもメリットがあるという前提が成立しづらくなっている。上海市は、6月1日から一部のリスク地域を除いて外出制限を解除し、正常な社会経済活動の回復を開始したが、封鎖期間は2か月以上に及んだ。また、5月下旬には四川省広安市や天津市の一部地域(和平区)が封鎖されるなど、地域的な広がりもみられている。さらに、短期間で封鎖を解除した都市では、感染が再拡大し封鎖措置が改めて導入される例も出ている46。中国経済の先行きについては、各種政策の効果もあり、持ち直しに向かうことが期待されるが、当面は一部地方での経済活動の抑制の影響が残ると見込まれる。
(2)中国国外に影響が波及する可能性
中国は、経済規模がアメリカに次ぐ2位の国であり、世界の工場及び市場として、各国経済と活発な貿易取引を行っている。厳格な防疫対策が、上海市のような国際貿易都市で約2か月に渡って実施されたことは、国際サプライチェーンを通じて、各国にとっても影響が生じ得るものと考えられる。以下では、便宜的に上海市を例に挙げつつ、短期的にみられた事象や、都市封鎖の解除後にも継続し得る中長期的な中国経済への影響が、各国に波及する可能性について、その経路ごとに整理を試みる。
(i)短期的影響
(1)市民が外出できない(買物に行けない)ことにより、中国では消費が減速する。各国では輸出受注の減少や輸出・生産が減速する。上海市の場合、特に選択的消費、耐久財への影響が大きく、同市の4月の新車販売台数はゼロであった47。これは中国での輸入需要の減少として波及し、各国では中国向けの輸出金額の減少がみられ、例えば、韓国では4月に前年同月比3.4%減(3月は16.6%増)、台湾では5月に同4.0%減(4月は12.3%増)とマイナスに転じた。
(2)工場が閉鎖することにより、中国の生産が減速する。部品・製品の輸出先国では、中国産の部品・製品の供給量が減少する。中国での輸入需要が減少することで、各国では輸出・生産が減速する。各国で中国製品の供給・販売が減少することから、各国の消費を下押しする影響も生じ得る。上海市の場合、同市の鉱工業生産は4月は前年同月比62.6%減(全国では2.9%減)、5月は30.9%減(全国0.7%増)となった。上海市の封鎖期間に当たる4~5月には、各国で工場の稼働率低下、短期間操業停止となる事例が報告された48。
(3)トラック配送の目詰まりにより、市外でも生産が停滞する。各国に対しては、上記(2)と同様に波及し得る。上海市の場合、同市近隣の江蘇省でも、鉱工業生産が4月は前年同月比12.3%減、5月は1.1%減となった。
(4)港の海運の目詰まりにより、中国への輸出、中国からの輸入が停滞する。各国に対しては、上記(2)(3)と同様に波及し得る。上海市の場合、上海港のコンテナ取扱量は4月は前年同月比17.2%減、5月は10.3%減となった。
(ii)中期的影響
(1)小規模店舗等が休業、(半)閉店状態が一定期間継続することで、労働需要の減少が継続し得る。上海市の場合、6月1日から、一部のリスク地域を除き外出制限が解除されたものの、約2か月に及ぶ封鎖を経て、店舗の営業再開ペースは緩慢な状況とされている。
(2)上記(ii)(1)を受け、(半)失業者が一時的に増加し、一定期間継続し得る。所得・雇用環境が悪化すれば、消費は中期的に下押しされ得る。上海市の場合、全国都市部調査失業率は4月は6.1%(うち若年(16~24歳)は18.2%)5月は5.9%(うち若年は18.4%)となった。
(3)上記(i)(1)や(ii)(2)等を背景に、一部地域から広域で住宅・不動産開発需要が減少すれば、住宅価格が下落する。上海市の場合、全国主要70都市平均住宅価格は4月は前月比0.3%下落、5月は同0.2%下落となった。
上記(ii)で指摘した影響が実際に生じ得るかについては、今後更に確認が必要である。
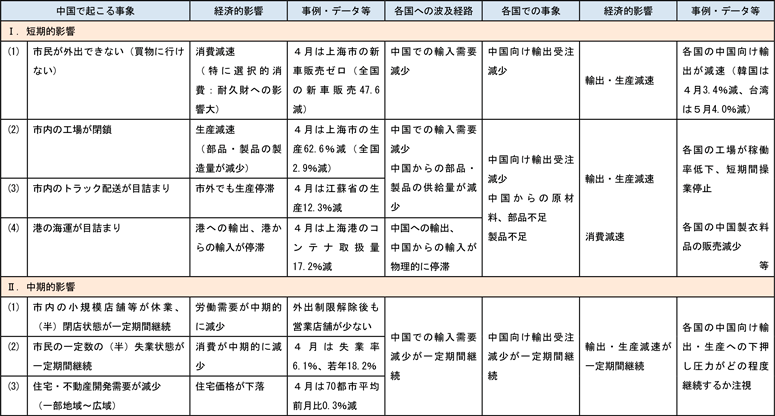
中国との貿易関係が密接な国では、上記のような影響を受けやすい可能性がある(第1-1-45図、第1-1-46図)。先に見たとおり、韓国や台湾においては、月次の中国向け輸出金額がマイナスに転じた。中国からの輸入額比率の高いベトナムにおいても、中国からの原材料輸入が滞ったことにより、衣料品製造工場の一時操業停止等の動きが生じている。上海市の外出制限は6月1日に解除され、生産、物流面の正常な秩序の回復が進められているところであるが、各工場の稼働率の回復や物流の正常化、各国への部品・製品の十分な供給にはなお一定の期間を要し、影響が残る可能性がある。
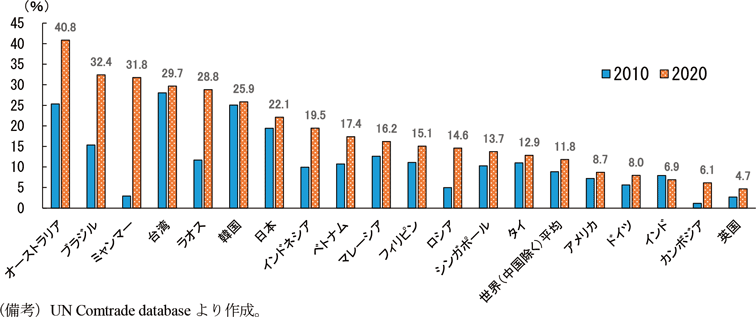
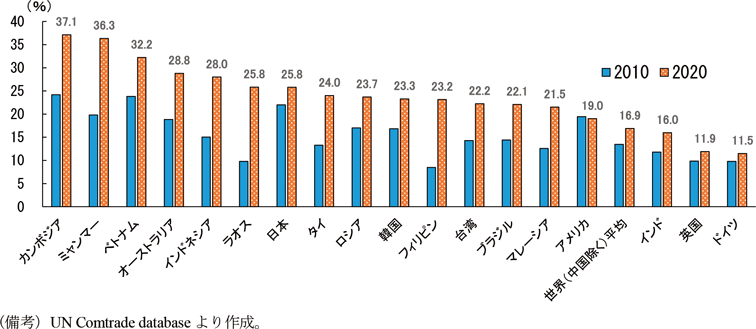
以上では、中国における都市封鎖が各国にもたらし得る影響の内、主に生産、物流、貿易面に焦点を当てたが、国際商品市況の変動を通じた物価面の影響も発生し得る。特に上海市の封鎖期間中には、中国経済の減速見通しが国際商品市場の下押し圧力となったが、6月1日に上海市が一部リスク地域を除いて外出制限を解除し、中国政府としても景気下支え策を相次いで発表したことも背景に、6月上旬には原油価格は上昇傾向に転じた。中国経済の減速懸念が緩和されれば、前項で議論したウクライナ情勢による国際商品市況の高騰を加速させる可能性も考えられ、引き続き注視が必要である。
5.世界経済の先行き
22年前半の世界経済は、持ち直しが継続する一方で、物価上昇の進行やその下での金融政策の進展、ウクライナ情勢や中国の防疫措置の今後の不透明感等を背景に、先行きの不確実性が高まっている。本項では、先行きの不確実性が示唆される経済指標を概観した上で、主要国際機関による見通しを示し、最後に今後の世界経済の主な下方リスクを整理する。
(1)先行きの不確実性の高まり
(景況感の低下)
欧米では、景気の持ち直しが続く一方で、ウクライナ情勢や中国の厳格な防疫措置、物価上昇の進行等を背景に、消費者マインドや製造業を中心とした企業の景況感の低下が続いている。消費者マインドについては、アメリカ、ユーロ圏ともに21年半ば以降の低下傾向が22年前半も続いており、特にユーロ圏では、ロシアのウクライナ侵攻開始後に大幅な低下がみられた(第1-1-47図)。
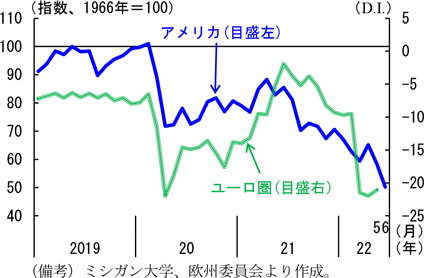
企業の景況感は、製造業については、21年下旬から22年初頭にかけてアメリカ、ユーロ圏ともおおむね横ばいで推移していたものが、22年2月以降それぞれ低下傾向となっている(第1-1-48)。非製造業は、アメリカでは21年後半以降低下傾向が続き、ユーロ圏では感染症の影響が緩和される中で年初から春頃にかけては上昇がみられたが、足下では低下に転じている(第1-1-49図)。22年前半の低下傾向が顕著な製造業について、供給面の認識に係る個別指数の動向をみると、いずれも22年に入ってから、仕入価格指数の水準が高まるとともに、入荷遅延指数の改善の足踏みがみられている。昨年来の世界同時的な景気回復の影響に加えて、ロシアによるウクライナ侵略の長期化や中国の厳格な防疫措置が、グローバル・サプライチェーンの新たな制約要因となっている可能性がうかがえる(第1-1-50図)。
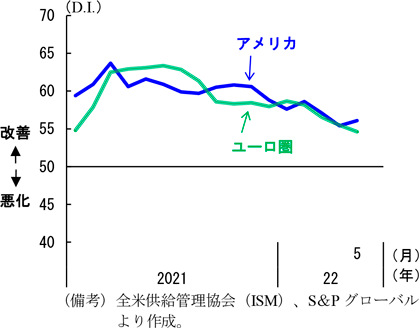
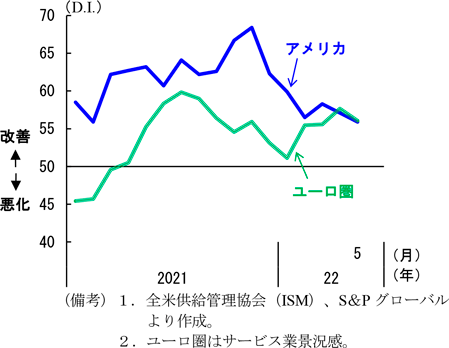
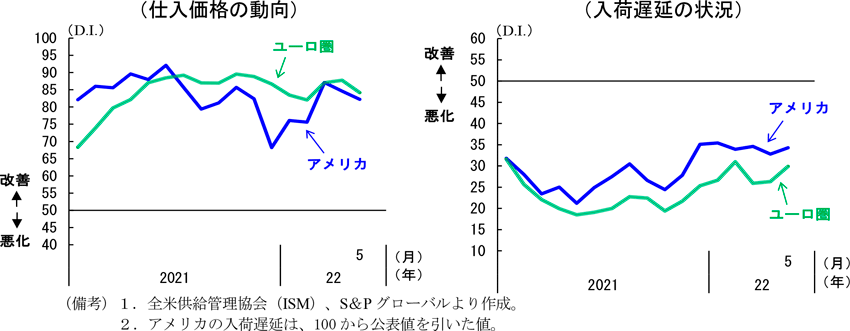
(国際貿易や生産活動の鈍化)
20年後半以降、世界全体の財貿易や生産活動は感染拡大前の水準を上回って拡大が続いていたが、ウクライナ情勢や中国の防疫措置等を背景に、22年前半はいずれも鈍化がみられている。まず、世界の財貿易量をみると、21年10月から12月にかけて一段と増加した後、22年前半は依然として感染拡大前を上回るものの、緩やかに水準を下げてきている(第1-1-51図)。世界の鉱工業生産については、22年2月まで増加傾向が続いていたが、3月に反転し、4月も減少が続いた(第1-1-52図)。5月には中国の防疫措置の一部緩和も背景に、それぞれ増加がみられた。
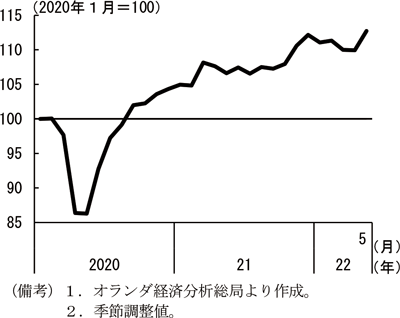
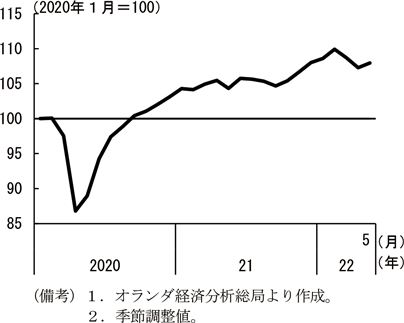
国際輸送コストを表すバルチック指数の動向をみると、海運指数は、21年秋頃をピークに22年初にかけて水準を大きく下げていたが、2月に上昇傾向に転じ、5月にかけて再び水準が高まった(第1-1-53図(1))。空運指数は、21年後半に一段と上昇した後、22年前半を通じて高水準で推移している(第1-1-53図(2))。輸送コストの上昇は、貿易量の下押し要因となり得るほか、貿易財への価格転嫁が進むことを通じて、各国の物価上昇の追加圧力となることも懸念される。
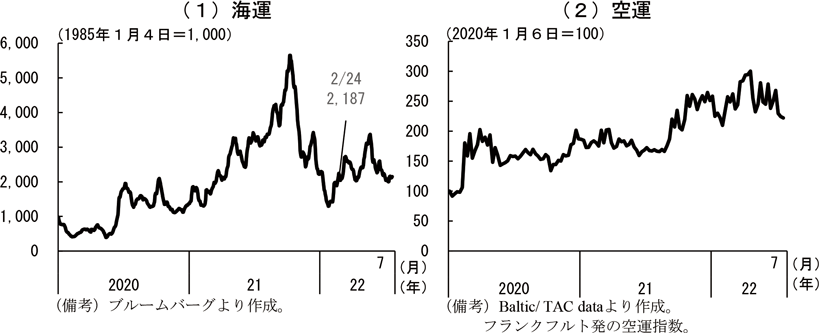
国際的な景気動向を反映するグローバルPMIをみると、四半期データのある先進国のGDP成長率と比較した場合、生産指数(製造業・非製造業)と新規輸出受注指数(製造業)の動向は一致、または先行する傾向がみられ、過去の景気悪化局面(08~09年の国際金融危機、20年のコロナ禍)においても同様であった(第1-1-54図)。22年3月以降、新規輸出受注指数は4か月連続で分岐点の50を下回って推移しており、貿易・景気の拡大テンポの減速が示唆されるところ、今後の動向に注視が必要である。
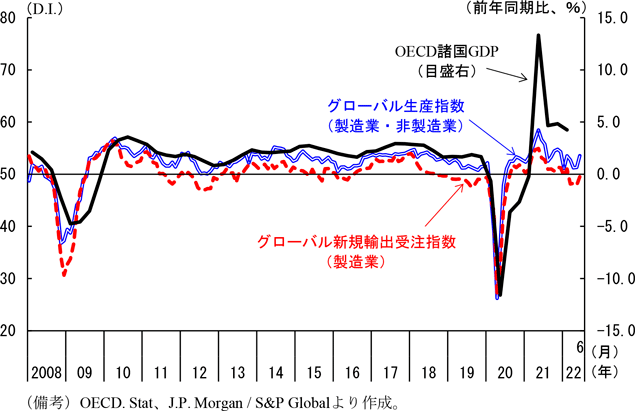
(金融資本市場の変動)
こうした世界経済の先行きの不確実性の高まり等も背景に、22年前半の金融資本市場は不安定な動きを示している。主要国の株価をみると、21年はアメリカ(NYダウ)、欧州(ドイツDAX)とも緩やかな上昇傾向で推移していたが、2月にウクライナ情勢の緊迫化がみられるとそれぞれ大きく下落し、3月以降も物価上昇の進展、さらにアメリカでは過去の例や当初の想定より速いペースで金融引締めが進められることなどが意識され、不安定な値動きとなっている(第1-1-55図)。また、市場のボラティリティを表すVIX指数49をみると、ロシアがウクライナ侵攻を開始した2月下旬に過去1年で最も高い水準となり、その後も2月下旬の水準には至らないものの、平均的な水準の上昇傾向がみられるなど、金融資本市場における変動の高まりがうかがえる(第1-1-56図)。
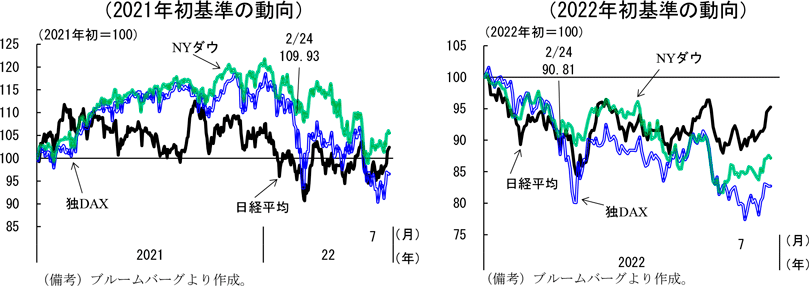
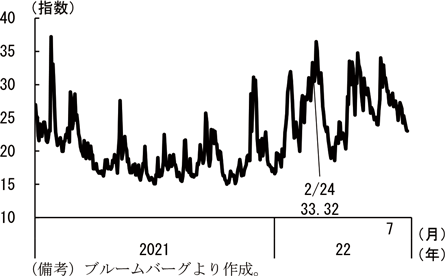
(2)主要国際機関による見通し
(経済成長率見通し)
22年後半以降の世界経済及び各国経済について、国際機関の見通しをみると、今後も持ち直しが続くことが見込まれているものの、ウクライナ情勢等を受けて、世界全体及び多くの国で従来の見通しから引下げが行われている。4月に公表されたIMF(2022c)、6月に公表されたOECD(2022)では、ウクライナ情勢の緊迫化等を受けて、それぞれロシアのウクライナ侵攻前に公表された前回見通し(IMF:1月、OECD:21年12月)から下方修正となった(第1-1-57表、第1-1-58表)。さらに、7月に公表されたIMF(2022d)では、(i)厳格な防疫措置の影響による中国経済の減速、(ii)主要中央銀行が物価上昇を抑制するために速いペースで利上げを進めるとの観測を背景とした金融環境のタイト化、(iii)ウクライナ情勢の影響の波及等を踏まえ、4月見通しから一段と下方修正となった50。この結果、IMF、OECDの最新の見通しによる22年の世界全体の成長率は3%台と、感染拡大前とおおむね同程度となっている51。なお、IMF(2022d)は、世界経済のリスクは下方に偏っていると指摘している52。
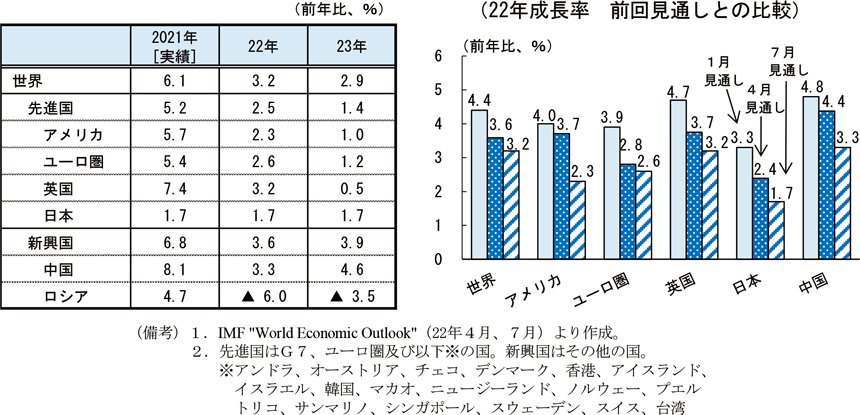
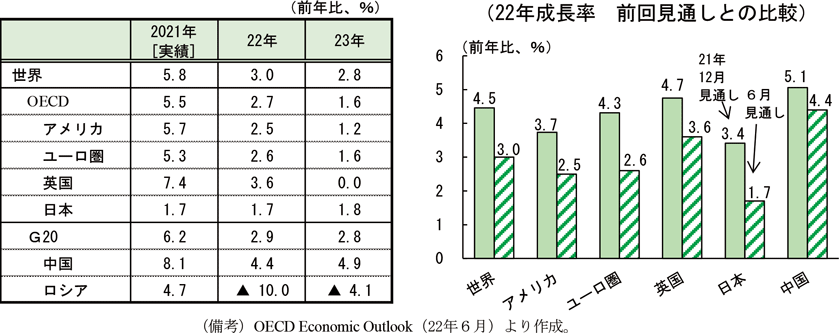
(物価上昇率見通し)
22年の物価上昇率は、IMF(2022c)、OECD(2022)のそれぞれにおいて、国際商品市況の高騰等を背景にウクライナ侵攻前の見通しが上方修正され、IMF(2022d)でも、食料・エネルギー価格の上昇等53を受けて、欧州諸国を中心に一段の上方修正となった(第1-1-59表、第1-1-60表)。23年は、全体的に伸びが緩やかになる見通しとなっているが、22年の高い物価上昇見通しの影響で、23年の上昇率が抑制されている側面もあると考えられるほか、各国際機関も種々の不確実性を指摘している。OECD(2022)は、エネルギー価格のピークが23年初と見込まれること、サプライチェーンの混乱が徐々に解消に向かうこと、需要の拡大が和らいでいることを挙げ、23年には多くの国で物価上昇が和らぐとする一方、生産者物価を通じた物価上昇圧力の持続を明白なリスクとして指摘している54。IMF(2022d)は、金融引締めやエネルギー価格の低下により23年は物価上昇率が抑制され、24年末には感染拡大前の水準まで低下するとの見通しをベースラインとする一方で、ウクライナ情勢による更なる供給ショックや労働市場のひっ迫状況次第で、物価上昇率が高止まりし、長期的なインフレ期待が高まり得るとしている55。
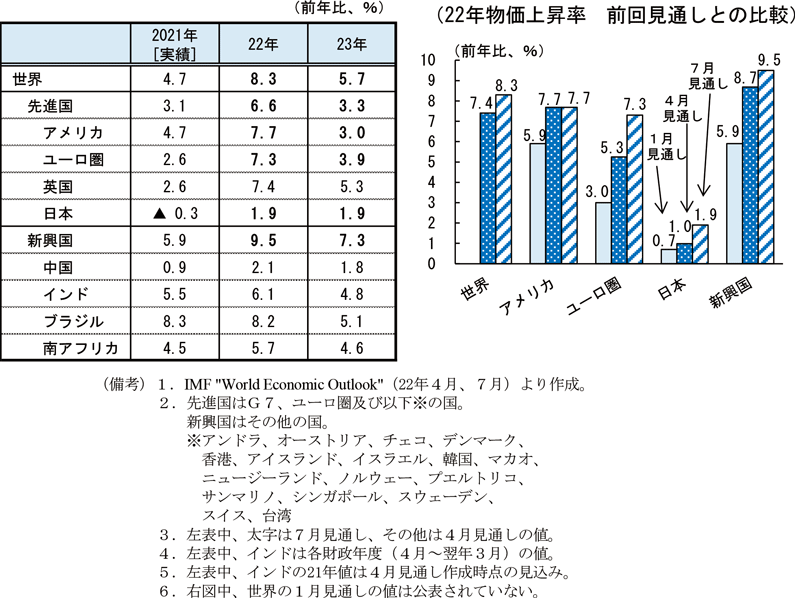
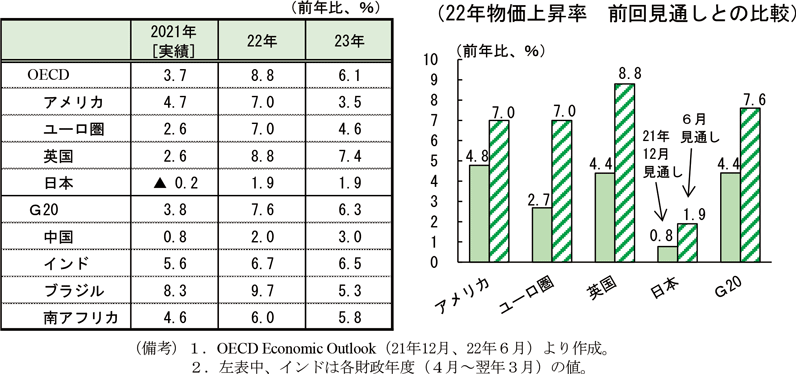
(財政見通し)
各国の財政収支と政府債務残高をみると、21年は先進国、新興国を問わず多くの国で、感染拡大下での大規模な財政支援を縮小したことに加え、経済の回復を反映して財政収支が改善し、債務残高も対GDP比で増加が抑えられている56。IMF(2022a)では、22年以降も多くの国で財政面の改善が見込まれている(第1-1-61図、第1-1-62図)。他方、先述した欧州各国を含め、財政支出を伴う物価高騰対策やウクライナからの避難民への対応策及び防衛費の増額等の影響が大きい国では、改善が見通しより遅れる可能性もある。なお、21年3月に欧州委員会は、コロナ禍を契機に導入した安定・成長協定の一般免責条項57の解除について、EUないしユーロ圏経済がコロナ禍以前の水準に戻ったか否かの総合的な判断によるものとした。22年春のヨーロピアン・セメスター58では、ウクライナでの軍事行動やエネルギー価格高騰、サプライチェーンの混乱の継続下で、EUないしユーロ圏経済は未だ正常化していないことを指摘し、23年も引き続き一般免責条項を適用することとした。
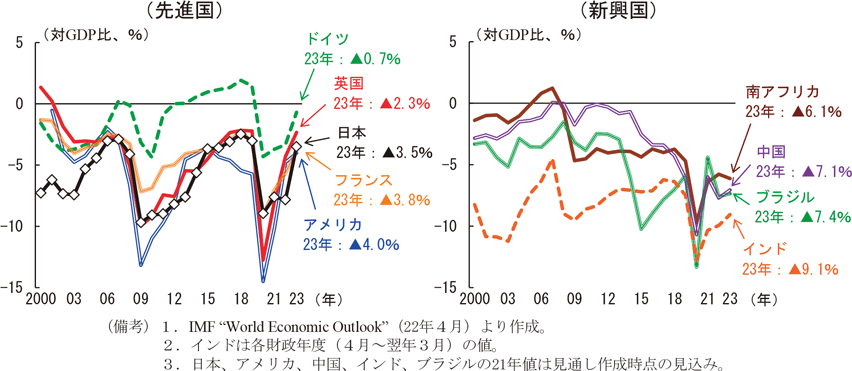
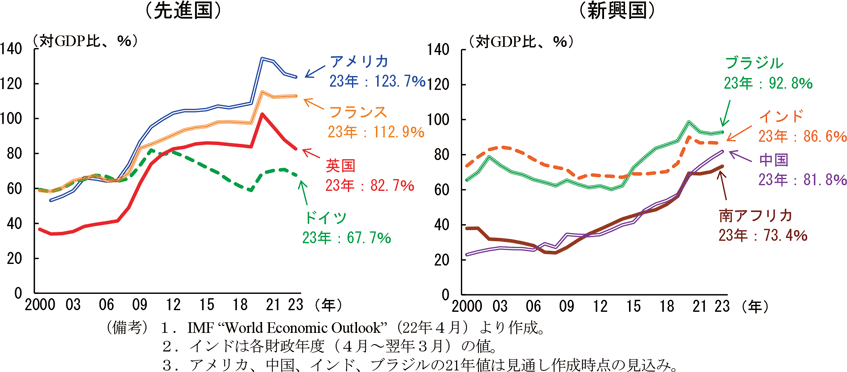
(3)世界経済の主な下方リスク(総括)
(ロシアによるウクライナ侵略の長期化)
22年7月現在も、ロシアによる侵略行為が続くなど、ウクライナ情勢は依然緊迫した状態にある。先述のとおり、ウクライナ情勢は、両国経済にとどまらず、世界経済全体に影響を及ぼしている。具体的には、両国はこれまで経済規模や貿易総額では世界に占める割合はそれほど大きくなかった一方、世界のエネルギーや穀物等の輸出において重要な位置を占めていたことから、2月下旬以降、両国が大きなシェアを有する国際商品の市況が高水準で推移し、各国において物価上昇や景況感の低下等の影響が生じている。欧米を中心に、ロシアへの制裁措置としてエネルギーを含む複数のロシア産品の輸入を制限するとともに、代替供給源の確保や中長期的なエネルギー戦略の見直しを進める動きがみられており、今後、各国経済におけるロシアの位置は、これまでと異なるものとなっていく可能性がある。しかし、これまでロシアへの依存度が相対的に高かった欧州や非資源国を中心に、代替供給の確保等には一定の期間を要するとみられる。このため、ロシアのウクライナ侵略が今後も続く場合には、国際商品市況や供給面の制約が、原材料価格や各国の物価動向に及ぼす影響を注視する必要がある。加えて、ウクライナ情勢等を背景に、2月から3月にかけて各国の株価が総じて下落する局面がみられたが、金融資本市場の変動は、短期間で世界全体に波及することがあり、その変動が特に大きい場合には、実体経済にも影響を及ぼす可能性がある。このため、経済の不確実性の高まり等を背景とした株価、市場金利等の変動についても、引き続き注視する必要がある。
(中国の防疫措置の動向)
上海市は6月1日に外出制限を解除し、社会経済活動の正常化を開始したが、6月末現在、感染者の発生した一部地域では引き続き厳しい移動制限等の措置が続いている。封鎖の解除後にも、市中感染が少数でも発生した場合に封鎖が再度導入される可能性がある。また、5月には、北京や天津の一部地域が封鎖されたところ、今後上海以外の都市でも大規模な封鎖が起こるリスクがある。感染力の高い変異株と、厳格な防疫対策を維持する方針の下で、中国の各都市は、急きょブレーキを踏まざるを得なくなる可能性があり、グローバル・サプライチェーンを通じた影響等に注視が必要である。
(金融引締めに伴う影響)
景気の持ち直しの進展やウクライナ情勢の影響等による物価上昇の進行等を受けて、欧米を含む各国で、金融緩和の縮小や金融引締めが一段と進展している。一般に、金融引締めは金融資本市場における調整を通じて、当該国の経済活動や労働市場における需要の抑制に作用する。これまでのところ、金融引締めは各国の経済状況等を勘案して決定されるとともに、特に欧米では引締めのペース等について調整の余地を持って進められている。しかし、今後、物価上昇率が高止まり又は一段と上昇するなどして、金融引締めのペースが想定より速まり、あるいは利上げ後の金利水準が高くなる場合には、各国経済の需要面への影響が大きくなる可能性がある。
また、特に先進国の金融引締めは、金融市場における調整を通じて新興国経済に影響を及ぼす可能性がある。この点、3月頃から非資源国では通貨の減価や資金流出の傾向がみられるものの、足下で新興国経済のファンダメンタルズは総じて安定した状態となっている59。しかし、先進国が金融引締めのペースを速め、あるいはより高い水準まで利上げを行うこととなった場合には、新興国経済への影響も大きくなる可能性がある。
(新興国や途上国等での財政状況の悪化)
国際金融市場の引締まりと、それに伴う海外からの資金調達コストの上昇は、対外債務残高が大きい新興国・途上国等にとって財政収支の悪化要因となり得る。これらの国々の多くで、コロナ禍で政府債務残高が上昇し脆弱性が高まっていたが、今後、物価上昇率が高止まりし、同時に景気持ち直しのペースが減速する状況になれば、財政基盤が相対的に強固でない新興国・途上国では、既に悪化している財政状況の改善の遅れや一層の悪化につながる可能性がある。加えて、物価高騰を受けた追加的な財政支出や、ウクライナからの避難民への対応等により、各国の財政状況は不確実性を伴うものとなっている。一部の新興国や途上国での利払い費の増大を通じた将来的な財政政策の余地の狭まり等、財政状況の不確実性が金融資本市場に与える影響を含めて、注視が必要である。
コラム1:主要国におけるコロナ禍前を上回る家計貯蓄の動向
コロナ禍における消費機会の減少等を受けて、先進国を中心に家計貯蓄の急増がみられてきた。ウクライナ情勢等による物価上昇の持続的な進行の下で、実質所得の目減りも懸念される欧米等では、こうした家計貯蓄が消費の下支えとなるか否かが注目される60。本項ではまず、20年1~3月期以降の家計貯蓄(家計可処分所得と家計最終消費支出の差)の19年同期差を、コロナ禍での消費減少等を受けた家計貯蓄の増加分(貯蓄超過)と捉え、アメリカ、ユーロ圏、日本における最新の動向を確認する。次に、フローの貯蓄超過とストックの貯蓄超過の違いに注意しつつ、各国の家計の貯蓄超過の要因を分析する。最後に、各国の家計の状況を整理した上で、家計の貯蓄超過の要因の違いが各国経済にもたらす含意を考察する。
(1)家計の貯蓄超過の動向
図1は、アメリカ、ユーロ圏、日本について、各期の家計貯蓄額の19年同期差(以下「フローの貯蓄超過」という。)を折れ線、20年1~3月期を起点とした19年同期差の累計(以下「ストックの貯蓄超過」という。)を縦棒で示したものである。まず、フローの貯蓄超過の動向をみると、アメリカとユーロ圏では21年4~6月期以降プラス幅が縮小し、アメリカでは直近の22年1~3月期はマイナスとなった(貯蓄が19年同期を下回った)。日本は、21年1~3月期から7~9月期にかけてはおおむね一定のプラス幅で推移し、10~12月期はプラス幅が小さくなった。この結果、ストックの貯蓄超過は、アメリカは足下で減少に転じ、ユーロ圏は21年中盤以降増勢が収まってきている。日本は、7~9月期まで緩やかに増加した後、10~12月期は増加が抑制的となっている。なお、足下のストックの貯蓄超過をGDP比でみると、アメリカは11.3%、ユーロ圏は6.8%、日本は9.7%となっている。
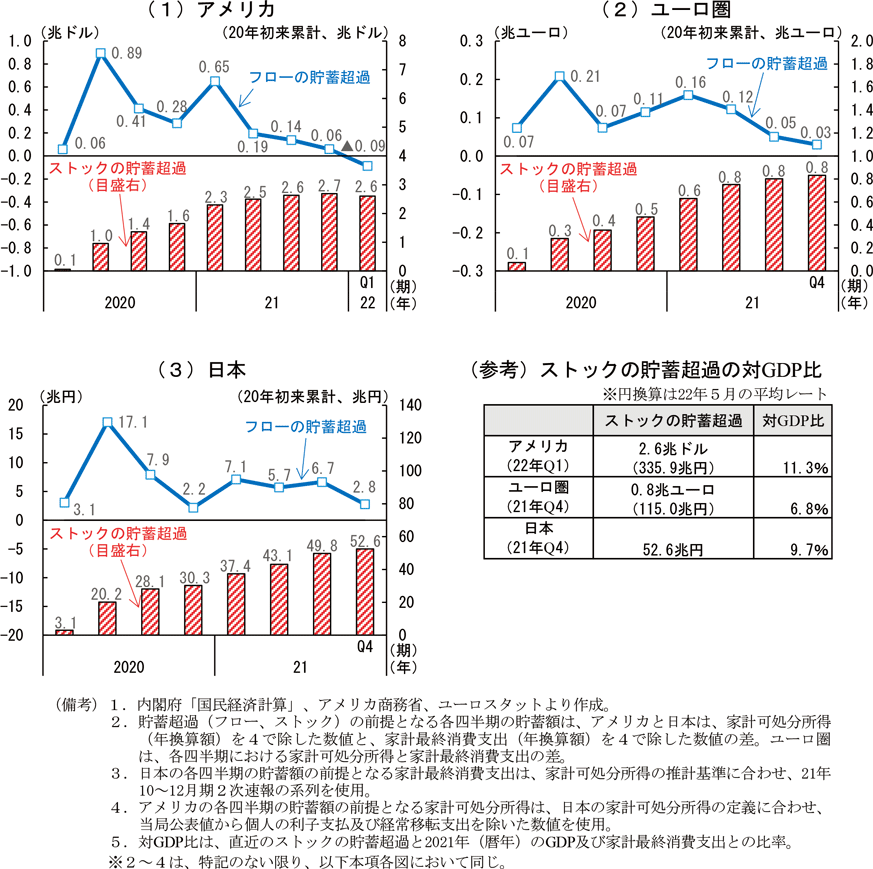
(2)家計の貯蓄超過の要因
IMF(2021)は、コロナ禍での各国の家計貯蓄急増の主な要因として、(i)感染拡大下での消費の減少と(ii)政府の財政支援による可処分所得の増加を挙げ、(i)は多くの国で共通して重要な役割を果たし、(ii)はアメリカにおいて特に大きな影響を与えたと指摘している。以下では、こうした指摘も踏まえつつ分析期間を延長し、各国の貯蓄超過(フロー、ストック)が消費減少と所得増加のいずれに起因しているかを確認する。
図2~4左は、先述の3か国・地域について、各期の消費支出と可処分所得(アメリカは内訳により表示)の19年同期差を、消費支出のみ逆符号に変えて示したもので、フローの貯蓄超過に対する消費減少と所得増加の寄与を金額ベースで表している。ここで、消費支出が19年同期と比べて増加している場合には、図では負の値をとり、フローの貯蓄超過は押し下げられる。図2~4右は、各図左で示した消費支出と可処分所得の19年同期差の20年初来累計額を示したもので、ストックの貯蓄超過に対する消費減少と所得増加の寄与を金額ベースで表している。以上を踏まえ、各国の貯蓄超過の要因を概観すると、アメリカ(図2)では、21年前半まではIMF(2021)が指摘するように現金給付等と失業手当がストックの貯蓄超過の主要因となっていた。しかし、同年後半以降は政府の財政支援の縮小を反映して、これらの寄与がフローでほとんどみられなくなり、代わって景気の持ち直しや賃金上昇等を背景とした雇用者報酬等の増加がストックの貯蓄超過への寄与を高めている。ストックの貯蓄超過に対する雇用者報酬等の寄与は、22年1~3月期で2.5兆ドルと、ストックの貯蓄超過そのものの金額(2.6兆ドル)に迫っている。一方、消費支出は、21年4~6月期以降ストックの貯蓄超過を押し下げるようになり、消費の持ち直しや物価上昇が続く中で押し下げ幅を拡大している。22年1~3月期にはストックの貯蓄超過を1.6兆ドル押し下げ、現金給付等と失業手当による増分(計1.7兆ドル)をほぼ相殺している。
ユーロ圏(図3)では、21年前半まではIMF(2021)が各国共通事項として指摘するように、消費支出減少がストックの貯蓄超過の主要因となっていた。しかし、21年後半になると、消費の持ち直しの進展や物価上昇を反映して、消費支出はフローの貯蓄超過を押し下げるようになった。足下のストックの貯蓄超過をみると、消費支出が0.6兆ユーロ、可処分所得が0.2兆ユーロと、依然として消費支出減少が主要因となっているが、このところは可処分所得の寄与が高まっている。
日本(図4)は、20年前半に消費支出減少と可処分所得増加の両面による貯蓄超過がみられた後、欧米と比較して消費の持ち直しが遅れていたことなどから、相対的に消費支出減少がストックの貯蓄超過に大きく寄与してきた。しかし、直近の21年10~12月期は、フローの貯蓄超過に対する消費支出減少の寄与が前期までと比較してやや小さくなった。これは、ベースラインである19年10~12月期の消費支出が消費増税の影響で抑制的であったこと61も影響しているが、前年(20年10~12月期)よりも消費減少の寄与が小さくなっている点、さらに可処分所得の増加の寄与が大きくなっている点は欧米と同様であり、今後、消費の持ち直しや雇用情勢の改善等がストックの貯蓄超過の動向に現れてくる可能性がある。
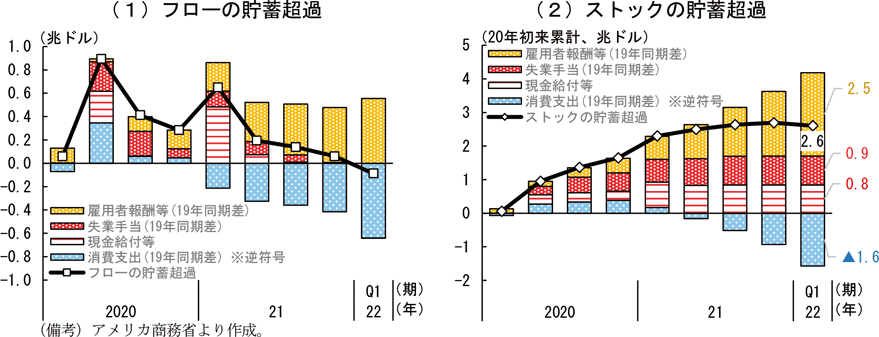
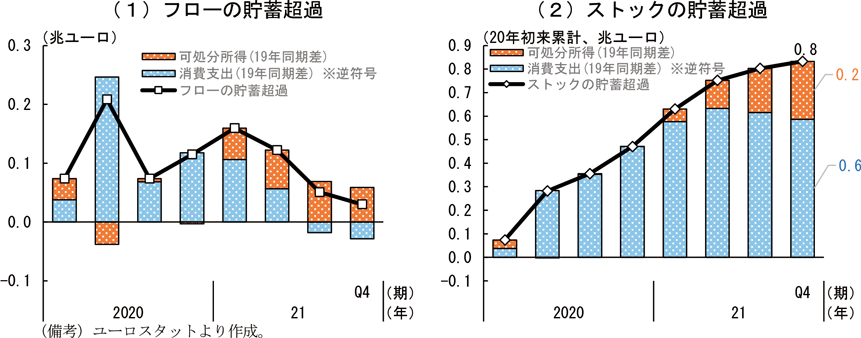
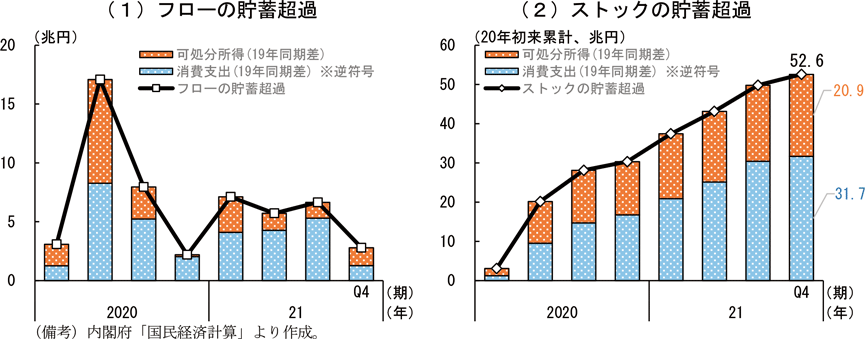
(3)家計の貯蓄超過の各国経済への含意
アメリカでは、22年1~3月期にストックの貯蓄超過が減少に転じた。ユーロ圏では、21年10~12月期時点でストックの貯蓄超過は増加が続いているが、消費要因の寄与の低下が続き、増勢は収まってきている。日本は、消費要因と所得要因の双方によりストックの貯蓄超過の増加が続いているが、直近の四半期では消費要因の影響が小さくなっており、今後増勢が和らいでくる可能性がある。以下では、各国の家計状況を整理した上で、ストックの貯蓄超過の要因に着目し、各国経済への含意と今後の見通しを考察する。
(各国の家計状況)
図5は、各国の四半期ベースの消費支出、可処分所得及び貯蓄の推移を示す。このうち消費支出は、物価上昇の影響を確認するため、名目ベースと実質ベースを示している。各国の動向を整理すると、アメリカでは、名目ベースの消費支出が顕著に増加する一方、可処分所得は足下おおむね横ばいとなっている。実質ベースの消費支出も増加が続いているが、21年後半以降、名目ベースとの差が拡大しており、物価上昇が名目ベースの消費支出を押し上げていることがうかがえる。つまり、アメリカでは、可処分所得がおおむね一定で、家計が物価上昇による消費支出負担の増大に直面する中でも、消費活動の水準(実質ベースの消費支出)の持ち直しが続いている。
ユーロ圏は、名目ベースの消費支出は増加、可処分所得は足下おおむね横ばい、消費支出の名目・実質差が拡大と、家計が直面している状況はアメリカとおおむね共通している。ただし、アメリカと異なり実質でみた消費活動の水準はこのところ持ち直しに足踏みがみられている。
日本は、21年以降をみると、7~9月期までは可処分所得がやや下向きに推移する中、名目ベースの消費支出は弱い動きとなった。10~12月期には、可処分所得が増加に転じ、消費支出も持ち直した。消費支出の名目・実質差は、21年はおおむね一定で、22年1~3月期に拡大した。以上をまとめると、日本は21年後半、欧米のような物価上昇による支出負担増がみられず、可処分所得が増加に向かう中で、家計の消費活動の水準も持ち直しに向かった。
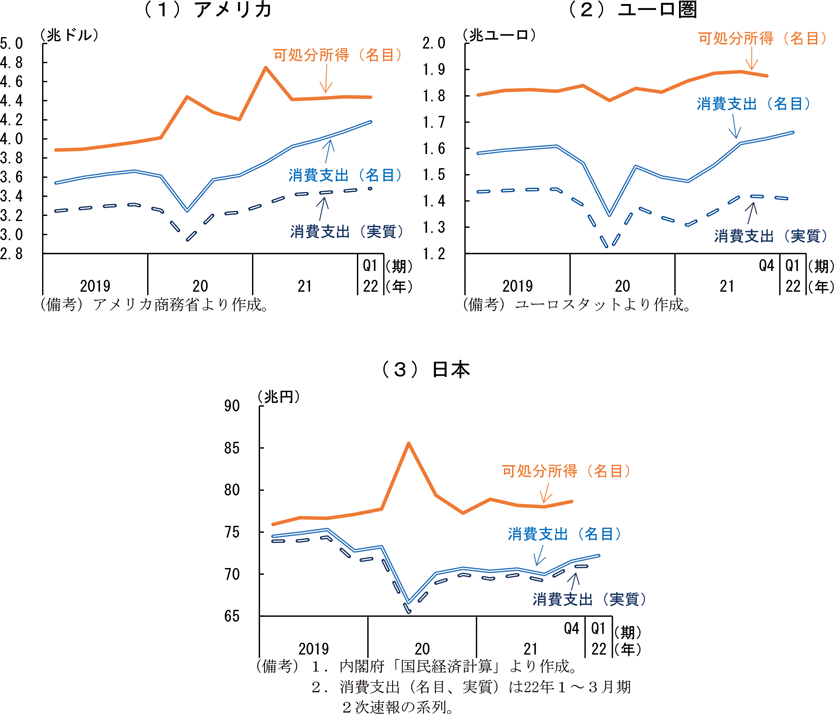
(家計の貯蓄超過の各国経済への含意)
上述のとおり、アメリカとユーロ圏の家計は、21年後半以降物価上昇による支出負担増に直面しているが、このうちストックの貯蓄超過が足下で減少しているアメリカでは消費の持ち直しが継続し、ストックの貯蓄超過の増加が続いているユーロ圏では消費の持ち直しに足踏みがみられている。コロナ禍からの景気の持ち直しの進展度合いや、物価上昇が生じている品目及びその程度の違いなど、消費動向の差異を生じる要因には様々なものが考えられるが、ここでは図2、3でみた両国のストックの貯蓄超過の要因の違いに着目し、貯蓄超過がアメリカの消費活動の下支えとなっている可能性や、ユーロ圏で下支え効果がアメリカに比べると限定的となっている可能性について、考え得る理由とともに考察する。
アメリカでは、21年後半以降のストックの貯蓄超過が、専ら可処分所得の増加(同年中盤頃までの政府の財政支援と、19年同期を上回って推移している雇用者報酬等)に起因している。可処分所得の増加により貯蓄が増えた場合、特定の支出を諦めることで貯蓄が増えた場合と比べれば、家計が一定の自由度を持って、その支出の時期や対象を決定できるとも考えられる。例えば、物価上昇により物品購入等に係る支出負担が増大し、手元の可処分所得が実質的に目減りした場合には、その目減り分を補てんする目的で支出される余地もあるものと考えられる。この点において、アメリカでは、ストックの貯蓄超過が足下の消費活動の下支えとなっている可能性がある。
一方、ユーロ圏の足下のストックの貯蓄超過は、大部分がコロナ禍での消費支出の減少に起因している。具体例としては、コロナ禍で当初予定していた旅行消費を取りやめ、使われずに手元に残った資金がこれに該当すると考えられる。仮に当該資金の使途として、将来の旅行消費を主に想定している場合には、可処分所得の増加によって得られた資金を充てる場合と比べて、当該資金を足下の物価上昇を受けた物品購入等の補てんに充てることは容易でない可能性がある62。このため、ともに物価上昇による支出負担増がみられる中でも、ユーロ圏ではアメリカと比較して、ストックの貯蓄超過の消費下支え効果が限定的となっている可能性がある。
(今後の見通し)
上でみたように、ストックの貯蓄超過が物価上昇による支出負担増の補てんに充てられるか否かは、貯蓄超過がどのような要因で発生し、蓄積されたかが影響する可能性がある。一方で、今後、物価上昇の進行により実質所得の目減りが続くとともに、生活必需品を含む広範な財・サービスに価格上昇が広がっていく場合には、その生じた要因によらず、ストックの貯蓄超過が消費の下支えとなっていく可能性もある。なお、ECB(2022)は、(i)物価上昇により貯蓄が目減りしていること、(ii)コロナ禍での貯蓄の増加は消費性向の低い高所得者や高齢者に集中してみられること、(iii)ウクライナ情勢による価格上昇はエネルギーや食料品にみられるが、これらはコロナ禍での貯蓄の増加が相対的に小さい低所得者において消費に対するシェアが高く、その影響が大きいことを挙げ、ユーロ圏においてコロナ禍で増加した貯蓄による消費の下支え効果は限定的になる可能性があるとしている。いずれにしても、本項の推計によるストックの貯蓄超過は各国のGDPの7~11%程度にも上ることから、その動向や各国経済への影響は、今後も注視が必要である。
コラム2:国際金融資本市場の動向と新興国経済
本節で述べたような世界的な不確実性の高まりを背景に、新興国をめぐる国際金融環境にも不安定な局面が散見されている。本コラムでは、ウクライナ情勢等を背景とする国際商品市況における資源価格高と世界的な金融引締めの流れを踏まえ、新興国のファンダメンタルズ(経済の基礎的条件)や新興国をめぐる国際金融環境の現状を確認する。その際、13年にみられた新興国の通貨安・資金流出入状況を参照しながら、新興国のファンダメンタルズについて、資源国と非資源国の違いを考慮しつつ63整理する。
(1)ファンダメンタルズ(経済の基礎的条件)64の状況
国際金融環境の健全性やショック耐性を検討する上で、対外支払能力に関連する観点から、経常収支や外貨準備高等がしばしば取り上げられ、また、その動向に関係するという観点から、財政収支や政府債務、インフレ率等が取り上げられる65。以下では、こうした指標から、最近の動向を確認する。その際、13年頃の新興国からの資金流出・通貨下落の動きの背景として、経常収支赤字の拡大等、ファンダメンタルズの弱さがあったことが指摘66されていることから、13年、コロナ禍前の19年、ウクライナ情勢下での最近の状況についてみる。
まず、経常収支および外貨準備高の動向を確認しよう。
同じ新興国であっても、資源国と非資源国では、国際的な資源価格の上昇がもたらす影響は異なる。エネルギーや食料等が豊富な資源国では、輸出する資源の価格が上昇すると、交易条件の改善・所得流入を通じて、経常収支の改善につながり、為替市場では自国通貨への需要増から通貨高圧力につながる。一方、非資源国(資源輸入国)は逆に経常収支の悪化と通貨安圧力が見込まれる。こうした経常収支の動向は、国際金融において支払い余力を示す外貨準備高に影響することになる。
コロナ禍前の19年第4四半期と直近の状況を比較すると、経常収支(対GDP比)については、資源国を中心に多くの国で黒字方向への変化もしくは横ばい程度と評価できる67(表1-1、表1-2)。また、13年と今回を比較した場合、経常収支は全体的に赤字幅が縮小している(図1)。
また、外貨準備高についても19年第4四半期と直近の状況とを比較すると複数国で増加し、目立って減少した国はみられない(表1-1、表1-2)。
次に、財政収支およびインフレ率の動向について確認する。なお、経常収支との関係では、財政収支が赤字化する場合には国内生産を上回る需要に対応するための輸入増につながり、インフレ率が上昇する場合には輸出競争力の低下から輸出減につながるという経路を通じて、経常収支が赤字化する方向に影響を与えることが考えられる。
財政収支(一般政府ベース、対GDP比)については、13年に比べて、今回は悪化している国が多い。インド、タイ、韓国等で財政赤字の拡大がみられる(図1)。これは、感染拡大を受けた財政支出を伴う支援策の実施等によると考えられる。加えて今後は、上述のような資源価格高騰への対応として、燃料等への補助金や減税措置、家計に対する支援策の実施を行う場合には、財政状況の悪化につながる懸念も指摘68されている。
インフレ率については、第1章第1節でみたように、G20の新興国は、先進国とともに上昇トレンドにあり、足下では、半分程度の国が7%以上の上昇率となっている。ウクライナ情勢を背景とする資源価格高によりインフレ懸念が強くなっている。
今回、新興国は、インフレ圧力への対応等のため、利上げを早いタイミングで進めてきた。この点は、13年とは対照的な状況となっている。具体的には、ブラジル(21年3月以降)、メキシコ(21年6月以降)、南アフリカ中央銀行(21年3月以降)等は、自国のインフレ動向に注意を払い、急激な政策金利の引上げにならないよう、段階的な引上げを進めてきた。
総じてみれば、新興国のファンダメンタルズは、経常収支や外貨準備高に着目した場合、13年との比較で今回は現在のところおおむね改善している。コロナ禍前の19年との比較でも今回は現在のところ大きな変化はみられていない。その中で、財政赤字や政府債務については、13年やコロナ禍前より悪化がみられている。今後のファンダメンタルズについては引き続き注視が必要と考えられる。
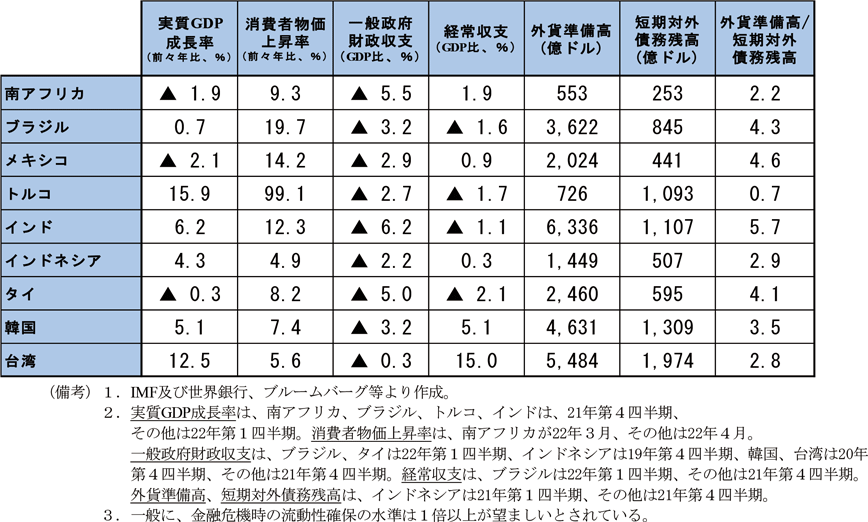
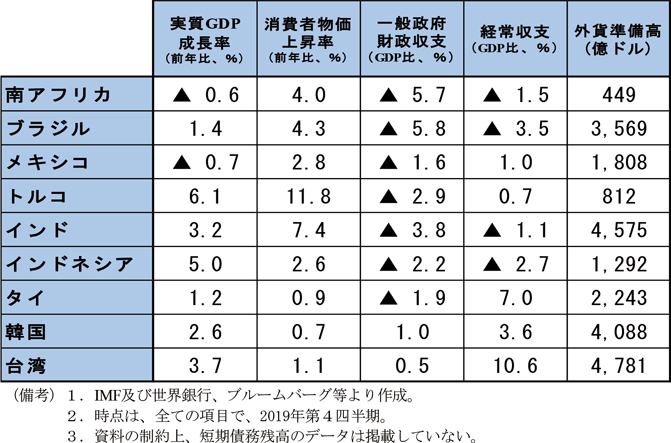
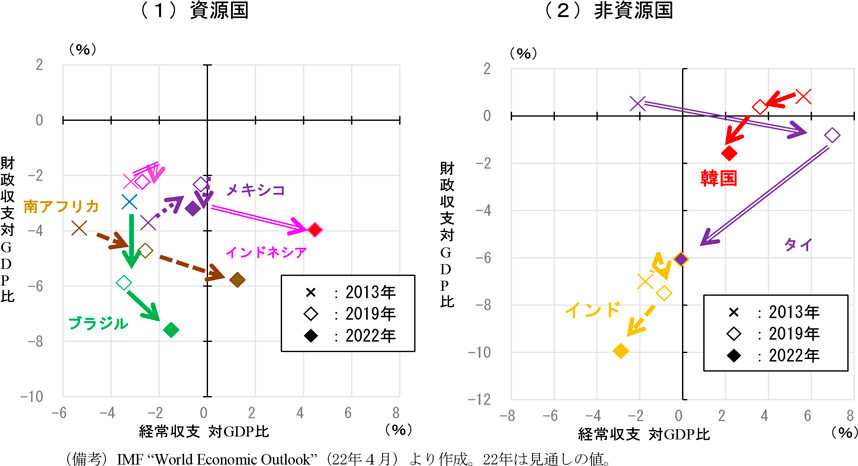
(2)国際商品市況の動向
次に、商品価格や株・為替といった金融市場の動向を確認する。
原油価格については、WTI原油先物価格は、2月24日のロシアのウクライナ侵攻後、原油の供給懸念等から急上昇し、3月1日には、14年7月以来となる1バレル100ドルを超えた。3月上旬には、米英によるロシア産原油の禁輸の発表を受けて、一時130ドル台にまで上昇した(図2)。
3月中旬には、ロシア・ウクライナ間の停戦合意への期待の高まりや、感染再拡大を受けた中国の地方都市でのロックダウンの実施などの中で、一旦90ドル台半ばへ低下したが、6月上旬までは上昇基調となった。ただし、その後には、世界的なインフレ圧力の高まりと金融引締めの動きなどを背景に、低下するなど、高水準で不安定な動きがみられている。
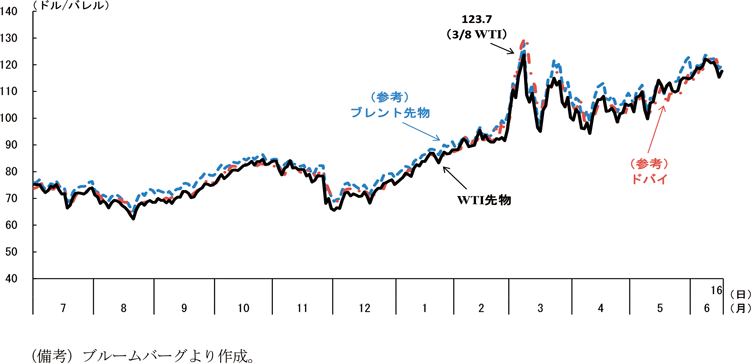
また、食料に関しては、ロシア及びウクライナが小麦、とうもろこしなど主要穀物の一大生産地69(図3、図4)であることから、ロシアによるウクライナへの侵攻に伴い、これらの供給懸念から、価格は大幅に上昇している。
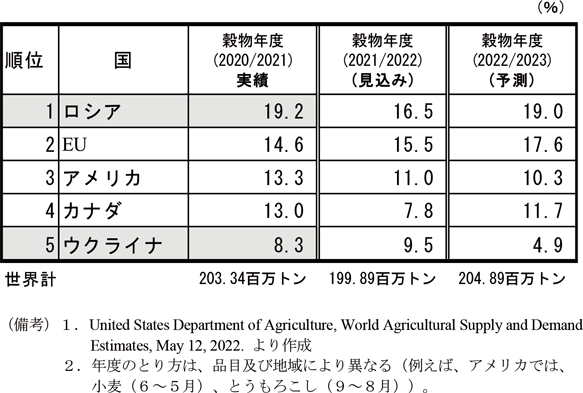
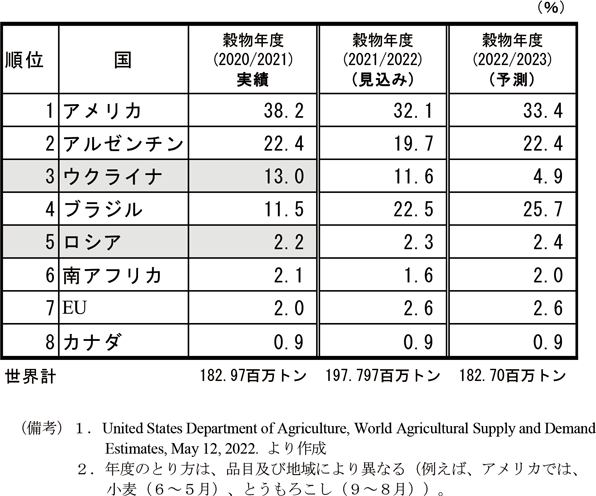
小麦は、22年3月上旬に1ブッシェル13ドル台と最高値を更新した。6月時点でも10ドル台後半と侵攻前に比べ2割程度高い水準で推移している(図5)。小麦価格の上昇を受け、インド70は食糧確保のため輸出禁止に踏み切り、更なる国際相場の上昇を招いている。
エネルギーや食料品等生活必需品を中心とする価格上昇は、両国からの穀物輸入への依存度が高い途上国を始めとして、各国の家計の負担増につながる。また、こうしたエネルギー価格の高騰等への政策対応を通じて各国の財政状況に影響を及ぼす可能性が指摘されている((1)参照)。
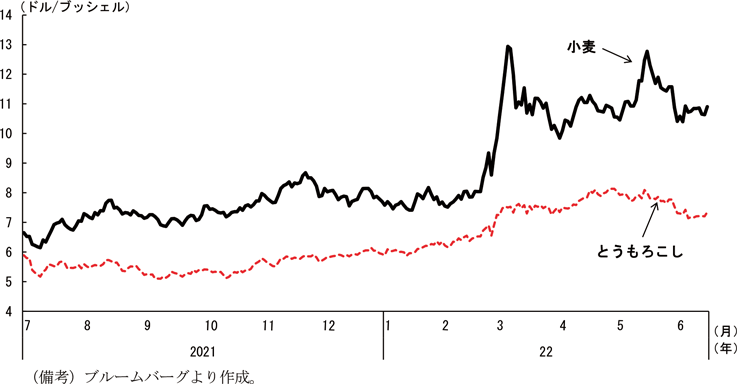
(3)為替相場の推移
次に、為替レートの動向を確認する。
ロシアによるウクライナ侵攻以来、資源国71の為替相場は、4月後半までは総じて上昇傾向で推移してきた。(2)でみたように様々な資源価格が上昇する中、資源を多く輸出する新興国では、大幅な貿易収支の改善が見込まれたことなどから、通貨の増価がみられた。その後、4月後半になると、欧米等の先進国のインフレ率の高まり、アメリカをはじめ主要国における早いペースでの金融引締めの観測、中国の感染再拡大に伴う経済活動の大幅な抑制等から、特にブラジル72や南アフリカの為替相場が押下げられた。その後、為替安が一服したものの、6月に入ると、各国通貨は再び減価傾向にある(図6(1))。
また、非資源国は、資源価格の上昇に直面し貿易収支の悪化が見込まれたことから、為替レートは総じて下降基調にあった。5月に入ってからは、通貨安は一服した状態で推移していたが、6月に入ると再び、各国通貨は減価傾向にある(図6(2))。
さらに、中東欧諸国については、ロシアへのエネルギー依存が高いことを背景に、ポーランド、ハンガリー、チェコ等で減価傾向がみられている73(図7)。
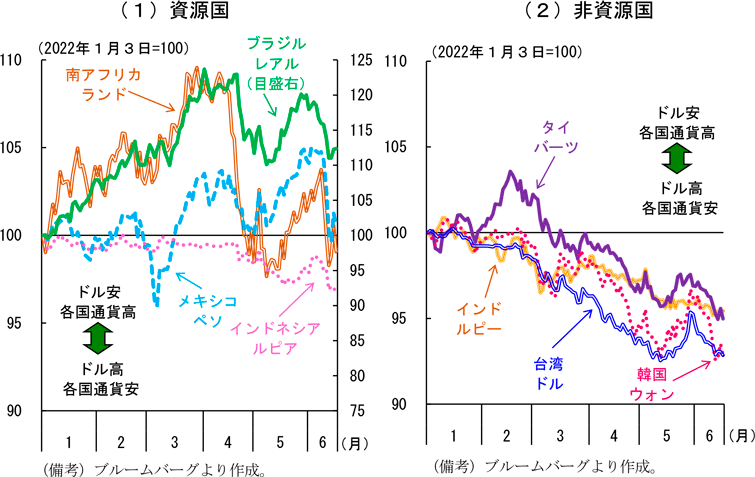
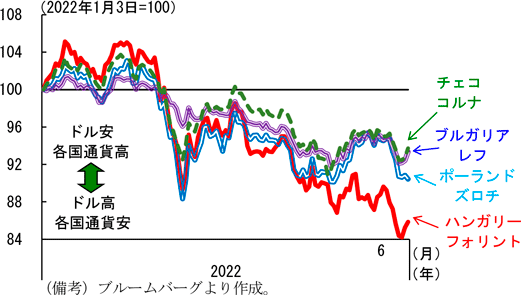
(4)資金流出入の状況等
最後に、新興国をめぐる資金流出入の状況を確認する(図8-1、図8-2)。
ロシアによるウクライナ侵攻直後は、新興国全般からの資金流出が目立った。その後は、4月半ばにかけて、資源国では資金流入超、非資源国では資金流出超の傾向がみられた。
5月下旬から6月半ばにかけては、資源国、非資源国ともに資金流入と資金流出が同様にみられた後、6月以降は、非資源国の流出超が資源国からの流出超に比べ、相対的に規模が大きくなっている。
新興国のこうした資金流出の背景には、外的要因(供給側要因)74として、世界的なインフレ圧力の高まり、それを受けた各国の金融引締め姿勢の積極化を背景とした金融資本市場の変動や、中国の地方都市でのロックダウンの長期化による経済活動の抑制や物流網の混乱等による下押し懸念等のさまざまな要因が影響していると考えられる。
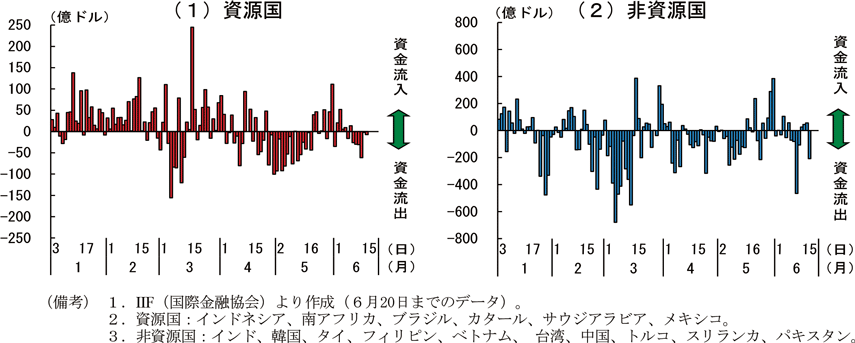
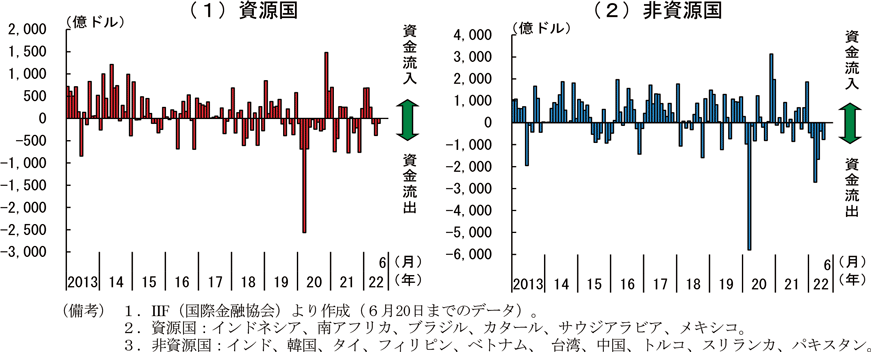
(5)最後に
以上でみてきたように、ウクライナ情勢等を背景に、国際商品価格が上昇し、最近にかけても高水準で不安定な動きとなっている。世界的なインフレ圧力の高まりもみられている。その下で、為替や資金流出入をみると、新興国をめぐる国際金融環境には不安定な動きが散見されている。今回の特徴として、国際商品価格の上昇という性格を背景に、資源国と非資源国でその影響は異なる面がみられている。ただし、特にウクライナ侵攻後は、新興国全体的に不安定な動きとなる局面もみられるなど、不確実性の高い状況となっている。
新興国は、13年にみられた国際金融環境の悪化の経験もあり、経常収支や外貨準備高といったファンダメンタルズを表す指標面からみると健全性・ショック耐性を高めている。インフレ懸念への対応等から早めに利上げを行うなどの傾向もみられている。一方で、財政収支については、感染症拡大期の経済支援策等から、これまで赤字拡大傾向がみられている。総じてみれば、対外的には経常収支の悪化がみられない中での動きであることから、その観点からは、国際金融環境の悪化に直ちにつながりにくい面もある。しかし、足下での物価上昇・生活費上昇への政策対応に伴う更なる赤字拡大の可能性も指摘されている。世界的な金融引締めが進む中での金融資本市場の変動や国際商品市況の不安定な変動による下振れリスクにも注意が必要である。
IMF(2022b)75では、新興国は、国際金融市場の引締まりに伴う過度の変動に対して依然としてぜい弱性があり、各国のインフレの先行き等に応じた一層の利上げや、コロナ禍で実施されてきた緩和政策の正常化が今後も必要であるとしている。こうしたぜい弱性は、コロナ禍でファンダメンタルズが悪化した国々で特に高まっていることから、これらの新興国にとって、外部からの経済ショックに耐え得るようなファンダメンタルズを備えていくことが一層重要になると思われる。
(1)市を跨る移動を原則禁止。市内交通(地下鉄・バス等)の運行停止。
(2)集合住宅の出入りを厳格に管理。全市民を対象に複数回のPCR検査を実施。
(3)一部を除き、企業は一律に在宅勤務とし、生産活動を一時停止。
(4)医療機関・薬局・食料品店・飲食店(出前のみ可)を除き営業停止。
4月12日時点では、(1)11,135区画:1,501万人、(2)2,682区画:178万人、(3)10,323区画:480万人。
5月30日時点では、(1)637区画:22万人、(2)6,052区画:67万人、(3)63,465区画:2,228万人。
・ウクライナ情勢を受けて食料・エネルギー価格が上昇した場合、コア物価(食料・エネルギーを除く物価)にも波及する可能性がある。これは、一段の金融引締めにもつながるところ、ショックが特に大きい場合には、景気後退と高水準のインフレの同時進行(「スタグフレーション」)が引き起こされるリスクがある。
・労働市場のひっ迫が続く中で、企業が雇用コストの上昇に対処しきれない場合には、物価上昇率が更に高まり、賃金と物価のスパイラル(相乗的な上昇)が生じるリスクがある。
なお、BISも、先進国で物価と賃金のスパイラルが生じる可能性について、今のところその裏付けとなるデータはみられないものの、リスクは軽視されるべきでない、と指摘している(Frederic, B. et al(2022))。

