第3章 労働参加の促進を通じた成長底上げ(第1節)
第1節 労働参加の促進要因
少子高齢化が進展する中、経済成長に対する労働力減少の影響を軽減させるためには、労働参加率の上昇による量の増加、生産性の向上による質の改善がともに重要である。量の増加について、とりわけ伸びしろがあると考えられるのは女性や高齢者の労働市場への参加である。女性や高齢者の労働参加を阻害している要因を除くことで、その労働参加が促されることが期待できる。
15歳以上65歳未満の男女別労働参加率について、2000年以降の推移をみると、国によってかなり異なる(第3-1-1図)。アメリカを除くG7やニュージーランド等は国ごとにレベルの差はあるものの、男女ともに労働参加率は緩やかな上昇傾向にある。男女を比べると女性の労働参加率の伸びの方が大きいため、男女間の参加率の差は縮小を続けている。
2000年と15年を比較すると、G7の中で女性の労働参加率が最も大幅に上昇したのはドイツ(63.3%→73.1%)、次いでイタリア(46.3%→54.9%)であった。日本や韓国でも相当程度の上昇がみられた(それぞれ59.6%→66.7%、52.0%→57.9%)。他方、北欧では、2000年時点で女性労働参加率は既に高水準であり、大きな変化はみられない。
逆に、男女ともに労働参加率が低下しているのがアメリカである。2000年から15年の間に、労働参加率は男性で5.5%ポイント(83.9%→78.5%)、女性で3.8%ポイント(70.7%→66.9%)下がり、結果的に男女間の差は他国ほど縮小していない。
65歳以上の労働参加率は北欧諸国等多くの先進国で上昇傾向にあり、2000年から15年の上昇幅も多くの国で5%ポイントを上回っている。特にニュージーランドでは、7.7%から22.1%と顕著な上昇がみられる。これに対し、2000年時点ですでに65歳以上の労働参加率が高かった日本や韓国では大きな変化はみられない(それぞれ22.6%→22.1%、29.6%→31.3%)。なお、アメリカの65歳以上の労働参加率の上昇(6.0%ポイント)は、それ以外の年齢層の労働参加率の低下を補うほどではないため、全体の労働参加率は低下を続けている。
こうした労働参加の動向を踏まえ、本節では、女性及び高齢者が労働市場でより活躍するための方策について順に論じる。
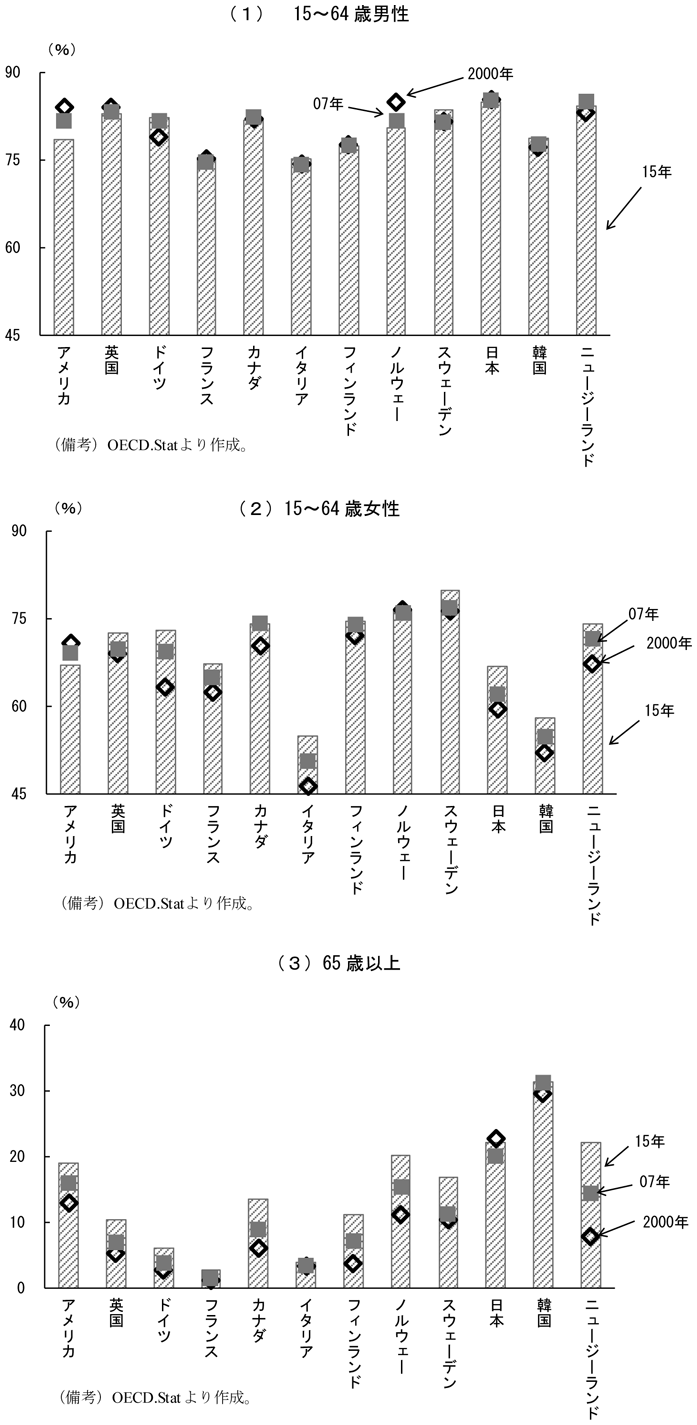
1.女性の活躍に向けた環境整備
女性が社会の様々な分野で活躍するには、仕事と子育てや介護等とを両立できる環境の整備が課題となる。具体的には、税制や各種給付等の財政政策、企業の女性労働力に対する需要を増やすための政策、その他女性が働きやすい条件や環境を整える政策等が効果的と考えられる。ここでは特に3番目の政策に着目し、高い女性労働参加率が維持されている、または女性労働参加率が上昇した各国の経験から、(1)家族に優しい政策、(2)多様な働き方、(3)柔軟な働き方の3つのグループに分け、いくつかの事例を紹介する。
(1)家族に優しい政策(ファミリー・フレンドリー施策)
仕事と育児の両立を可能にする政策は、女性が継続して働くサポートになる。北欧諸国では早くから手厚い政策が施行されており、90年代初めには既に女性の労働参加率が高かった。ノルウェーでは77年に既に18週の育児休業が規定され、87年には42週に延長された。93年には世界初のパパ・クォーター制(育児休業のうち父親のみ4週間取得可)が導入されている。
スウェーデンにおいても、95年の育児休業導入当初は両親で1か月ずつの育児休業が規定されたが、順次延長され、現在では子供1人につき両親に各240日間ずつ、合計で480日間の育児休業の受給権が認められている。16年1月現在、各240日のうち60日を除き、父親、母親間で休業を取得する権利をやりとりできる。また、74年に育児休業の収入補てん制度が導入された。受給権のある480日のうち390日は80%の所得補償がある1。
フランスでは、77年に、出産後最長2年の育児休業が導入され、86年には3年に延長された。14年の法改正では、3人以上の子供を持つ親は、子供が6歳になるまで育児休業を取得することができることとなった(子供が1人の場合は従来通り3歳未満)。また、この期間、休業か短時間勤務かを選択することができ、さらに乳幼児受入手当の基礎手当や、就労や保育の状況に応じて補助手当の支給を受けることができる。
ニュージーランドは、女性(25~64歳)の労働参加率が2000年の69.1%から14年には78.1%へ大きく上昇した国であるが、80年代から順次進んでいる女性の雇用環境を改善させる法整備が実を結んでいると考えられる。87年には雇用保護法が施行され、52週までの無給の育児休業及び14週までの有給の出産休暇が規定された。ニュージーランドでは、既に60年、72年に男女の賃金格差是正関連法が施行されており男女の賃金格差は極めて小さかったが、90年には雇用機会均等法も施行され、賃金だけでなく雇用機会も平等に扱われるようになった。02年には12週間の有給育児休暇制度が創設され(04年に13週間、05年に14週間に延長)、07年には3・4歳児を対象として、週20時間まで無償で教育を受けることが可能となる制度が創設されている。
また、保育及び就学前教育にかかる公的支出のGDP比は2000年から11年にかけてほとんどの国で増えている。11年には北欧諸国やフランス、英国、ニュージーランドで1%を超えている(第3-1-2図)。北欧諸国の高い女性労働参加率は、こうした公的支出によって支えられている面もあると考えられる。
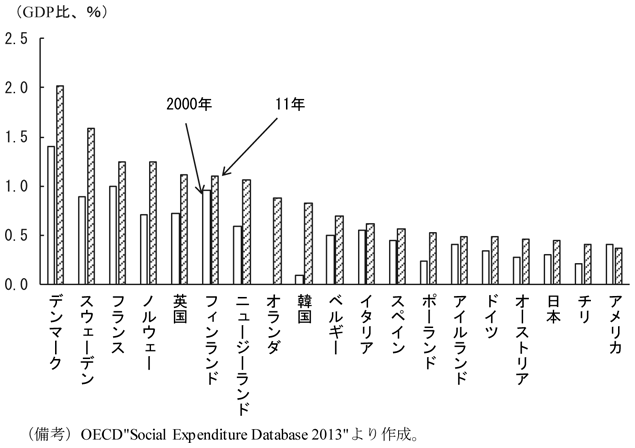
一方、前述の国々と対照的に、アメリカでは男女ともに労働参加率が低下傾向にある。最近の研究成果では07年以降の労働参加率の変化のうち、半分程度が高齢化要因で、残りは需要側の要因等で説明できるとされている2。また、90年から10年の変化に注目し、この期間中にアメリカ以外の多くの国で、(1)より長期の法定産休制度が導入され、かつ多くの場合有給であったこと、(2)パートタイム労働者の権利の法制化が進んだことを挙げ、他国でみられた女性労働参加率の上昇がアメリカでみられなかったことの主要因とする指摘もある3。アメリカではM字カーブはみられないものの、05年から15年の間に40~50歳代前半の女性で労働参加率(5歳刻み)が2~3%ポイント程度低下した(第3-1-3図)。対照的に、日本では同期間中、40・50代の女性労働参加率は3~9%ポイント、ドイツでも5~11%ポイント上昇している。こうした中、日本の女性労働参加率の上昇(特に13年以降)とその要因や政策との関係についてアメリカでも関心が高まっており、15年大統領経済報告書では安倍政権の待機児童対策や女性活躍推進法について1ページを割いて紹介している4。
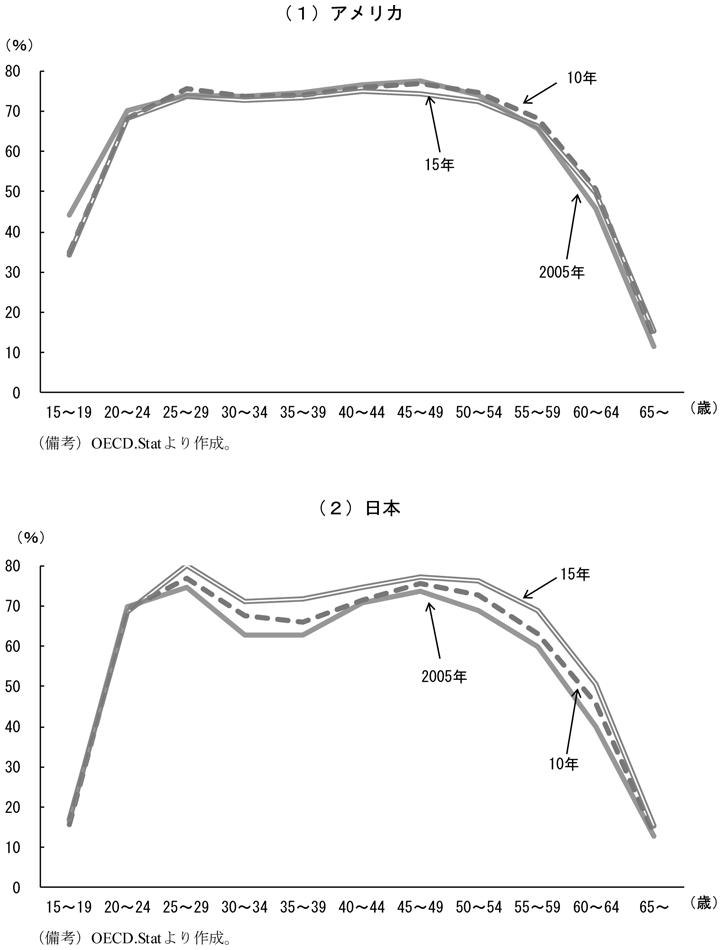
家族に優しい政策は、女性の労働参加に対するインセンティブを妨げないように適切にデザインされることが必要である。出産や育児にあたり労働市場から離脱する期間が長くなれば、スキルや知識を得る機会をより失いやすくなる。他方、休業中の所得代替率が高いほど、早く復職しようとする経済的なモチベーションを失う可能性がある。このため、OECD諸国の制度設計をみると、取得可能な休業日数が長い国では概して所得代替率は低い傾向にある(第3-1-4図)。例えば、取得可能な休業日数が長いフィンランドでは、母親が取得できる休業日数(産休及び育児休業日数)は161.0週とOECD平均(54.1週)の約3倍だが代替率は26.5%と低い。
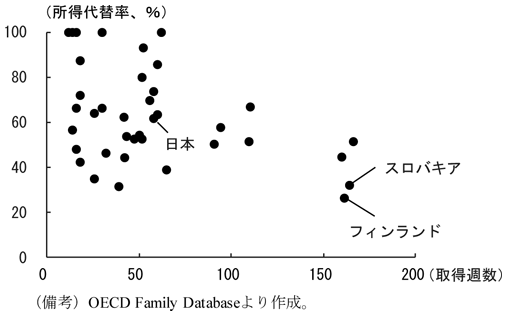
(2)多様な働き方
労働市場改革が多様な働き方を可能にしたことで、女性の労働参加が大きく進んだケースもみられる。改革の内容は、規制改革によるパートタイムや派遣労働といった多様な就業形態の推進や、パートタイムの労働条件の改善5、男女の賃金格差の是正に向けた取組等が挙げられる。パートタイムや派遣労働の場合、フルタイム正規労働と比べて雇用が不安定、賃金が低い、能力開発の機会が限られているなどの課題が指摘されている。これについては、労働者の希望や意欲・能力に応じた正社員への転換や待遇改善に向けた取組が重要となる。他方で就業形態や労働時間が柔軟であることから、女性が子育てや介護等との両立を図りやすいというメリットもあり、女性が労働市場で活躍する際の重要な入口となりえることが指摘されている6。
ドイツでは、2000年代半ばに行われた一連の労働市場改革(ハルツ改革)によって、特に女性と高齢者の労働参加率が上昇した。具体的には、女性の労働参加率は2000年の66.2%から14年には77.6%と、大きく上昇した(前掲第3-1-1図)。改革により、柔軟な就業形態、柔軟な労働時間を始めとする柔軟な労働環境が女性や高齢者の労働市場参加を促していると考えられる(第3-1-5表)。女性の労働参加が進む中、パートタイムや有期雇用、派遣雇用であっても、標準労働と平等な扱いを原則とすることが法制化されており、就業形態としては特にパートタイムや有期雇用の伸び率が高くなっている(第3-1-6図)。例えば、女性の標準労働者数は04年に比べ14年にはフルタイムでは4%の増加だったがパートタイムは67%以上と大幅に増加した。また女性の有期雇用者数も33%近くの伸びとなっている。
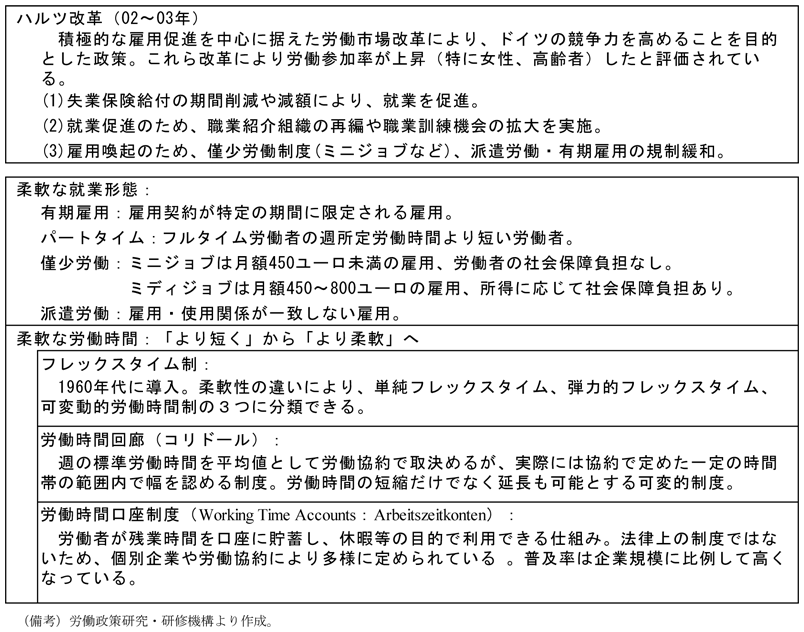
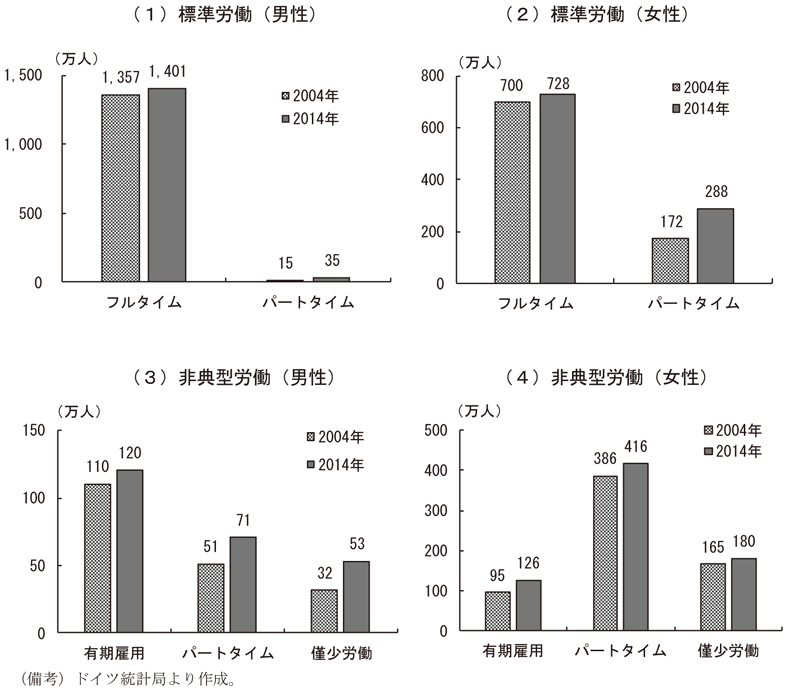
パートタイム労働の権利を保障することや、インセンティブを高めたことで、女性の労働市場への参加が増加したケースもみられる。
オランダでは、女性のパートタイム比率は76.6%と、EU平均の32.2%と比較して際立って高くなっている。この背景には、96年の労働時間差別禁止法によって、賃金や昇進等全ての労働条件においてフルタイムとパートタイム労働者に同等の権利が保障されたことに加え、2000年の労働時間調整法によって、労働者が週当たりの労働時間を決められるようになったことがある。これらの改革の効果もあって、女性の労働参加率は2000年の53.7%から14年には58.5%に上昇した。
また、イタリアでも03年の労働市場改革が女性の労働参加率を高めたことが知られる。イタリアは、女性や若年層の就業率が他のEU諸国に比べて低いこと、長期失業率が高いこと、南北格差及び仮装自営業者が多いなどの問題を抱えており、90年代より、労働市場を硬直化させている規制の見直しを行ってきた。03年に制定された労働市場改革法(ビアジ改革)は、上記のような構造問題に対応し、就業率を高めることを目的とした弾力的な契約形態の拡充、具体的にはパートタイム労働へのインセンティブ、派遣労働の柔軟化等を実施した。併せて、市場メカニズムを徹底的に活用し透明性と効率性を持たせるような改革、具体的には職業紹介などの労働市場サービスを提供する機関に対する許認可手続きの明確化等を実施した8。ビアジ改革は即効性を発揮し、女性の労働参加率は03年の48.3%から1年で2.5%ポイントも上昇した(14年は55.2%)。中でも女性の雇用に占めるパートタイム比率が高まった(03年17.3%→14年32.2%)。
(3)柔軟な働き方
働く時間や働く場所の柔軟化も女性の労働参加率を上昇させる要因と考えられている。逆に、勤務時間が長いと女性の労働参加にはマイナスであるとの指摘があり、各国横断的にみても年間労働時間と女性労働参加率の間には負の相関がみられる(第3-1-7図)。
このうちドイツの年間労働時間は15年に1,371時間とOECD諸国の中でも最低水準にある。時短が非常に進んだ環境下で、近年ドイツの労働時間制度は一層の短縮ではなく柔軟化に焦点を当てて見直されるようになり、こうした中で登場した制度が「労働時間口座制度」であった(前掲第3-1-5表)。労働時間口座は90年代に自動車産業等から導入が進んだもので、フィンランド、デンマーク、スウェーデン、オーストリアでも普及している。これは、一定期間の幅で1日または週の労働時間を変動的に配分できる制度で、労働力の有効活用を目的として労働者が残業時間を各人の口座に貯蓄し休暇等に利用できる仕組みであり、そもそも年次休暇の完全消化が前提となっていると言える9。
柔軟化はヨーロッパの各国で進んでいる。データが利用可能な23か国中10、労働時間を少なくとも一定程度自分の裁量で決められる労働者の割合が特に高く、5割を超えているスウェーデン、オランダ、デンマークの3か国では、女性の労働参加率は平均57.7%と全体の平均を9%ポイント近く上回っている。こうした国々では、労働者自身が働く時間を柔軟に調整できることで、育児と仕事を両立させている両親にとっても働きやすい職場環境となっていると考えられる。
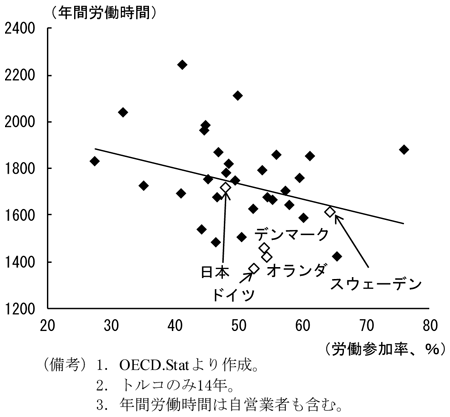
スウェーデンでは、子供が8歳になるまで労働時間をフルタイムの75%まで短縮可能とする労働時間短縮制度も設けられていることに加え、労働時間を自ら決定することのできる労働者の割合が高くなっている。10年にヨーロッパ7か国(フランス、ドイツ、イタリア、ポーランド、スペイン、スウェーデン、英国)で行われた調査によると、スウェーデンの女性労働者はオランダと並んで、自分で労働時間を決められる比率が最も高くなっており、41.0%の回答者がある程度の制限はあるものの自分で労働時間を決められる、13.6%が自分で労働時間を決められるとしている(オランダはそれぞれ38.3%、15.3%)。個人的な都合で職場を1~2時間抜けることについても、84.8%の回答者が何の問題もないと回答しており、半数近くが難しいと回答しているドイツ(52.6%)やフランス(44.6%)と比較して対照的である11。
これに対しアメリカでは、職場環境や勤務時間に制約が大きく、労働参加率を押し下げているとの指摘がある。14年に行われた調査によると、18歳未満の子供がいる親の約半数(49%)が、家庭で必要な役割を果たすのに支障があることから、新しい仕事を諦めたことがあると回答した12。
働く場所の柔軟化の典型例がテレワークである。日本の状況にかんがみると、テレワークのメリットとして、(1)育児や介護を理由とする女性のターンオーバーの低下、(2)人的資源のより効率的な活用の2点が挙げられる13。EU全体の取組としては、02年にはテレワーク枠組合意(European Framework Agreement on Telework)が欧州産業連盟や労働組合連合等との間で署名された。EUでは、2000年に、雇用創出や競争力強化によりEUを知識経済に発展させることを10年までに目指すリスボン戦略が打ち出され、その一環としてICTを活用した新たな就業形態としてテレワークの促進が図られた。これを機にEU各国ではテレワークが積極的に活用されるようになり、05年時点で既に、EU27か国において、就業時間の4分の1以上をテレワークで行う労働者が全体の7%となった14。10年時点の調査結果で、主な仕事場所が自宅である、あるいは過去3か月以内に自宅で勤務したことのある者の割合が高いデンマーク、オランダ、フィンランド、スウェーデンはいずれも女性労働参加率が高い国々であり、働く場所の柔軟性もまた、女性の労働参加率を高めるための環境整備の一環として有益である可能性が高いと考えられる(第3-1-8図)。
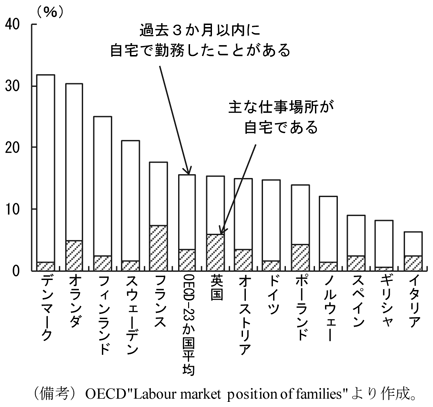
2.高齢者の活躍に向けた環境整備
高齢者の労働参加を促進する要因としては、(1)研修機会の確保や柔軟な労働環境の構築を通じた雇用可能性の拡大、(2)年齢等の就労条件の設定による労働市場への参入障壁の撤廃、(3)公的年金や失業保険が働き続けるインセンティブを阻害しないことが挙げられる15。各国ともに高齢者の労働参加率は上昇傾向にあるが、中でもニュージーランドと北欧諸国の上昇が目立っている(前掲第3-1-1図)。
ニュージーランドの高齢者の労働参加率は、2000年には7.7%であったが、14年には21.4%と約3倍となり、OECD加盟国の中で最も労働参加率の上昇幅が大きかった。この背景には、各種の政策変更が影響したとされる。年金支給開始年齢は77年に65歳から60歳に引き下げられ、以降、早期退職の動きが強まったため、92年から01年までの間に逆に60歳から65歳に段階的に引き上げられた。加えて、98年以降、それまで13年にわたって実施されてきた収入審査(income test)が廃止され、他の収入があってもペナルティを課されることなく年金を受給できるようになり、高齢者が働き続けるインセンティブが増していると考えられる。
北欧諸国では、労働時間の柔軟化、定年延長・廃止の実現、公的年金の支給開始年齢の引上げ等が進められてきたことが、労働参加率上昇の背景にある16。
また、ドイツでは、ハルツ改革において、高齢者を雇用する企業に対する社会保障負担の免除やパートタイム就業の促進といった、55歳以上の雇用拡大のための措置が採られたことにより、高齢者の労働参加率の上昇につながっている(前掲3-1-5表)。
一方で、韓国の高齢者の労働参加率が高い背景には、年金制度の整備の遅れが指摘されている。韓国の年金制度は88年に導入されたものの、年金の金額自体が少ないことに加え、受給割合も低水準にとどまっている。加えて、11年に行われた調査結果によると、中堅・大手企業の4割が55歳定年で、60歳以上を定年とする企業は全体の4分の1にも満たなかった17。定年が早く、かつ年金制度の整備が遅れていることから、多くの高齢者が定年後も就業を続けている。このため、高齢者の労働参加率は高いものの、安定的な就労の機会が得られているとはいえない。65歳以上の労働者のうち臨時雇用の比率はOECD加盟国の中でも最も高く、14年には59.8%である(OECD平均は17.4%)(第3-1-9図)。
結果的に、韓国では貧困状態にある高齢者の比率が高い18。60歳以上を対象とした内閣府「高齢者の生活と意識に関する国際比較調査」(10年)によると、韓国では回答者の半数程度が「日々の暮らしに困っている」あるいは「少し困って」おり、他の調査国(ドイツ、日本、スウェーデン、アメリカ)と比較して突出して高くなっている(第3-1-10図)。多くの高齢者が経済的な理由から働かざるを得ない状況と解釈できる。
こうした高齢者の貧困の問題に対応するため、13年に定年を60歳に義務付ける法案が成立し、14年5月に施行された。企業規模によって導入に猶予があるものの、17年1月には完全実施される見込みである19。
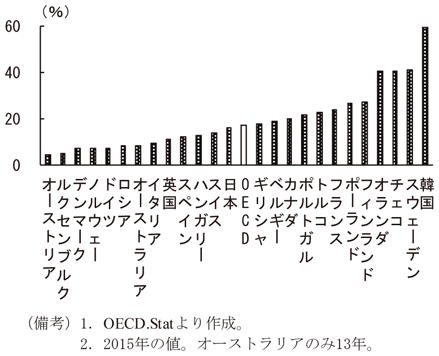
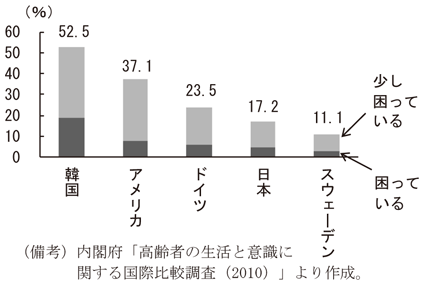
3.高齢者、女性の活躍による労働供給制約要因の緩和
医療技術の進歩によって健康寿命20も伸びてきていることから、一個人が就労可能な期間も物理的に長くなっている。主要先進国の男性健康寿命は2000年から12年の間にフランスでは67歳から68歳、ドイツと英国では67歳から70歳、日本では71歳から72歳、アメリカでは66歳から68歳へ延びている。
一方、個人が就労期間を決める際、年金支給開始年齢など年金制度から受ける影響が大きいと考えられる。主要先進国における年金支給年齢と実際の退職年齢の関係をみると、日本や韓国では平均退職年齢が年金支給開始年齢を上回っているものの、ヨーロッパでは逆になっている国が多い(第3-1-11図)。今後、平均寿命上昇の影響を緩和するため、主要先進国ではおしなべて年金支給開始年齢が引き上げられる可能性が高い。その結果、ヨーロッパ諸国でも平均退職年齢が上昇する可能性も考えられる。平均退職年齢の上昇が全体の労働参加率を押し上げる影響を考えるため、65歳以上の労働参加率が上昇したと仮定すると、フランスとドイツでは、65歳以上の労働参加率が14年の水準から1%ポイント上昇した場合、全体の労働参加率をそれぞれ0.22%ポイント、0.24%ポイント押し上げられる。
また、女性労働参加率の上昇も労働力人口の減少を軽減する効果がある。現在の年齢別労働参加率に変化がないと想定したケース1と、女性労働参加率が北欧並みに上昇すると想定したケース2の労働力人口を比較すると、15年から25年の間でケース1からケース2になった場合、日本では労働力人口は減少から増加に転化(ケース1:▲8.0%、ケース2:2.1%)、ドイツでは減少幅が縮小(同▲7.6%、▲0.5%)、アメリカでは増加幅が拡大(同2.4%、14.0%)すると試算される(第3-1-12図)。
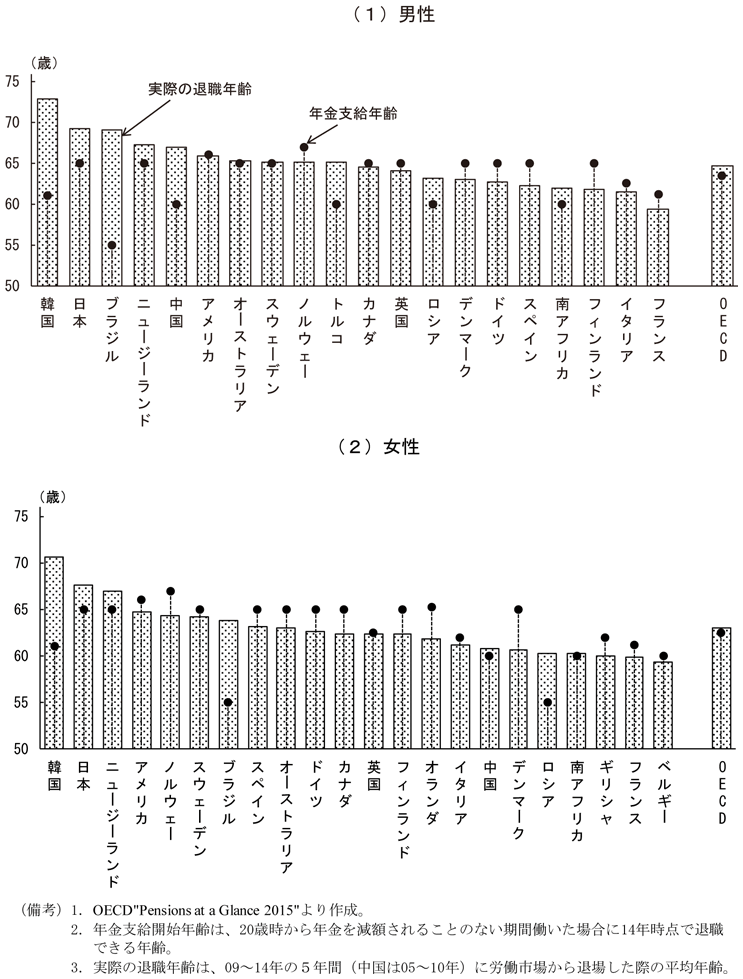
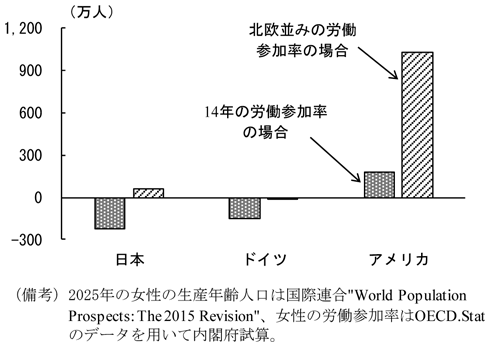
テレワークは一定程度普及したと判断されたことから、EUによるテレワーク推進策は06年に終了した。
は韓国で47.2%とほぼ半数に近く、OECD平均の12.8%を大きく上回っている。

