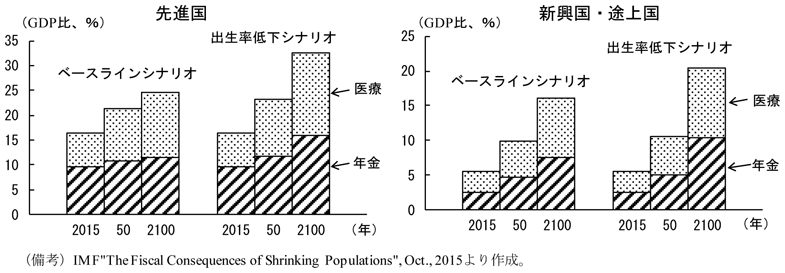第1章 世界金融危機後の成長鈍化(第3節)
第3節 先進国の成長率低下とその要因
1.世界金融危機後の弱い回復
100年に一度と言われた世界金融危機から7年が経過したが、先進国の景気回復は金融危機直後の2010年を除き緩やかなペースにとどまっている。今回の景気回復のペースを、それより一つ前の回復期にあたる02年頃以降と比較してみよう。
第1-3-1図(1)~(3)は、G7各国について02年以降と09年以降の需要項目(個人消費・民間企業設備投資・輸出)別の回復のペースを比較している。国や項目によって回復のペースにはばらつきがあるが、09年以降の方が02年以降より回復ペースが順調な需要項目は限られている。まず、個人消費については、ドイツ以外のほとんどの国で回復のペースは前回より緩やかになっている。民間企業設備投資はアメリカや英国では前回並みないしそれを上回るペースで回復しているが、フランスや日本ではペースが遅く、カナダでは12年までは順調に回復したがその後減速し、15年には大きく減少している。投資の伸びの下落は、前述の長期停滞論とも関連する重要な論点であり、後述するようにその要因について様々な議論が行われている。輸出は、カナダ、イタリア以外の各国で09年以降の回復ペースが前回の回復局面と比べて顕著に遅い。
また、近年のG7諸国の潜在成長率は、イタリアや日本が低水準で推移している他、90年代には3%を超えていたアメリカも2%以下へと低下している(第1-3-1図(4))。また、G7のGDPギャップは08年と比較すれば全般に縮小傾向にあるものの、いまだにマイナス圏で推移している(第1-3-1図(5))。
このように、需要面、供給面のいずれも力強さに欠ける中、各国において緩和的な金融政策が続いている。アメリカでは08年末から15年にかけて事実上のゼロ金利政策(FFレート誘導目標0.00~0.25%)が実施され、累次の量的緩和策も実施されてきた。15年12月にFFレートは0.25~0.50%に引き上げられたものの、FRBは今後の利上げペースは緩やかなものになるとしている。ユーロ圏では政策金利が11年後半以降段階的に引き下げられ、16年3月にゼロとなったほか、15年1月には量的緩和策の導入が決定された。日本では13年4月に量的質的金融緩和が導入された。この間の各国・地域のマネタリーベースのGDP比の推移をみると、13年4月以降急増している日本を含め危機前と比較して大幅に上昇していることが見てとれる(第1-3-1図(1)~(3))。
一方、財政政策については、世界金融危機後の財政出動により、各国の財政収支は08年から09年にかけて大幅に悪化した。その後各国で財政再建が進み、ドイツでは財政収支が黒字に転じている。
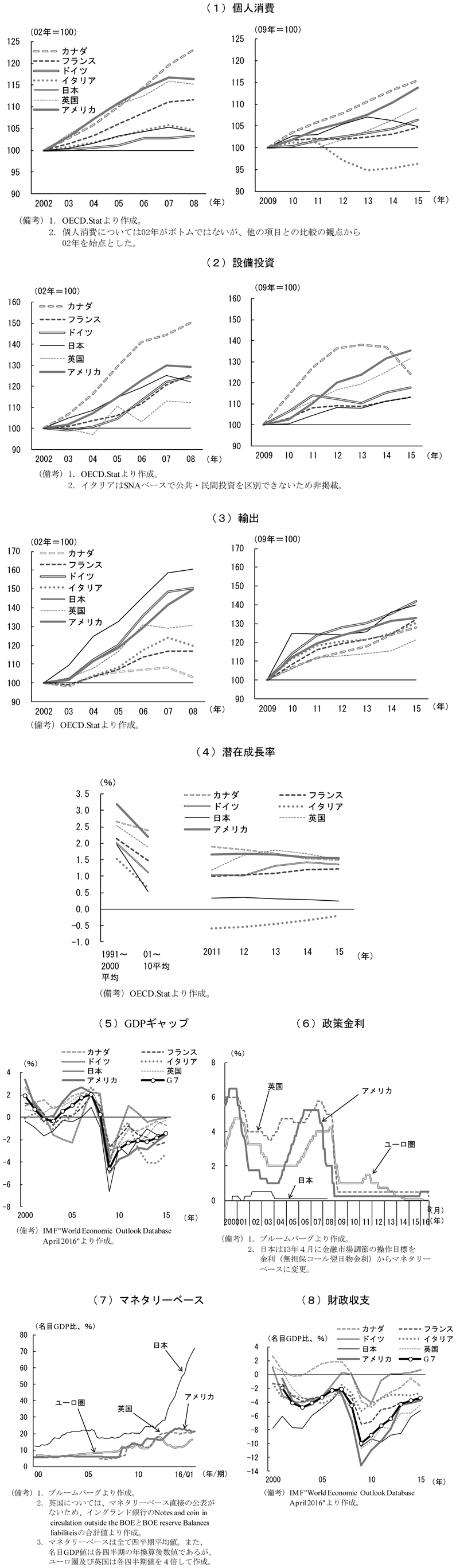
2.設備投資を巡る議論
(世界金融危機後の設備投資の動向)
世界金融危機後の設備投資の伸びが緩やかなものにとどまっている要因について、多くの国で議論が行われている。設備投資の構成要素別にアメリカとEU諸国の動向を比較すると、危機後の一時期を除き、アメリカ、ユーロ圏のいずれについても知的財産投資の伸びが顕著であるのに対し、建設投資(アメリカでは構築物投資、ユーロ圏では建設投資)は、アメリカ、ユーロ圏のいずれにおいても低迷しており、世界金融危機前の水準を回復していない(第1-3-2図)。機械・機器投資はアメリカでは危機前の水準を大幅に上回る水準まで回復しているのに対し、ユーロ圏では危機前の水準を下回って推移しており、対照的な姿となっている。機械・機器投資の内訳をみると、アメリカでは世界金融危機の際、特に大きく落ち込んだ輸送機械が反動で大きく増加しているが(09年から15年にかけて+328%)、ユーロ圏ではそれほどの伸びはみられない(同期間に+15%)。

民間企業設備投資については、ユーロ諸国を対象に国ごとの投資の成長率の背景を説明する3つの経済モデル、(1)加速度モデル(予想経済成長率に依存)、(2)新古典派モデル(資本の実質費用に依存)、(3)加速度+αモデル(経済成長率に加え、不確実性、借入コスト等に依存)を比較検証した結果4、要因は国によって様々であるが、不確実性が大半の国で投資の伸びを抑制していることが示されている5。企業が直面する様々な不確実性については第2章で議論するが、この節では(1)の考え方に基づき経済成長率の見通しと企業の設備投資の伸び率の関係を分析し、続いて設備投資の動向に関連する様々な議論を紹介する。
(欧米における予想成長率の低下)
ECB(欧州中央銀行)の調査によれば、ユーロ圏の実質経済成長率見通しは、世界金融危機や欧州債務危機による短期的な落ち込みを挟みながら、長期的に緩やかな低下傾向にある。また、ECBのレポート6によると、設備投資の抑制要因として足元や将来の需要の弱さを挙げる企業が多く、加速度モデルと整合的である。2000年以降の民間企業設備投資の前年比の動きは、1年先の成長率見通しの動向と連動しており、世界金融危機後の予想成長率の低下と設備投資実績の低迷にはつながりがあると考えられる(第1-3-3図)。
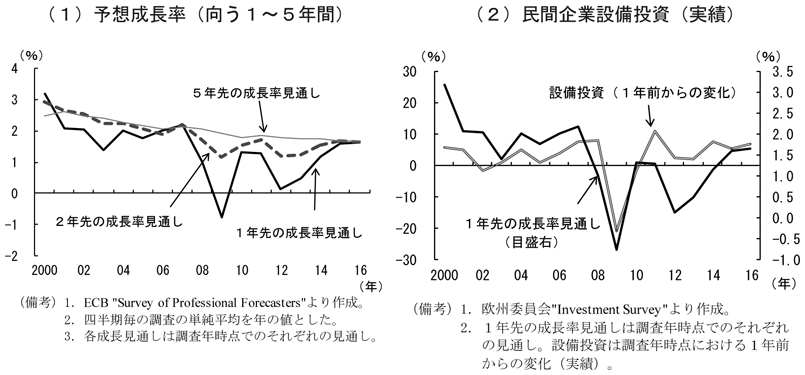
前述のECBのレポートによれば、15年の設備投資の内訳を、設備投資を20%以上増やした企業での平均と全企業平均とで比べると、更新投資比率では前者は後者より10%ポイント近く低い一方、生産技術の向上やITへの投資比率では前者が後者を上回る。このことから、一部の設備投資に積極的な企業を除き、生産性の向上につながる前向きな投資意欲が弱いことが示唆される。
また、アメリカでは、世界金融危機後の設備投資の伸びは前回の回復局面の伸びとほぼ同じペースである(第1-3-4図)ものの、90年代以前の景気回復局面と比べると力強さに欠けるとの指摘もある7。それによると、アメリカの設備投資の動向は概して加速度モデルと整合的であることから、予想成長率の伸び悩みが設備投資の弱さの要因とされている。加えて、より長期的な影響要因として金融危機からの履歴効果や金融政策の効果の限界(前掲コラム1-1)が挙げられている。
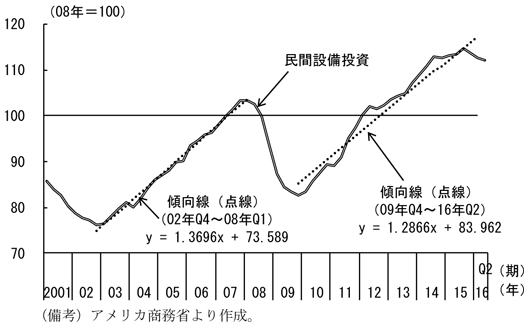
(設備投資を阻害する制度的要因)
制度的要因も設備投資の阻害要因となっているとの指摘もある。OECDのBIAC(経済産業諮問委員会)が15年3月から4月にかけて行ったアンケート調査によると、設備投資を阻害する要因としては、政策や規制の不確実性、税金やその他の事業コスト及び規制が「とても重要」とする企業の比率が高い(第1-3-5図)。
また、前述のECBのレポートにおいても、需要見通しが弱いことを除けば、政策の不確実性、労働コスト、行政手続きに要するコスト及び労働規制が挙げられるケースが多い。特にユーロ圏以外への投資が多い企業では、その他の企業より、こうした要因を投資の阻害要因として挙げることが多い。例えば、全企業では25%強が政策の不確実性を、2割程度が労働コストを、2割弱が労働規制を投資制約要因として挙げているが、ユーロ圏以外への投資が多い企業はそれぞれ約35%、3割程度、4割弱が該当すると回答しており、その比率はいずれも全企業平均より高い。
調査結果からは、因果関係は明確でないにせよ、ユーロ圏外への投資が多い企業はこうした制度的要因が投資を阻害しうると感じる傾向が強いことが示唆される。このことは、ユーロ圏内に存在する規制の見直し等が、こうした企業がユーロ圏内の設備投資により前向きになることにつながりうることを意味している。
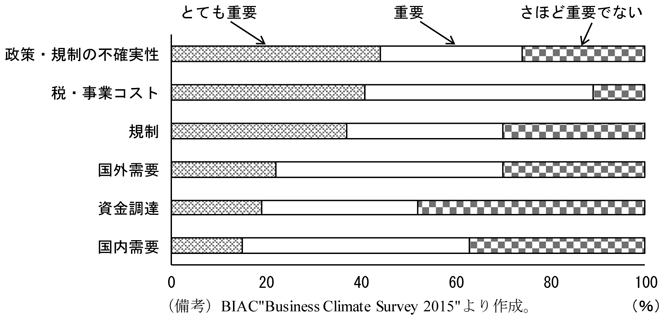
(アメリカでのR&D投資の動向)
前述のとおり、アメリカでは知的財産投資の増加が堅調となっている。その大半を占めるR&D投資について業種別にみると、製薬業が占める割合が年々高まっており、2000年の16.6%から15年には24.8%にまで上昇した(第1-3-6図)。
R&D投資は将来の生産性向上につながるものと考えられているが、投資が実際に収益増につながる確率は、業種や技術革新の動向によって異なると考えられる。例えば高齢化の進展に伴い、日常生活に薬を必要とする人が増加し、新薬に対する需要は持続的に高まっている。R&D投資に対する企業収益の比率(投資効率)をみると、製薬を含む化学では製造業全体よりも投資効率が低くなっている上に、09年ごろをピークとして低下が続いている(第1-3-7図)。化学での低い投資効率は、投資の拡大が必ずしも画期的な薬の開発等に結び付くものではないことを示唆している。こうした投資効率の低下が続く業種では、今後R&D投資全体が下押しされる可能性がある。但し、製造業全体をみると、R&Dの投資効率は08年をピークに12年までは低下していたものの、その後は上昇に転じており、収益増につながる投資として、今後もその伸びが続くことが期待される。
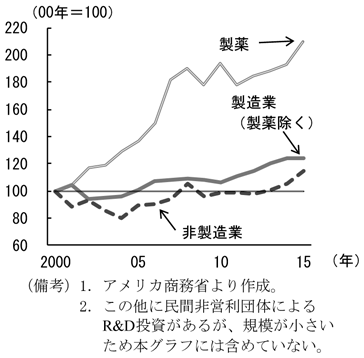
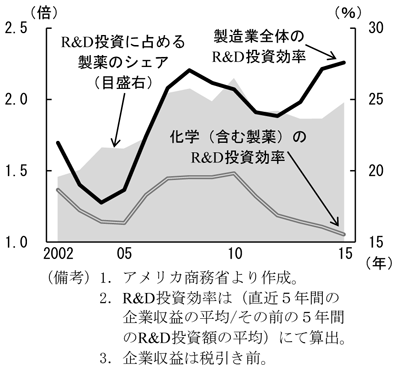
(低下傾向にある公共投資)
現在の低金利環境は長期的な成長につながる投資を行う絶好の機会であるとの指摘がある。G7では09年ごろをピークに公共投資のGDP比が低下傾向にある国が多い(第1-3-8図)。例えばアメリカでは、インフラの老朽化が大きな問題になっており、生産性低下の一因であると考えられている。CEA(米大統領経済諮問委員会)のレポートでは、公共交通インフラ不足による道路混雑は、年間で家計に対し1,200億ドル、ビジネスに対しても300億ドルのコストを生じさせていると推計されている8。このため、成長基盤の強化につながるインフラ投資を実施すべきとアメリカ政府も主張しているが、インフラ投資の主要な意思決定主体である州や地方政府間での調整の難しさや、議会とのねじれの中で実現が難しい状況が続いている。
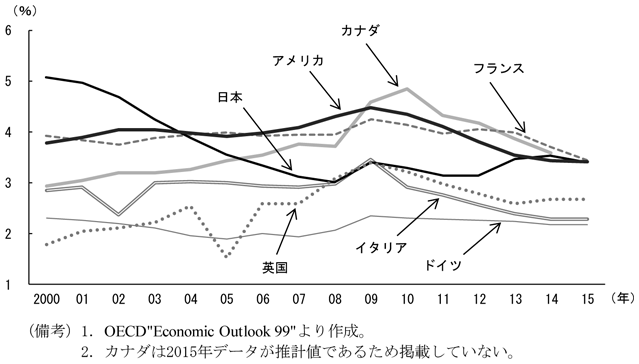
3.少子高齢化の経済成長への影響
経済成長に影響を及ぼす先進国共通の課題として、少子高齢化の進展が挙げられる。程度の差はあるものの、先進国はいずれも生産年齢人口比率が低下しており、将来的にも低下が続く見込みである(第1-3-9図)。
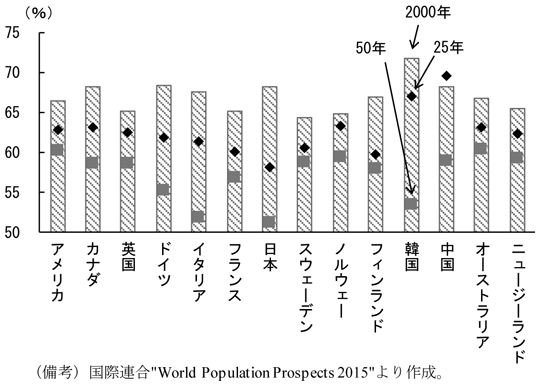
なお、少子高齢化の影響を取り除くために生産年齢(15~64歳)人口一人当たりの実質経済成長率をみると、通常の実質経済成長率とはやや異なった姿となる。13~15年の平均についてG7各国を比較すると、実質経済成長率では英国が第1位(2.6%)、アメリカが第2位(2.4%)で日本は第6位(0.3%)になるのに対し、生産年齢人口一人当たりの実質経済成長率では、日本は英国(2.2%)、アメリカ(2.2%)に次いでG7中第3位(1.7%)となる(第1-3-10図)。この期間中、経済成長率が生産年齢人口の増加率を上回ったのはイタリアと日本だけであり、特に日本での差は大きい。少子高齢化が進む中で経済のパフォーマンスを評価するためには、通常の経済成長率だけでなく、生産年齢人口一人当たりの経済成長率に着目することも重要である。
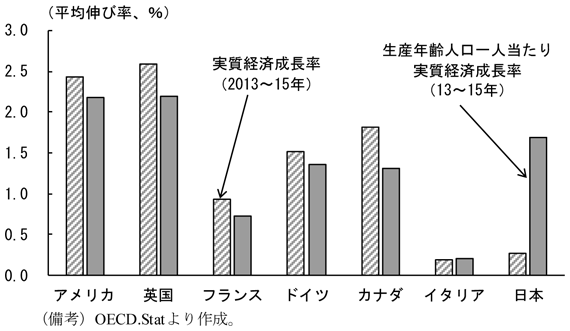
高齢者比率の上昇は経済に対してどのような意味を持つのであろうか。高齢者は一般的にフローの所得が低いため、高齢者比率が増加すると、マクロ全体の所得が低下し、ひいては個人消費の伸びが鈍化する可能性がある。一方、高齢者ほど保有する資産が大きい場合は、その取り崩しを通じて消費が維持・促進される可能性もある。次に、欧米の高齢者の消費内訳の変化に着目すると、医療関係への支出割合が他の世代と比較して高くなっている一方、衣服や交通費等にかける割合は低くなっている(第1-3-11表)。今後高齢者比率が高まることによって、平均消費性向、全体の消費構成ともに変化が生じると考えられる。
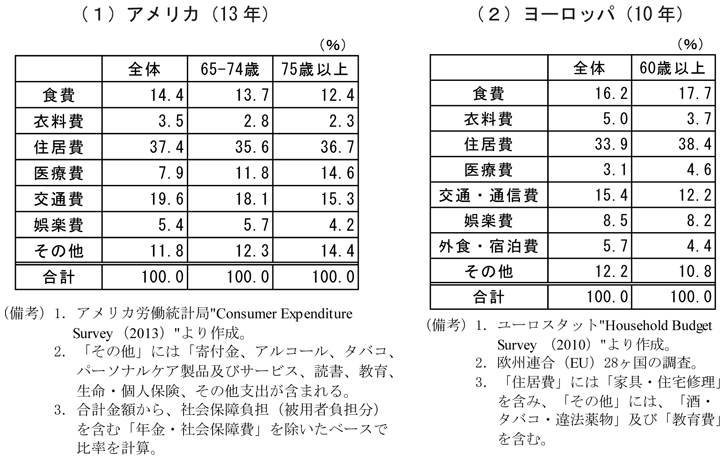
また、高齢化の進展はリスクテイク行動にも変化を起こすとみられる。高齢者が若年者より安全志向が高い傾向にあるため、高齢者比率の上昇により、経済のダイナミズムが低下するとの指摘がある。例えばアメリカでは、35~44歳の人口比の減少が開業率にマイナスの影響を及ぼしているとの分析がある9。
さらに、高齢化の進展は、医療費や年金給付額等の増加による社会保障費の増加、ひいては国民負担の増加につながりうる。IMFの試算によれば、医療費及び年金給付額の合計額のGDP比は、先進国では、15年の16.4%が、50年にはベースラインシナリオで21.3%、出生率がベースラインよりも低下するシナリオでは23.2%まで上昇する見込みとなっている。新興国でも同様に、15年の5.5%が、50年には9.9%、出生率低下シナリオでは10.6%まで上昇すると予測されている(第1-3-12図)。一方、社会保障負担率(GDP比)を各国比較すると、OECD平均でも2000年の8.6%から13年の9.1%に上昇しているが、特に高齢化の進展スピードが早い日本や韓国では増加のペースが速い(日本で9.4%→12.4%、韓国で3.6%→6.4%(ともに2000年から13年の変化))。
高齢化の影響が拡大する中、働き方の改革を通じて高齢者が労働参加しやすい環境を整備することが経済活性化にもつながると考えられる(第3章)。