第1章 世界金融危機後の成長鈍化(第1節)
第1節 世界経済の成長率の低下
近年の世界経済の成長率低下の要因の一つとして、世界金融危機後に実施された4兆元の景気対策後の調整が続く中国経済の減速を挙げることができる。中国の実質経済成長率は10年に10.6%を記録して以降低下傾向にあり、15年には6.9%となった。世界第2位の経済規模となった中国経済の減速は、貿易や投資を通じて新興国を始めとする各国の経済にも幅広い影響を及ぼしている。一方、先進国においては、世界金融危機から7年を経てもいまだにマイナスのGDPギャップが残るなど、回復のペースは緩やかなものとなっており1、いわゆる「長期停滞論」(コラム1-1)を含め、低成長の要因や対応策に関する議論が行われている。
(新興国の成長鈍化と中国の影響)
最初に、90年以降の世界経済の成長率の推移を振り返ってみよう(第1-1-1図、第1-1-2図)。まず、90年代から2000年代にかけては先進国と中国以外の新興国・途上国の間に成長率の差はほとんどなかったことが分かる。この間の中国の成長率は比較的大きく変動しているが、世界全体の成長率に与える影響は限定的であった。2000年代に入ると中国以外の新興国・途上国の成長が加速し、成長率が低下した先進国との差が拡大した。中国の成長率も上昇し、09年にはGDPでみて世界第2位の経済大国となった。世界金融危機により08年、09年の成長は世界的に大幅に鈍化したものの、4兆元の景気対策の効果もあり、中国はいち早く成長を回復し、危機後の世界経済を下支えした。その後は中国及び中国以外の新興国・途上国の成長率が減速し、世界全体の成長率も10年の5.4%をピークに低下し、15年には危機後最低の3.1%となった(第1-1-1図、第1-1-2図)。なお、世界のGDPの成長率への中国の寄与の割合は80年代の7%程度から2000年代の13%程度へと拡大し、13~15年平均は28%程度にまで上昇している。
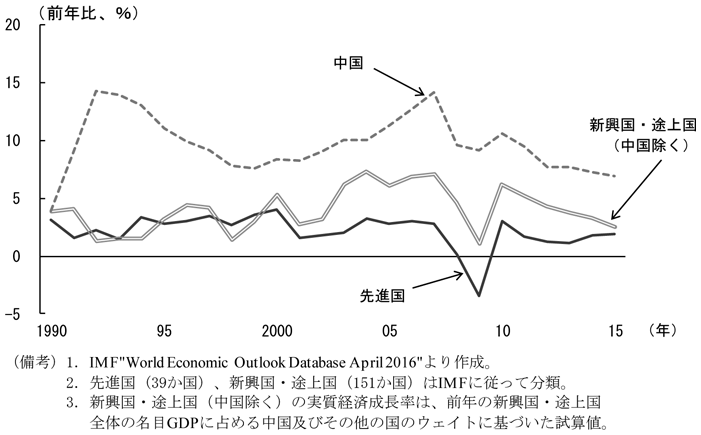
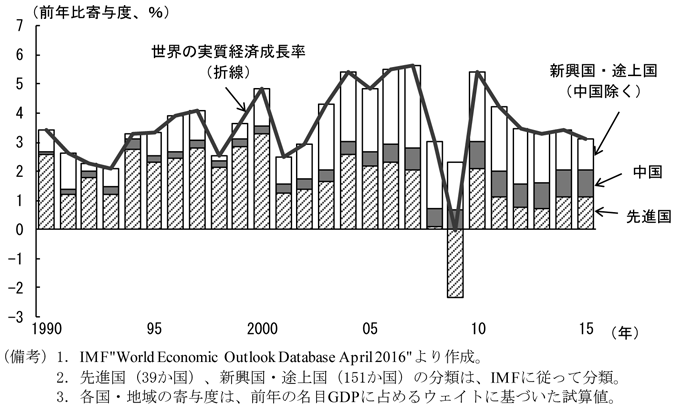
一方、世界貿易の推移をオランダ経済分析総局のデータでみると、世界金融危機後に一時的に落ち込んだ後、10~11年には急回復したものの、12~14年にかけて大幅に伸びが鈍化し、15年には09年以来のマイナスに転じた。その推移を数量と価格それぞれについてみると、まず数量は、10~11年に大幅に増加したものの、12年以降は2~3%程度の小幅な増加で推移している。一方、価格は、原油を含む国際商品価格の上昇に伴い、10~11年にはプラスで推移したものの、12年にはこれら商品価格の伸びが急低下し、15年には大幅なマイナスに転じた。ITC(国際貿易センター)のデータをもとに世界の名目輸入額を輸入国別に寄与度分解すると、09年から10年に大幅に増加(21.5%)した際は中国の寄与が3.1%と最も大きく、次いでアメリカの2.9%であった。14年から15年の減少(▲12.8%)についても、輸入国別では中国の寄与が▲1.5%と最も大きく、次いで日本の▲1.0%であった。これらの結果から、世界貿易の動向については、各国の輸入額の変動の中でもとりわけ中国の動向が大きな影響を及ぼしていることが明らかである(第1-1-3図)。
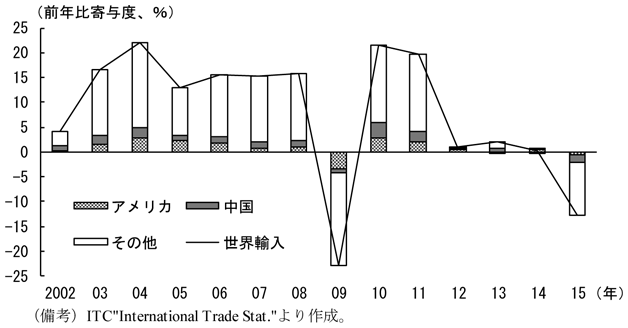
コラム1-1:長期停滞論(Secular Stagnation)について
長期停滞論とは、1930年代にハンセン・ハーバード大学教授が、アメリカ経済の大恐慌からの回復が緩やかにとどまっている状況を指して唱えたものである。第2次世界大戦の特需等によってアメリカ経済が急成長したこともあり、その後この主張は忘れられた存在となっていたが、ローレンス・サマーズ・ハーバード大学教授(元アメリカ財務長官)が13年11月の講演で、先進国経済の金融危機後の回復が緩慢であることについて「長期停滞に陥っている」と問題提起をしたことで、経済学者や政策担当者の間で再び注目されるようになった。
1.長期停滞とは
OECDは「長期停滞」について、長期にわたる経済の低迷により、労働の履歴効果(景気後退による一時的な失業者の増加が、技能など人的資本の劣化を招き、長期的な失業水準の上昇に繋がる現象)や投資減退を通じて潜在成長率が低下し、自然利子率が低いあるいはマイナスの状態になり、ゼロ金利政策によっても需要を喚起することができない状態と定義している(注1)。サマーズ教授は、アメリカの自然利子率は世界金融危機前の2000年代初期には既にマイナスとなっていたと指摘し、当時インフレなき完全雇用が達成されていたのは信用バブルと住宅バブルによるものに過ぎないとした。また、日本やヨーロッパについても長期停滞の状態にあると指摘した(注2)。加えて、長期停滞の状態の下では、伝統的な金融政策では、(1)完全雇用、(2)十分な成長、(3)金融の安定の同時達成は困難であるとも指摘した(注3)。
2.自然利子率低下の要因
自然利子率の低下の要因については様々な議論があるが(注4)、サマーズ教授は、経済全体が貯蓄志向となり、慢性的な貯蓄過剰の状態にあることが要因であるとしている。こうした貯蓄・投資のバランスの変化を起こす要因としては、人口成長率や労働力の伸び率の低下のほか、所得格差の拡大によって、より貯蓄性向の高い富裕層への富の分配により貯蓄率が上昇したこと、技術革新により投資需要が減退し、その結果企業が投資や借り入れを減らしていること等が挙げられている。
3.長期停滞の影響と政策対応について
自然利子率がマイナスであれば、政策金利をゼロにしても貯蓄と投資の間の均衡は回復できず、金融政策は限界に直面することになる。齋藤(2014)は、長期停滞の状況下での金融政策の有効性について、全く失われるわけではなく、(1)インフレ期待引き上げを通じたマイナスの実質金利の実現、(2)中央銀行のバランスシート拡大に伴うポートフォリオ・リバランシング、(3)為替レートの減価などを通じた政策効果の可能性を指摘している。
ユーロ圏などでは、マイナス金利の導入により、実質金利を自然利子率以下に引き下げようとする金融緩和政策がとられている。しかしながら、サマーズ教授は、長期にわたる低金利政策への依存は、大規模なバブルの発生と危険なレバレッジの累積を招く可能性があるとして、長期停滞への処方箋としては自然利子率の水準に依存しない需要喚起策を取るべきだと主張している。具体的には、規制・税制改革による民間投資の促進や、貿易の自由化、拡張的な財政政策が有効などとしている。齋藤(2014)も、潜在成長率の低下の背景にある構造問題への取組み、例えば人口動態変化や新興国との競争の強まり、イノベーション加速に対応した経済システムの見直しの重要性を指摘している。
(注1)OECD (2014)
(注2)Summers (2014)
(注3)CEPR (2014)
(注4)Gordon, R.による生産性低下など供給サイドの要因、Rogoff, K.の金融危機時の過剰債務によるデット・オーバーハング説、Bernanke, B.の新興国による過剰貯蓄説、Krugman, P.による流動性の罠などの要因が指摘されている。

