第1章 2022年後半の世界経済の動向(第1節)
第1節 世界経済の動向
2022年後半の世界経済は、国際商品市況の2022年夏頃にかけての高騰や経済全体での労働コストの増加等を背景として物価上昇が進行した。そのために物価安定に向けて金利及び量の双方から、過去と比較しても急速な金融引締めが進み、経済活動に対する政策的な下押しがみられた。しかしながら、新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)に対するワクチン接種の進展等による経済活動の再開の進展、雇用の安定、感染症対策等により形成された貯蓄超過や物価高騰対策等により、底堅い動きがみられた。
一方で、2023年の世界経済は、国際機関の見通しによれば成長の減速が見込まれており、マインド指標においては既に減速の可能性が示されている。
なお、急速な金融引締めが進む中で、金融市場においては、ドイツとユーロ圏の一部の国との国債利回りの差の拡大、国債市場のボラティリティの高まり、新興国等における為替相場の大幅な変動や資金流出入等の市場の変動もみられている。
本節では、世界経済の動向を、特に物価動向や金融政策の動向等に着目して、2022年後半を中心に分析する。続いて、世界経済の先行きやリスクについて概観する。また、欧州におけるエネルギーの確保と節約、各国のエネルギー価格高騰対策について整理するとともに、今後の設備投資や生産に大きな影響を与える重要な政策課題である脱炭素に向けた取組及び半導体のサプライチェーン強化に向けた取組についても概観する。
1.物価動向
本項においては、2022年後半の世界経済の動向を分析するにあたり最も重要な課題となっている物価上昇について、国際商品市況、労働コストの推移及び総需要と総供給の引締まりを踏まえて分析する。
(世界的に物価上昇が進展)
感染症拡大以降のG20諸国の消費者物価上昇率(総合、中央値)の推移を振り返ると、2020年4-6月期には経済社会活動の制限を背景に、輸送サービス及び飲食・宿泊サービス価格等の下落や原油価格の下落を受けて消費者物価上昇率は大きく低下した1。その後、行動制限の緩和や原油価格の持ち直し等があるものの、2020年末頃までは先進国においては、消費者物価上昇率はゼロ近傍で低迷した。
しかしながら2020年末以降、ワクチン開発及び接種の進展等に伴う経済活動の再開、及びそれに伴い原油価格が上昇傾向となるとともに2、部品供給の不足、物流の停滞及び人手不足といった供給制約等を受けて消費者物価上昇率は先進国及び新興国において上昇傾向となった3。
そのような状況下において、2022年2月のロシアによるウクライナ侵攻を背景としたエネルギー価格及び小麦価格等の高騰が生じ、先進国及び新興国共に消費者物価の上昇は加速した4。先進国においては2022年6月以降は7%台で推移し、新興国は3月から9月にかけて7%台で推移したものの、10月以降は下落に転じている(第1-1-1図)。
以下では、物価上昇の要因として国際商品市況、労働コスト(単位労働費用)及び総需要と総供給の引締まり(GDPギャップ)を確認した上で、アメリカ、ユーロ圏及び英国の物価上昇について分析する。
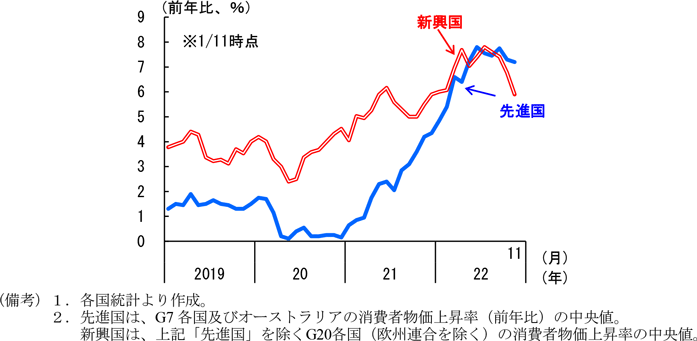
(国際商品市況:不安定な動きだが2022年夏頃の水準より下落)
(ⅰ)原油
物価動向を分析するにあたり、物価上昇の大きな要因となっているエネルギー価格の動向をみてみる。まず、原油価格については、2022年2月末のロシアによるウクライナ侵攻を受けて侵攻前の1バレル約93ドルから3月上旬には約124ドルまで急騰し、7月中旬頃までは100ドルを超える水準で推移した。
8月以降の原油価格の動向について、需要面では、各国中央銀行による金融引締めペースの加速に伴う世界景気の減速懸念、及びゼロコロナ政策の維持による中国経済の減速等による需要減の動きがみられた。
供給面では、OPECプラスの減産合意、イラン産原油の供給再開見通しの不透明感、及びロシア産原油の供給をめぐる不透明感等から供給面での不安がみられた。なお、ロシア産原油の供給については12月に入ると、G7とEU、オーストラリアは、ウクライナ侵攻に対する追加制裁措置として、ロシア産原油への上限価格を設定するとともに(1バレル=60ドル)、EUはロシア産原油に対する禁輸措置を実施した。
こうした需給両面の動きを受けて、原油価格は不安定な動きを伴いながらも、12月半ば時点では、ロシアによるウクライナ侵攻前の水準よりも低い70ドル台半ばで推移している。
(ⅱ)天然ガス
欧州における天然ガスの卸売価格は、2010年頃までは長期契約による石油価格にリンクした価格(石油インデックス)であったが、2010年代には市場における競争価格(スポット価格)への移行が進んだ5。このために他地域での需給動向が欧州の市場価格に反映されやすくなった。
こうした市場構造の中で、欧州のガス卸売価格のベンチマークであるTTF価格については、2021年央より、感染症からの経済活動再開に伴うアジア市場での需要増の影響に加え、ロシアから欧州へのガス供給が低調であったことから需給がひっ迫して徐々に上昇6し、12月中旬には2020年初と比較して15倍近い水準まで高騰した。その後2022年に入ると、ロシアによるウクライナ侵攻後、ロシアからのガス供給が徐々に減少することに伴いTTF価格は更に上昇し、8月下旬には2020年初と比較して26倍近い記録的な高水準にまで高騰した。
その後、欧州各国による2022年冬に向けたガス備蓄確保に一定の目途が立ったことから、9月初旬以降は低下傾向にあったが、11月に入ると暖房需要もありやや上昇し、12月中旬には100ユーロ/メガワット時台後半と、依然として高い水準にとどまっている。
今後については、暖房需要が膨らむ冬季に備え、EU各国はガス貯蔵を進めてきた結果、2022年冬のガス需給は緩和すると見込まれているものの、厳冬の可能性等には引き続き留意が必要である。
なお、欧州各国と域内企業は、ロシア産化石燃料への依存解消・代替調達先の確保を急ぐとともに、省エネやエネルギー調達の多様化と脱炭素に向けた取組を進めている(後述の5項(3)脱炭素に向けた政府と民間の取組を参照)。
(ⅲ)小麦
食料価格に大きな影響を与える小麦価格については、ウクライナ産小麦の輸出再開に関するロシアとの合意(以下、「輸出再開合意」という。)への期待等を受けて、6月下旬頃にはロシアによるウクライナ侵攻前の水準付近まで低下した。しかしながら、8月下旬以降は、ウクライナ情勢の長期化を受けて同国からの輸出への再懸念等から上昇し、10 月上旬には9ドル/ブッシェル台前半に値を上げた。その後、11月の輸出再開合意の延長やロシア産小麦の供給増加等から12月上旬には7ドル/ブッシェル台前半に値を下げたものの、ウクライナからの穀物輸出への不透明感の高まり等から値を上げ、12月中旬では7ドル/ブッシェル台後半で推移している(第1-1-2図)。
このように物価に大きく寄与するエネルギーや小麦価格は不安定な動きだが、2022年夏頃の水準より下落して推移している。
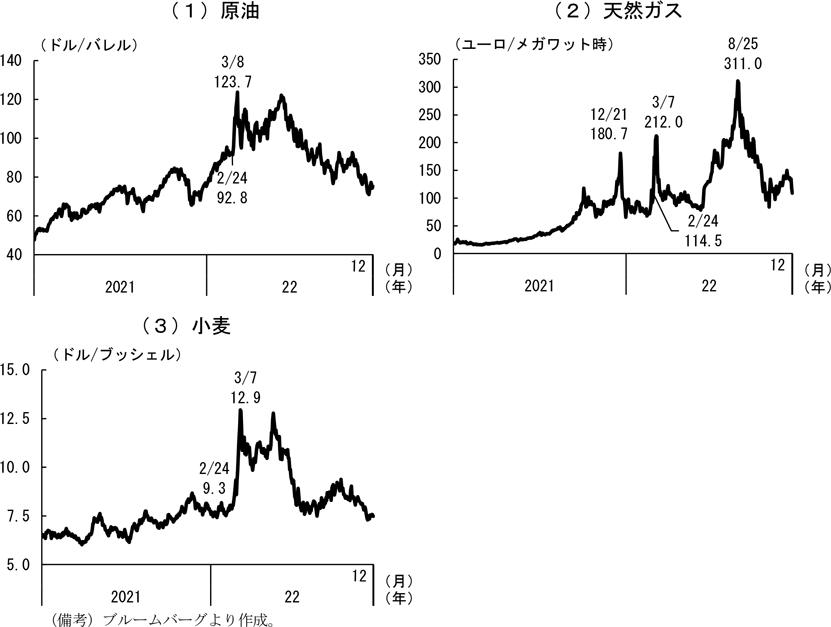
(単位労働費用:増加は物価上昇に寄与)
さらに、供給側からみた物価上昇要因となる労働コストの動向を確認するために、単位労働費用の推移をみてみる。単位労働費用は実質GDPを一単位生産するために必要な名目総労働費用を表し、労働コストの観点からみた物価変動の指標とされる7。単位労働費用の2019年から2022年4-6月期までの推移をみると、2020年から2021年にかけては感染症の拡大及び減退に伴う実質GDPの急速な増減を受けて大きく変動したものの8、2021年半ば以降はアメリカ、ユーロ圏、英国においていずれも上昇基調となっている(第1-1-3図)。こうしたことから、2022年4-6月期まで労働コストの増加が物価上昇の一因となっていたと考えられる。
なお、物価上昇が賃金上昇をもたらし、それが更なる物価上昇を引き起こすといったスパイラル的な物価上昇の懸念がみられ始めているところ、賃金及び労働費用面の動向には引き続き注視が必要である9。
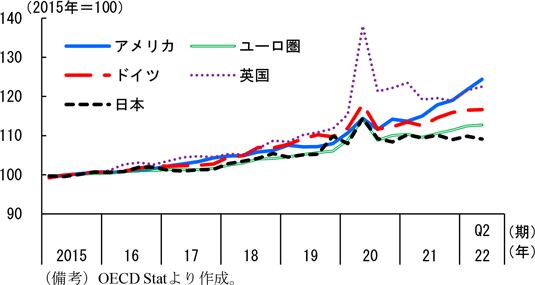
(GDPギャップ:感染症拡大前の水準に近づき、需給は引締まり)
マクロ経済全体での需給の引締まりを示すGDPギャップにつき、IMF(2022d)による推計値の推移及び今後の見通しをみると、アメリカ、ユーロ圏及び英国等においては、供給制約がある中において、経済活動の再開等に伴い需要が回復したことにより、GDPギャップが感染症拡大以前の水準に急速に近づき、経済全体での需給が引き締まっていることがうかがえる(第1-1-4図、第1-1-5表)。
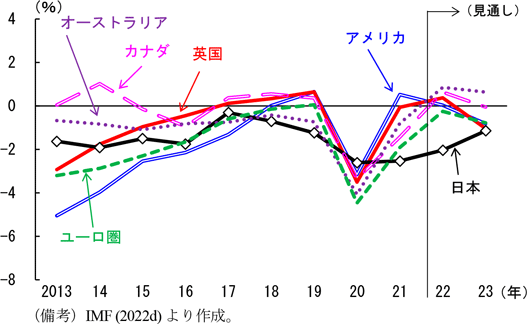

(アメリカの物価上昇はコア品目へと移行)
以上を踏まえ、アメリカ、ユーロ圏、英国の消費者物価上昇率(総合、前年同月比)の動きをみると、アメリカは原油価格の低下を受けて夏以降は低下傾向にあり、2022年6月に9.1%まで上昇した後、11月は7.1%まで低下している。一方で、ユーロ圏はガス卸売価格が高水準にあることなどを受けて10月には10.6%まで上昇した後に11月には10.1%、英国も同様の理由で10月には11.1%まで上昇した後に11月には10.7%となり、一服感がみられている(第1-1-6図)。
さらに、総合指数をエネルギー、食料(生鮮含む)、財(エネルギー、食料以外)とサービスに分けてみると、ユーロ圏では総合指数への寄与度の約6割、英国では約5割をエネルギー及び食料が占めており、引き続き国際商品市況を受けた物価上昇圧力が大きい状況が続いている。
これに対し、アメリカでは、ユーロ圏及び英国に比べてエネルギー供給制約が限定的であることから、夏以降、財及びサービスといったコア品目に物価上昇の主要因が移行していることが確認できる。アメリカのコア品目の内訳をみると、感染症拡大による景気減速からの回復局面初期においては、行動制限のために財需要がサービス需要よりも相対的に強かったため、財価格の上昇が先行した。その後、行動制限緩和に伴うサービス需要の高まり、労働コストの上昇及び住宅価格上昇に伴う住居費の上昇を受けてサービス価格が上昇傾向となり、アメリカの消費者物価全体に対する最大の押上げ要因となっている。なお、住宅価格は2022年後半に入り下落していることから、住居費については今後一定期間の遅れを伴って上昇率が低下する可能性がある10(住宅価格については後述の2節1項を参照)。
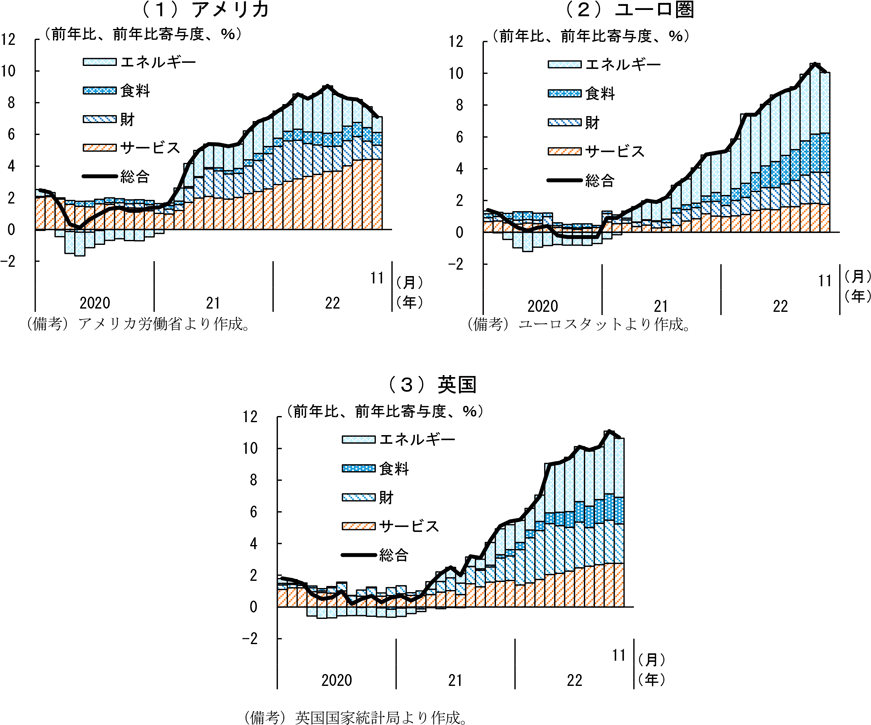
2.金融政策の動向
2項では、1項で確認した物価上昇の加速を受けた、欧米による物価安定に向けての急速な金融引締め状況とその影響を分析する。
(金融引締めは2021年に新興国が先行)
2021年以降、経済活動の再開と物価上昇を背景に各国で金融緩和の縮小や金融引締めが進められた。2022年は物価上昇の加速を受けて、こうした動きに一段の進展がみられたが、新興国と先進国では利上げの開始時期や頻度が異なる。
G20諸国の各月の政策金利変更回数をみると、新興国については、2021年前半から複数の国が利上げを行っており、2021年後半以降は利上げを行う国が一段と多くなった。この中で、ブラジルは2021年3月と早期に利上げを開始し、2022年9、10月の政策決定会合では政策金利を据え置くなど、一部の新興国においては金融引締めのテンポ鈍化に向けた動きがみられる(後述の4項(3)国際金融環境において金利引上げ幅も含めて新興国の動向について確認する)。
一方、先進国については、利上げは2021年末から実施されており、2022年春以降になり利上げを行う国が増えるなど、新興国に比べて遅いタイミングでの金融引締めがなされている(第1-1-7図)。
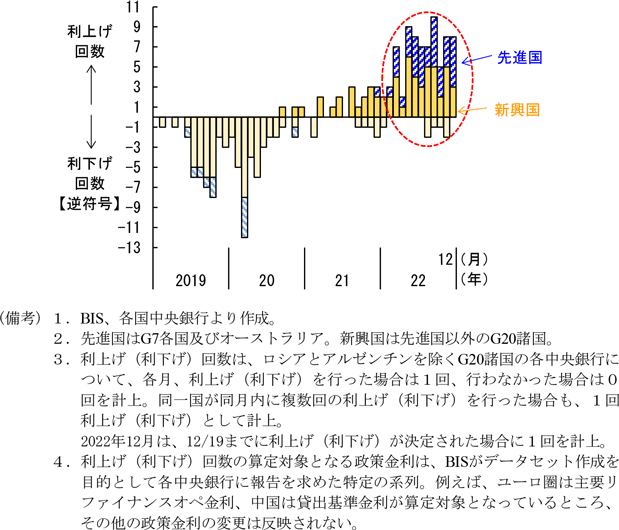
(欧米中銀は物価安定に向けて急速に金融引締めを実施)
また、欧米中銀は政策金利を連続して大幅に引き上げるといった急速な金融引締めを進めており11、アメリカの連邦準備制度理事会(FRB)は2022年3月の連邦公開市場委員会(FOMC)においてフェデラル・ファンド・レート(FF金利)の誘導目標範囲を0.25%ポイント引き上げて以降、2023年2月までに累計で4.50%ポイントの大幅な引上げを行った。欧州中央銀行(ECB)は7月の理事会において主要リファイナンスオペ金利を0.50%ポイント引き上げて以降、2023年2月までに累計で2.50%ポイント引き上げた。また、イングランド銀行(BOE)は2021年12月の金融政策委員会においてバンク・レートを0.25%ポイント引き上げて以降、2023年2月までに累計で3.75%ポイント引き上げた(第1-1-8図)。
さらに、量的緩和を意図した保有資産の削減については、FRBは予定されていた9月以降の削減の上限額引上げを実施するとともに、BOEは後述するように延期となっていた国債の売却を11月から開始するなどの対応を行っている(第1-1-10表)。
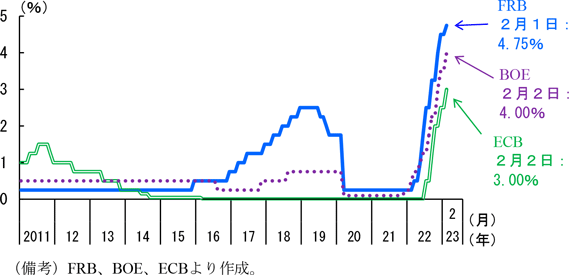
以下、欧米主要国・地域の金融引締めの進展状況について中銀ごとに確認する。
(ⅰ)アメリカ
FRBは、引き続き金融引締めを進展させており、2022年6月以降は4回連続でFF金利を0.75%ポイント引き上げた。12月以降は2回連続で利上げ幅を縮小し、12月のFOMCにおいて0.50%ポイント、2023年2月に0.25%ポイント引き上げ、誘導目標範囲は4.50~4.75%となっている。今後の利上げ予定について、FRBは誘導目標範囲の継続的な引上げが適当とし、2022年12月に示したFF金利の予想12は、9月に示した予想13よりも最終的な金利水準が高くなる可能性を示し、物価上昇率が2%に戻ると確信できるまでは利下げは考えないとした。
(ⅱ)ユーロ圏
ECBは、7月の11年ぶりの利上げ(0.50%ポイント)決定後も、9月及び10月の政策理事会において利上げ幅を0.75%ポイントに拡大した後、12月及び2月の理事会においては0.50%ポイントの利上げを決定しており、主要リファイナンスオペ金利を3.00%とするなど金融引締めを進展させている。今後の利上げの予定についてECBは、2月の政策理事会において、次回3月の理事会で再度0.50%ポイントのペースで利上げを行い、さらに金融政策の今後の道筋を検討する予定とした上で、物価上昇と経済の見通しに基づいて会合ごとに決定するとしている。また、ECBは12月の政策理事会において、資産購入プログラム(APP)において償還された元本の再投資を3月以降一部停止するなどの量的引締め開始に向けた方針14を示した。
なお、金融引締めが進む中で、2021年秋以降、ユーロ圏の一部の国の国債利回りが上昇し、ドイツの10年物国債との利回りの差が開く状況が生じている(第1-1-9図)。ECBは、この状況が続けば、財政状況がぜい弱な国では資本流出や利回りの上昇が起こり、金融環境が過度に引き締まる結果、資金調達環境の悪化といった自己実現的な財政問題(self-fulfilling financial tensions)が引き起こされるとの懸念を示している。
ECBは、このような事態を回避し、金融政策を効果的に波及させるための対応として、感染症拡大時に導入した資産購入プログラムである「パンデミック緊急購入プログラム」(PEPP:Pandemic emergency purchase programme)の再投資資金の柔軟化活用を行い、イタリアとスペインの国債についてはキャピタルキー(ECBへの出資比率)を上回って購入し、これらの国々とドイツとの金利差が大きく開かないよう調整している。しかしながら、この枠組みは再投資資金枠内での買入れしか実施できないなどの制約があることから、市場の更なるストレスに対応するために、新たな枠組み(TPI:Transmission Protection Instrument)を7月に導入した15。
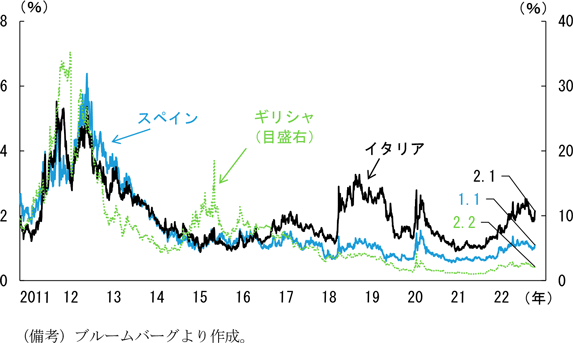
(ⅲ)英国
BOEは、引き続き金融引締めを進展させており、8月及び9月の金融政策委員会において利上げ幅をそれまでの0.25%ポイントから0.50%ポイントに拡大、11月の同委員会では更に約33年ぶりとなる0.75%ポイントにまで拡大した後、12月及び2月の同委員会では0.50%ポイントの利上げを決定した。その結果、バンク・レートは4.00%となった。今後の利上げの予定について、BOEは、2月の同委員会において、物価上昇率を中期的に持続的に2%の目標まで戻すために必要に応じて金利を調整するとの方針を示している。
また、資産購入枠において保有していた国債の売却を当初9月に開始することを予定していたが、トラス政権による物価対策の事業規模と財源に対する市場の不安等を受けた国債利回りの高騰等の市場の混乱を受けて延期され、11月1日より開始された。なお、社債の売却については2月より開始されていたが、9月27日の売却実施後に同様に延期され、10月25日に再開された。

(長期金利は急速に上昇し、住宅需要は減少)
このような政策金利の引上げや保有資産の削減を受けて、長期金利は2022年初から上昇傾向となり、特に夏から10月にかけては欧米中銀がそろって政策金利を大幅に引き上げたことなどから、2022年10月頃にかけて長期金利が3%ポイント以上上昇した。なお、アメリカの前回の利上げ局面(2015年末~2019年半ば)では約3年かけて1%ポイント長期金利が上昇していることから、今回は長期金利の上昇ペースも急速であったことが確認できる(第1-1-11図)。このような長期金利の急上昇はアメリカにおいては住宅ローン金利を通じて住宅需要を減少させているが(後述の2節を参照)、ユーロ圏や英国においても同様の効果が見込まれている。
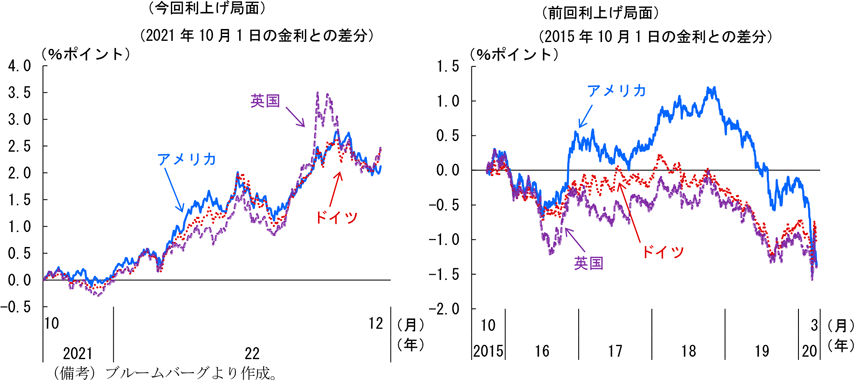
(金融引締めに伴う副次的な影響に留意が必要)
今回の金融引締め局面においては、英国の物価対策に関連する市場の混乱、イタリア等の国債利回りとドイツ国債利回りの差が広がる状況、長期金利の急速な上昇、アメリカにおける国債価格の変動リスクの高まり(第1-1-12図)及び新興国等におけるドル高・各国通貨安や資金流出入の変動(後述の4項(3)国際金融環境を参照)といった金融市場における副次的な影響がみられている。今後とも欧米中銀においては政策金利の引上げが見込まれるとともに、ECBにおいても量的引締めが開始される予定となっており、金融市場には更なる副次的な影響が生じる可能性がある。このような影響は実体経済にも伝播する可能性が否定できないところ、今後とも金融市場の動向を注視する必要がある。
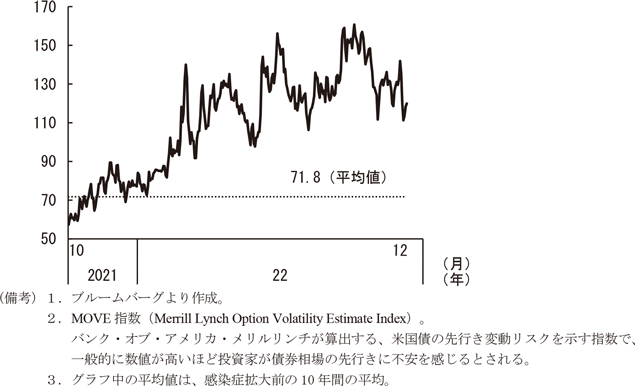
3.世界経済の動向と背景
このように物価上昇率が高い状況において急速な金融引締めが行われた中、世界経済はどのように推移してきたのだろうか。以下では実質GDP成長率及び主要な需要項目等から現在の経済動向を確認し、2節において地域ごとにより詳細な分析を行う。
(1)先進国
(アメリカはユーロ圏や英国に比べ回復力が強い)
まず、先進国における経済動向を確認する。先進国の実質GDPをみると、2022年7-9月期はアメリカ及びユーロ圏はプラス成長となりながらも、アメリカはユーロ圏に比べ相対的に回復力が強く、英国は2022年7-9月期に若干のマイナス成長となり足踏み状態となった(第1-1-13図)。感染症拡大前と比べると、実質GDPはおおむね感染症拡大前の水準を回復している。
需要項目別にみると、2022年4-6月期、7-9月期は、個人消費はサービス消費を中心に回復しているが、消費者物価上昇率の違いなどを背景に、アメリカでは持ち直しの動きが続いているものの、ユーロ圏においては持ち直しに足踏みがみられ、また英国においては弱含んでいる。設備投資はアメリカ及びユーロ圏ではR&Dやソフトウェアといった知的財産生産物を中心に持ち直しているものの、英国においては横ばいとなるなど、内需の主要項目は、相対的にアメリカの回復力が強い状況となっている。
また、貿易面をみると、2022年4-6月期、7-9月期は、輸出においては、アメリカは原油や天然ガス等の工業原材料を中心に底堅く推移する一方、ユーロ圏及び英国は持ち直しから減速傾向となった。輸入においてはアメリカ、ユーロ圏及び英国においても頭打ちとなっている(第1-1-14図)。
なお、2022年10-12月期においては、アメリカは貿易面においては減速感がみられるものの、個人消費と設備投資は引き続き持ち直しており、プラス成長を維持している。ユーロ圏においても10-12月期は引き続きプラス成長を維持しているが、アメリカの回復力が相対的に強い状況が続いている。
このようなアメリカとユーロ圏及び英国の経済動向の背景には、(ⅰ)経済活動の再開の進展、(ⅱ)雇用の安定、(ⅲ)感染症対策等により形成された貯蓄超過の取崩しと物価高騰対策(5節にて詳述)という回復要因がある一方で、回復力の違いの背景としては、物価上昇率の違いに加えて、(ⅳ)エネルギー価格高騰等による交易条件の改善及び悪化、が考えられることから、以下において確認する。
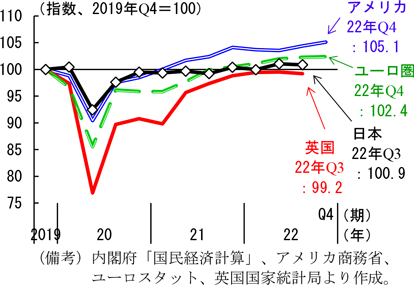
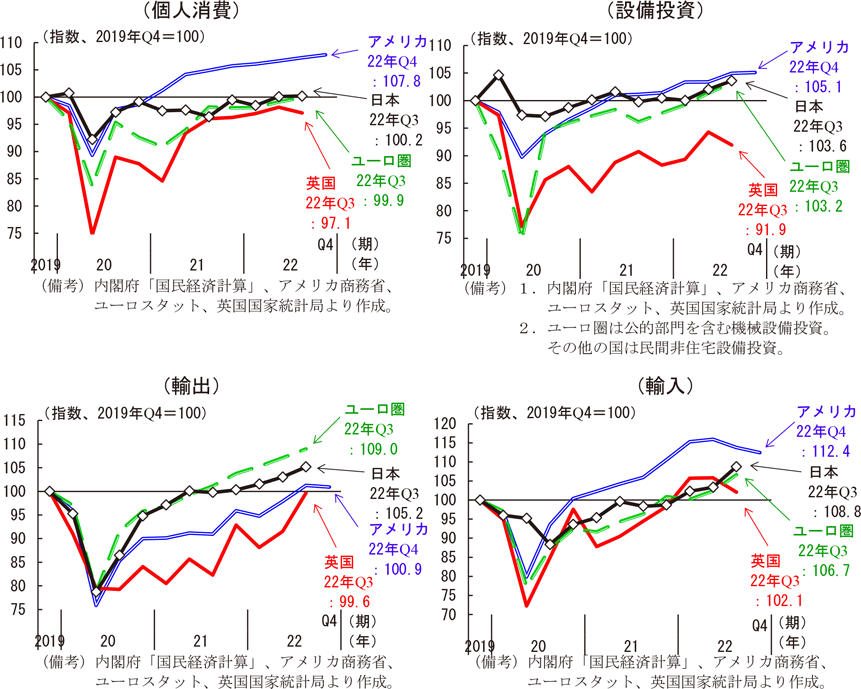
(経済活動の再開の進展)
2021年前半にワクチン接種が進展したことにより、ユーロ圏においては2021年夏頃に経済活動の再開に伴って旅行代理店、宿泊業、飲食サービス業を含むサービス業の景況感は大きく改善した。その後、季節的な変動に加えて、変異株の感染拡大に伴う一時的な行動制限等による低下を伴いながらも、2022年4-6月期にかけて改善している。また、7-9月期も、物価上昇による可処分所得の減少がみられる中においても夏季の旅行需要が堅調であったことから、サービス業の景況感は減速しながらも改善を続けた。10-12月期に入っても底堅く推移していることから、経済活動の再開の進展が消費を下支えしていることがうかがえる(第1-1-15図)。
また、感染症拡大を受けて実施が先送りされていた設備投資も回復しており、アメリカやユーロ圏においては知的財産生産物を中心に増加がみられている(地域別の詳細は後述の2節を参照)。
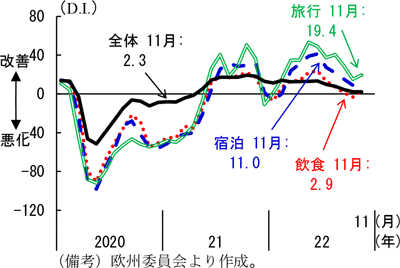
(雇用は安定)
雇用情勢について、主要国の失業率をみると、ユーロ圏と英国では2021年末頃には感染症拡大前(2020年3月)の水準を下回り、緩やかな減少傾向が続いている。アメリカも2022年夏頃までに感染症拡大前(2020年2月)とほぼ同水準まで低下した後、同水準で推移している(第1-1-16図)。このように雇用は安定しており、労働市場の引締まりを受けた名目賃金の上昇(地域別の詳細は後述の2節を参照)が消費の下支えに寄与している。
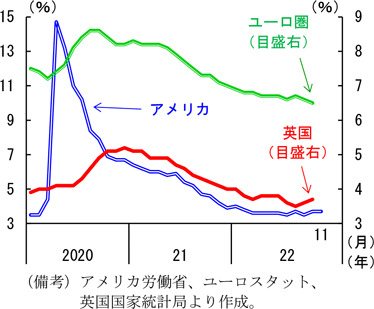
(感染症対策等により形成された貯蓄超過は、アメリカでは取崩しが進み消費を下支え)
アメリカ及びユーロ圏においては、感染症対策の一環としての現金給付等の政策の下支えや消費の抑制により、家計貯蓄の増加(貯蓄超過)が2020年以降みられるようになった16。
コロナ禍前(2019年)のフローの貯蓄額からのかい離を積み上げて推計した貯蓄超過ストックはアメリカにおいては2021年7-9月期にかけて約2.4兆ドル(対GDP比約12%)まで積み増されてきたが、物価上昇率が一段と上昇し始める2021年10-12月期より0.1~0.3兆ドルずつ取り崩す動きがみられており、物価上昇下にあっても堅調な消費の下支えに寄与していると考えられる。
一方でユーロ圏においては緩やかではあるものの貯蓄超過を積み増す動きが引き続きみられ、2022年4-6月期では約1.0兆ユーロ(対GDP比約9%)まで積み増されており、また物価上昇による目減りもユーロ圏では大きいことから、消費の下支えには寄与していないものと考えられる17(第1-1-17図)。
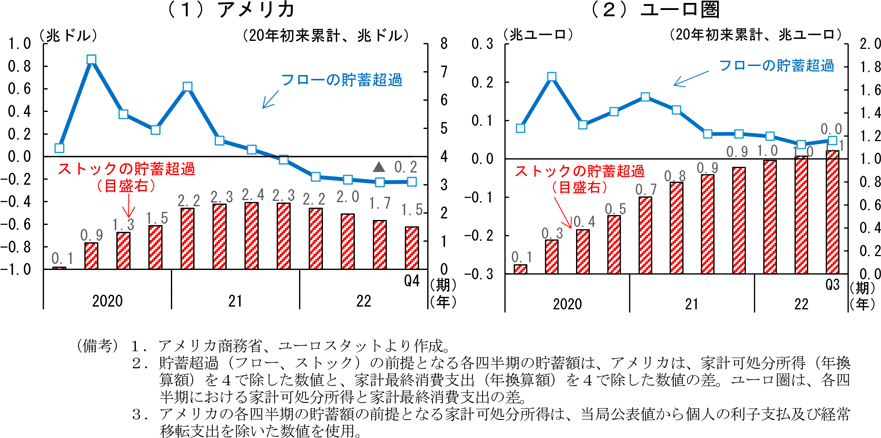
(交易条件はアメリカでは改善し所得流入、ユーロ圏では悪化し所得流出)
他方、交易条件の改善ないし悪化の違いが回復力の違いの背景にあると考えられる。
アメリカは2020年半ば以降、食料品やエネルギーを中心に交易条件は改善傾向にあったことに加え、2022年に入りウクライナ情勢を背景としたエネルギー価格高騰等を受けて交易条件が更に改善し、海外からの所得流入が増加した。
一方、ユーロ圏及び英国は2021年後半にはエネルギー価格上昇に伴い交易条件が既に悪化していたことに加え、2022年になりウクライナ情勢によりエネルギー価格が高騰したこと等を受けて交易条件が更に悪化し、所得流出が拡大している(第1-1-18図、第1-1-19図)。
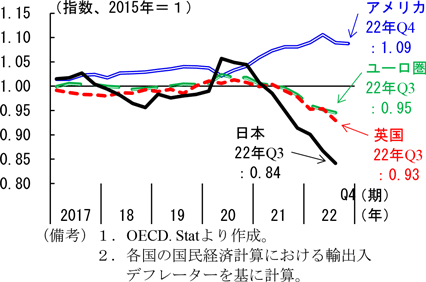
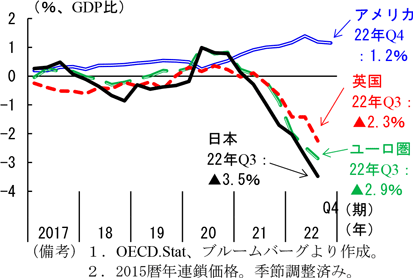
(2)新興国
(新興国は感染拡大前の実質GDP等の水準を回復)
続いて、新興国に目を向けると、中国では、2022年4-6月期には感染症拡大により一部地方の経済活動が抑制されたことで持ち直しの動きに足踏みがみられたものの、7-9月期は猛暑と水不足を背景とした電力制限が一部地域で発生した中でも、インフラ投資や自動車販売の促進等を背景に、実質GDP成長率が前年比・前期比共に+3.9%となるなど持ち直しの動きがみられた。その後、10-12月期は感染症再拡大の影響から、輸出を含む各種指標に弱さがみられることとなり、実質GDP成長率は前年同期比+2.9%、前期比+0.0%と減速し、2022年通年の成長率は前年比+3.0%にとどまった。その他の主な新興国では、いずれも7-9月期の実質GDP成長率が、インドで前年比+5.7%、ブラジルで同+3.6%、南アフリカで同+4.2%となり、これらの国々の実質GDPおよび需要項目別内訳はおおむね感染症拡大前の水準を回復した(第1-1-20図、第1-1-21図)。
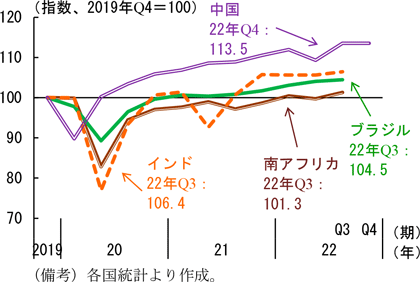
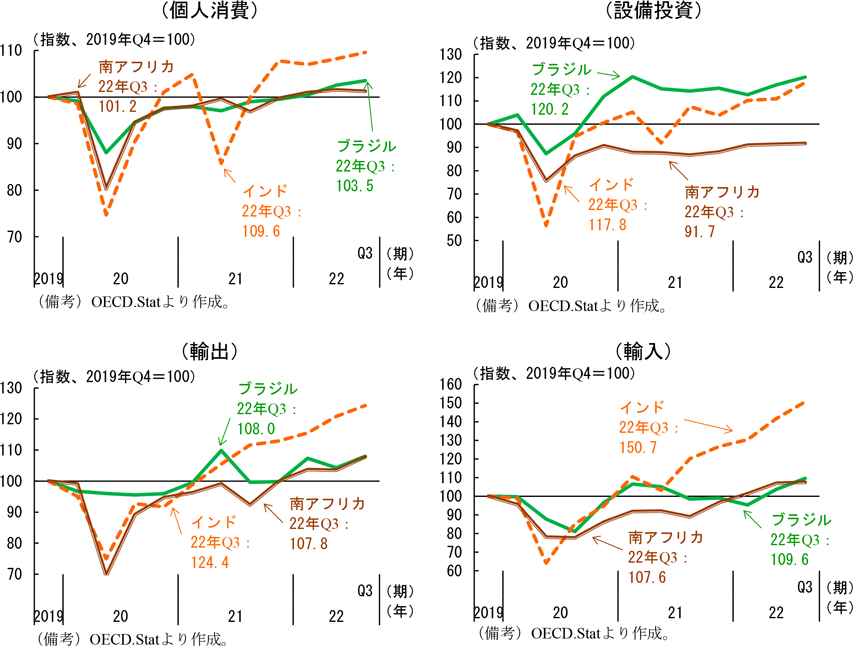
(3)世界経済
(世界経済は2022年後半にかけては総じて底堅い動き)
このように先進国及び新興国の実質GDPはおおむねプラス成長を維持するとともに、感染症拡大前の水準を回復している。先進国においては、経済活動再開の継続や雇用の安定に加え、政策等により形成された貯蓄超過はアメリカにおいて消費を下支えし、欧州では物価高騰対策が進められている。こうした中で世界経済は2022年後半にかけては総じて底堅い動きがみられた。一方で、物価上昇率がより高いことと、エネルギー価格高騰に伴う交易条件の悪化により、ユーロ圏及び英国の回復力はアメリカとは異なる点には留意が必要である。
4.世界経済の先行き
本項では経済活動の先行きにつき各種指標から確認し、主要国際機関による見通しを整理した上で、国際金融環境について整理する。
(1)経済指標の動き
(財貿易は横ばいとなり、国際輸送コストは弱い動き)
まず世界の財貿易量の動向をみると、中国の防疫措置の一部緩和を受けて5月に増加したものの、半導体の需要鈍化や中国経済の減速等を受けて、2022年後半の財貿易量は横ばいで推移している(第1-1-22図)。こうした貿易量の伸び悩みを背景に、世界の鉱工業生産も2022年後半は横ばいで推移している(第1-1-23図)。
国際輸送コストを表すバルチック指数の動向をみると、海運指数18は2022年5月下旬にかけて上昇したものの、11月末にはロシアによるウクライナ侵攻以前の水準を下回り、2021年2月上旬頃の水準まで低下している(第1-1-24(1)図)。空運指数は2021年9月以降に上昇傾向となった後、2022年前半は高い水準で推移したものの、2022年7月以降は低下傾向となり、11月末には2021年8月末の水準までおおむね低下した(第1-1-24(2)図)。いずれも感染症拡大以前の水準よりは高いものの、このような国際輸送コストの低下は貿易財の価格低下を通じて今後各国の物価上昇率を引き下げることが考えられる。
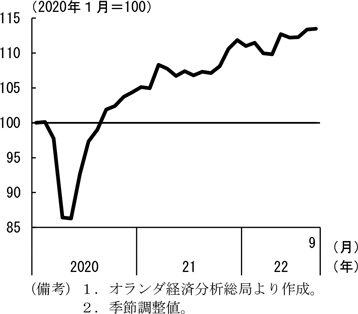
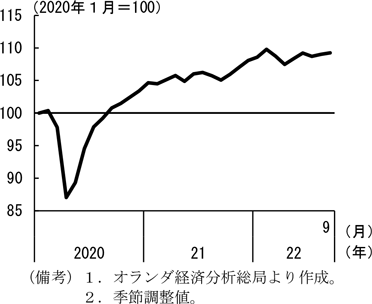
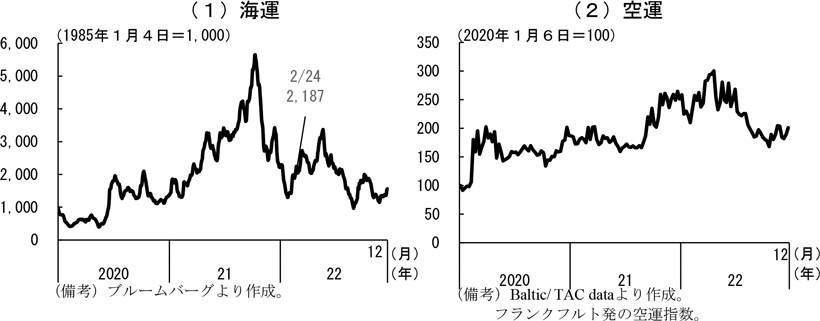
(マインド指標は景気の減速を示唆)
次に、国際的な景気動向を反映するマインド指標であるグローバルPMIをみると、2022年3月以降、新規輸出受注指数(製造業)は分岐点の50を下回って推移している。また、生産指数(製造業・非製造業)は8月以降、50を下回って推移している。これらの指標の2008年のリーマンショック以降の推移をみると、OECD諸国全体でのGDPの前年同期比とおおむね一致または先行する傾向がみられている。2022年後半までは世界経済は総じてみれば底堅さがみられたものの、マインド指標が低下していることに鑑みれば、今後景気が減速する国や地域が増える可能性があると考えられる(第1-1-25図)。

さらに、欧米企業の景況感をみると、製造業に関しては、2021年後半には景況感は緩やかな低下基調となり、特にユーロ圏は天然ガス価格の高騰等の影響を受けてアメリカよりも相対的に景況感が悪化し、2022年夏以降は分岐点の50を下回ることとなった。ユーロ圏に続き、11月にはアメリカも50を下回ることとなった(第1-1-26図)。
また、非製造業に関しては、アメリカでは底堅い新規受注や入荷遅延の改善等を背景に、景況感が50を上回って推移しているが、ユーロ圏においては製造業と同様に天然ガス価格の高騰等の影響から2022年夏以降は50を下回ることとなった(第1-1-27図)。
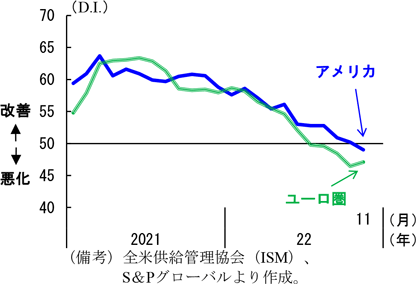
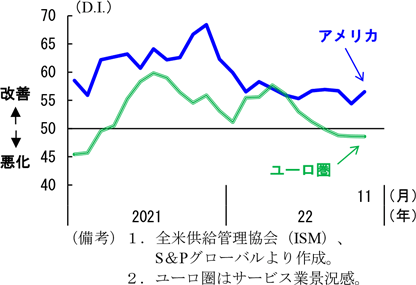
他方、企業だけでなく、消費者の観点から景気の先行きを考えるために、欧米の消費者マインドをみると、アメリカでは消費者物価上昇率が夏以降は低下傾向で推移していること等を背景に、2022年後半は消費者マインドが横ばいで推移している。一方、ユーロ圏の消費者マインドは、消費者物価上昇率の上昇の持続を背景に、2022年を通して悪化傾向が続いている(第1-1-28図)。

(2)国際機関の見通し
(成長率見通しは下方修正から上方修正に)
続いて、2023年の世界経済及び各国経済について、国際機関の成長率見通しをみると、物価上昇等を受けて従来の見通しから下方修正が続いていたが、IMFの最新の見通しでは英国以外は総じて上方修正された(第1-1-29表)。10月に公表されたIMF (2022d)では、(ⅰ)多くの地域における金融引締めの影響、(ⅱ)中国経済の急減速、(ⅲ)ロシアから欧州へのガス供給削減等を踏まえ、7月の見通しから2023年の成長見通しが一段と下方修正された19。しかし、1月に公表されたIMF (2023a)では、(ⅰ)2022年後半の予想以上に堅調であった欧米等の国内需要のキャリーオーバー効果20、(ⅱ)経済活動の再開による中国経済の回復、等の結果、2023年の世界全体の成長率は2.9%と、7月に公表されたIMF (2022c)と同程度まで上方修正となった21。なお、IMF (2022d)は、世界経済は下方リスクの方が支配的であると指摘しているが22、後述する脱炭素やサプライチェーン強化に向けた設備投資関連の動きについては上方リスクとしている。これに加え、IMF (2023a)は、上方リスクとして貯蓄超過を原資としたサービス消費の回復や、早期の物価上昇率低下の可能性等を指摘した上で、下方リスクの方が依然として大きいものの、その程度はIMF (2022d)よりも緩和しているとしている。

(物価上昇率の見通しは上方修正)
一方、IMF (2022d)においては、2022年、2023年の物価上昇率見通しが上方修正された(第1-1-30表)。その背景としては、感染症の収束に伴う需要回復、財需要から観光等のサービス需要へのリバランス、国際商品市場における食料・エネルギー価格の上昇が消費者価格に遅れて波及すること等が指摘された。また、国・地域ごとに状況は異なり、欧州ではウクライナ情勢を受けた食料・エネルギー価格の高騰が主な物価上昇要因となる一方、アジアではエネルギー及び食料価格の上昇が穏やかであることから物価上昇が欧米と比べて相対的に緩やかとしている23。さらに、物価安定に向けて急速な金融引締めが進む中、物価上昇率は2022年にピークを迎え、2023年は総じて低下する見込みとなっている。
加えて、IMF (2023a)では2022年、2023年の物価上昇率見通しがわずかながら更に上方修正されたものの、2023年以降の物価上昇率の低下要因として、需要減による国際的な原材料価格の下落、金融引締めによるインフレ抑制効果を指摘している。

(財政収支GDP比は改善し、政府債務残高GDP比は上昇が抑えられる見通し)
各国の財政収支と政府債務残高の対GDP比をみると、2022年は景気回復と感染症対応のための大規模な財政支援の縮小等24を背景に財政収支対GDP比が改善し、政府債務残高対GDP比も上昇が抑えられると見込まれている。2023年以降も多くの国で財政面の改善が見込まれている(第1-1-31図、第1-1-32図)。
他方、先進国、新興国を問わず一部の国々では、2023年には金利上昇や成長率の低下を受けて財政収支対GDP比の悪化や政府債務残高対GDP比の上昇が見込まれている。こうした状況を受けて、IMF (2022a)では財政健全化が物価安定に向けた強いシグナルになるとの立場から、物価上昇率が高い国においては財政政策のターゲットを絞るなどの取組を通した歳出削減により25、財政規律を取り戻すことが重要としている。また、財政健全化による早期の物価安定は中央銀行による将来の利上げ幅を小幅に抑え、金融引締めの景気抑制効果を緩和することにつながるとしている。
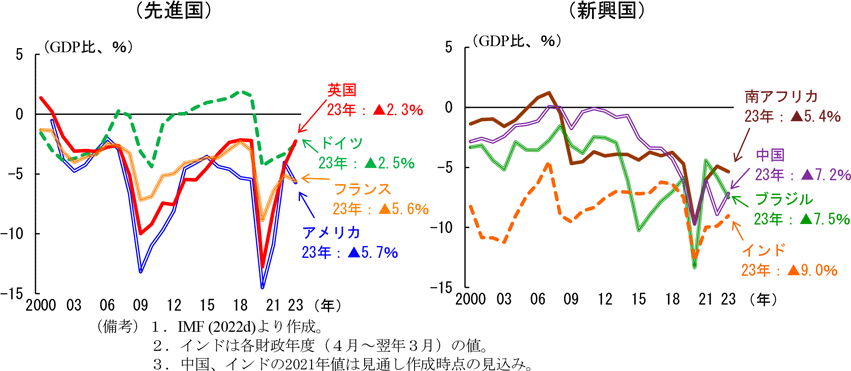

(3)国際金融環境
(為替相場は金利動向等を反映しドル高基調が続いた後、反転ドル安の動きへ)
最後に、国際金融環境について整理する。
まず為替相場の状況をみてみる。先進国通貨はFRBが連続して大幅利上げを実施したこと等の影響もあり2022年3月頃から10月頃にかけて対ドルで減価傾向となったが、11月に入るとアメリカが利上げペースを緩めるとの見方等から対ドルで各国通貨高の傾向となった(第1-1-33図)。
新興国通貨はFRBが連続して大幅利上げを実施したこと等の影響もあり、2022年6月以降、一部の国を除き対ドルで減価傾向となった。
資源国通貨については、2022年7月以降、ブラジルやメキシコの為替相場は対ドルで一定の水準を維持している一方、インドネシアと南アフリカの為替相場は引き続き対ドルで減価傾向が続いており、資源国の中でも為替相場の動向に国ごとの違いがみられる。ブラジルは、新興国の中では比較的早期の2021年3月に利上げを開始し、2022年8月までに累計で11.75%ポイントの利上げを行い(第1-1-34図)、物価上昇率が低下26したこと等から通貨レアルの対ドル為替相場の水準が維持されたとみられる。また、メキシコは、ブラジルより3か月遅れたものの、比較的早い時期に利上げを始め、2022年11月までに累計で6.00%ポイントの利上げを行っている。さらに、メキシコはアメリカへの輸出が輸出総数量の8割を占め、アメリカへの貿易依存度が高く、アメリカの需要が引き続き堅調であること等から通貨ペソの対ドル為替相場の水準が維持されたとみられる。
非資源国通貨については、2022年8月に入ると各国の利上げの効果もあり通貨安が一服したものの、2022年9月以降、再び対ドルで減価傾向に戻った。これは、非資源国の利上げ幅は、先進国(特にアメリカ)や資源国(ブラジル、メキシコ等)に比べると、限定的であること等が一因とみられる(第1-1-34図)。なお、11月に入るとアメリカが利上げペースを緩めるとの見方に加えて、各国中央銀行自身が景気にも配慮しながら利上げを続ける意向が強いとの見方から、対ドルで各国通貨高の傾向にある。
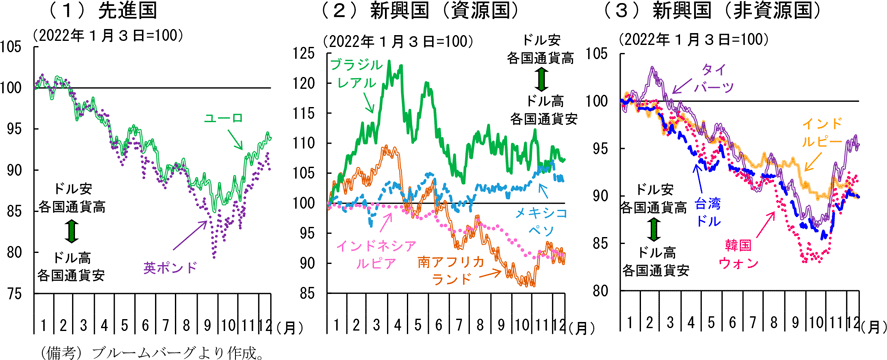

(資金流出が非資源国で続いた後、方向性に欠ける動き)
続いて、資金流出入の状況をみてみる。新興国における資金流出の背景には、世界的な物価上昇、それを受けた各国の急速な金融引締めや、新興国経済のファンダメンタルズ(基礎的条件)27等の要因が影響していると考えられる。
2022年は、2月のロシアによるウクライナ侵攻後は、非資源国からの一貫した資金流出超過がみられたが、8月以降は流出入について一貫した方向性はみられない(第1-1-35図)。

5.エネルギー確保・価格高騰対策と脱炭素に向けた取組の進展
ロシアによるウクライナ侵攻は原油や天然ガスといったエネルギー価格の高騰を招くとともに、欧州においてはロシアからの天然ガス供給が滞るなど経済活動の基盤そのものが脅かされる事態となった。そのために地球温暖化対策の観点から脱炭素に向けて進められてきた再生可能エネルギーの供給拡大については、エネルギー自給率を高めるといった経済安全保障の観点からも重要な課題となった。
本項では、欧州におけるエネルギー確保と消費削減、及びエネルギー価格高騰に対する欧州主要国等の価格抑制策や低所得者向けの給付といった短期的対応を整理した後、脱炭素に向けた欧米各国の政府及び民間による取組状況を紹介する。
(1)欧州におけるエネルギー確保と消費削減
(欧州ではエネルギーの備蓄、火力発電所の再稼働等と消費削減に同時に取り組む)
EUは、ガス輸入の40%以上をロシアからの供給に依存(2021年値)していることからエネルギー危機の深刻度がより高いために、EU全体として以下のようなエネルギー確保及び消費削減策が採られている。
一つ目は、エネルギー需要が増加する冬季に備えたガス備蓄の引上げである。ガス地下貯蔵施設を有する18の加盟国に対し、2022年11月1日までに自国内のガス貯蔵施設の備蓄上限の8割(2023年11月以降は9割)を備蓄することを義務付ける規則が7月より施行された。これによりユーロ圏のガス貯蔵レベルはEU全体では11月末時点で95%程度まで上昇するなど例年より高い水準まで備蓄されており(第1-1-36図)、今後の天候条件にもよるものの、今冬分の需要については確保された可能性が高いと考えられる。
二つ目は、火力発電所の再稼働等である。ドイツは、期間を限定して石炭火力発電所を稼働させることに加え、原子力発電所についても2022年末停止予定の3基のうち2基について2023年4月中旬まで緊急時予備電源に振り向ける予定であったが、残りの1基も追加し、電源確保に取り組んでいる。フランスはエネルギー供給確保に向けて経営権拡大のためにフランス電力(EDF)を100%国有化することとした。
三つ目は、ガス消費の削減に向けた取組である。8月に、全加盟国を対象とし、2023年3月31日までの期間、過去5年の同時期平均と比べて、ガス消費量を自主的に15%削減するよう要請する規則が施行された。なお、エネルギー需給がひっ迫しEUレベルの警報が発動された場合にはこの15%削減は義務化されることとなっている。また、ドイツ及びフランス等は公共のビルの暖房の設定温度を最高19度に設定するとともに、街灯の点灯時間の制限等を実施するなどのエネルギー消費の抑制に努めている。

(2)各国の短期的なエネルギー価格高騰対策
続いて、エネルギー価格高騰に対する短期的な対応策を確認する。
欧州主要国においては、各国の制度や状況等によって異なるが、特に今夏以降、エネルギー価格の高騰を受けた緊急措置として、エネルギー価格の抑制や、家計の実質所得が目減りすることを防ぐための低所得者向けを中心とした給付を積極化した。また、企業向けにも特に燃料価格上昇の影響が大きい事業分野を中心に支援を行っている。
(家計向けにはエネルギー価格の抑制と低所得者向け給付を組み合わせている)
家計向けの支援としては第1-1-37表のように、ドイツでは、2023年から全世帯に対し、一定量まで電気・ガスを定額で利用可能にし、それ以上は市場実勢価格を適用する二階層方式(two-tier pricing system)の料金ブレーキ制度を導入する予定である。低所得者対策としては、1世帯当たり約5.8万円以上の暖房費の補助を一時金として9月から支給している。
英国では、10月から消費者に対し、約6.6万円相当の電力料金の減額を実施している。また、10月から1年半の間、家計向けの電気・ガス料金に上限を設定し、2023年度の平均世帯の年間エネルギー支出が約8万円節約可能となる見込みとなっている。
フランスでは、燃料価格の割引やガス料金凍結措置を2022年末まで延長し、2023年に入って以降は電気・ガス料金の上昇率を抑制する方針としている。低所得者対策としては、一時金として、大人1人当たり約1.4万円、子供1人当たり約0.7万円のインフレ手当を9月から支給しているほか、石油代として約1.4万円分のバウチャーによる暖房手当を11月から支給している。また、約1.4万円の光熱費補助手当の対象を2023年には約1,200万世帯に倍増させる予定となっている。
なお、アメリカでは、州独自の取組として物価高騰対策が行われているところ、例えば、カリフォルニア州においては、1人当たり最大で約4.8万円の還付金を10月から支給を開始している。
(企業向けにもエネルギー価格の抑制とともに、融資等を実施)
企業向けの支援としては第1-1-38表のように、ドイツでは、2023年から中小企業に対し、家計向けと同様に料金ブレーキ制度を導入する予定である。また、ウクライナ情勢の影響を受けた企業に対し、その運転資金として、低金利の融資を実施している。
英国では、10月から6か月間、企業(公的も含む)に対してガス、電気の卸売価格の割引を実施するとともに、エネルギー価格の高騰に直面しているエネルギー関連企業に対して流動性供給をBOEと共同で実施することとしている。
フランスでは、年末まで一定の要件を満たす企業に対して燃料費増加分の5割を国が補填し、政府保証付融資及び電気・ガス料金凍結措置を延長するとともに、年明け以降は電気・ガス料金の上昇率を抑制する方針としている。

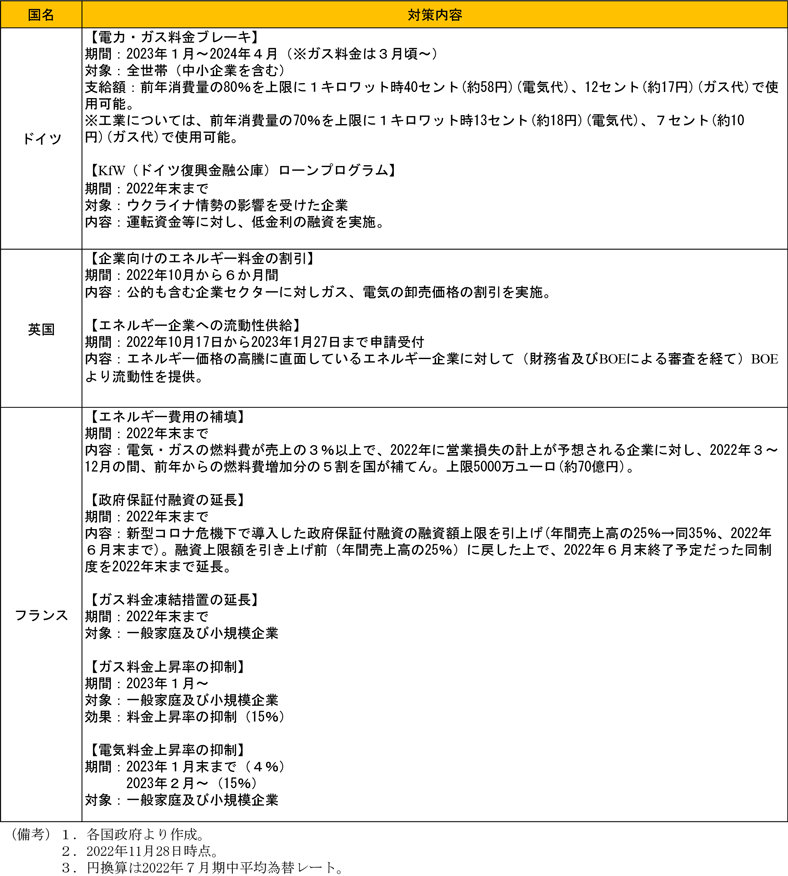
(エネルギー需要の抑制と所得の下支えのバランスが課題)
エネルギー価格高騰対策については、前述のドイツの料金ブレーキ制度を例に取ると、二階層方式(two-tier pricing system)となっているため、単純にエネルギー料金の上昇率を一定比率に抑制する場合と比べ需要を抑制する効果が高いと考えられており28、価格シグナルによる需要抑制と所得下支えの適切なバランスを図ることが意図されていると考えられる。
このようなエネルギー価格高騰対策の適切なバランスを図ることの重要性についてはユーロ圏内でも共有されている。12月5日に開催されたユーロ圏財務相会合は、ユーロ圏各国の2022年のエネルギー価格高騰対策は域内GDPの1.3%に相当し、その大半が所得要件等を課さないエネルギー価格抑制策であると指摘している。また、2023年における対策は同0.9%に達すると推定され、措置の拡充や延長次第で更に大幅に上昇するとの懸念を示している。このため、同会合は、財政の持続可能性に配慮したより効率的な措置として、脆弱な世帯と一時的に危険にさらされている存続可能な企業に対象を限定した措置を、2023年に検討するとしている。具体的にはユーロ加盟国に対し、対象を絞り、各国の特性を反映した二階層方式等の検討を要請している。
(3)脱炭素に向けた政府と民間の取組
(脱炭素に向けた政府の取組は進展)
各国政府は同時に、中長期的な視点に立って脱炭素に向けた取組を進めている。
EUは、2030年温室効果ガス削減目標達成に向けた政策パッケージである「Fit for 55」に基づく取組として、年間排出枠の引下げによるEU排出量取引制度の強化等の施策を推進している。また、ウクライナ情勢を受けて欧州委員会が2022年3月に公表した「REPowerEU」計画に基づきガス供給源を多様化するとともに、2022年末までにEUのロシアのガスに対する需要を3分の2削減することを目指している。なお、10月に開催されたEU経済財政閣僚理事会(ECOFIN)において、復興・強靭化計画29にREPowerEUに関する章も追加することが合意された。これによりREPowerEUに充てられる各計画に含まれる金額の一部について事前融資が行われることとなる。
特に、ドイツは2022年4月に策定した新エネルギー戦略「イースターパッケージ」において、太陽光発電の増強等を通じ再生可能エネルギーが電力消費に占める比率(2021年時点で約42%)を2030年には80%、さらに2035年にはほぼ100%に引き上げるなどの目標を示しており、7月には同戦略に基づいて再生可能エネルギー法等の関連法を改正した。
アメリカにおいては、バイデン政権が2021年4月に議会に提案した「米国家族計画」等を受け246兆円(1.8兆ドル)規模の「ビルド・バック・ベター法案」が作成されたが、与党内の調整が難航し、2022年8月になって規模を縮小させる形で「インフレ抑制法」が成立した(第1-1-39表)。本法の歳出総額は10年間で59.2兆円(4,330億ドル)となるが、そのうち約85%の50.4兆円(3,690億ドル)がエネルギー関連政策及び気候変動対策に充てられることとなった。エネルギー省は、インフレ削減法に盛り込まれた気候変動対策によって、他の政策との連携により、2030年までに温室効果ガス排出量を40%削減できると試算している30。
本法における歳出の内訳をみると、エネルギー安全保障とクリーンエネルギー国産化のために太陽光パネル、ウインドタービンや蓄電池等の国内生産促進のための税額控除(総額4.1兆円(300億ドル))や、脱炭素政策として州政府や電力会社等のクリーンエネルギー転換促進に係る補助金及びローン(総額4.1兆円(300億ドル))等が盛り込まれている。なお、本法における歳入総額は10年間で101兆円(7,390億ドル)と見込まれ、内訳は大企業に対する法人最低税率の適用(42.8兆円(3,130億ドル))、メディケアに係る処方制度改革(39.4兆円(2,880億ドル))等となっており、41兆円(3,000億ドル)超の財政赤字削減を通じてインフレ抑制に寄与することとなる31。

(脱炭素に向けた企業の投資は引き続き堅調に推移する見込み)
脱炭素の取組を進めるためには、積極的な環境関連の設備投資が必要である。例えばドイツ商工会議所が2022年4月に行ったアンケート調査(第1-1-40表)32では「環境保護」を理由としたドイツ企業の国内投資はロシアによるウクライナ侵攻前後では大きな変化はみられておらず、脱炭素に向けた取組を含めた環境保護投資は引き続き堅調に推移すると見込まれる。
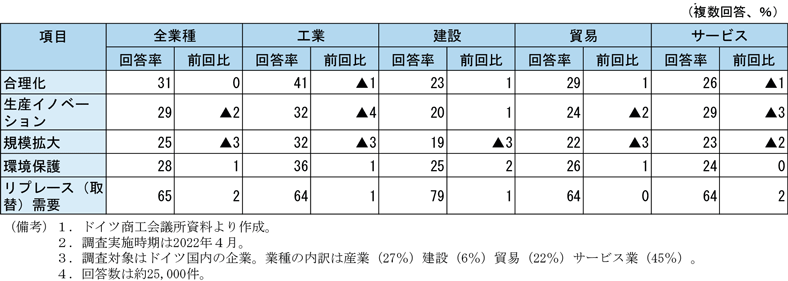
(短期的なエネルギー対策と脱炭素の取組の双方を実施する必要)
IEAのビロル事務総長は、これまでの脱炭素投資が十分ではなかったことが今回のエネルギー危機の背景にあるとの認識の下、「クリーンエネルギーへの大規模な投資は、将来のエネルギー安全保障を保証する最良の方法である」と指摘している。一方で「今日のエネルギー危機への対応と気候危機への取組のいずれかの選択ではなく、(両者は密接に関連していることから)両方を実行する必要がある」と現在の短期的なエネルギー対策及び各抑制策等への理解を示している33。
上述のとおり欧州各国は現在、短期的なエネルギー確保及び消費削減に取り組むとともに、エネルギー価格抑制策についてはより効果的な政策となるよう改善を進めている。これらについては経済活動そのものを当面維持するためにも実施する必要がある。
一方で脱炭素に向けた取組は複数のエネルギー調達手段の確保につながり、特定地域に遍在する化石燃料の価格変動によるエネルギー価格全体の変動のリスクを減少させ、これにより物価安定及び経済活動の安定化にも寄与すると考えられることからも、脱炭素の取組は積極的に推進される必要がある。
6.サプライチェーンの強化に向けた動き:半導体を例に
サプライチェーンに関する問題については、内閣府(2021)において、輸入先が特定の国に頼る傾向が強まれば、供給ショック等のリスク対応がより困難になることから、リスクに対する備えが重要との問題意識が感染症拡大を受けてより明確になったと指摘されている。
本項では、サプライチェーン上の重要分野となっている半導体に焦点を当て、欧米における半導体生産におけるサプライチェーンの強化に向けた政府及び民間による取組を概観する。
(アメリカでは「CHIPS及び科学法」が成立)
アメリカでは、2021年2月の「アメリカのサプライチェーンに関する大統領令」を受け、同年6月、サプライチェーンにおけるリスクの特定及びそれに対する政策提言をとりまとめた報告書をホワイトハウスが公表した。報告書では重要4分野34のうちの半導体については、アメリカはその生産を2019年時点で台湾に20%、韓国19%、日本17%、中国16%等、東アジアに依存していること、また最も先進的な半導体の製造には数十億ドルの投資が必要であること等を指摘した。その上で、産業界と連携した投資の促進、同盟国等との多様なサプライチェーン構築、製造業企業(特に中小企業)における研究開発のための資金調達を支援すること等を提言した。
上記報告書を受けて法整備が進められてきたが、2022年8月に連邦議会は「CHIPS35及び科学法」を可決した36。その主な内容は以下のとおり商務省所管の半導体製造インセンティブ事業や研究開発事業となるが、国防総省の事業も一部含まれている。
(ⅰ)商務省製造インセンティブ(5.3兆円(390億ドル)):半導体の製造、試験、先端パッケージング、研究開発のための国内施設・装置の建設、拡張または現代化に対する資金援助。うち、0.3兆円(20億ドル)は成熟分野の半導体に対して、0.8兆円(60億ドル)は直接融資または融資保証に使用可能。
(ⅱ)商務省研究開発(1.5兆円(110億ドル)):商務省管轄の半導体関連の研究開発プログラムへの予算充当。
(ⅲ)その他(0.4兆円(27億ドル)):労働力開発や国際的な半導体サプライチェーン強化の取組、国防総省主導の半導体関連事業者等のネットワーキング事業への予算充当。
このうち設備投資に直接結びつくものは(ⅰ)の商務省製造インセンティブの5.3兆円(390億ドル)と見込まれるが、後述するように本法の成立を受けて民間企業によるアメリカ国内における設備投資が活発となっており、予算規模を超えた投資誘発効果が今後期待される。
本法に定められた半導体製造支援関連の予算措置の規模は2022予算年度から2027予算年度の5年間で7.2兆円(527億ドル)となり、CBO(議会予算局)によると2023予算年度から2031予算年度にかけて毎年約0.3兆円(20億ドル)から1.2兆円(90億ドル)程度の規模で支出されると見込まれている。
(アメリカ国内では半導体工場の新設が広域的に進む見込み)
アメリカでは、CHIPS及び科学法の成立を受けて、半導体工場の国内全域への新設の動きが活発となっている(第1-1-41表)。投資規模は約0.3兆円(20億ドル)から 約5.5兆円(400億ドル)、直接雇用は700人から9,000人程度と幅があるものの、この中には州内で初となる半導体工場の新設や、地元の大学との産学連携による案件も含まれており、国内における半導体供給能力の強化のみならず、国土全体での人的資本や社会インフラの活用による地域間の格差の是正に資するものともなっている。また、投資規模についても更に拡大する方針が一部の事業では示されており、地域内における工場新設も更に増やす計画があるなど、旺盛な投資需要がうかがえる。
一方で新興国に比べて人件費面等で割高なアメリカ国内に工場を新設することに伴うコストの増加37や、供給能力の向上による中長期的な需給の不均衡を引き起こす可能性が指摘されている38。そのために、経済安全保障の観点からのサプライチェーン構築と、コスト面及び需給面からの持続可能性のバランスを考慮しながら、官民が連携して投資を進めることが重要と考えられる。

(欧州では欧州半導体法案の成立に向け審議中)
欧州では、欧州委員会による戦略的分野に係るレビューにおいて、半導体については、EUは一般的な半導体はアメリカに、先進的な半導体はアジアに強く依存していること、また最も先進的な半導体の設計及び開発には0.1兆円(10億ユーロ)を要すること、半導体の開発や製造に対する補助金の投入が増えていることで、公平な競争環境が保たれていないこと等が指摘された。その上で、復興・強靱化基金の活用、外国政府による補助金によって生じた競争環境の歪みのアセスメント、国際連携の拡大によるサプライチェーン強靱化への取組等を提言した。
2022年2月には、上記提言を踏まえた欧州半導体法案が欧州委員会より発表された。その主要な内容は、(ⅰ)次世代半導体の研究開発力の強化、(ⅱ)先端半導体の設計から製品化する能力の増強、(ⅲ)2030年までに半導体の域内生産の世界シェア20%(2022年2月時点で約10%)を目指し量産能力強化、(ⅳ)人材不足対策、(ⅴ)半導体サプライチェーンの監視と危機対応、とされている。
同法案は、欧州委員会より、EU理事会と欧州議会に提出されており、現在審議中である。その後、修正等を経て三者が同法案に合意すれば成立となる見通しである。
また、本法案における施策を実施するために官民協同による「欧州半導体インフラコンソーシアム(ECIC)」を設置し、EUと加盟国が1.5兆円(110億ユーロ)規模の公的資金を共同で出資し、次世代半導体の技術開発や試作のライン等の強化を図るための「半導体のための欧州イニシアチブ」を立ち上げることとなっている。なお、民間投資も含めた本法案の事業規模は、既存の半導体研究及びイノベーション関連計画(ホライゾン・ヨーロッパ、欧州デジタル計画)分を含め、2030年までに6兆円(430億ユーロ)と見込まれている。
(官民連携の下でサプライチェーン強化が必要)
上述のとおり、アメリカにおいては法整備を受けて民間の投資が活発となっており、半導体のサプライチェーンの強化が進んでいる。コスト面及び需給面からの持続可能性についての課題はあるものの、国内における半導体供給能力の強化のみならず、国土全体での人的資本や社会インフラの活用による地域間の格差の是正に資するものともなっている。我が国においても引き続きこのような官民連携の下でのサプライチェーン強化の取組がなされることが求められる39。
(※)経済産業省半導体・デジタル産業戦略検討会議第7回会議資料3参照。
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/joho/conference/semicon_digital/0007/0007.html(2023年2月2日取得)
また、日本の半導体市場の動向については「日本経済2022-2023」を参照。

