第2章 主要地域の経済動向と構造変化(第2節)
第2節 アメリカ経済
1.アメリカ経済の動向と見通し
アメリカ経済は、世界金融危機後、7年半に及ぶ回復を続けている5。雇用者数は世界金融危機前の水準を回復し、失業率は完全雇用に近い状態まで低下した。個人消費は増加を続けており、金融危機により打撃を受けた住宅市場も回復した。2015年に進んだドル高や原油安の影響により弱めの動きがみられていた企業部門にも足下では回復の動きが広がっている。物価の安定と雇用の最大化の「デュアル・マンデート」の達成状況に照らし、FRBは16年12月、1年ぶりに政策金利の引上げに踏み切った。雇用・所得環境の改善が続く中、アメリカ経済は今後も回復が続くと見込まれている。
回復の続くアメリカ経済ではあるが、実質経済成長率や賃金の伸びは緩やかなものとなっている。雇用者数の増加はサービス業に集中しており、比較的平均賃金の高い製造業の雇用者数は金融危機前の水準を大幅に下回って推移している。
こうした状況で16年11月に行われた大統領選挙では大胆な政策転換を訴える共和党のトランプ候補が勝利した。トランプ次期大統領は、税制改革、通商政策の見直し、規制緩和、インフラ投資、移民政策の厳格化等の政策を掲げて選挙戦を戦った。これらの政策がどのように具体化され、実施されるのか、今後の政策の動向及び影響に留意が必要である。
本節ではまず、アメリカ経済の最近の動向を振り返るとともに、17年の見通しとリスクを点検する。次に、今回の大統領選挙における経済関係の争点のいくつかについて、その背景を整理する。最後に、アメリカ経済の強さの源泉と言われる企業のダイナミズムの現状について、様々なデータを用いて検証する。
(1)回復が続く個人消費と住宅市場
16年のアメリカ経済は、ドル高と原油価格下落の進展を受け、企業部門の一部に弱めの動きがみられたものの、雇用・所得環境の改善等を背景とした個人消費の増加に支えられて景気回復が続き、16年後半には企業部門の弱めの動きもほぼ解消した。個人消費は、自動車販売の伸びが横ばいになっているものの、無店舗販売(インターネット販売等)やヘルスケアを中心に増加が続いている(第2-2-1図、第2-2-2図)。
一方、過去最高の販売台数を記録した15年の自動車販売については、ガソリン価格の低下等を受けた買換え需要の発現に支えられた面があり、アメリカの人口動態等のファンダメンタルズを踏まえるとやや過熱気味であったとの指摘もある。16年の販売台数は15年並みにとどまり(第2-2-3図)、17年以降は緩やかに減少する可能性もあると考えられる(コラム2-1参照)。
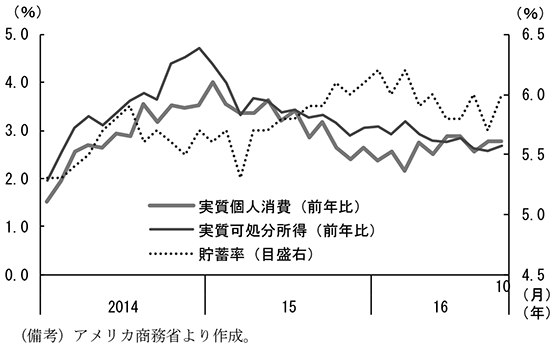
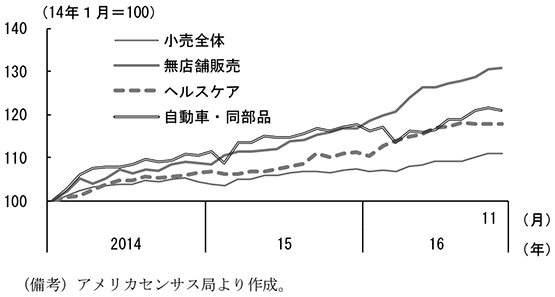
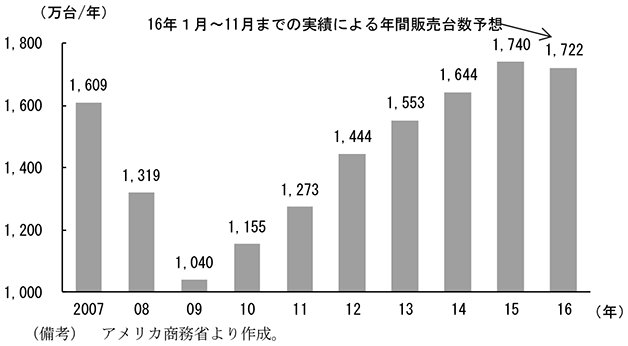
コラム2-1:アメリカの自動車販売を巡る状況
15年のアメリカの自動車販売は、雇用・所得環境の改善が続く中、低いガソリン価格や自動車ローン金利に支えられ増加した(図1、図2)。このような好条件は16年に入ってからも大きくは変わっていない。
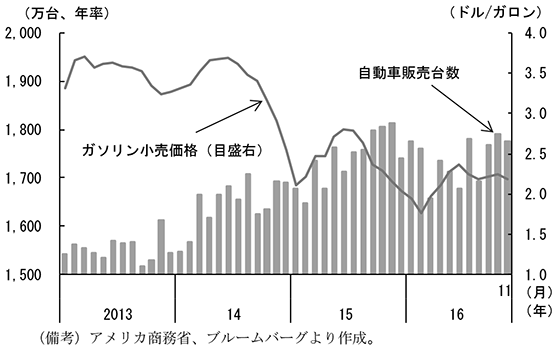
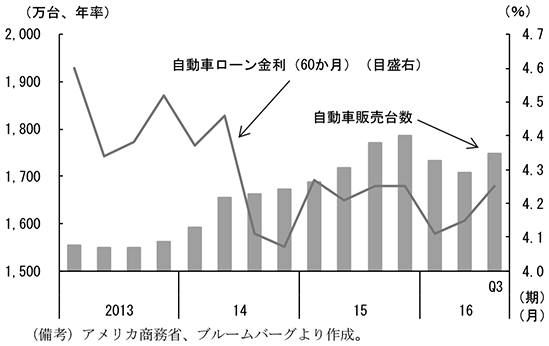
前述のとおり、16年に入ってから自動車販売はおおむね横ばいで推移しているが、そうした中、自動車メーカーから自動車ディーラーへの販売奨励金(インセンティブ)が16年半ば頃から増加傾向にある(図3)。すなわち、足下の自動車販売は、インセンティブの効果に支えられている面がある。
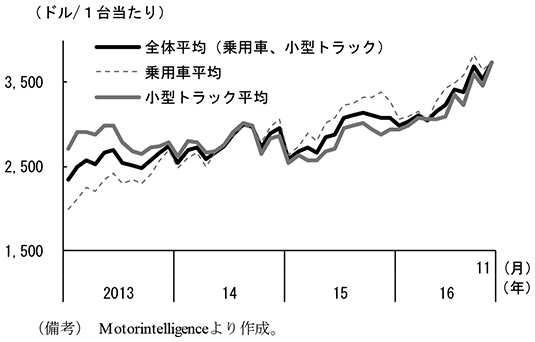
また、低い自動車ローン金利が続く中、サブプライム層と呼ばれる返済能力の低い消費者層による借入が増加している(図4)。自動車市場におけるサブプライムローン借入基準(クレジットスコア)は厳格化の進んだ住宅市場のサブプライムローン借入基準と比較すると緩くなっており、借入れがしやすい状態が続いていた(図5)。米国では学費高騰等を背景に学生ローン残高が2000年代に急増し、返済に伴う問題が深刻化しているが、自動車ローン残高の増加ペースは学生ローンと同様になっている(図6)。
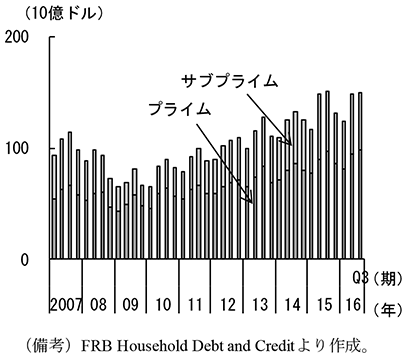
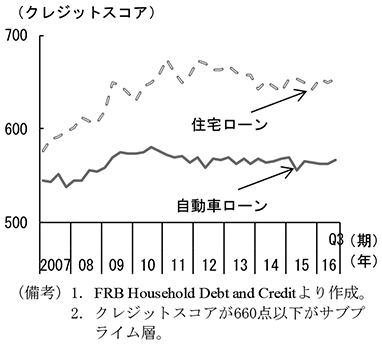
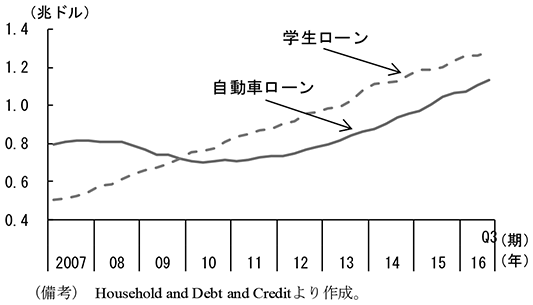
これまでのところ、自動車ローン延滞率の大幅な上昇はみられないものの(図7)、このところ金融機関の自動車ローン貸出態度には厳格化の動きがみられる(図8)。今後自動車販売が大きく減速するリスクは小さいものの、ローン返済の問題を含め、自動車市場の動向には注意が必要である。
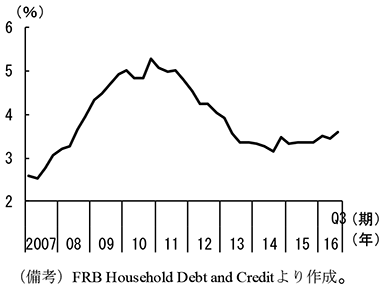
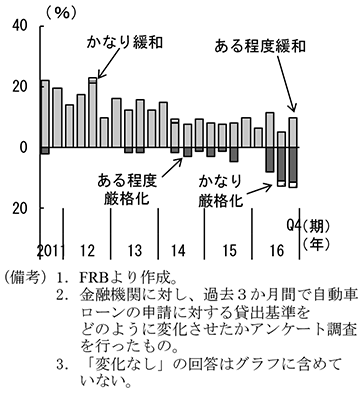
世界金融危機後に大きく落ち込んだ住宅市場についても、堅調な雇用・所得環境や低い住宅ローン金利を背景に、回復が続いている。住宅着工件数は、16年に入ってからは年率100万~120万戸の水準で推移している(第2-2-4図)。世帯数の増加ペースと比較すると住宅着工件数の伸びは力強さを欠いているが、その要因として、建築労働者の不足といった供給側の制約が指摘されている。そうした中、住宅メーカーは利益率の高い大規模住宅の建築を優先しているとの見方もある6(第2-2-5図)。
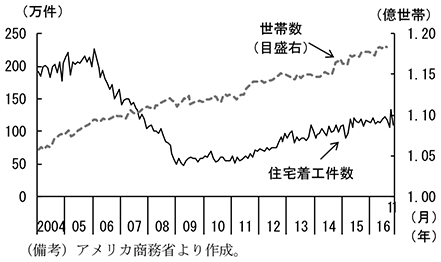
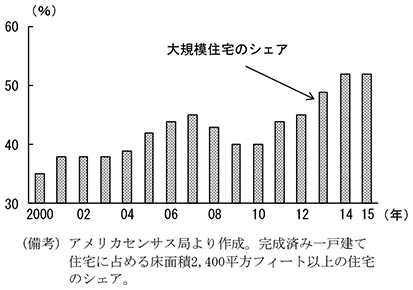
供給制約の影響は住宅価格の動向にも表れている。ケース・シラー住宅価格指数は前年同月比5.0%以上の上昇を続けており、06年のピーク時の価格水準に迫っている(第2-2-6図)。こうした中、持ち家比率や初回住宅購入者の住宅取得能力指数は低下傾向にあり、特に若い世代が住宅を持ちにくくなっているとの指摘もある(第2-2-7図)。
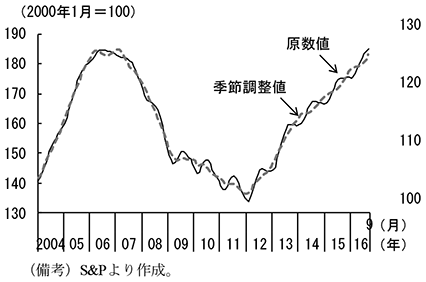
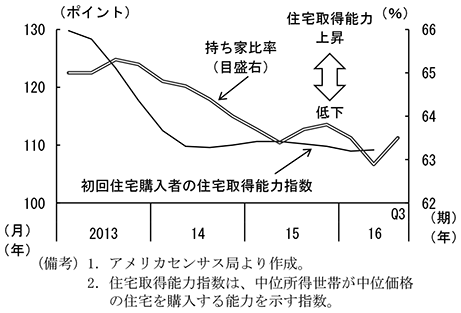
(2)労働市場の改善
労働市場の改善も続いている。FRBが金融政策判断の材料として重視する指標の一つである非農業部門の雇用者数については、15年中は前月差20万人を上回る月が多かったが(15年平均は22.9万人)、16年には増加幅はやや鈍化し、1~11月の平均で18.0万人となっている。もっとも、完全失業率(U3)7は既にFOMCメンバーの予想する長期的な失業率8(4.7~5.0%)のレベルまで低下しており(第2-2-8図)、今後は雇用者数の伸びが鈍化していく可能性が高い(第2-2-9表)。
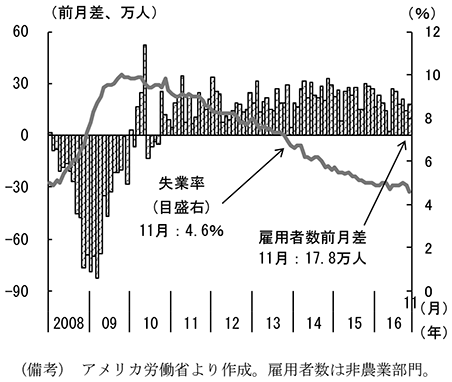
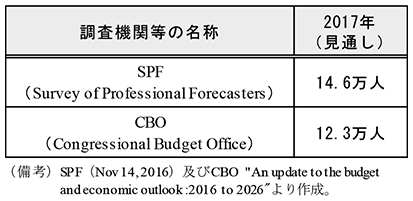
労働市場の改善が進む中、世界金融危機後に大幅に増加した長期失業者数や非自発的パートタイム労働者数の減少も続いており(第2-2-10図、第2-2-11図)、広義失業率(U6)9は金融危機前の水準近くまで低下している。16年に入ってからは労働参加率に下げ止まりの動きもみられ、労働市場の改善の影響がより広範囲に及んでいることがみてとれる(第2-2-12図)。
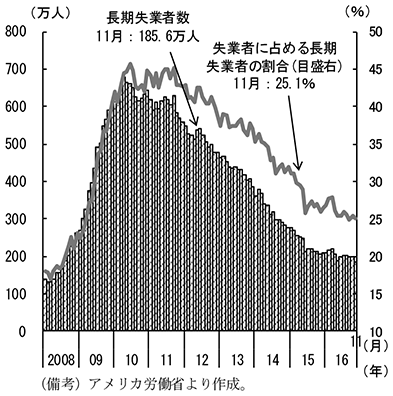
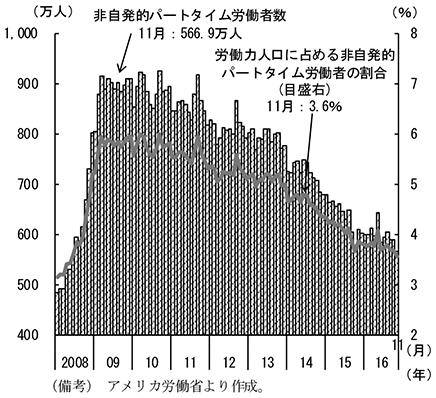
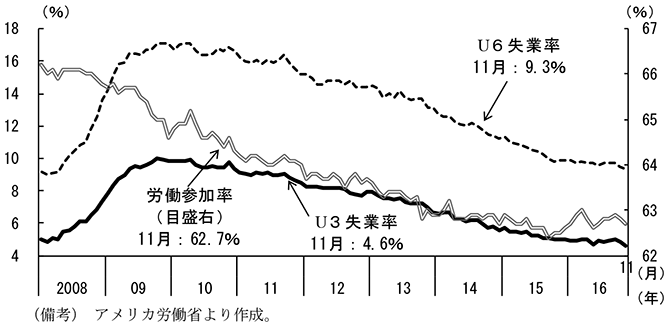
(3)企業部門の弱めの動きは解消
14年半ば以降の原油価格の大幅な下落により、鉱業部門は不振に陥った。原油価格の下落とともに、原油の採掘に使用される掘削装置(リグ)の稼働数とシェールオイルの生産量はいずれも大幅に減少し(第2-2-13図)、鉱業部門の不振が生産全体、さらには設備投資全体の大きな下押し要因となった(第2-2-14図、第2-2-15図)。石油関連企業の破たん件数も16年の半ばにかけて急増した(第2-2-16図)。
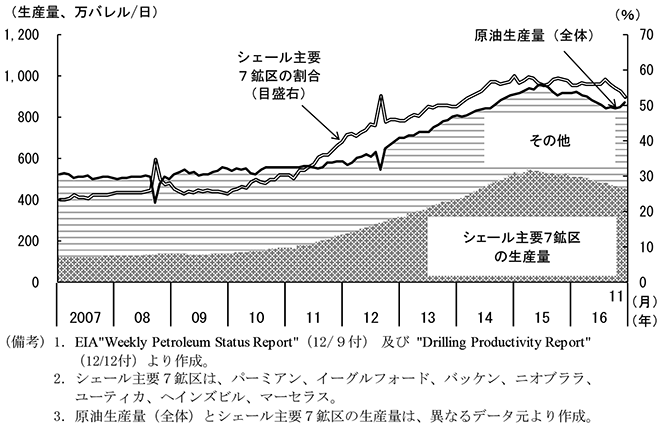
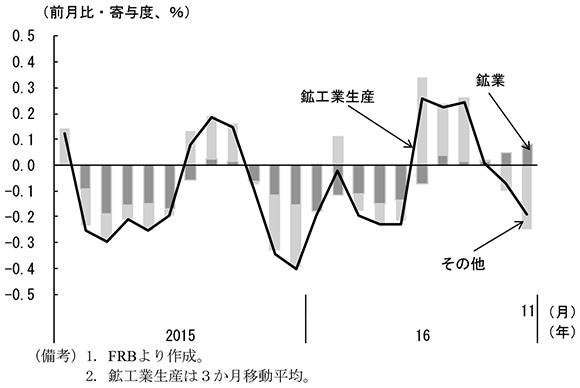
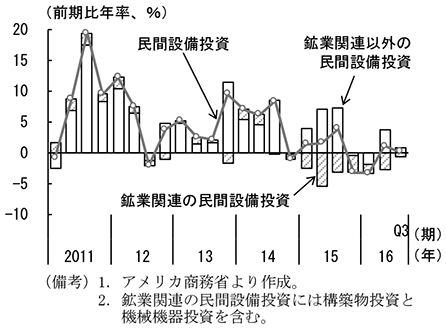
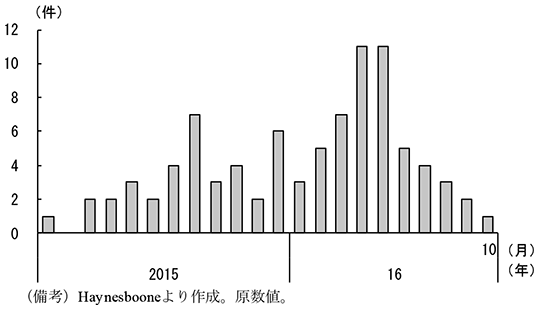
原油価格の下げ止まりを受け、16年後半には石油関連企業の破たん件数は減少に転じ、生産や投資への下押し圧力も低下した。このような動きを受け、足下ではリグ稼働数が再び増加に転じており(第2-2-17図)、リグ関連の機械の受注も増加してきている(第2-2-18図)。こうした動きは原油価格の下押し圧力になる可能性もあることから注意が必要である(第2章第5節参照)。
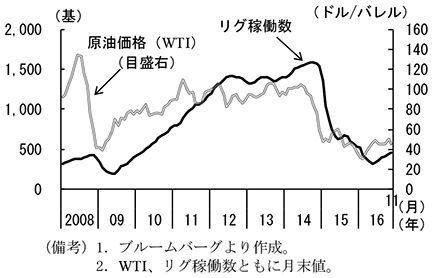
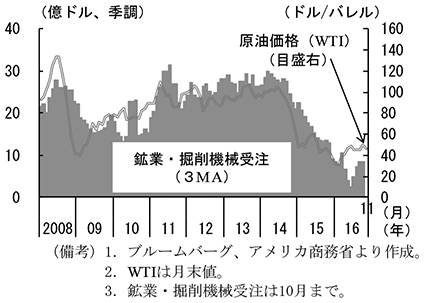
鉱業部門の弱さに加え、14年後半以降に進んだドル高や、海外経済の弱さもあり(第2-2-19図)、財輸出は弱い動きとなっていたが、足下ではおおむね横ばいとなっている(第2-2-20図)。
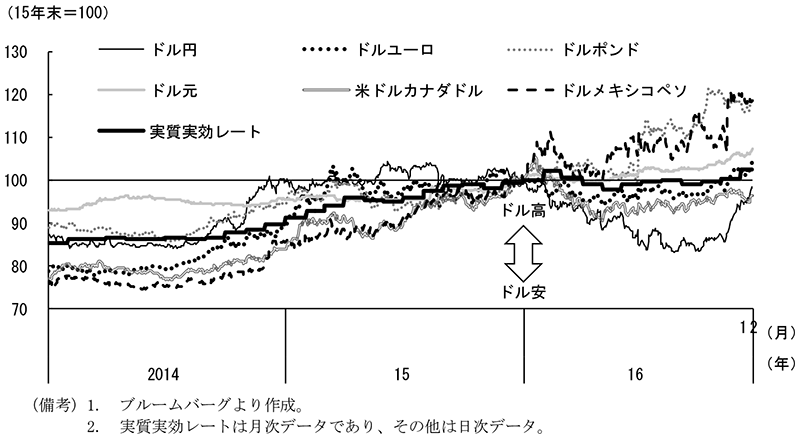
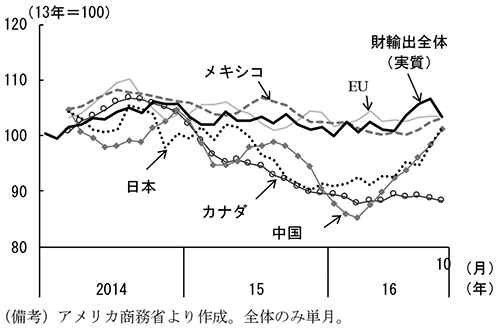
(4)金融政策の正常化
前述の通り、アメリカの雇用情勢は改善が続いており、賃金の伸びも次第に高まってきている(第2-2-21図)。また、ドル高や原油価格の持ち直しもあり、輸入物価指数の前年同月比のマイナス幅は縮小している(第2-2-22図)。PCE総合物価上昇率についてもFRBが長期的な目標とする2%に向かって高まってきている(第2-2-23図、第2-2-24図)。
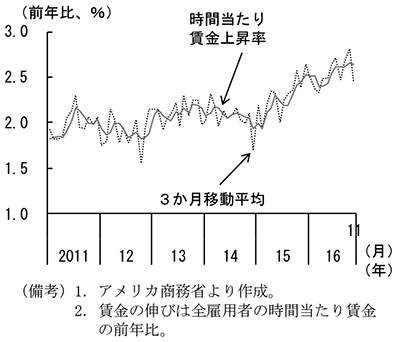
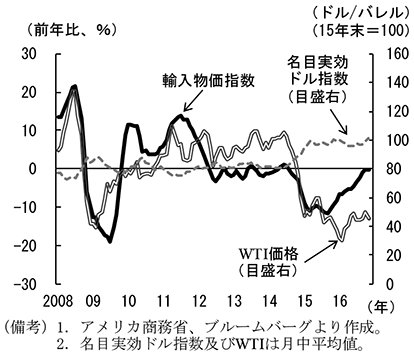
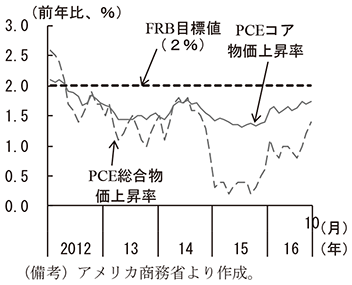
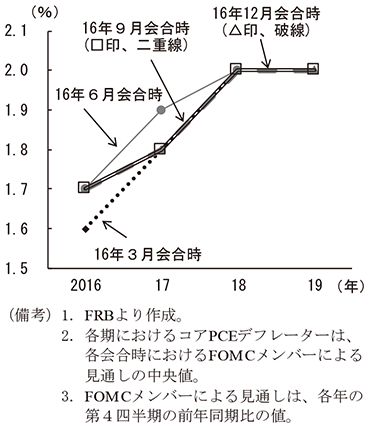
FOMCは15年12月、9年6か月ぶりに政策金利の誘導目標であるFFレート(フェデラル・ファンドレート)の引上げ(0.00~0.25%から0.25~0.50%)を決定した。FOMCによる声明文では、経済状況はFFレートの緩やかな引上げしか正当化しないとしつつも、FOMC参加者によるFFレートの見通し(中央値)では、16年末までに更に1%ポイントの引上げ10が想定されていた(第2-2-25図)。
しかしながら、16年年初以降の国際金融資本市場の大幅な変動や、英国におけるEU離脱を問う国民投票等、主に海外経済の不透明感の高まりを受け、政策金利の引上げは見送りが続いた。物価の安定と雇用の最大化の達成状況に照らし、16年12月のFOMCにおいて、FFレートを0.25~0.50%から0.50~0.75%に変更する1年ぶりの利上げが決定された。
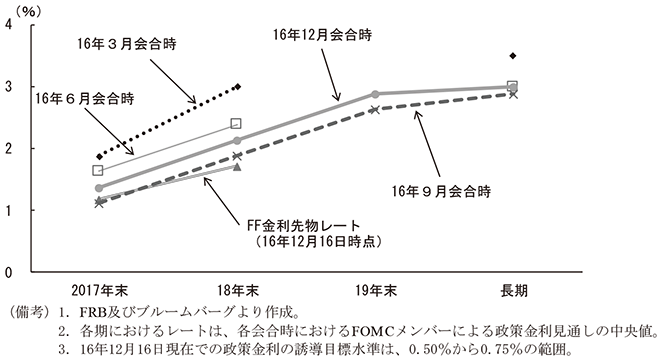
(5)アメリカ経済の見通しとリスク
アメリカ経済は、雇用・所得環境の改善が続く中、個人消費の増加に支えられ、引き続き回復が続くと見込まれる。アメリカ政府や国際機関等の見通しによれば、17年の実質経済成長率見通しは2~2%台半ば程度になると見込まれる(第2-2-26表)11
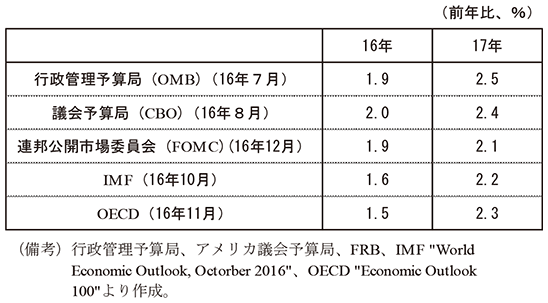
次期大統領のトランプ氏は、オバマ大統領の政策からの大胆な転換を訴えて当選したことから、今後の政策の動向及び影響等に留意する必要がある。
2.2016年大統領選挙における議論とその背景
16年11月8日に行われた大統領選挙では、共和党のドナルド・トランプ候補が民主党のヒラリー・クリントン候補を接戦の末破り、第45代アメリカ大統領に就任することになった(参考1)。また、同日行われた連邦議会選挙においては、上院、下院のいずれにおいても共和党が過半数を占める結果となった(参考2)。トランプ新大統領は17年1月20日に就任し、選挙中に掲げた各種の政策の実現に取り組むことになる(参考3)。以下では、選挙戦において争点となった主要な経済問題の背景について整理する。
(1)経済成長、インフラ投資、税制改革
既に述べたとおり、アメリカ経済は、7年半にわたる景気拡大を続けている。一方、実質経済成長率は長期的に低下傾向にあるほか(第2-2-27図)、CBOの試算による潜在成長率も下方修正が繰り返されている(例えば、16年の潜在成長率は、12年頃に公表されたものでは2%台半ばとされていたが、最新のものでは1%台半ばと推計されている)(第2-2-28図)。成長率低下の要因としては、高齢化の影響や、労働生産性の低下が指摘されている(第2-2-29図)12。
こうした中、公共インフラへの投資を拡大すべきとの意見が高まっている。アメリカにおける公的資本形成のGDP比は低下の一途をたどっている(第2-2-30図)。15年12月には当面のインフラ予算を確保する措置が採られたが13、安定的な財源の確保は今後の課題となっている。税収に頼らず、PPPを含む民間資金の活用を求める意見もある。
抜本的な税制改革の必要性も指摘されている。法人税については、レーガン政権による86年の税制改革法に基づく改革以降、抜本的な改革が行われておらず、法定税率は先進国で最も高い水準となっている。各種の控除により実際の税負担はそれほど重くないとの指摘もあるものの、税制の簡素化と法定税率の引下げの必要性はこれまでも各方面から求められてきた。
一方、アメリカの財政赤字のGDP比は3.5%、公的粗債務残高のGDP比は105%(いずれも15年、一般政府ベース。IMF推計)と先進国の中で高水準となっていることから、今後の政策の財政への影響にも留意が必要である(第2-2-31図)。
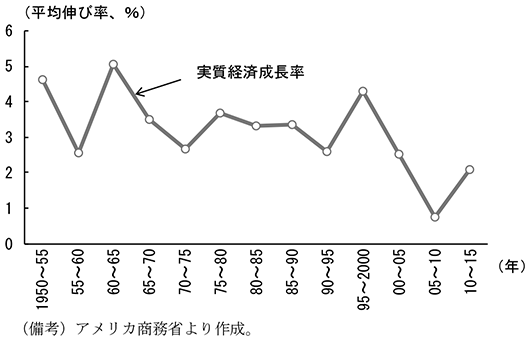
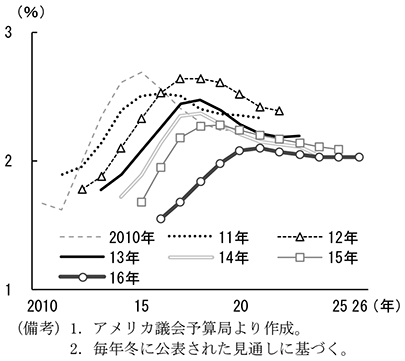
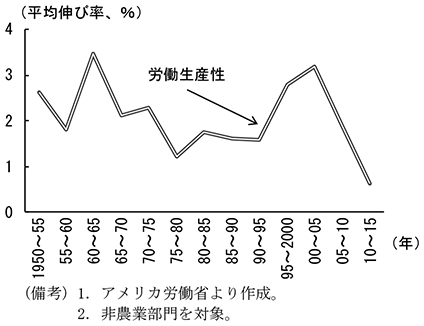
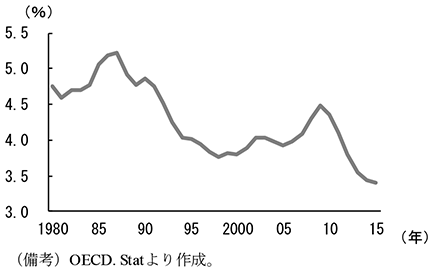
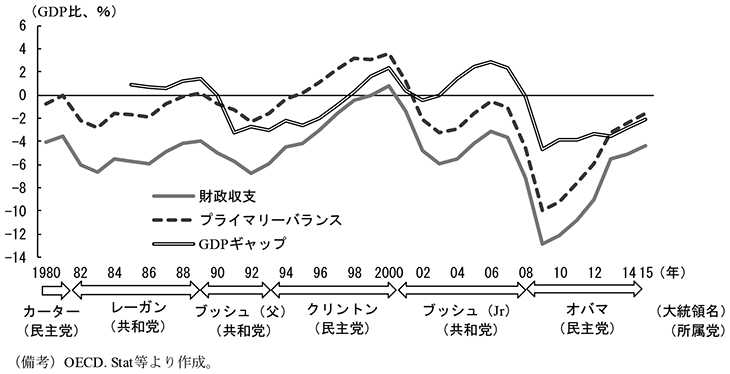
(2)産業、雇用関係
アメリカの非農業部門雇用者数は世界金融危機直後の08年1月から10年2月にかけて約870万人減少し、その後、16年10月までに約1,520万人増加した。雇用者数全体は危機前を大幅に上回る水準まで回復したものの、その内訳は大きく変化し、08年1月と16年10月の雇用者数を比較すると、サービス業雇用が約900万人の増加となっているのに対し、製造業雇用は約147万人の減少となっている(第2-2-32図)。なお、サービス業雇用の増加は飲食店、ヘルスケア、小売業等が中心となっている。
製造業の平均賃金は雇用の増加した小売業等に比べて高いため、製造業の雇用拡大を求める意見がある。新政権の経済政策が産業構造や雇用、更には貿易に与える影響が注目される(第2-2-33図、第2-2-34図)。
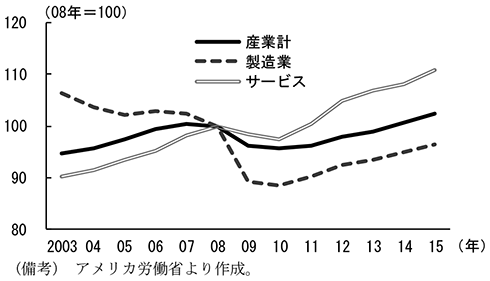
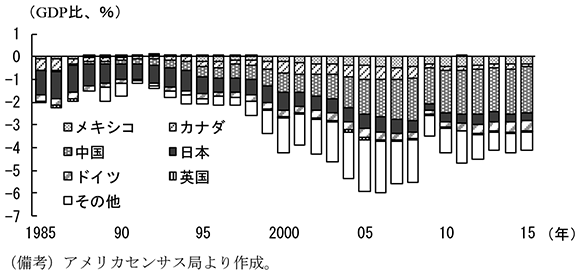
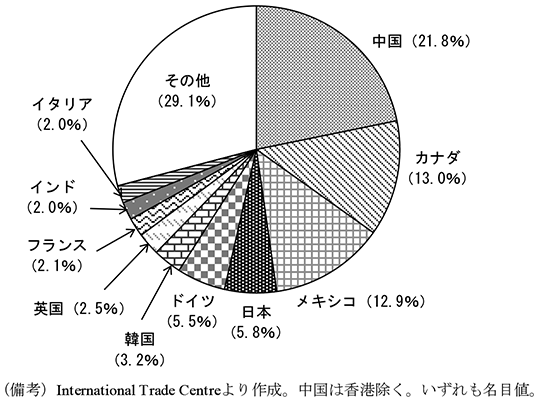
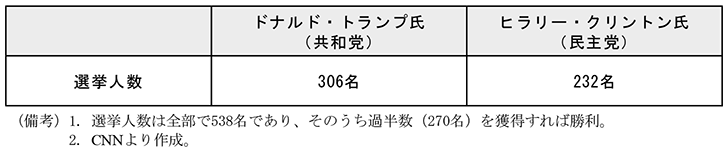
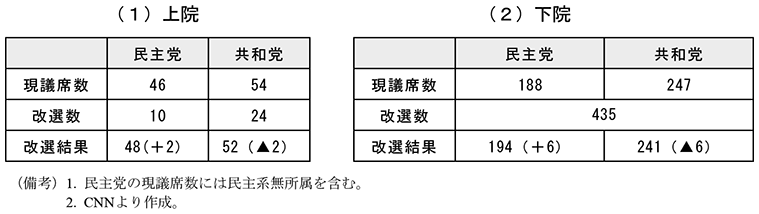
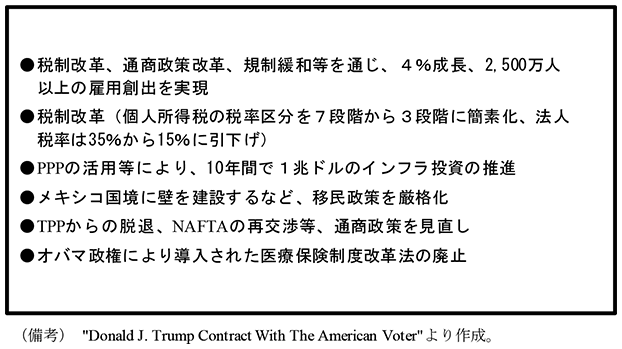
3.アメリカ企業の成長の源泉
(1)アメリカにおける起業を取り巻く状況
(i)アメリカの起業環境
アメリカ経済の強みは、旺盛な起業家精神、企業の新陳代謝、柔軟な経済構造等にあると言われてきた(Decker, Haltiwanger, and Jarmin(2014)等)。「起業化精神指数」や「起業に対する見方」といった指標からも、アメリカには他国と比較して起業を前向きに捉える風土があり、それを支える環境が整備されていることがみてとれる(第2-2-35表、第2-2-36図)。一方で、企業の参入率・退出率が年々低下するなど、アメリカ経済のダイナミズムは低下してきているとの指摘もある。ここでは、アメリカにおける企業の参入や再編等のビジネスダイナミズムの現状と経済成長への影響について、様々なデータを用いて検証を行う。
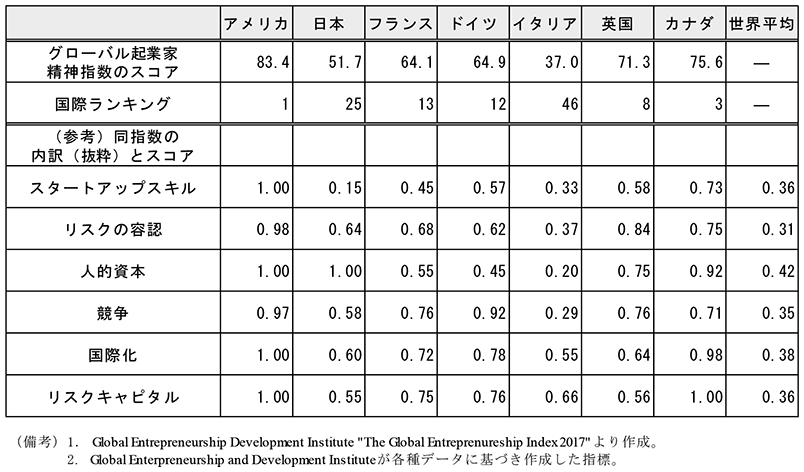
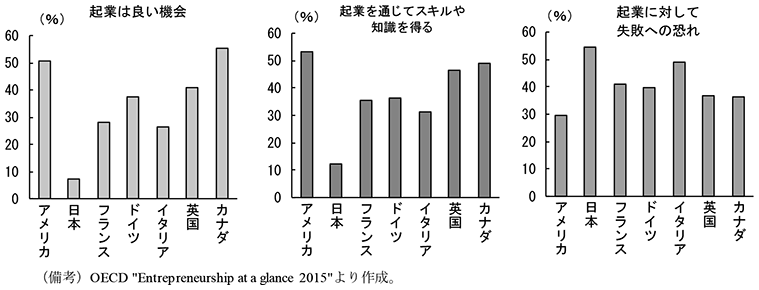
(ii)アメリカにおける起業状況
2000年以降のアメリカの起業件数の推移をみると、世界金融危機前後に大きく落ち込んだものの、その後やや持ち直しており、15年には57万件の起業が行われている(第2-2-37図)。その業種別内訳をみると、07年頃に顕在化したサブプライムローン問題や08年の世界金融危機を契機に、「建設業」や「金融業」の起業件数が大幅に減少したほか、実店舗からネット販売への移行が影響していると考えられる「小売業」の起業件数も減少していることがわかる。また、「製造業」は低い水準で低下傾向にある14。一方、新しい知識や技術を活用する専門・科学・技術サービスや経営管理サービスといった業種が含まれる「専門サービス」の起業件数が高い水準で推移しているほか、「ヘルスケア」の起業件数も増加を続けている(第2-2-38図)。これらのデータからは、起業件数には景気との相関関係があること、その業種別内訳にはアメリカの産業構造の変化が反映されていることがみてとれる。
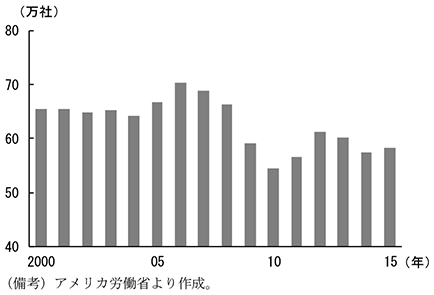
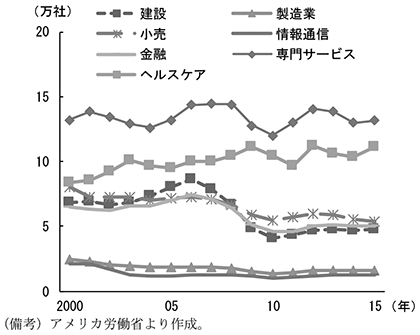
こうした起業活動を支えているのは、新興企業を資金面で支援するベンチャーキャピタルである。ベンチャーキャピタル投資額はITバブル期の2000年頃に急増し、その後減少したものの、14年以降は2年連続で投資額が増加している(第2-2-39図)。
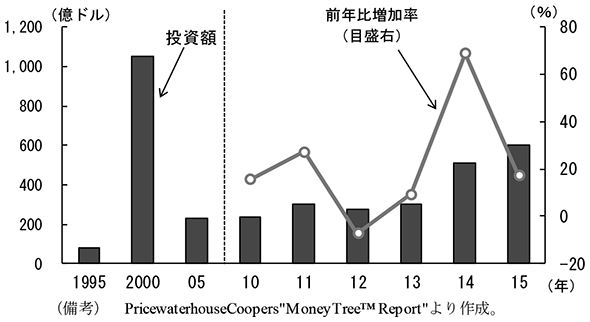
ベンチャーキャピタル投資額を分野別にみてみると、まず、「ソフトウェア」分野への投資がITバブル崩壊に伴い大幅に減少し、その後停滞していたものの、13年から再び増加に転じ、15年には全投資額の約半分を占めるに至っている。他の主要分野である「メディア・エンターテイメント」、「消費者向け製品・サービス」、「ITサービス」、「バイオテクノロジー」についても14年から再び投資額が増加しているほか、「医療機器・設備」、「工業・エネルギー」についても安定的に投資が行われている(第2-2-40図)。IT関係を中心に、ベンチャーキャピタル投資が幅広い分野で行われていることがわかる。
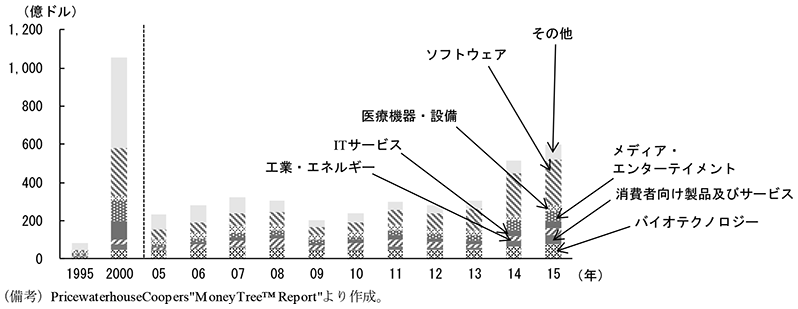
純粋なスタートアップ(創業)に加え、企業の合併及び買収(M&A)もアメリカでは企業の再活性化手段として活発に用いられている(第2-2-41図)。ベンチャーキャピタルから投資を受けた企業についても、M&Aや新規公開株(IPO)といったコーポレートアクション15を通じて次の成長段階に進むことが多い。このいずれの手法についても、世界金融危機後の減少を経て、近年再び活発化してきている(第2-2-42図)。
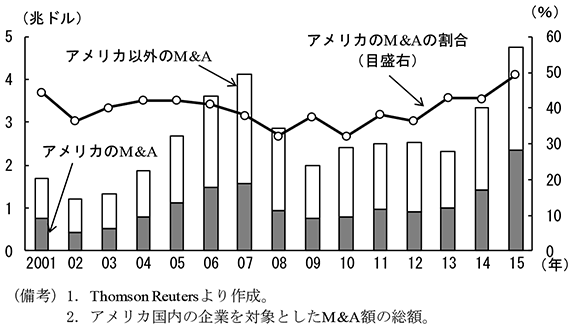
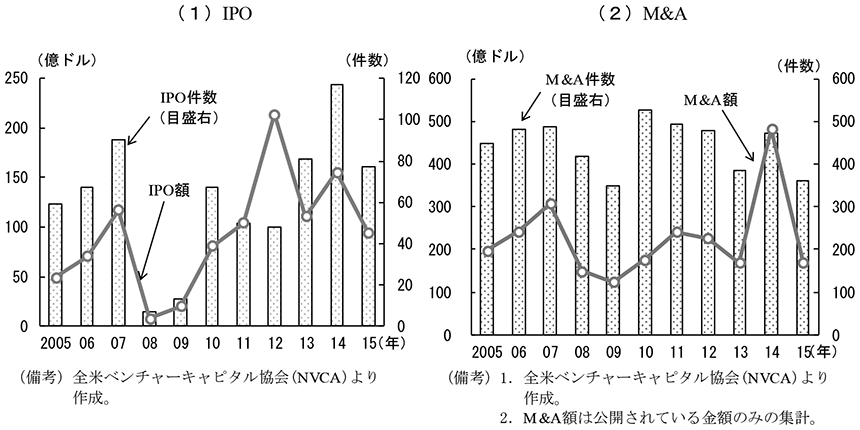
(2)個別企業データを用いた分析
次に、起業や事業再編と企業の成長との関係について、個別企業のデータベースを用いて検証を行う。
(i)売上高上位500社に占める社齢の若い企業
最初に、アメリカと日本における売上高上位500社について、社齢別の企業数を05年及び15年のデータを用いて比較する16(第2-2-43図)。まず、アメリカについては、社齢の若い企業が売上高上位企業の多くを占めており、社齢20年以下の企業の割合は05年には約52%、15年には約45%とそれぞれ約半数となっている。ただし、社齢10年以下の企業の割合に着目すると、05年から15年にかけてやや減少している。これに対し、日本では、戦後10年以内を設立年とする企業の数が圧倒的に多く、逆に社齢の若い企業の割合はアメリカと比較して非常に小さいことがわかる(社齢20年以下の企業の占める割合は15年に約15%)。
なお、ここで言う社齢の若い企業には、創業からの期間が短い企業に加え、元々は創業年の古い企業が、M&Aや破たん後の再上場といったコーポレートアクションを通じて新しい企業に生まれ変わり設立年が変更された事例も含まれていることに留意が必要である。
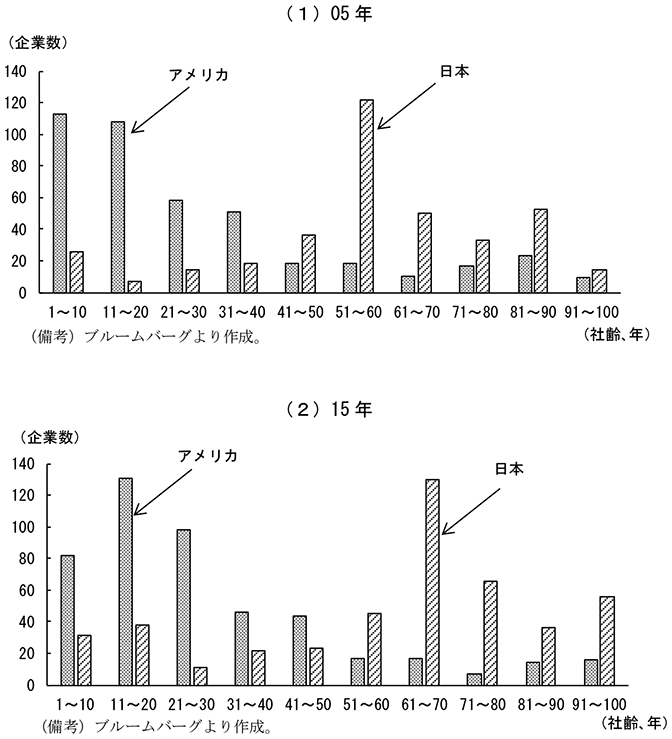
(ii)アメリカの若い企業による雇用創出力
次に、個別企業のデータベースを用い、06年から15年の間の雇用者数の増減を社齢別に日米比較してみよう17。まず、アメリカにおいては、社齢が20年以下の企業による雇用創出が全ての企業による雇用創出の約71%を占めている(第2-2-44図)。これに対し、日本では、戦後10年以内の間に設立された企業による雇用創出の割合が最も大きくなっており、社齢20年以下の企業による雇用創出の割合は全体の約21%にとどまっている。アメリカにおいては、新たに創業した企業、M&Aなどのコーポレートアクションを経て生まれ変わった企業の両方を含む社齢の若い企業が雇用創出において大きな役割を果たしていることが分かる18。
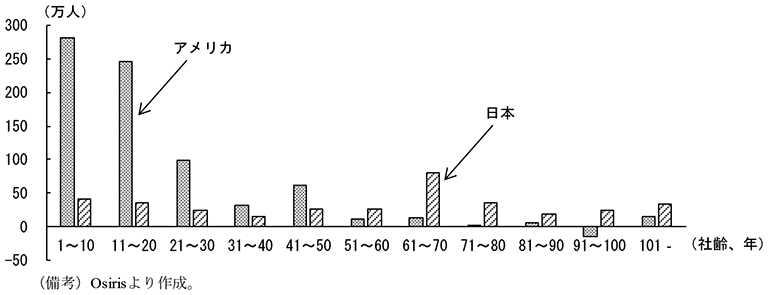
(iii)社齢が若く急成長している企業の特徴
以上の分析では、純粋なスタートアップ企業と、コーポレートアクションを通じて社齢が若くなった企業を区別することができなかった。そこで、以下では個別企業に関する情報も踏まえながら、社齢の若い企業の特徴を確認していくことにする。まず、日米の売上高の大きい企業について、社齢別の売上高の分布をみてみよう(第2-2-45図)。アメリカの上場企業を対象とした企業データベースから抽出した3,917社のうち、社齢が20年以下の若い企業の割合は90%を超えているのに対し、日本では同様の3,230社に占める社齢20年以下の企業の割合は2割程度にとどまっている(第2-2-46表)。また、アメリカにおける社齢20年以下の企業の中には、売上高が1,000億ドルを超える企業が8社存在していることも分かる。経済規模の違い等により単純には比較できないものの、日本については社齢20年以下で売上高10兆円を超える企業は確認できない。
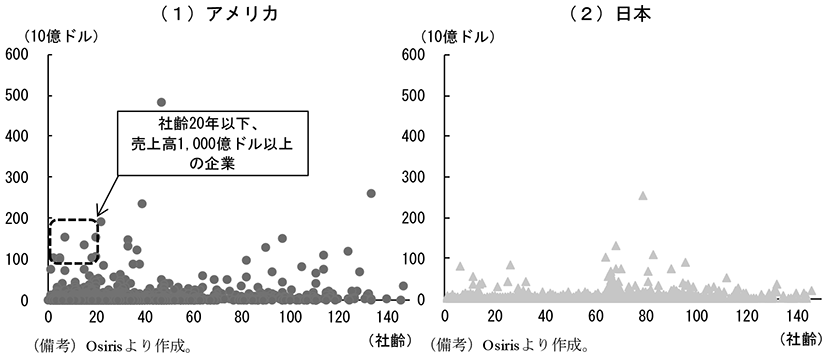
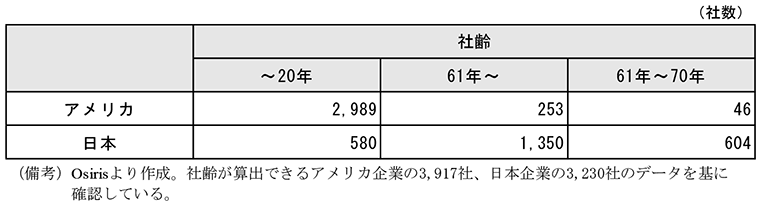
社齢が20年以下で売上高が1,000億ドル以上となっている企業(8社)を個々にみてみると、5社については、古い企業がM&A等のコーポレートアクションを通じて新しい企業に生まれ変わったものである19(第2-2-47表)。他の2社は1980年代創業で、M&A等のコーポレートアクションを経て急成長を遂げたものである。残りの1社は、創業年が1994年と新しく、起業後、わずか20年程度で売上高1,000億ドルを超えるネット小売りの世界最大手へと成長を遂げた企業である。
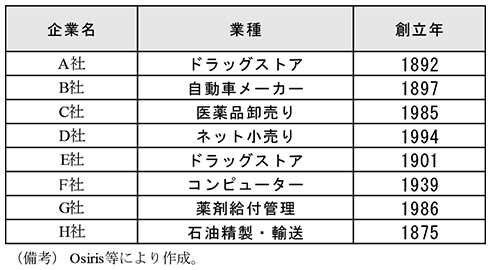
次に、対象を広げ、社齢20年以下、売上高100億ドル以上の企業について分析してみよう(第2-2-48表)20。今回使用したデータベース上、アメリカについてはこの条件を満たす企業は77社あり、そのうち72社はM&Aといったコーポレートアクションを通じて設立年が変わり、社齢の若くなった企業、残りの5社は、起業後短期間で売上高100億ドルを超えるまでに急成長した企業であった。5社の内訳は、2社がエネルギー関連、3社が情報技術関連である。情報技術関連の3社は、いずれもインターネット時代に対応した新たなビジネスモデルを提示することにより、急速に世界的な企業に成長した事例である。なお、日本については同様の基準を満たす企業が15社あるものの、すべてがM&Aといったコーポレートアクションを通じて設立年が変わり社齢の若くなった企業であり、起業後に急成長して売上高100億ドル以上となった企業は今回使用したデータベース上では確認できない。
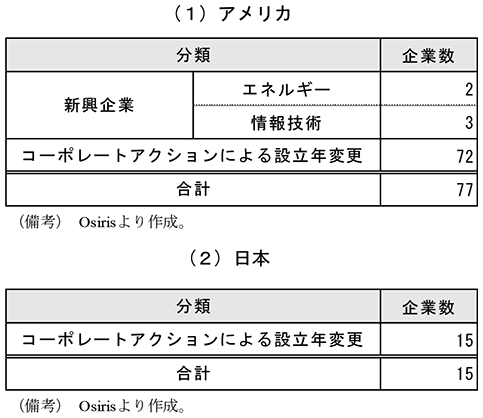
次に、77社の業種別分布をみてみると、エネルギー分野の企業が最も多くなっている(第2-2-49図)。これは、いわゆるシェール革命により大手企業から中小企業まで多くの企業がシェールビジネスに参入する中で、様々なコーポレートアクションを通じて関連企業の再編が進んだ結果、売上高の大きな企業が誕生することになったためであると考えられる。また、ヘルスケア分野の企業も多数含まれている。患者と製薬企業の間で医療費削減交渉を行うサービスを提供する企業や、M&A等を通じて大規模化したドラッグストア等が含まれている。そのほか、小売・卸売、食品・飲料(たばこを含む)、情報技術といった分野の企業がM&A等のコーポレートアクションを通じて新しい企業に生まれ変わっていることが分かる。
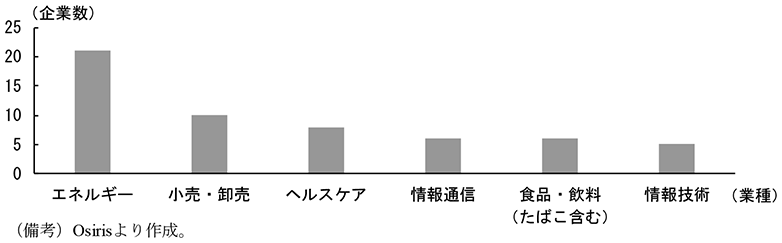
(3)結論
以上、アメリカにおける起業を取り巻く環境や、企業の新陳代謝の状況について分析してきた。まず、アメリカは他の主要国と比較して起業を巡る環境が整っており、世界金融危機後に減少した起業活動やベンチャーキャピタル投資、更にはM&Aが近年再び活性化してきていることが分かった。また、アメリカでは創業からの期間が短い企業や、M&A等のコーポレートアクションを通じて生まれ変わった企業が売上高上位に占める割合が非常に高く、短期間で世界的企業に急成長した企業も存在する。業種別にみると、エネルギー関連、ヘルスケア関連、情報通信関連等の分野で活発な起業や事業再編を通じて成長している企業が多いことがみてとれた21。アメリカ経済には起業文化が依然として残っており、企業の新陳代謝が経済成長に重要な役割を果たしている。このようなビジネスダイナミズムを維持・強化するための環境整備が重要であると考えられる。
アメリカ:425件(05年)、472件(15年)
日本:373件(05年)、458件(15年)

