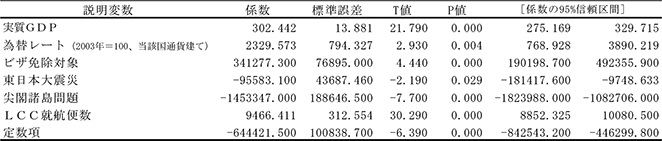付注、付図
付注1-1 有効求人倍率及び完全失業率の増減要因分解について
(有効求人倍率の増減要因分解)
有効求人倍率変化分の要因分解は以下のように行った。有効求人数と有効求職者数をそれぞれ𝑂,𝐴と表し、添字の0は基準時点を、𝑡は比較時点を表す。有効求人倍率の基準時点から比較時点までの変化分は
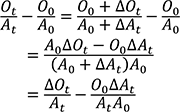
となる。上記第1項が求人要因、第2項が求職者要因である。ここで比較時点の15歳以上人口を𝑃、労働参加率を𝐿𝑃𝑅、失業率(有効求職者数/労働力人口)を𝑈𝑅とすると、求職者数の変化分Δ𝐴𝑡は更に以下の通り近似的に分解できる。
従って
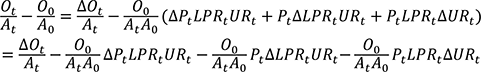
上記第1項が求人要因、第2項が人口動態要因、第3項が労働力率要因、第4項が失業率要因となる。
(完全失業率の増減要因分解)
失業率変化分の要因分解は以下のように行った。失業者数を𝑈、就業者数を𝐸、労働者数を𝐿とすると、失業率は以下の通り表すことができる。ただし、添字の0は基準時点、𝑡は比較時点を表す。
従って
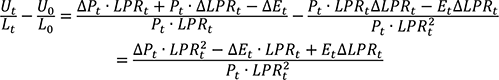
上記第1項が人口動態要因、第2項が就業者要因、第3項が労働力率要因となる。
付注1-2 賃金関数の推定について
ここでは、第1章(第1-1-12表)において行っている、賃金関数の推定方法について参考に示す。
まず、被説明変数については、厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より一般労働者及び短時間労働者の名目賃金(所定内給与額を所定内労働時間で除したもの)の対数を用いている。また、説明変数については、厚生労働省「一般職業紹介状況」より有効求人倍率(ここでは1期前のデータ)、内閣府「県民経済計算」より民間消費デフレーターの対数、労働生産性(就業者一人当たりの実質付加価値額)の対数をそれぞれ用いている。各変数の記述統計量は以下の通りである。有効求人倍率は1期前のデータを用いるため、2010年から2014年までの5年分、それ以外は2011年から2015年までの5年分を使用している。また、各データは県民経済計算によるものは年度、それ以外は暦年である。

付注1-3 シフト・シェア分析について
ここでは、第1章(第1-2-3図~第1-2-6図)において行っている、シフト・シェア分析19の考え方について、雇用を対象にして記す。基本的な考え方は、付加価値額など量として計れるものは同様に分析できる。
シフト・シェア分析は、各地域における雇用の成長率の全国平均からの乖離を、産業構成要因、産業内格差要因に分解し、雇用成長の特徴を分析するものである。
ある地域kの雇用成長率をGk、全国の雇用成長率をGnとすると、両者の乖離は
Gk-Gn=(Gk-Gkn)+(Gkn-Gn)
と表現できる。ただし、Gknは地域kの産業jが、産業jの全国値と同率で成長した場合の地域kの産業計成長率であり、Nkjを地域kにおける産業jの従業者数とし、期間をtからt+1と表せば、以下のようになる。
ここで、
(Gkn-Gn)を産業構成要因、(Gk-Gkn)を産業内格差要因と呼ぶ20。
産業構成要因は、地域kにおいて雇用が成長している業種の集積が大きいと正となる。地域kの産業構造に起因する成長性を評価する指標と解釈できる。一方、産業内格差要因は、産業構成要因で説明されない雇用増を表す。これが正の場合、地域kが産業の活動や立地に関して何らかの有利な条件をもつことが考えられる。
これを、簡単な数値例を用いて表すと以下のようになる。今、仮に全国の雇用者数が製造業50、非製造業50であったものが、次の期に製造業45、非製造業55となったとする。この場合、製造業の増加率は10%減、非製造業の増加率は10%増、全体としては100で不変なので、0%となる。
これをもとに地域Aが製造業30、非製造業70から次の期に製造業36、非製造業84となった場合の要因を産業構成要因と産業内格差要因に分解してみる。まず、地域Aにおいて、製造業、非製造業ともに全国と同様の増加率であったとすると、製造業は10%減少の27、非製造業は10%増加の77となる。この和である104と元の100の差が産業構成要因に相当する部分である。これは、成長産業である非製造業のウェイトの方が製造業より高いために生じる格差である。実際には、地域Aの製造業は36、非製造業は84、合計120まで伸びている。これは全国平均の増加率を上回って増加している。この120と104の差(産業構成要因で説明できない差)が産業内格差要因に相当するものである。
地域Bについて、同様にみてみる。地域Bは製造業が70、非製造業30から次の期に製造業56、非製造業24となった。地域Bにおいて、製造業と非製造業ともに全国と同様の増加率であったとすると、製造業は10%減少の63、非製造業は10%増加の33となる。この和である96と元の100の差が産業構成要因である。ここでは、成長産業である非製造業のウェイトが低いことから産業構成要因がマイナスとなっている。実際には、地域Bの製造業は56、非製造業は24まで減少し、合計が80となっている。この80と96の差が産業内格差要因である。
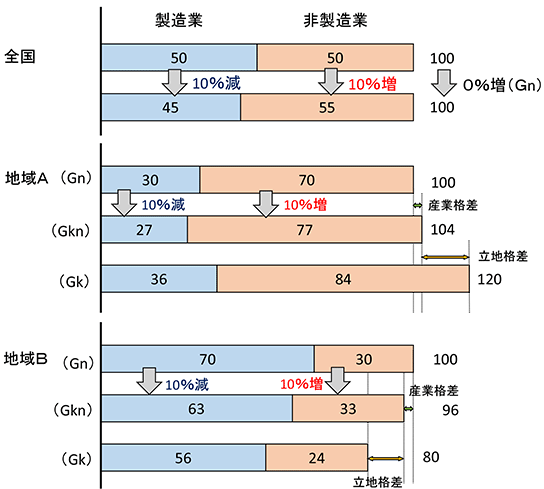
付図1-1 地域別職業間ミスマッチの推移
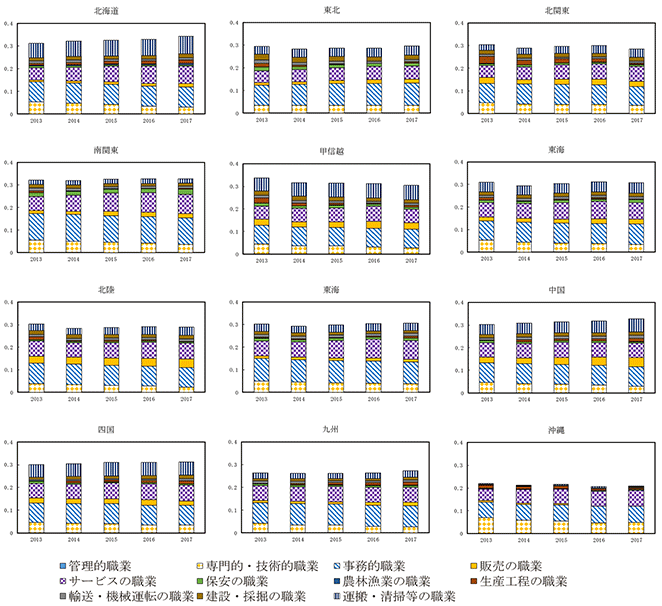
付注2-1 潜在成長圏を訪れる外国人旅行者の特性
インバウンド需要が少ない潜在成長圏(「宿泊旅行統計調査」(観光庁)における2017年のデータに基づく外国人延べ宿泊数の上位5都道府県(東京都、大阪府、北海道、京都府、沖縄県)を除く42県。)を訪れる外国人旅行者の特性を捉え、誘客要因を探ることを目的として、「訪日外国人消費動向調査」(観光庁)の2017年第1四半期から第4四半期までの個票データを用いて分析を実施した。具体的には、「潜在成長圏を訪れたか否か」を被説明変数とし、国籍・地域等の基本属性や日本で行ったことなどを説明変数として、ロジットモデルによる実証分析を行っている。
本分析で用いたモデルは以下のとおりである。
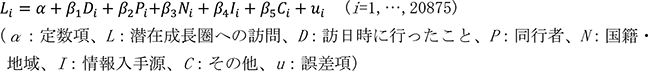
添え字の𝑖は訪日外国人旅行者(調査サンプル:観光・レジャー目的)を示す。「その他」には、性別、年齢、滞在日数、訪日回数、支出額が含まれる。推計時点は2017年である。推計に用いた変数とその定義、記述統計量及び推定結果については、以下の表のとおりである(表1~3)。
また、上記分析では、訪日回数が多いほど潜在成長圏を訪れる旅行者が多いという結果となったところ、具体的に何回目から多くなるのかをみるため、説明変数のうち訪日回数を場合分けして分析した結果、3回目以上において、潜在成長圏を多く訪れる傾向がある。推定結果は以下の表のとおりである(表4)。
表1 推計に用いた変数一覧
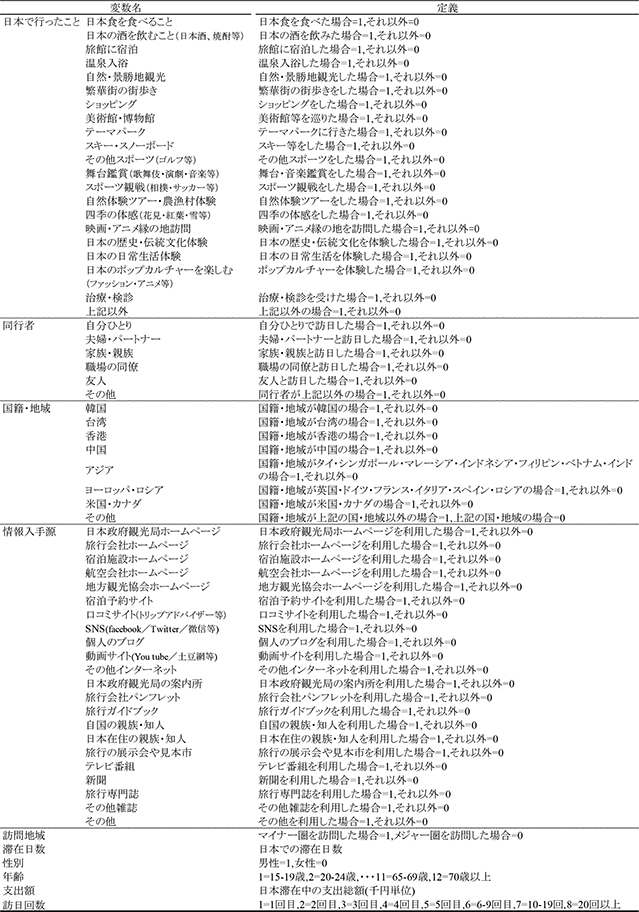
表2 記述統計量
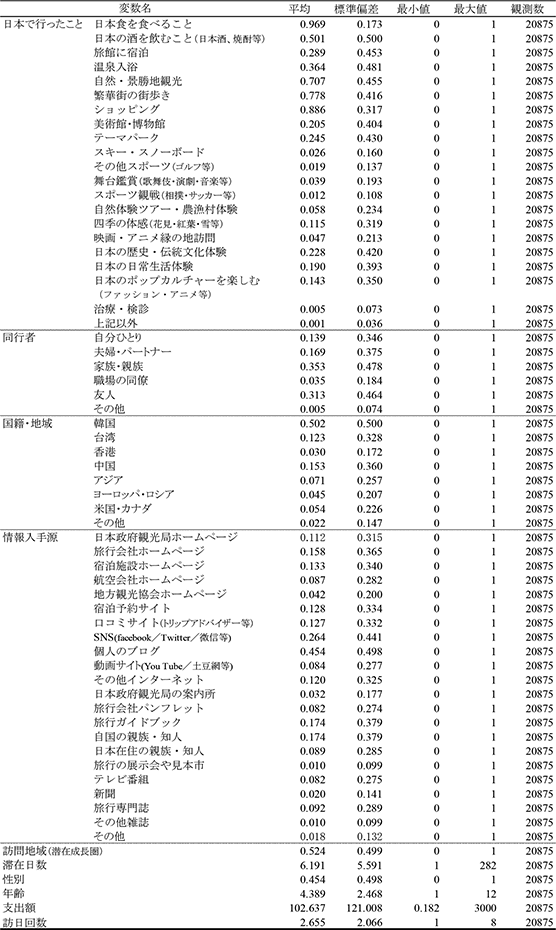
表3 潜在成長圏への訪問に係る推定結果

表4 潜在成長圏への訪問に係る推定結果(訪日回数(3回目以上))
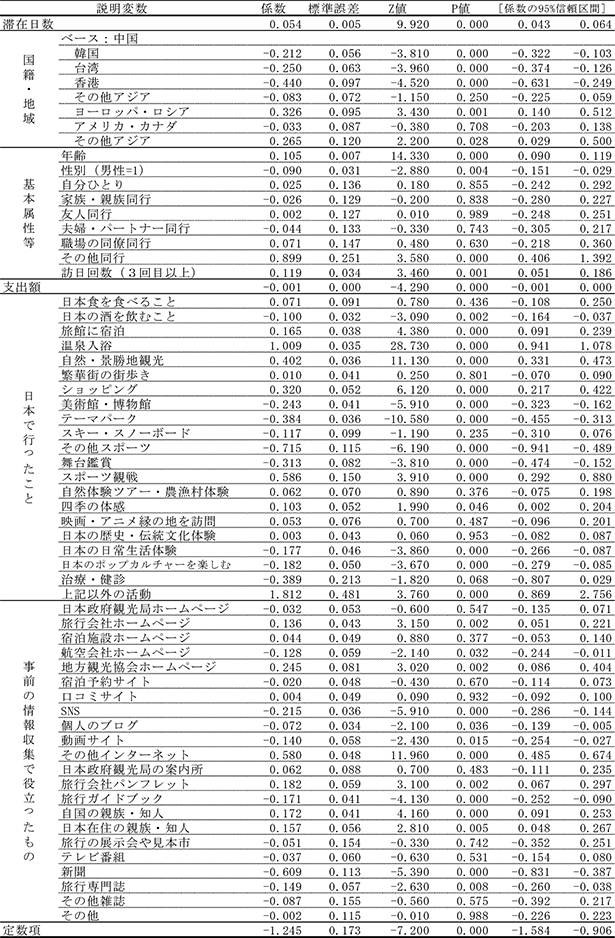
付注2-2 再訪日意欲の高い外国人旅行者の特性
インバウンド需要のすそ野を広げるのに必要なリピーター旅行者になる要因を捉えるため、再訪日意欲の高い外国人旅行者の特性を探ることを目的として、「訪日外国人消費動向調査」(観光庁)の2017年第1四半期から第4四半期までの個票データを用いて分析を実施した。具体的には、「また日本に来たいと思いますか」という問いに対する「必ず来たい」から「絶対来たくない」までの7段階の回答(再訪日意欲)を被説明変数とし、訪問地域(成熟圏・潜在成長圏)や日本で行ったことなどを説明変数として、順序ロジットモデルによる実証分析を行っている。
本分析で用いたモデルは以下のとおりである。
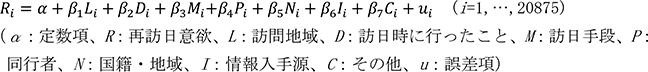
添え字の𝑖は訪日外国人旅行者(調査サンプル:観光・レジャー目的)を示す。「その他」には、性別、年齢、滞在日数、訪日回数、支出額が含まれる。推計時点は2017年である。推計に用いた変数とその定義、記述統計量及び推定結果については、以下の表のとおりである(表1~3)。
表1 推計に用いた変数一覧
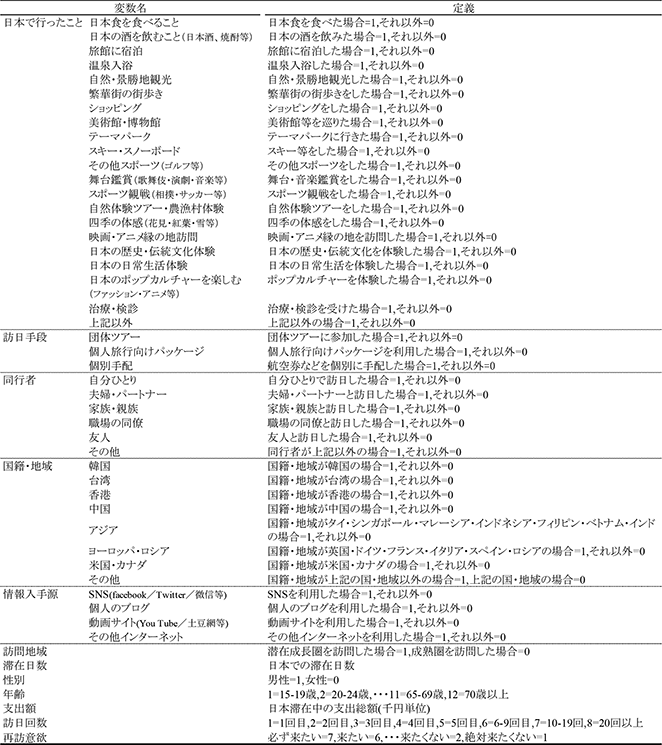
表2 記述統計量
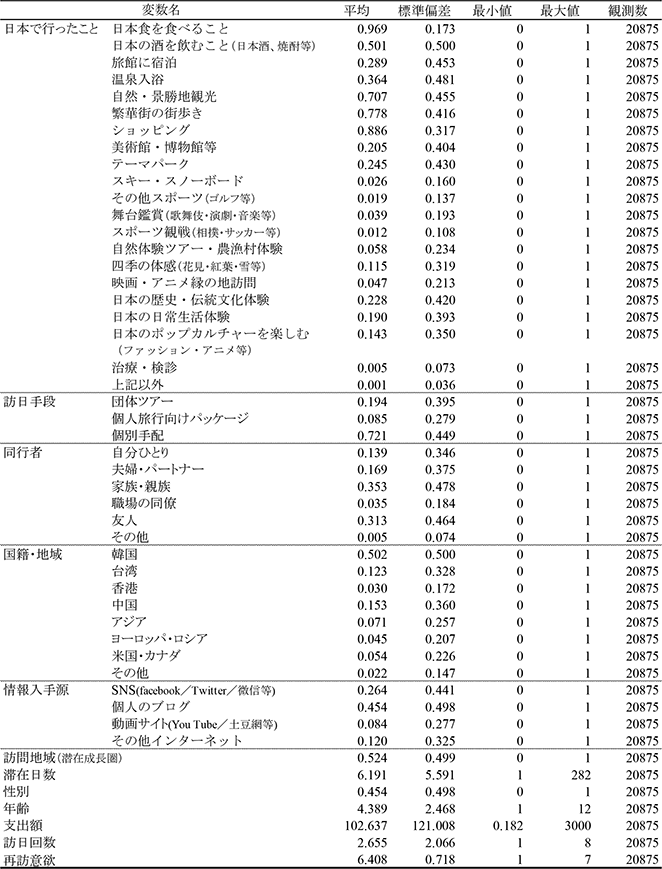
表3 再訪日意欲に係る推定結果

付注2-3 訪日外国人旅行者数の変化要因
訪日外国人旅行者数を決定している要因を分析するため、「訪日外客数」(日本政府観光局)から訪日旅行者数が入手可能な36の国・地域から構成されるパネルデータを構築し、各国の訪日旅行者数がそれぞれの実質GDP、対円名目為替レート、ビザ発給免除措置の有無、東日本大震災ダミー、尖閣諸島問題ダミー、LCC(格安航空会社)就航便数で説明するモデルを推定した。
本分析で用いたモデルは以下のとおりである。
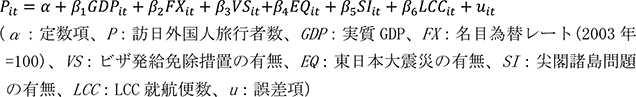
添え字の𝑖は国・地域、𝑡は時点(年)を示す。推計した国・地域数は、36ヶ国・地域、推計期間は、2003年~2017年であり、観測数は540となる。変数に関して、各国の「実質GDP」(IMF“World Economic Outlook”より作成。)を用いるとともに、「名目為替レート」(当該国通貨建て、IMF“International Financial Statistics”より作成。)は、2003年を基準として指数化しており、値の上昇は円安を示す。また、ダミー変数について、「ビザ発給免除措置の有無」(外務省資料による。)は、免除された場合に1、免除されていない場合は0、「東日本大震災の有無」は、2011年に1、それ以外の年は0、「尖閣諸島問題の有無」は、中国のみ2012年と2013年に1、それ以外の国・地域及び年は0、「LCC就航便数」は、LCCによって運行される各国と日本間の定期直行便の週当たり便数(国土交通省「国際線就航状況」)としている。
記述統計量及び推定結果については、以下のとおりである(表1、2)。
表1 記述統計量

表2 訪日外国人旅行者数に係る推定結果