第2節 アジア経済
1.軟着陸を模索する中国経済:投資主導による経済成長の限界
中国は、2010年に日本を抜き世界第2位の経済規模となるなど、世界経済におけるプレゼンスが拡大する一方、その成長の原動力となってきた投資が国内経済にもたらした様々なひずみが顕在化しつつある。中国政府も従前よりその是正に向けた取組を明言しているものの、構造改革が着実に行われているとは言い難い状況にある。以下では、投資主導の経済発展の経緯を概観し、投資主導による経済成長がもたらした問題の1つである、不動産市場の歪みの現状と背景について分析するとともに、中国政府の12年の重点政策目標1である投資主導から消費主導への転換の可能性について展望する。
(1)投資主導で高成長を続けてきた中国経済
中国は1978年以降の改革開放政策の実施以降、高成長を持続しており、2000年から11年までの平均成長率は10.2%、08年の世界金融危機後は若干低下しているものの9%を超える成長率を維持してきた(第2-2-1図)。
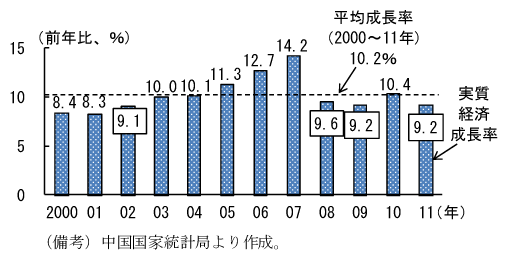
この高成長を支えてきたのは、投資(固定資本形成)である。2000年から11年までの実質経済成長率に占める固定資本形成の寄与率平均は50%を超えている。なかでも、世界金融危機後の09年の寄与率は90%を超えており、08年以降に行われた4兆元の景気対策2のインパクトの大きさがうかがえる(第2-2-2図)。
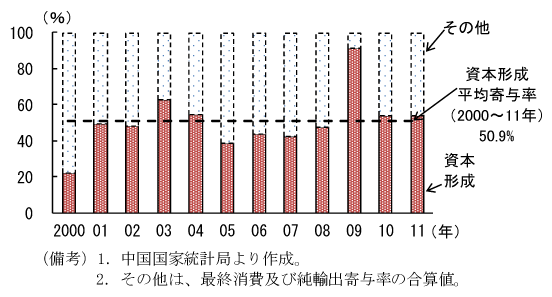
投資規模の大きさについて名目経済成長率に占める総固定資本形成の割合(投資率)から国際比較を行うと、中国における投資率は、近年高成長を続けるインド、インドネシアと比較しても10%ポイント以上、日本、アメリカ、ドイツと比較すると約2倍の差があり、中国の投資率の高さが浮き彫りとなっている(第2-2-3図)。
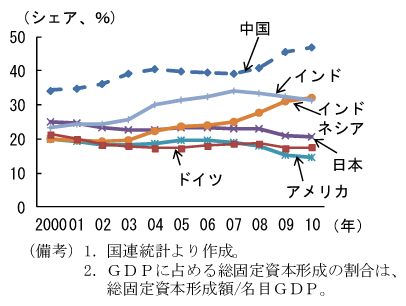
こうした投資率の高さ(=投資主導)の要因の1つとして、国内各部門において貯蓄が積極的に行われている点が挙げられる(第2-2-4図)。家計等各部門の貯蓄額(名目GDP比)は、2000年以降も緩やかに増加し、各部門を合算した国内総貯蓄額3(同上)は2000年の37%程度から08年には50%を超えており、国内各部門4で蓄積された貯蓄が投資への原動力となっていることがうかがえる。
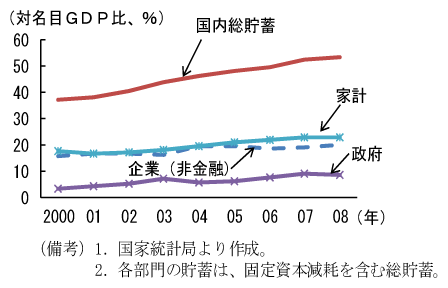
また、金融面からもみても、08年の世界金融危機時に金融緩和政策を実施した結果、09年の新規貸出額は前年の約2倍の規模となり、4兆元の景気対策を推進するため、大量の資金供給が行われたことがみてとれる(第2-2-5図、第2-2-6図)。
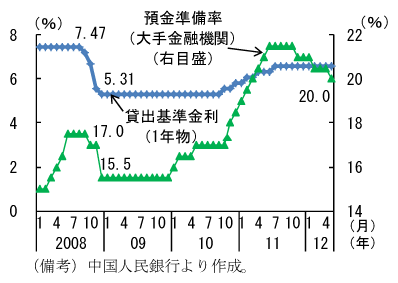
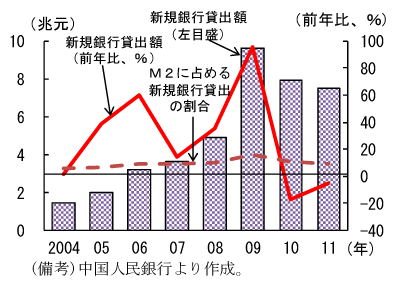
続いて、固定資産投資の動向を産業別、地域別からみていく。まず、2000年以降の産業別の投資動向をみると、製造業等の第2次産業と並び、第3次産業の寄与が大きい(第2-2-7図(1))。さらに、第3次産業の内訳をみると、不動産サービス業を含む不動産業の寄与が大きく、不動産開発が投資のけん引役となっていることが分かる(第2-2-7図(2))。
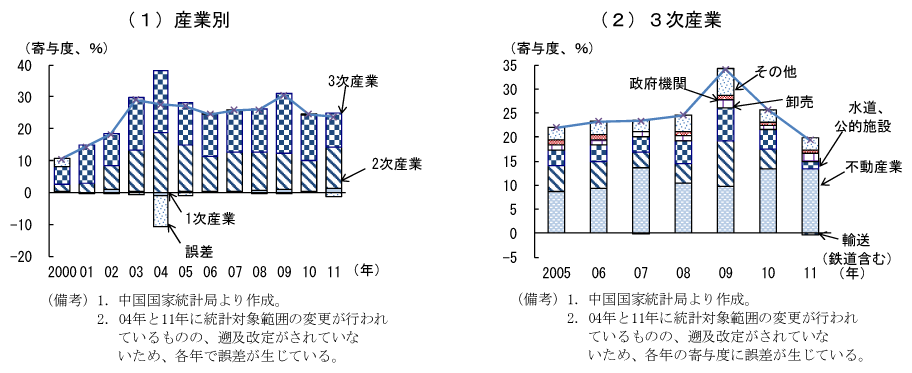
地域別でみると、内陸部の中西部に比べ、沿岸地域の東部地域のシェアが圧倒的に高い。近年、西部開発を始めとした内陸部への投資プロジェクトの実施等により、中西部地域の投資額に占めるシェアは拡大傾向にあるものの、東部地域のシェア及び寄与度が全体に占める割合が高い傾向はここ10年でほぼ変化していない(第2-2-8図)。
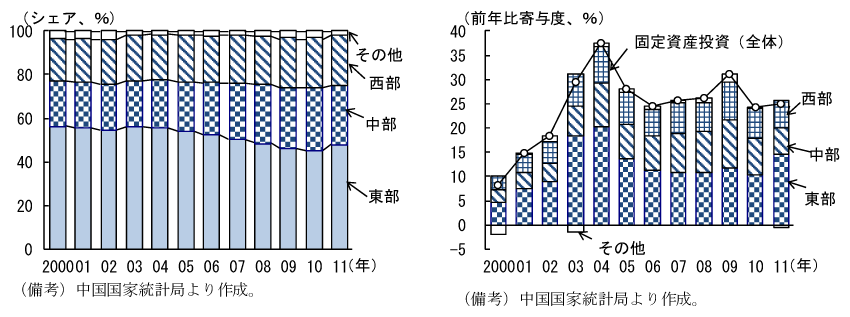
(2)投資主導型の経済成長が生んだ歪み
(i)過熱してきた不動産市場
(ア)不動産市場に流れ込む流動性
このような投資主導の経済成長が産んだ最大の歪みが、一部都市を中心とした不動産市場の過熱である5。中国の不動産価格は、後述するような実需と投資需要から上昇を続けてきたが、とりわけ08年の世界金融危機後、東部の主要大都市を中心に著しく上昇した(第2-2-9図)。
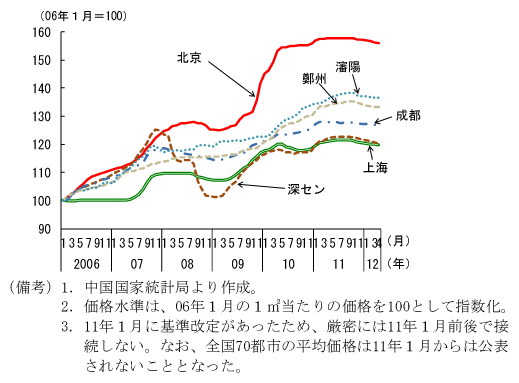
その背景として、中国政府が4兆元の景気刺激策を打ち出したことや金融政策の緩和に伴い市中に流動性が流れ込んだことが挙げられる(第2-2-10図)。名目GDPと対比した流動性の大きさを示すマーシャルのkをみると、09年に大幅に上昇していることが分かる(第2-2-11図)。また、実質金利をみてみると、低い水準あるいはマイナスが続いており、余剰資金が投機目的で不動産市場に流れやすい環境が存在していたといえる(第2-2-12図)。
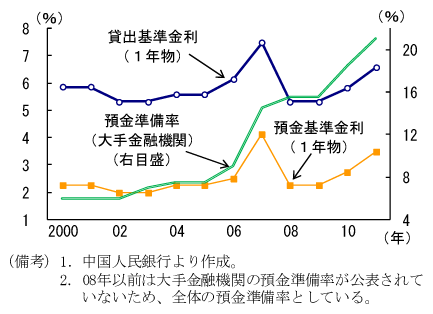
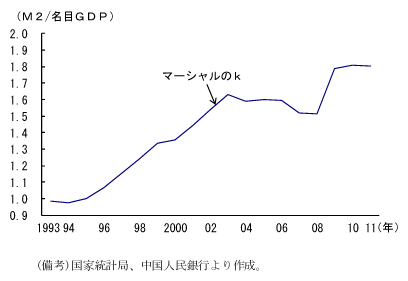
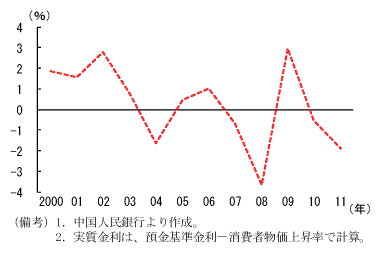
さらに、金融市場が発展途上であることや資金運用のための金融商品が限られていることも、投機資金の不動産市場への流入を促したと考えられる。上海総合株価指数と住宅価格の推移をみると、住宅価格が金融緩和時には上昇しているのに対し、株式指数は必ずしも同様の動きをしていない(第2-2-13図)。中国の株式市場は多くの取引規制が存在していることや不動産の転売によって得られるキャピタルゲインとの比較においても、株式市場よりも不動産市場へより資金が流れやすい構造が存在しているといえる。
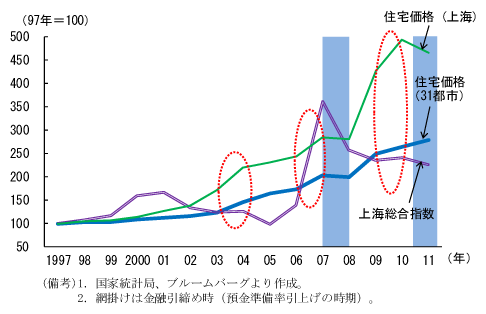
(イ)不動産市場過熱がもたらした格差
このような低金利の継続や金融商品の未発達を背景に、企業や富裕層の間で、資産運用のために不動産投資・投機が活発化した。また、国有・民間企業ともに、不動産事業に進出し、本業部門以外に設立した不動産部門が収益全体の大部分を占める例もあるといい、上海A株市場に上場する企業のうち、不動産業務を手掛ける企業の割合は年々増加してきている(第2-2-14図)。
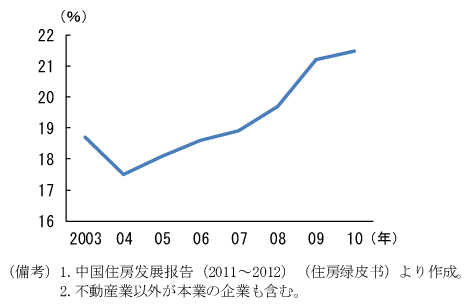
大都市における不動産価格の高騰は、一部の富裕層以外の階層の住宅購入を困難なものとさせた(第2-2-15図)。また、それら一部富裕層は、自らの居住以外にも住宅を保有して家賃収入を得るケースもあり、都市住民間における格差の一因となっている(第2-2-16図)。
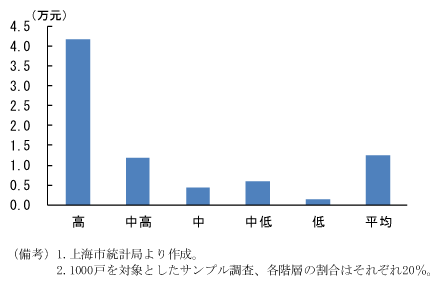
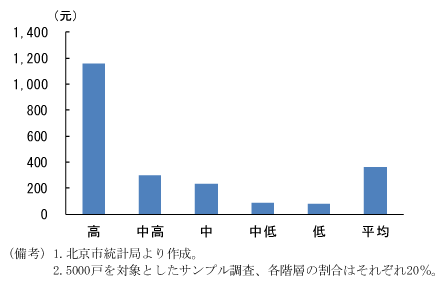
(ウ)地方政府の潜在的債務問題6
地方政府融資プラットフォーム(以下「プラットフォーム」という。)の債務問題は、不動産市場を過熱させた要因の1つであるとともに、過熱した不動産市場が生んだ歪みの1つであるといえる。
地方政府は、恒常的に財源不足に陥っているものの制度的に直接資金調達ができない7。そのため、地方政府は、プラットフォームという第3セクターを設立し、それを利用して銀行から融資を受け、土地開発業者に投資して土地開発を行わせる。そして、不動産開発業者が、地方政府から土地使用権を譲渡される際に地方政府に収める土地使用権譲渡金をもって財源不足を補充する。不動産開発をめぐってこのような三者関係が形成されている。
しかし、プラットフォームは、常に不動産譲渡金を債務返済に充当し続けなければならず、不動産開発の減少とともに、プラットフォームの債務、すなわち実質的には地方政府の潜在的債務は増大している。特に、08年の金融危機後に実施された景気刺激策の影響8で、地方政府はプラットフォームを通じて調達した資金を元に不動産投資を含めたインフラ投資を推進し、結果的に09年以降、地方政府の債務は増加した。審計署(会計検査院に相当)の報告によると、プラットフォームの債務を含めた地方政府の債務残高は10年末で、約10.7兆元(10年名目GDP比26.7%)に上り、とりわけ、不動産開発が旺盛であった東部に集中していることが分かる(第2-2-17図)
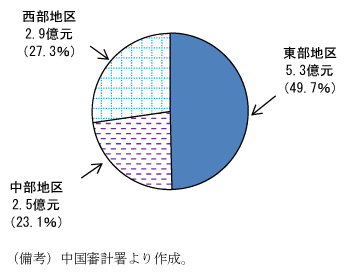
中国政府は、12年の「政府活動報告」の中で地方政府融資プラットフォーム問題の解決を重要政策として掲げており、引き続き、今後の動向に注意が必要である9。
(ii)転換期にある不動産市場
(ア)ばらつきがみられる住宅価格
これまでの各地の住宅価格の推移をみると、一律に同じ動きをしているわけではない。全国の直轄市・省(台湾を除く)・自治区(以下、31直轄市・省等)の1m2当たりの価格をみると、東部では、早くから価格が上昇して、高水準で推移してきたことが分かる。一方、中部や西部では、水準は東部よりはまだ低い状態であるが、価格上昇の伸び率は東部より高まってきている(第2-2-18図、第2-2-19図)。
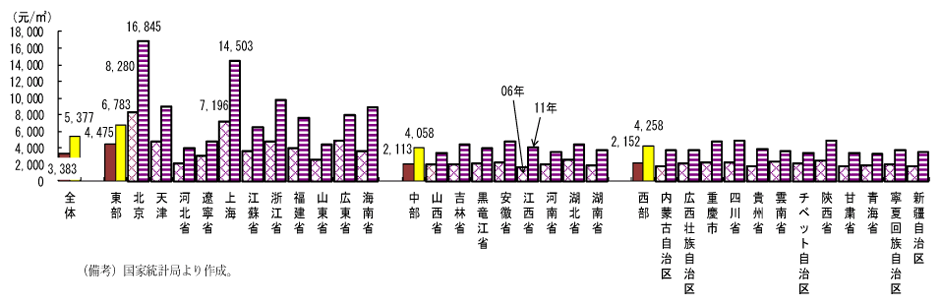
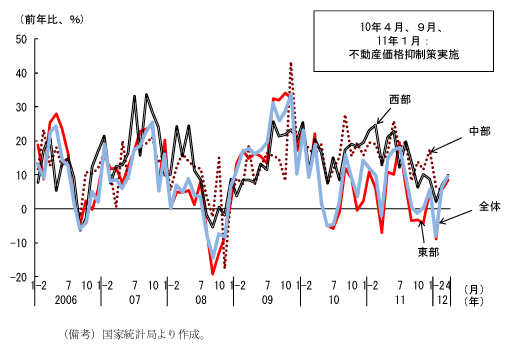
さらに、個別に直轄市・省レベルでみると、06年1月から11年2月までの価格上昇局面では、総じて価格の伸び率が上昇しているのに対し、11年3月から12年1月までの価格下落局面では、東部のうち特に上海と北京の伸びが際立って低下していることが分かる(第2-2-20図)。
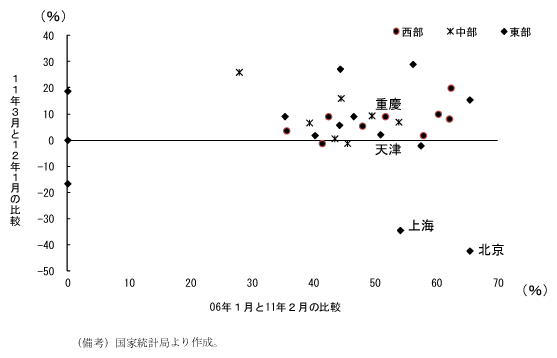
次に、31直轄市・省等の分譲住宅販売価格のばらつきの変化について、変動係数10を計算して調べてみると、08年は前年に比べて低下しているが、03年から10年にかけて上昇基調となっている。すなわち、住宅価格が全体的に上昇する一方で、地域間で価格のばらつきが広がってきていることが確認できる(第2-2-21図)。ただし、その後11年にはばらつきがやや低下している。
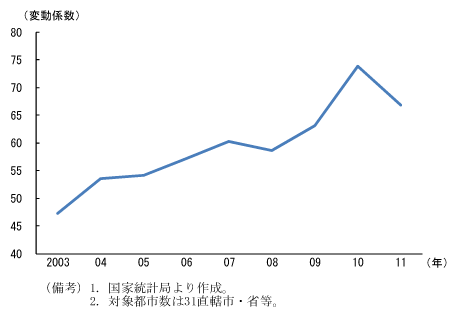
(イ)不動産開発投資の減速と下落をはじめた不動産価格
こうした一部の大都市での不動産価格の高騰を抑えるため、政府は10年4月以降、2軒目の住宅購入の頭金比率の引上げ、当地戸籍非保有者の住宅購入制限等、投機需要を抑制することを主な内容とする不動産価格抑制策を相次いで打ち出すとともに、金融引締めを継続的に行ってきた11。
その結果、09年半ば以降高い伸びを続けてきた不動産開発投資は、11年7月以降前年同月比で低下している(第2-2-22図)。
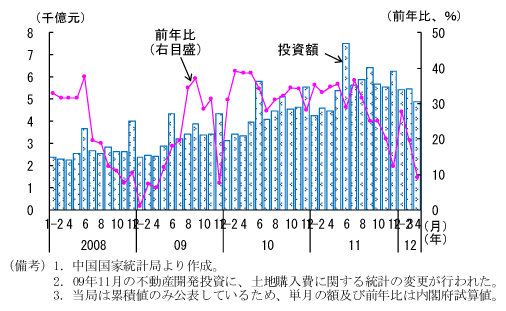
また、住宅販売価格も東部の大都市を中心に低下し、11年1月をピークに価格が前月比で上昇した都市数は減少傾向にある(前掲第2-2-9図、第2-2-23図)12。
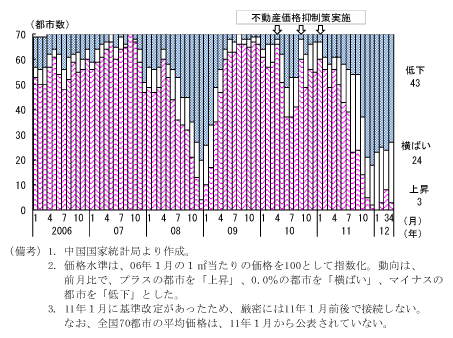
(ウ)先進諸国における不動産市場過熱との比較
不動産市場が過熱した国々と、住宅価格と経済のファンダメンタルズを示すとみられる名目GDP、可処分所得、及び都市人口の推移について比較してみると、中国(31直轄市・省等)の住宅価格は必ずしもこれらの動きからかい離して顕著に上昇しているわけではなく、むしろ名目GDPと可処分所得の勢いは、住宅価格を上回っており、都市人口増加のペースも他国より速い(第2-2-24図)。
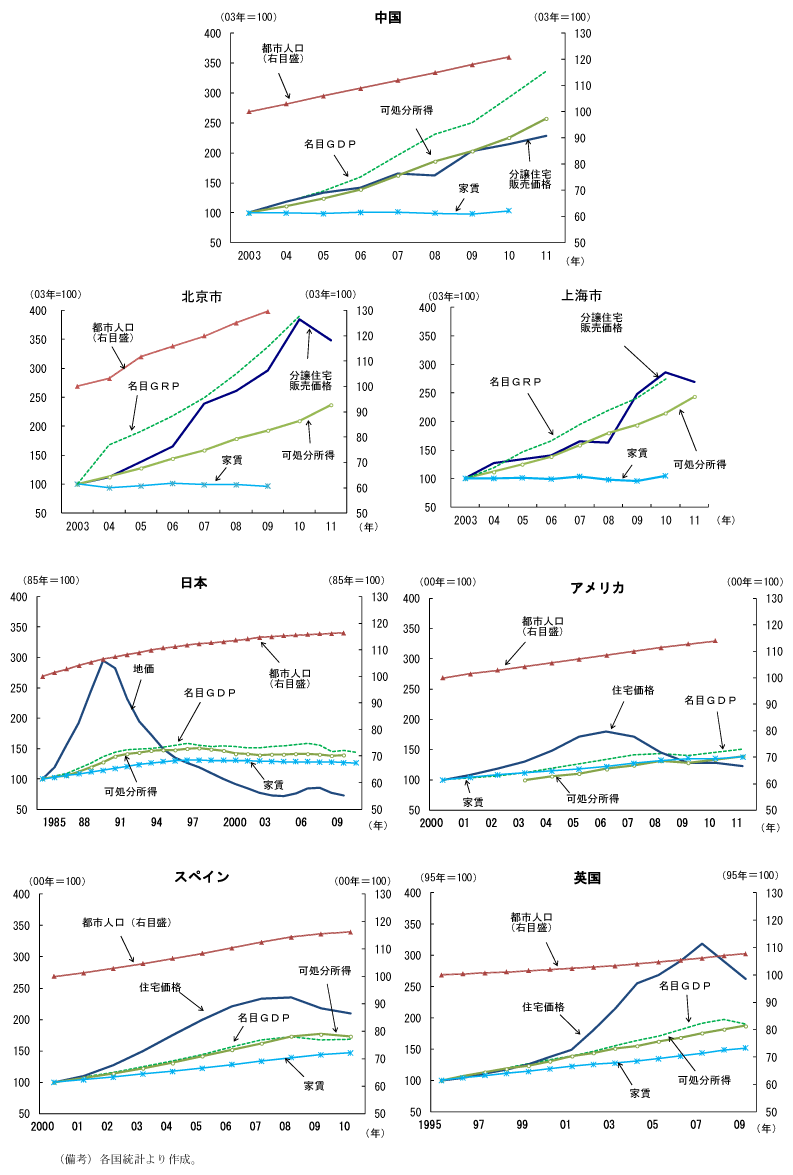
一方、家賃価格の推移をみると、緩やかに上昇している他国と比べて、中国ではほとんど横ばいとなっている。これは、前述のように、持ち家住宅への投機的需要が特に旺盛であることに加え、持ち家志向の強さから賃貸住宅市場が未発達であること、賃貸市場のルールが規範化されておらず住宅賃貸にかかるリスクが高いことなどを背景として、持ち家住宅市場と賃貸住宅市場の間に裁定が働いていないことが原因のひとつと考えられる13。
以上のように、中国の住宅市場は、必ずしもいわゆる「不動産バブル」を経験した国々ほどの過熱をしているわけではないことが分かる。ただし、価格の水準が高い上海では、住宅価格の上昇が、可処分所得や名目GRPの上昇を上回る局面がみられることには注意すべきである 。
コラム2-4:人民元の国際化に向けた動き
96年、中国はIMF8条国入り(注1)をした。しかし現在も、株式投資等の取引を当局が承認した一部の適格海外機関投資家(QFII(注2))にしか認めていないなど、資本取引における規制は依然として厳しい状態である。
中国の経常収支をみると、財・サービス貿易収支にけん引され、黒字で推移している(図1)。中国の貿易額の推移をみてみると、貿易取引額は増加しており、貿易収支は11年1~3月期を除いて黒字で推移していることが分かる(図2)。その背景の一つとして、中国政府が段階的に経常取引の規制緩和を行ってきたことが挙げられる。中国人民銀行は11年8月、クロスボーダー人民元建て貿易決済の対象範囲を中国全土にある全ての企業と世界各国に広げ、12年3月には輸出入経営ライセンスを持っている全ての企業の元建て貿易決済が可能になる通知を発表するなど、段階的に経常取引の可能範囲を拡大してきた(表1)。これらの措置を受け、10年では約5340億元だったクロスボーダー人民元建て取引額は、11年では2兆元を超える額となり前年比で大幅に増加した(図3)。
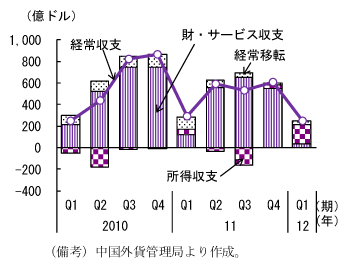
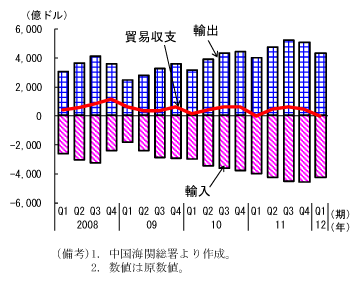
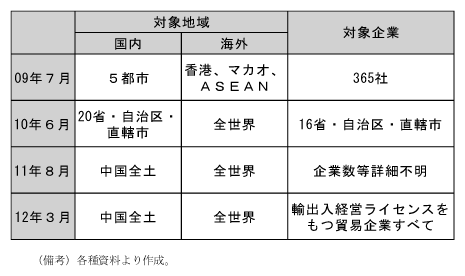
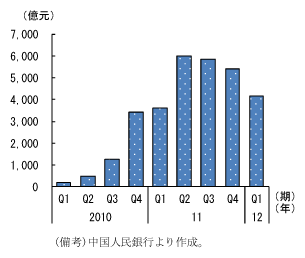
一方、資本取引については依然として厳しい規制が存在しており、対外・対内投資をみると、直接投資に支えられる形で対内投資が対外投資を上回っている。結果として資本収支は黒字で推移し、流入超の状態が続いている(図4)。
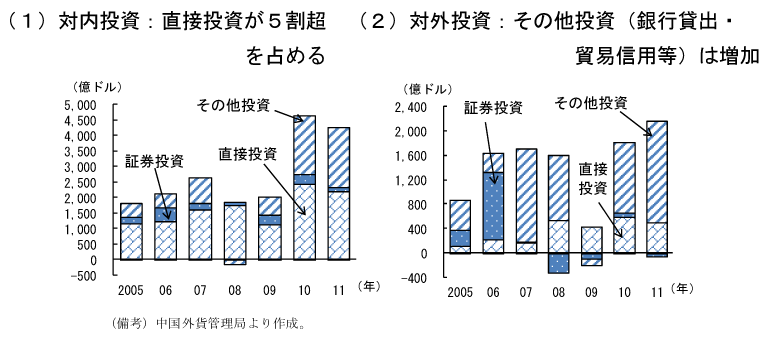
こうした状況下で、12年2月に中国人民銀行が部局及び個人名で公表した資本取引自由化に向けた報告は注目に値する。報告では、10年かけて段階的に資本取引の自由化の範囲を直接投資から不動産取引等へ拡大していくことが提案されており、人民元の国際化へ向けた積極的な姿勢が示されている(表2)。
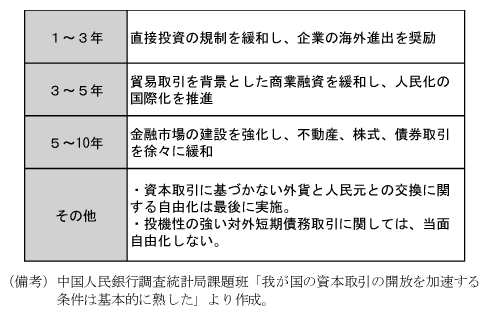
さらに、12年4月に、QFIIのA株(注3)への投資枠を従来の500億から800億ドルに引き上げることを通知するなど、資本取引規制の緩和をすすめていることがうかがえる。しかし、前述した報告の中でも指摘されていたように、資本取引の自由化に伴い、短期債務の増加等のリスクが発生する可能性もあり、規制緩和には注意も必要である。
12年4月14日に、人民銀行は、人民元の変動幅を従来の0.5%から1.0%へ拡大することを発表した。これには、11年8月頃から貿易黒字が縮小傾向にあることや、対中直接投資が11年11月から6か月連続で前年比の伸びが低下していることが背景にあると考えられる(図5)。変動幅を拡大するのは07年5月以来の約5年振りとなる。これにより、人民元は元高・元安双方向への振れ幅が大きくなり、それぞれの方向でのリスクが考えられ、今後それらにどのように対応していくか注視が必要である。
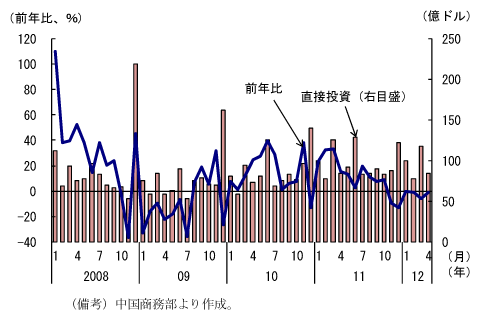
(注1)IMF協定第8条は、加盟国に対して経常取引のための支払い及び資金移動に対する制限を禁止している。自国通貨の経常項目における交換性を実現している国をIMF8条国と呼んでいる。
(注2)QFIIとは、中国証券監督管理委員会(「証監会」)の認定を受けて、中国の証券市場において投資を行うことができる海外の証券会社、保険会社、商業 銀行、基金管理機構、投資信託会社およびその他の資産管理機関等をいう。
(注3)詳細は内閣府(2011b)参照。
(3)内需中心の成長構造は投資主導から消費主導へ
(i)政策の重点は消費拡大へ
消費の動向をみると、主要指標である社会消費品小売総額(名目)は、08年の世界金融危機発生の影響を受け同年8月をピーク(前年比23.2%増)に伸びは鈍化したが、09年から始まった自動車や家電の買換え支援策等の消費刺激策の実施により、09年以降、前年比15%以上の高い伸びを続けてきた(第2-2-25図)。しかし、この買換え支援策の多くが10年末に終了14したことの影響で、11年に入ってからは伸びがやや鈍化している(第2-2-26表)。
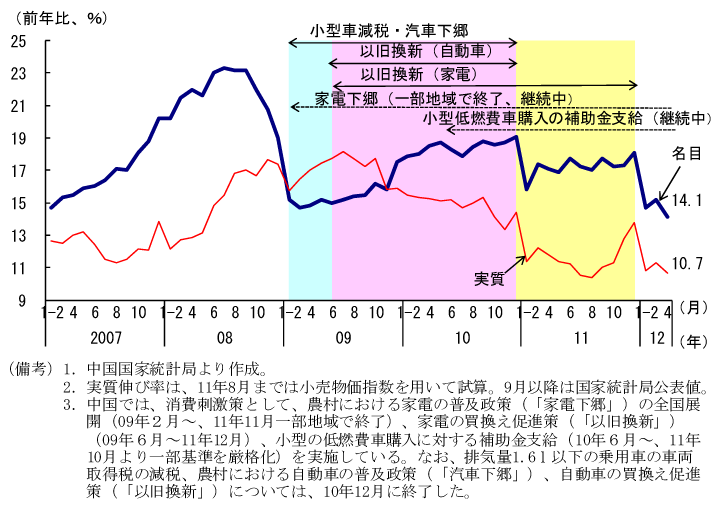
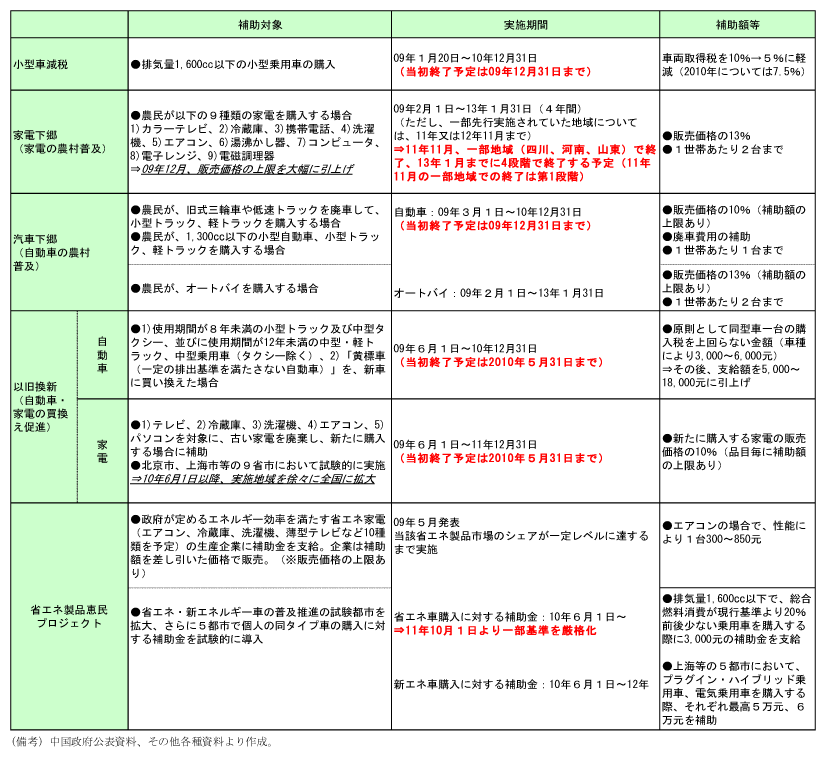
近年の家計消費のGDPに占める割合の推移をみると、家計消費の割合は低下している(第2-2-27図)。これまで内需の拡大は、第11次5か年計画(06~10年)でも重点課題として中長期的に取り組まれてきた課題であり、特に08年に世界金融危機が発生した後は外需が落ち込みをみせる中でその必要性への認識がさらに高まっていた。しかし、高水準の伸びで推移した投資に対し、消費が経済成長をけん引する度合いが強まることはなかった。
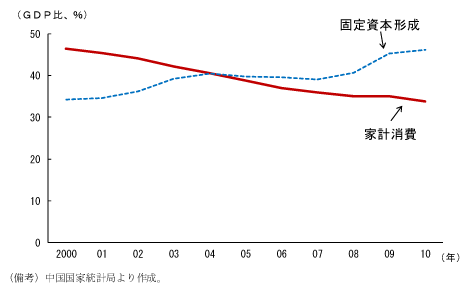
12年3月に開催された全国人民代表大会(以下「全人代」)では、長期にわたって安定したより速い経済発展を目指すため、内需拡大、特に消費の拡大がマクロ経済運営の最優先課題と位置付けられた。具体的には、前述の社会消費品小売総額が12年は前年比14%増とすることを目標とし、所得分配の構造調整や中低所得者層の収入増による購買力の向上等を図るとした。それを受けて、5月には省エネ家電等の消費促進策を実施する方針15が発表されており、今後、こうした政策の実施による消費の伸びの高まりが期待される。
(ii)耐久消費財の普及や消費の高級化等による消費の拡大余地
中国における消費を取り巻く環境として、所得環境と耐久消費財の普及状況等をみることとする。
まず、所得環境のうち賃金動向をみると、中国では平均賃金上昇率(名目)は前年比10%台で推移しており、過去数年にわたり最低賃金も引上げが実施されている(第2-2-28図)。実質賃金の伸びについても、その伸びは消費者物価上昇率が高めに推移してきたことから低下傾向にあるが、依然として増加を続けている。しかし、名目賃金上昇率や雇用者数の増加率も経済成長率(名目)ほど伸びが高まっておらず、労働分配率は低下傾向にあるとみられる16。企業が賃金引上げによって利益をさらに労働者に還元することを通じて、消費が喚起される可能性もあろう17。
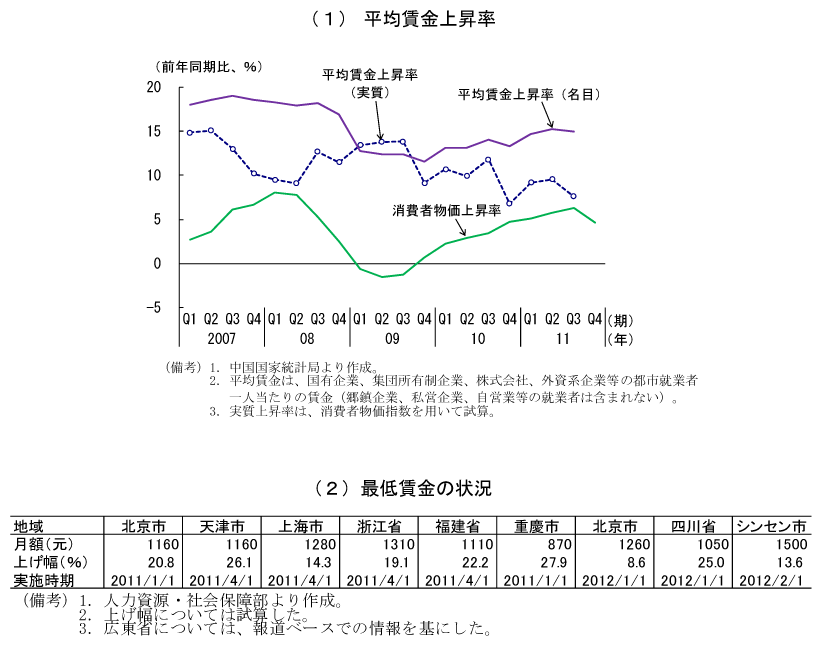
また、都市部と農村部の所得比は依然として低い水準に留まっているが、中国政府が所得格差の是正に努めていることなどから、今後の農村部における所得増も期待される(第2-2-29図)。
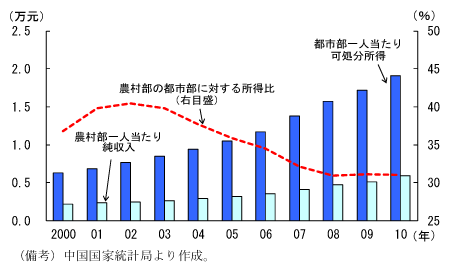
次に、耐久財普及率をみると、農村部ではまだ消費拡大の余地がみてとれるが、都市部では2000年に比して急速に普及してきた後18、ここ数年の動きからは、洗濯機、冷蔵庫、カラーテレビ等はすでに飽和状態に近いことがうかがえる(第2-2-30図)。しかし、環境に配慮した製品への需要が増す動きもあり、今後買換え需要を含め、より質の高い商品への需要が期待できる面もある。また、乗用車の保有台数を日本やアメリカと比較すると依然として大きな差があり、自動車に対する潜在的な需要は依然大きいと考えられる(第2-2-31図)。
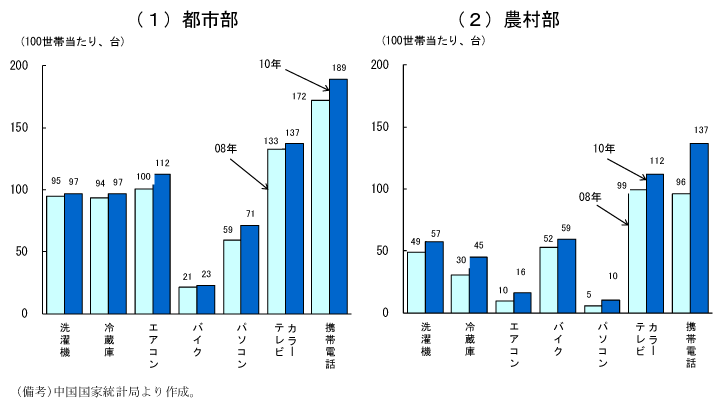
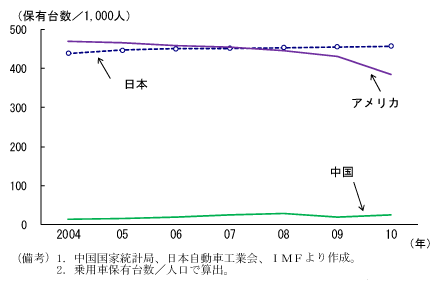
また、中国で最も所得の高い上海市をみると、文化・娯楽サービスに関する消費額が急速に高まっている(第2-2-32図)。収入全体を上回る伸びをみせており、特に、所得層が高いほど、これらの消費額が高まる傾向にある。例えば、海外旅行者数は増加傾向にあり、海外旅行時にはブランド品等の高級品を購入する目的もあると指摘されている(第2-2-33図)19。
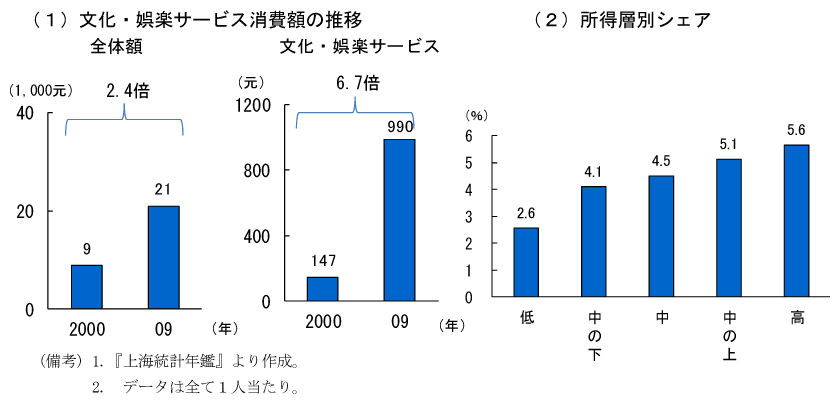
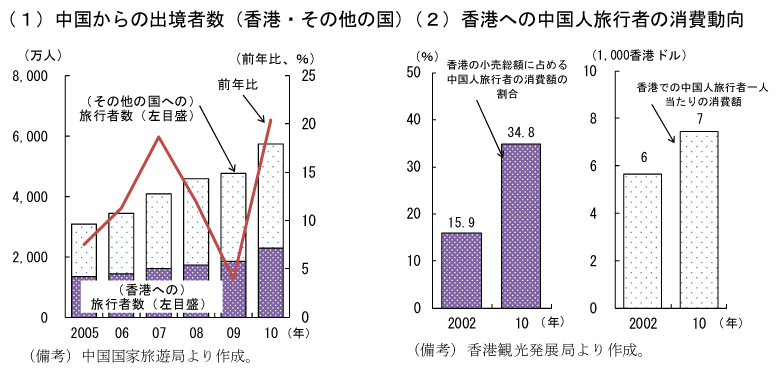
今後、中国が消費を拡大させ、成熟した消費社会に移行していくには、物価の安定と所得の増大による実質所得の向上に加え、農村所得の底上げによる所得格差の是正、将来の生活不安による予備的貯蓄動機に基づく家計の貯蓄行動を和らげる社会保障制度の整備等の政策対応が肝要であろう。
コラム2-5:第11期全国人民代表大会の概要
2012年のマクロ経済運営の基本方針を決定する、全国人民代表大会(以下、全人代:国会に相当)では、財政政策については、09年から引き続き「積極的な財政政策」を維持する一方、金融政策については、11年に引き続き「穏健な(中立的)金融政策」を維持することが決定された。また、マクロ経済運営の最優先課題は「内需(特に消費)拡大」となり、11年の「物価水準の安定」から変更となった(表1)。
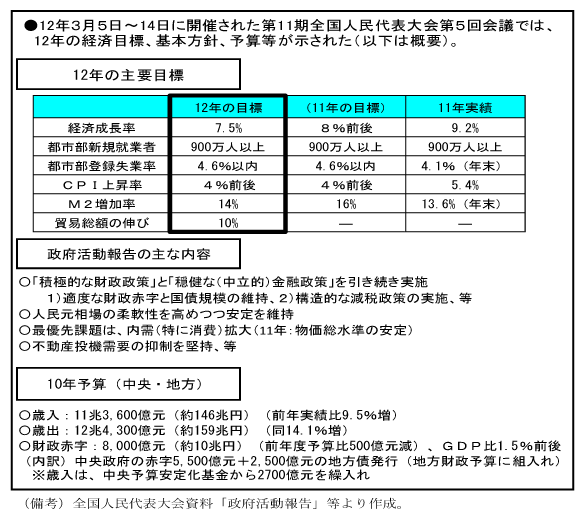
12年の主要目標をみると、実質経済成長率については7.5%と設定され、これまでの8%前後という目標値から引き下げられた。実質経済成長率を引き下げた理由としては、1)国内外の経済の動きの反映、2)第12次5か年計画の目標との整合性20、3)資源・環境制約の軽減等を挙げている。
12年の予算案をみると、歳入は前年比9.5%増、歳出は同14.1%増となっている(図1)。11年に続き、中央政府と地方政府を合わせて財政赤字を計上しているが、財政赤字の規模は昨年の当初予算案で500億元減額し、8,000億元(GDP比1.5%前後)と見込んでいる。なお、そのうち5,500億元は中央政府に計上され、残りの2,500億元については地方債を発行し、地方政府予算に組み入れることとされている。
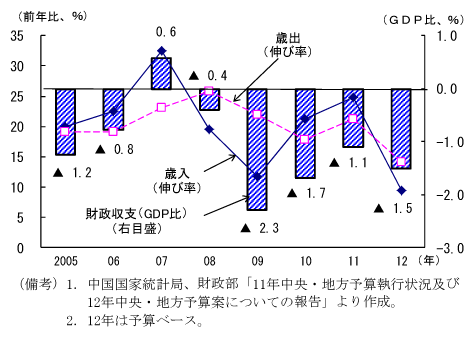
中央財政支出(地方への移転支出含む)は前年比13.7%増。この内訳をみると、人民大衆の生活に直結する教育や医療衛生、社会保障・雇用、住宅保障、文化等の諸分野に振り向ける支出は前年比19.8%増(10年同18.1%増)とされる。
12年は政権交代等も控えていることから、11年12月中央経済工作会議で掲げられた「穏中求進(安定の中でさらなる発展を追求する)」という基本方針の下、安定重視の経済運営が行われることが見込まれる。

