第2章 感染症による影響から回復に向かう世界経済(第2節)
第2節 主要地域の経済動向
1.アメリカ経済
アメリカでは、20年前半に感染症の拡大を受けて景気が急速に悪化したが、同年中盤以降は持ち直しに転じ、足下でも持ち直しが続いている136。特に21年前半は、経済活動の再開や現金給付を伴う追加経済対策137の効果等により、個人消費や民間設備投資が大きく伸長し、4~6月期には実質GDPが感染拡大前の水準を上回った。続く7~9月期は、供給制約や感染再拡大等が影響し、前2四半期と比較すると伸びが縮小したが、引き続きプラス成長が維持され、経済の底堅さが示された。10~12月期は、在庫投資の増加に加え、個人消費も堅調に推移した結果、前期比年率+6.9%と再び成長ペースを上げてきた(第2-2-1図、第2-2-2図)。
ただし、感染拡大の影響やその後の持ち直しの進展は業種等により一様でなく、21年末時点でなお、感染症の影響が残っている業種等も存在する。本節では、アメリカ経済のうち、特に個人消費、生産及び雇用に係る主要指標について、21年後半を中心とした感染拡大後の動向を概観するとともに、各指標の業種等による動向及び持ち直しの進展の相違を確認する。また、持ち直しが遅れている業種等については、その背景や今後の更なる進展に向けた課題を検討する。
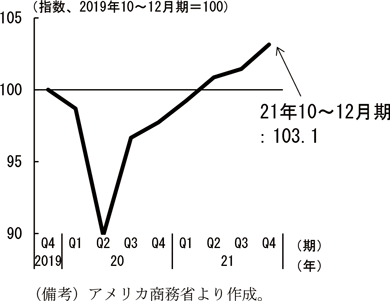
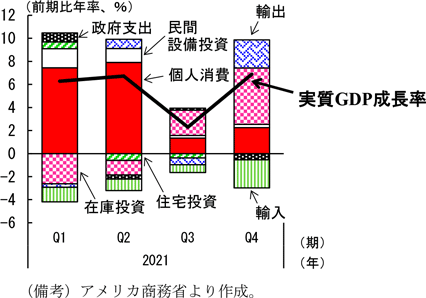
最初に、感染拡大後の個人消費全体の動向を振り返る。実質個人消費支出(総合)は、20年5月以降持ち直しを続ける中で、特に上述の追加経済対策の策定直後に顕著な増加を示し、21年3月には感染拡大前の水準を上回った。同年4月以降は、しばらく横ばいで推移した後、夏頃から再び増加傾向となり、供給面の制約やそれに伴う消費者物価の大幅な上昇(第1節を参照)に直面する中でも、引き続き個人消費が堅調であることが示された138(第2-2-3図)。
次に、実質個人消費支出を耐久財、非耐久財及びサービスの3部門に分けて、部門ごとに動向や持ち直しの進展が異なることを確認する。まず、21年3月までの部門別の動向を概観すると、耐久財消費は、比較的早期に感染拡大前の水準を持ち直し、その後は追加経済対策に合わせて段階的に水準を上げる形で推移した。非耐久財消費は、早期に持ち直した点は耐久財と同様であるが、対策に伴う増加は耐久財と比べて小幅となった。一方、サービス消費は、感染拡大時の落ち込みは耐久財と同程度であったが、その後の持ち直しは大幅に遅れ、対策に伴う増加もわずかにとどまった。中でも、飲食・宿泊サービス、輸送サービス及び娯楽サービスは、感染拡大時の落ち込みが大きかったことに加えて、20年末頃の感染再拡大時にも減少傾向がみられるなど、持ち直しの遅れが顕著であった(第2-2-4図)。これらのサービスは、一般に人の接触や移動を伴うことから、感染症下で特に消費需要が減少したと考えられるが、それに加えて、感染拡大時や20年末頃からの感染再拡大時に各州で講じられた経済活動の制限措置139が、飲食店等で特に厳しく適用されたことも影響した可能性がある。
続いて21年4月以降の動向をみると、耐久財消費は、夏頃にかけて減少が続き、3月の対策による増加分がほぼ消失したものの、9月以降は再び増加傾向に転じた。このうち夏頃までの減少局面では、特に自動車・同部品について、半導体不足等の供給面の制約(第1節参照)を背景に大幅な減少がみられたが、PC・AV機器等を含め、その他の耐久財でも緩やかな減少傾向がみられたことから、耐久財全般にわたって、物流面を含めた供給面の制約が生じていた可能性がうかがえる140。非耐久財消費は、夏頃にかけておおむね横ばいで推移した後、耐久財同様、秋頃からは緩やかな増加傾向を示すようになった。一方、サービス消費は、感染症が比較的落ち着いていた3~7月には以前より速いペースで持ち直したが、その後感染者の増加がみられるようになると、相対的に持ち直しが遅れていた3業種を中心に伸びが緩やかになった。このうち、飲食・宿泊サービスは9月に感染拡大前の水準を回復したが、輸送サービスと娯楽サービスは11月末時点でも感染拡大前を10%以上下回る水準にとどまっている。もっとも、飲食・宿泊サービスを細かくみると、飲食サービスは感染拡大前の水準を上回っている反面、宿泊サービスは8割5分程度の回復にとどまることから、不特定多数との接触や長距離の移動を伴うサービスについては、感染症の影響が依然として残っているといえる。
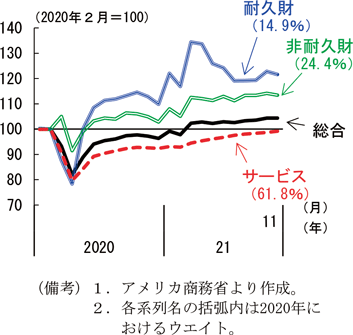
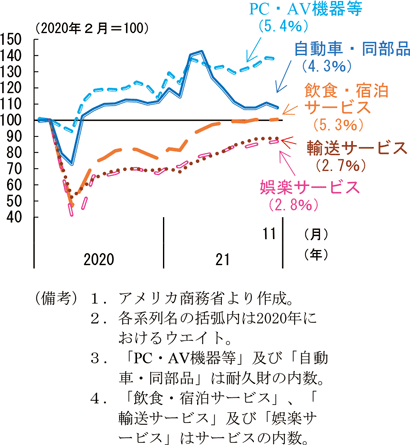
鉱工業生産は、感染拡大の影響で20年3~4月に大幅な落ち込みを示したが、5月以降は持ち直しが続いた。21年に入ってからも、2月には南部の寒波の影響で半導体や化学製品等の工場の多くが操業を停止したこと、8月末~9月上旬にはハリケーン・アイダの影響で石油化学製品やプラスチック樹脂、石油精製等の工場が閉鎖されたことにより、それぞれ一時的な落ち込みがみられたが、全体としては持ち直しの基調が続き、製造業では7月、総合では11月に、感染拡大前の水準を回復した(第2-2-5図)。
しかし、鉱工業生産においても、個人消費と同様、業種ごとに感染拡大後の動向や持ち直しの進展は異なる。鉱工業生産の7割強を占める製造業について、主な業種別の動向をみると、自動車・同部品は、20年4月には2月の2割程度の水準にまで落ち込むなど、感染拡大の影響が特に大きくみられたが、消費の持ち直しとあいまって7月には感染拡大前の水準を回復した。しかし、21年に入ると、世界的な半導体不足(第1節を参照)を受けて複数の自動車メーカーで断続的な生産停止が行われるようになったほか、夏頃からは東南アジアでの感染再拡大に起因する部品調達難もみられるようになり、2月に半導体不足と寒波の影響を受けた樹脂部品等の供給不足があいまって大きく落ち込んだ後は、再び感染拡大前の水準を下回って推移している(第2-2-6図)。航空機は、20年10月に感染拡大前の水準を回復し、その後も増加基調が続いている。2度の墜落事故を受けて運航が禁止され、20年1月から生産停止となっていた大手航空機メーカーであるボーイングの新型機について、同年11月18日に当局が当該機種の運航再開を承認し、航空各社の運航路線において再び運用が開始されたことも、生産活動の追い風になっていると考えられる。加工金属は、感染拡大に伴う落ち込みは自動車・同部品や航空機より小さかったものの、その後の持ち直しでは遅れをとっており、緩やかな増加傾向を維持しつつも、21年12月時点で依然として感染拡大前の水準を下回っている。一方、コンピュータ・電子機器は、感染拡大に伴う落ち込みが小幅にとどまるとともに、その後も順調な増加が続いている。この要因としては、感染拡大後のテレワークの進展が指摘されている。
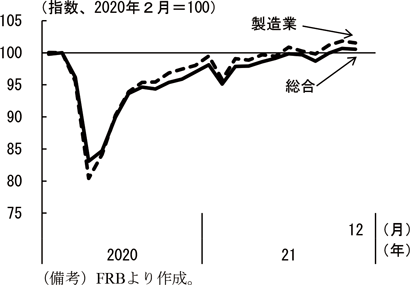
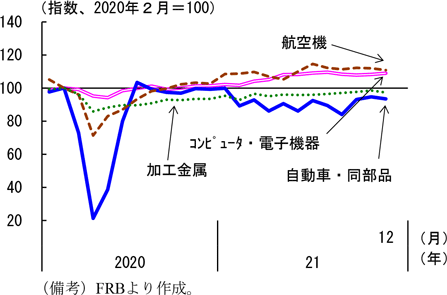
非農業部門雇用者数は、感染拡大の影響で20年2月から4月にかけて2,236万人の大幅減となったが、その後は経済活動の再開等を受けて持ち直しが続き、4月以降21年12月までに1,879万人を回復した。このうち21年の動向をみると、年前半は、ワクチン接種の進展や感染者数の減少、追加経済対策等を背景とした経済活動の一段の進展等を受けて、感染拡大時の落ち込みが特に大きかったレジャー・接客業で持ち直しが大幅に進展したことから、年央にかけて早いペースでの増加が続いた。一方で8月以降は、デルタ株による感染再拡大等を受けてレジャー・接客業の伸びが減速したことに伴い、非農業部門全体としても増加ペースが緩やかとなった(第2-2-6図)。
なお、非農業部門の約7割を占める民間サービス部門の主な業種別に21年の雇用者数の動向をみると、先述のレジャー・接客業を始め、小売業、医療・福祉サービス業といった相対的に対面サービスによるところが大きいとみられる業種で年後半の増加ペースが緩やかになった一方で、輸送・倉庫業や金融業、専門・ビジネスサービス業では21年を通じてほぼ一定の増加ペースが維持されており、個人消費や鉱工業生産と同様に、業種によって動向に相違があることが確認できる(第2-2-7図)。また、各業種の足下の水準をみると、21年後半に増加ペースが緩やかになった業種、すなわち相対的に対面サービスが多いとみられる業種ではいずれも感染拡大前を下回ったままとなっているが、増加ペースが維持された業種では、輸送・倉庫業と金融業が感染拡大前の水準を上回り、専門・ビジネスサービス業も同水準にほぼ到達する状況となっている。各業種において持ち直しが始まった当初は、小売業は財消費の持ち直しとあいまって速いペースで進展し、医療・福祉サービスも輸送・倉庫業等と同等以上のペースで持ち直していたが、21年末時点でみると、こうした対面サービスによるところの大きい業種では、感染症の影響が依然として残り、持ち直しの進展も遅い傾向となっている。
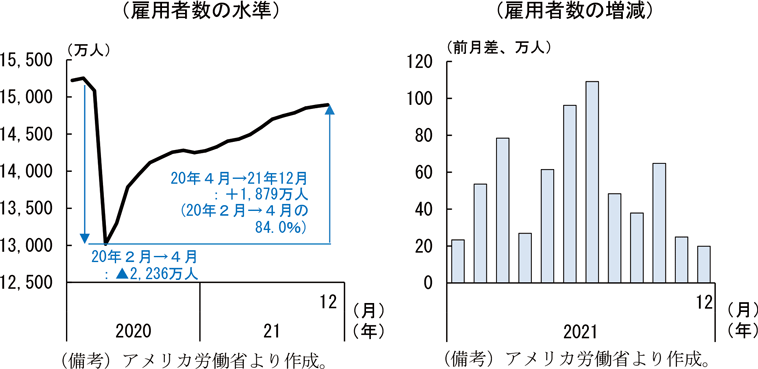
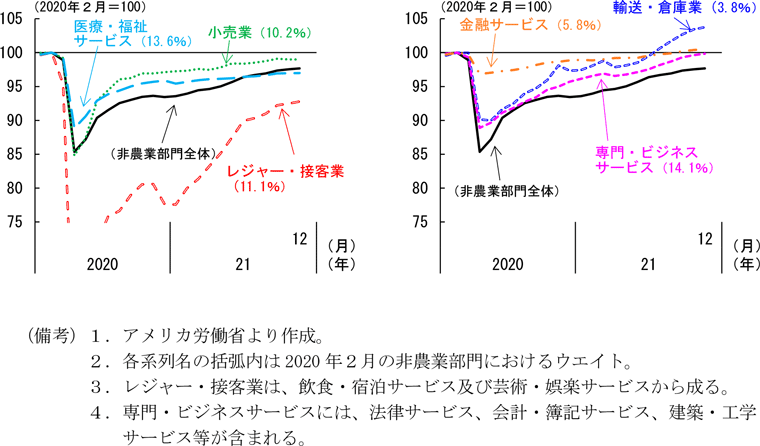
失業率は、感染拡大を受けて20年2月の3.5%から4月には14.7%と急激に上昇したが、5月以降は低下基調が続き、21年12月時点で3.9%まで低下してきている(第2-2-9図)。このうち21年の動向をみると、特に7月以降、低下ペースが一段と速まっている。この要因としては、感染拡大後に経済対策として実施されてきた失業保険の上乗せ措置が21年6月から9月にかけて終了したこと(第1節を参照)が影響しているとの指摘もある。
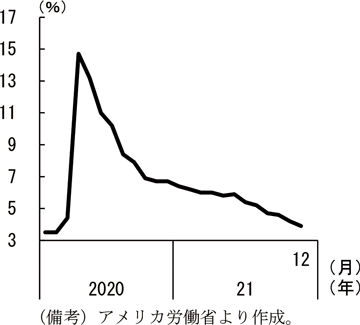
Box.労働参加率の動向
雇用者数が感染拡大前の水準に向けて着実に持ち直しを続ける中、労働参加率は感染拡大時の落ち込みの約半分の回復にとどまったまま、20年後半以降ほぼ横ばいで推移しており、労働市場の現状及び今後をみる上での注目点となっている(図1)。感染拡大以来の労働参加率の低迷の要因としては、高齢化の進展やそれに伴う退職の増加といった構造的要因に加えて、感染症に起因する育児等の必要性や感染症そのものへの懸念が仕事への復帰を阻害していることなどが指摘されている141。実際に、年齢層別の労働参加率の動向をみると、特に子育てに直面する人が多くなるとみられる30代後半~40代前半と、キャリアの終盤から老齢期に当たる55歳以上の年齢層で、感染拡大に伴う落ち込みからの戻りが遅れていることが分かる(図2)。
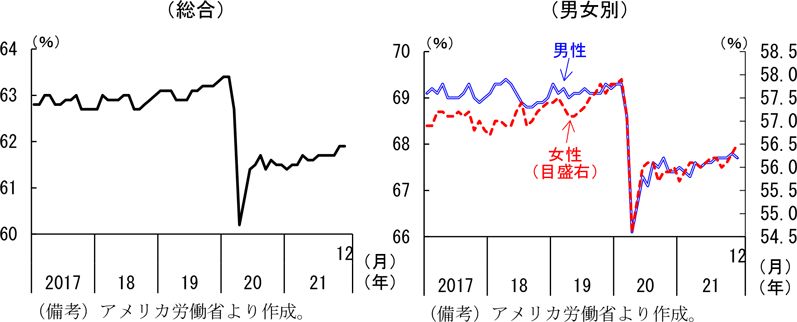
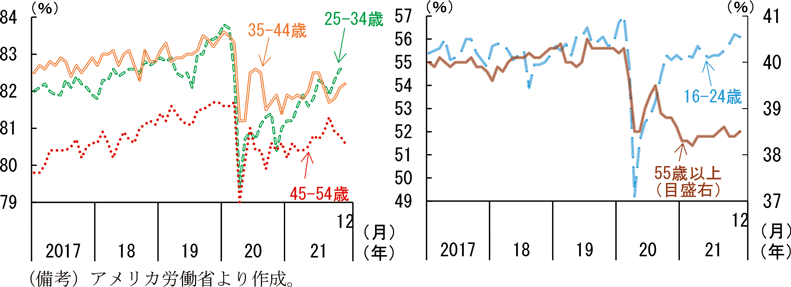
以上に示したように、各指標のヘッドライン(代表的な系列)でみると、個人消費と鉱工業生産は感染拡大前の水準を上回り、雇用者数や失業率も感染拡大前の水準に向けて進展が続いていることから、総じてみれば、アメリカ経済は各面において感染症からの持ち直しが進展している。しかし、個別の業種等に目を向けると、人の接触や移動を伴う一部のサービス部門で消費や雇用の持ち直しが顕著に遅れているほか、労働市場では、失業者の職業復帰は着実に進展している一方で、子育て世代や高年齢層を中心に、感染拡大を機に労働市場から退出した者の職業復帰は遅れているといった課題もみられる。22年に入っても、オミクロン株の影響で感染者数が急増するなど、感染症下での経済活動が続いている中、今後、上述の感染症に関連する課題が改善に向かうか否かは、アメリカ経済の更なる持ち直しの鍵になると考えられる。
トピック1:アメリカの住宅市場 -過去最高の住宅価格上昇率をどう考えるか-
アメリカでは、感染拡大後、住宅価格の大幅な上昇が続いている。全米主要20都市圏142の中古住宅の価格動向を示すケース・シラー住宅価格指数の上昇率(前年同月比)をみると、20年12月に約7年ぶりの10%台となる10.2%、21年5月には2000年代の住宅バブル期143のピーク(04年8月:同17.1%)を上回る17.3%、7月には20.2%と、20年後半から21年中盤にかけて加速度的に上昇し、21年後半も、依然として住宅バブル期を上回る上昇率を維持している。こうした中、2000年代の住宅バブル崩壊が、サブプライム住宅ローン問題を通じて世界金融危機の遠因となったことを念頭に、金融当局者を中心に、当時を上回る上昇率を示す足下の住宅価格動向への関心が高まっている144。ここでは、2000年代の住宅バブルと感染拡大後の住宅価格上昇の背景を説明した上で、両期間の家計の債務状況を比較し、足下の大幅な価格上昇に伴うリスクを整理する。
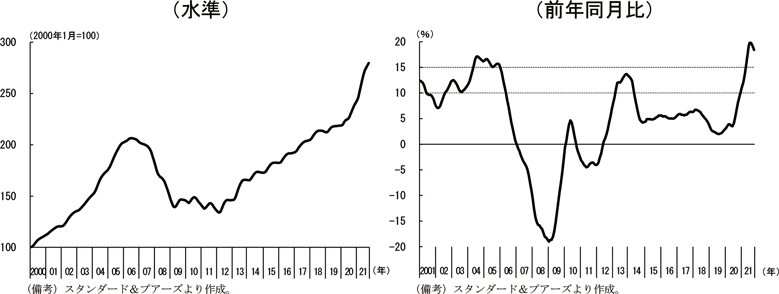
(1)住宅価格上昇の背景
2000年代の住宅バブルでは、主に住宅ローン金利の低下等を受けて住宅需要が増加したことから、価格上昇が生じたと考えられている145。一方、感染拡大後の住宅価格上昇については、住宅ローン金利の低下や感染拡大を受けた郊外志向の高まり146を背景とした需要増と、資材不足等による供給制約の両面から、価格上昇が生じていると指摘されている147。以下では、特に供給制約の状況に着目し、両期間で価格上昇の背景が異なることを確認する。
感染拡大後の住宅市場における供給制約は、住宅着工件数と、その先行指標である住宅建設許可件数の「差」に表れている。許可件数と着工件数は、傾向として、若干のタイムラグをもってほぼ一致する関係にあるとされている148。この点を踏まえて、住宅バブル期と感染拡大後の両指標の水準を見比べると、住宅バブル期は、ピーク時(許可件数:年換算226万件(05年9月)、着工件数:同227万件(06年1月))を始め、許可件数と着工件数は若干のタイムラグをもってほぼ一致する傾向を示した(図2)。一方、感染拡大後は、当初から許可件数に対して着工件数が低調に推移し、特にピーク時(許可件数:年換算188万件(21年1月)、着工件数:同173万件(21年3月))には10%近い差が生じている。
許可件数に対する着工件数の不足は、許可取消や着工前キャンセルがない限りにおいて、住宅着工の遅れ(住宅の供給遅延)が生じていることを示す。そこで、許可取消や着工前キャンセルを除いた着工待ち住宅の件数(各月のストック)を確認すると、建設許可が着工に先行する関係上、両件数の増加局面であった住宅バブル期にも3年で約10万件の増加がみられたが、感染拡大後は1年で約10万件と、住宅バブル期を大幅に上回るペースで増加が進んでおり、供給遅延の程度が深刻であることが分かる(図3)。
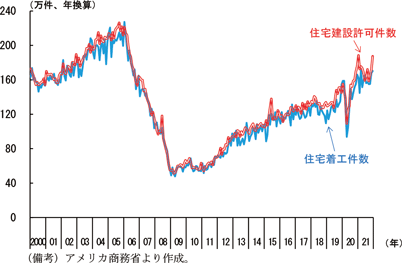
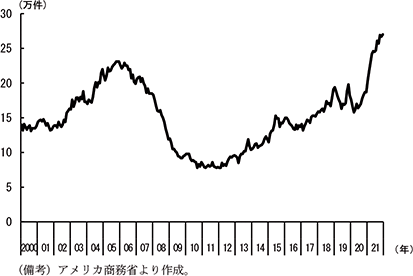
感染拡大後の住宅市場で、住宅の供給遅延が生じている要因の例としては、第一に、主要な建築資材である木材の不足、あるいはそれに伴う木材価格の高騰が考えられる。木材価格の動向を示すシカゴ・マーカンタイル取引所の木材先物価格(各月末の水準)をみると、感染拡大後ほどなくして上昇基調となり、21年4、5月には感染拡大前の3倍強(4月末:1,377ドル、5月末:1,310ドル)、21年末にも同2.8倍(1,143ドル)の水準を示すなど、感染拡大前を大きく上回る状況が続いている(図4)。住宅バブル期の最高値が441ドル(04年8月)、この時の上昇率(02年末比)が2.0倍であることを踏まえると、感染拡大後は、住宅バブル期と比べても大幅に、木材の調達が困難となっている可能性がうかがえる。
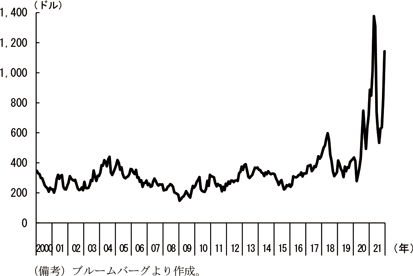
また、アメリカでは感染拡大後、労働市場のひっ迫が続き、広範な業種で人手不足が指摘されているところ、建設労働者の不足も、住宅の供給遅延要因となっている可能性がある。建設業の求人と採用の動向をみると、住宅バブル期を含む2000年代には、約30万件の幅をもって採用が求人を上回る構図となっていたが、21年はこの差がほとんどない状態で推移しており、月によっては求人が採用を上回る事態も生じている(図5)。10年頃以降19年初にかけて、求人・採用差は段階的に縮小してきた経緯があり、2000年代と21年の動向の違いには構造的な変化も含まれる可能性があるが、いずれにしても、これまで相対的に豊富な労働供給が維持されてきた建設業で、求人を充たすことができない事態が生じていることは、感染拡大後、建設労働者の確保がこれまでになく困難になっていることを示唆している。
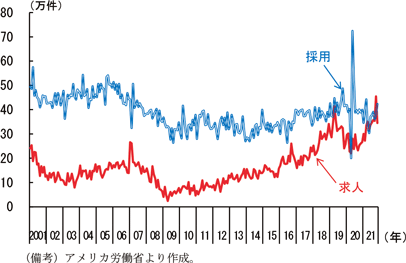
(2)家計の住宅ローンの借入状況等
以下では、住宅バブル期と感染拡大後を、家計の債務状況の観点から比較する。
まず、家計債務残高と、その内数である住宅ローン残高の動向を確認する。住宅バブル期は、家計債務全体、住宅ローンとも増加基調が続き、その結果、08年9月のいわゆる「リーマンショック」発生前には、いずれも2000年初比で2.5倍を上回る水準となった(図6)。また、各残高の可処分所得比をみても、それぞれ上昇基調が続き、このうち家計債務残高については、住宅バブル後半に100%を上回り、金融危機前には120%近くまで上昇した。これに対して、感染拡大後は、いずれも感染拡大前から続く傾向として、実額では家計債務全体、住宅ローンともに増加しているが、可処分所得比は金融危機を経て低下後の水準からおおむね横ばいとなっている。
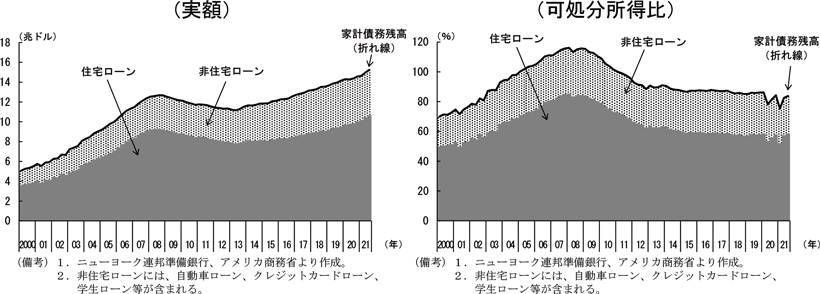
次に、金融機関等による四半期ごとの住宅ローン貸出額を借り手のクレジットスコア149別に確認する。住宅バブル期は、その後のリーマンショック前まで続く傾向として、660~719点、720~759点及び760点以上の3区分を中心に借り手のクレジットスコアが分散するとともに、信用力の低いサブプライム層(クレジットスコア620点未満の者)にもおおむね10%を上回る割合で貸出が行われていた(図7)。一方、感染拡大後は、貸出額はそれ以前から大幅に増加しているが、各期とも約7割がクレジットスコア760点以上の者への貸出となっており、サブプライム層への貸出割合は2%程度と、感染拡大前をも下回って2000年以降の最低水準となっている。
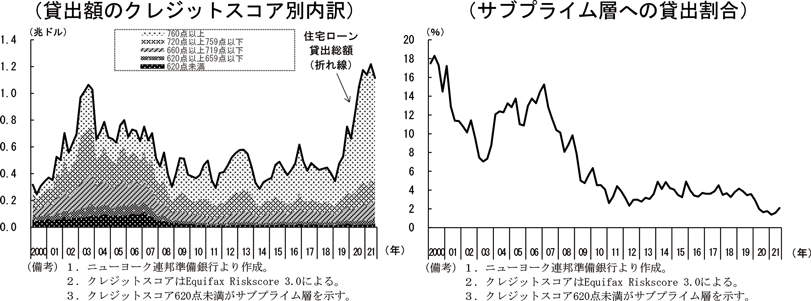
最後に、金融危機前に大幅な上昇がみられた住宅ローン延滞率(90日以上)150と住宅ローン対象住宅の差押え比率についても、住宅バブル期と感染拡大後の動向を確認する。住宅バブル期には、住宅ローン延滞率、差押え比率ともにおおむね横ばいで推移した。一方、感染拡大後は、いずれも2000年以降の最低水準で、延滞率は低下、差押え比率はゼロ近傍で横ばいの動きとなっている(図8、9)。
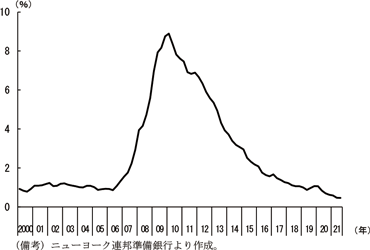

以上の各指標の動向をまとめると、次のとおりである。すなわち、住宅バブル期には、家計は住宅需要の増加を背景に可処分所得の増加を上回るペースで住宅ローンの借入を行い、かつ、その中には信用力の低いサブプライム層も一定程度含まれていた。その結果、住宅価格が下落に転じると、住宅ローンの返済に支障を来す者が現れ、住宅ローン延滞率や住宅ローン対象住宅の差押え比率が高まった。一方、感染拡大後は、同じく住宅需要が増加する中で住宅ローンの借入が活発化しているが、その増加ペースは可処分所得相応であり、家計債務全体でみても可処分所得で賄うことができる水準となっている。また、感染拡大後の住宅ローン貸出は、専ら信用力の高い者を対象に行われており、サブプライム層への貸出は実額、割合ともに低水準となっている。さらに、住宅ローン延滞率や住宅ローン対象住宅の差押え比率は、いずれも2000年以降で最低の水準で、横ばいないし低下傾向を維持している。
(3)考察と今後の見通し
感染拡大後の住宅価格の大幅な上昇は、住宅需要の増加と住宅供給の制約という、需給両面の動向に起因している。このため、今後供給面の制約が解消に向かえば、仮に旺盛な需要が続くとしても、需給バランスの調整により価格上昇が幾分緩和される可能性がある。また、住宅バブル期と異なり、サブプライム層への住宅ローン貸出が実額、割合とも極めて小さくなっていることなどを踏まえると、今後、住宅価格上昇の長期化により住宅需要が沈静化するなどして、住宅価格が下落に転じた場合でも、世界金融危機と同等以上の事態につながるような深刻な資金調達や信用不安が直ちに生じる可能性は低いとみられる。
2000年代の住宅バブル崩壊は、世界金融危機の遠因となったことのほかにも、3年以上にわたる住宅投資のマイナス成長をもたらし、世界金融危機に先立つアメリカ経済の後退の一要因となった。このため、足下の価格上昇の実体経済への影響については、引き続き留意する必要がある。いずれにしても、足下の住宅価格上昇を考える上では、単に価格上昇率が過去最高となったことのみならず、先述した住宅価格上昇の背景や、家計の債務状況にも目を向けることが重要である。
トピック2:アメリカの債務上限問題
アメリカでは、連邦政府の債務残高の上限が法律で規定されており、債務残高が法定上限に達すると、政府は各種施策や国債の元利払い等に係る国債の新規発行を行うことができず、債務不履行(デフォルト)のリスクが生じることとなる(いわゆる「債務上限問題」)。一方、法定上限は議会の立法プロセスを通じて引上げや適用の一時停止が可能となっており、これまで債務残高が法定上限に達した際にも、法定上限の引上げや適用停止が講じられてきた(図1)。
21年は、19年8月に成立した2019年超党派予算法に基づく法定上限の適用停止措置が7月31日に期限を迎え、翌8月1日以降、債務残高が法定上限に達した状態となることが決まっていた。しかし、7月末までに上限引上げや再度の適用停止は講じられず、8月以降も議会の対応は難航した。ここでは、21年の債務上限問題への議会の対応を概観するとともに、債務上限問題の構造的な課題を考察する。
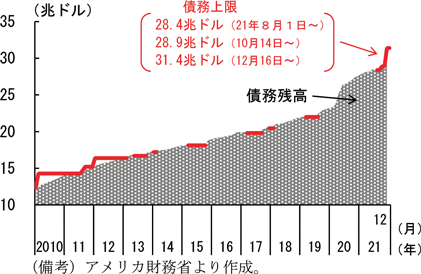
(1)当面の支出の確保(4,800億ドルの上限引上げ)
債務残高法定上限(以下「債務上限」という。)の適用再開が約1か月後に迫った6月23日、イエレン財務長官は議会証言で、財務省による「特別の措置」(extraordinary measures)151の実施可能性に言及しながらも、感染症下で資金に係る不確実性が存在することを踏まえ、「8月の夏季休会前の可能な限り早期」に債務上限の引上げ又は適用停止を決定するよう議会に求めた。しかし、与野党が党派を越えて対応に当たるべきとする与党・民主党と、与党単独で法案可決に取り組むべきとする野党・共和党の対立から、7月に入っても議会では目立った進展がみられない状況が続いた。7月下旬には、「特別の措置」を含めた財務省の資金繰りの限界を「10~11月」とする議会予算局(CBO)の推計結果が公表されたが、議会はなおも膠着状態が続き、8月1日、ついに議会の対応が講じられないまま債務上限(28.4兆ドル)の適用が再開された。
債務上限の適用再開後、財務省は「特別の措置」により資金繰りを行いながら、議会の進展を待った。9月に入り、イエレン財務長官から「10月中」にも財務省の資金が尽きるとの見込みが示されると、ついに議会も対応に向けて動き出したが、ここでも与野党の対立が尾を引いた。9月21日、下院で債務上限の適用を22年12月16日まで停止する法案が可決されたが、上院では与野党の調整が難航し、再び膠着状態となった。9月末、イエレン財務長官から「10月18日」、CBOから「10月末~11月初旬」と、財務省の資金が尽きる見通しが具体的に示された。ここにきてようやく、与野党は当面の危機を回避することについて合意し、債務上限を4,800億ドル引き上げる法案が、10月7日に上院、12日に下院でそれぞれ可決された(成立は14日)。これにより、財務省の資金が尽きるとされた日を目前にして、一旦デフォルトの危機は回避されることとなった。
(2)長期的な確実性の保証(2.5兆ドルの上限引上げ)
4,800億ドルの債務上限引上げは、あくまで当面の危機を回避するための方策であったところ、10月18日、イエレン財務長官は引上げ後の債務上限(28.9兆ドル)による財政運営の可能性を「12月3日」までとした上で、議会に対してより長期的な解決策を講じることを求めた。しかし、与野党の対立が続く中、11月にはイエレン財務長官の見通しが「12月15日」までに改められたこともあって、議会での進展は12月を待つこととなった。なお、CBOも同月末、財務省の資金繰りの可能性を「12月末」までとする推計結果を公表した。
12月に入ると、まず、与党単独で法案を可決するための準備が進められた152。そして、準備が整ったところで、債務上限を2.5兆ドル引き上げる法案が、12日に上院、14日に下院でそれぞれ可決された(成立は16日)。これにより、債務上限は31.4兆ドルに引き上げられ、23年頃までデフォルトの危機が回避される見通しとなった153。
(3)債務上限問題の構造的な課題
以下では、21年の一連の対応を踏まえ、債務上限問題の構造的な課題を考察する。21年の債務上限問題では、8月1日時点で債務残高が法定上限に達することが前もって明らかであったにもかかわらず、12月に2.5兆ドルの上限引上げが行われるまで、少なからずデフォルトのリスクが存在する状況が続いた。その背景には、歳出の国債依存や、歳出を遅らせることのできない義務的経費の存在、議会における与野党の対立など、様々な事情が介在するが、8月以降の歳出が予算として既に決定されているにもかかわらず、それに対応する債務残高水準が確保されていなかったことも、背景の1つとして指摘できる。換言すれば、21年度予算の決定時点で、21年度予算に係る国債発行に見合うだけの債務上限水準への引上げ等が実施されていれば、デフォルトのリスクを相応に軽減できた可能性がある。
債務上限の引上げと歳出・歳入の決定の結びつきを強化することの重要性については、その具体的な方策(現行制度の代替案)と合わせて、過去に会計検査院の議会報告書でも指摘されており154、21年にも、審議入りには至らなかったものの、財務長官に上限引上げの権限を付与する法案が議会に提出されるなど、現行制度の見直しを模索する動きがみられた。今後、債務残高が法定上限に接近する場合には、足下のリスクへの対応に加えて、こうした構造的な課題への対応が進展するか否かも注目される。
2.中国経済
中国では、財政・金融政策による景気下支えを図りつつ、いち早く新型コロナウイルス感染症の感染抑制に成功し、20年4月以降、経済活動の正常化が進んだ。これにより内需が持ち直すとともに世界的な需要回復を背景に輸出も増加し、21年夏までは景気は緩やかに回復した。しかし、世界的な供給制約に加え、夏から冬にかけて断続的に感染が再拡大し経済活動の制限措置が強化されたことや、8月以降の政府の環境規制の強化や石炭等の原材料価格の上昇による電力供給不足の深刻化に伴う生産の下押し、さらに累次の不動産市場の過熱抑制策の強化を背景とした不動産開発市場の冷え込み等を背景に、夏頃から景気回復のテンポが鈍化した。
21年の実質経済成長率をみると、1~3月期には前年比18.3%増と前年同期の反動もあり伸びが大幅に高まり、4~6月期も堅調に推移した(第2-2-10図)。しかし、7~9月期は、世界的な需要回復等の下での原材料価格の上昇や半導体、部品の供給不足に加え、電力供給不足や不動産過熱の抑制策等を背景に、前年比4.9%増と減速し、10~12月期には、同4.0%増となった。なお、21年通年では、前年比8.1%増となり、21年の政府目標(6%以上)を達成したものの、四半期でみると減速が進んだ。需要項目別にみると、4~6月期までは、最終消費が景気回復をけん引し、資本形成、純輸出もプラス寄与となった。しかし、7~9月期は、投資が伸び悩む中で、資本形成の寄与が20年1~3月期以来、初めてマイナスに転じた。こうした投資の弱さは、原材料価格の高騰や不動産市場の過熱抑制策等により建設業や不動産業がマイナスに落ち込んだことを反映している(第2-2-11図)。なお、21年7~9月期の産業別の成長率は、感染再拡大の影響を受け宿泊・飲食も他の産業と比較して大きく落ち込んだ。
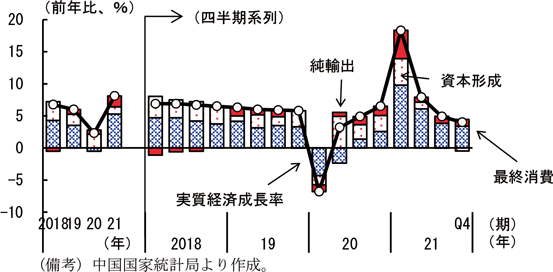
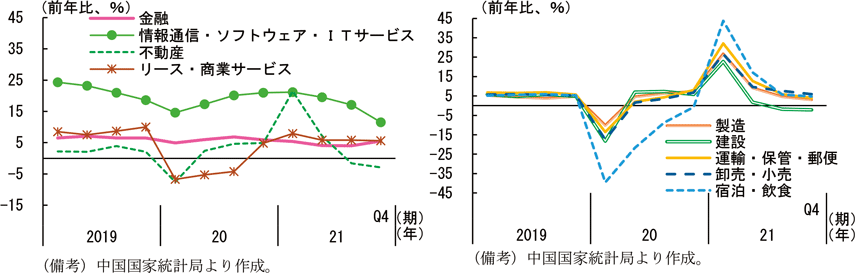
(1)個人消費
(個人消費は伸びが低下)
個人消費の動向をみると、小売総額(名目値)は、前年の消費の落ち込みを反映して、21年1~2月期は前年比33.8%増と大幅に伸びが高まったが、その後は徐々に伸びが低下し、21年後半は3~4%前後の伸びで推移している(第2-2-12図)。内訳をみると、20年に全体を下押ししていた飲食サービスは21年に入っても回復を続けたが、8月の感染再拡大以降は、区域をまたぐ移動の制限等の措置の影響により、全体を下回る伸びで推移している。商品小売総額の品目別では、自動車は政策効果もあり20年半ば以降は持ち直しをけん引していたが、21年半ば以降は世界的な半導体不足等に伴って伸びが低下し、マイナス圏で推移している(第2-2-13図)。
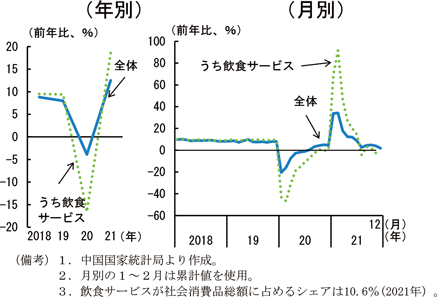
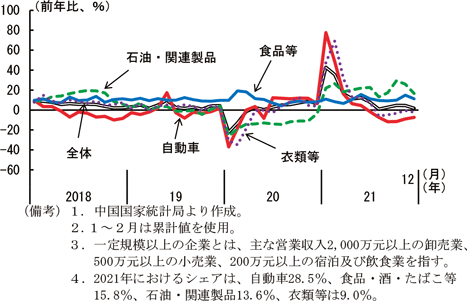
感染流行による消費の落ち込みを受け、政府は、20年2月以降、複数の消費促進策を打ち出している。21年についてみると、1月5日に商務部等は農村の消費促進策155を発表し、自動車・家電・家具の購入又は買換えや飲食消費等を促進する方針を示した。また、9月16日には、新車及び中古車、家電・家具、飲食や新型消費156の促進、消費プラットフォームの改善等14の重点措置を発表した157。
(雇用環境は改善しているものの、所得の伸びはやや鈍化)
雇用環境をみると、都市部調査失業率158は、21年第1四半期は感染再流行の影響等によりやや上昇したが、4月以降は19年末を下回る水準で推移している159(第2-2-14図)。また、都市部の累計新規就業者数の純増分を示す都市部新規就業者数160は、21年に入ってからは前年比で伸びが低下したものの、10月には21年5月の全人代の目標である1,100万人以上に達している。次に、所得環境をみると、一人当たり可処分所得(実質)は、年初来累計値で、21年1~3月期に前年比13.7%増と前年の反動もあり高い伸びとなっており、その後も伸びが低下しつつも高い水準となっている161(第2-2-15図)。

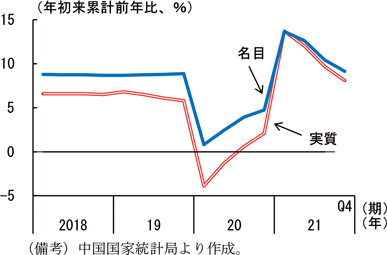
(2)輸出入
(輸出は増加)
中国の財輸出額162は、20年6月に増加に転じてからは伸びが高まり、21年以降伸びは低下傾向にあるものの、2桁台の伸びで堅調に推移している(第2-2-16図)。ただし、商務部は、輸送コストの高騰、原材料価格等の上昇、人民元の高止まり、労働コストの上昇に留意する必要があると指摘している。財輸入額は、20年9月以降増加が続いており、特に21年に入ってからは国際商品価格の上昇163もあり、2桁台の高い伸びを維持している。
財輸出の主要品目をみると、21年にかけて、特に電気機器、一般機械、家具類の寄与が高まった一方、紡績用繊維製品は5月以降マイナスとなっている(第2-2-17図)。個別の品目では、リモートワーク等の増加を背景に、自動データ処理機械・ユニット(パソコン等)がプラスで推移し、集積回路は20年11月以降20~30%台の高い伸びを維持している。また、防疫物資(マスク、防護服等)が含まれる織物が前年比で21年4月以降、マイナスで推移していたが、感染再拡大を背景に10月以降はプラスを維持している。
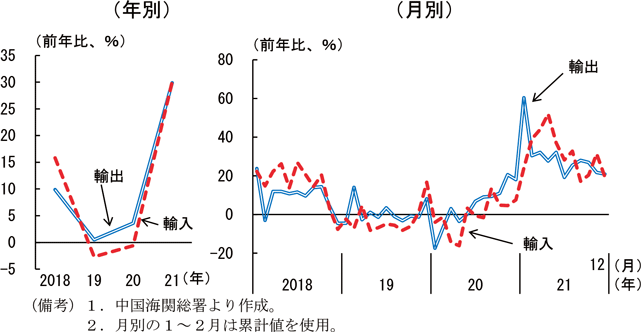
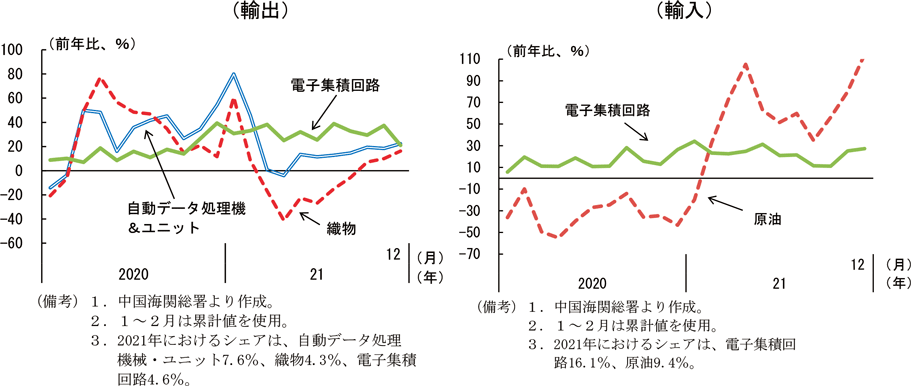
財輸入の主要品目をみると、21年に入ってからはいずれもプラス寄与が続き、特に電気機器や鉱物性製品の寄与が高い。個別の品目をみると、電気機器の中で最大の輸入品目である電子集積回路は、20年に引き続き2桁台の高い伸びで推移している(第2-2-17図)。また、国際原油価格が上昇する中、鉱物性製品の中で第2位の輸入品目である原油は、3月に前年比でプラスに転じて以降、2桁台の高い伸びで推移している164。
(3)生産
(生産は伸びがおおむね横ばい)
鉱工業生産は、20年11月以降は前年比7%台以上で推移し、19年12月(同6.9%増)を上回る伸びとなった(第2-2-18図)。21年は年初以降伸び率が低下し続け、9月は前年比3.1%増と20年1~2月以来最も低い伸びとなり、その後は3%台で推移している。
内訳をみると鉱業は、3月以降、前年比で3%台かそれを下回る低い伸びとなっており、全体を下押ししている。製造業も21年を通して伸びが低下し続けており、9月は広東省等複数の地域において電力供給制限が強化され一部工場が稼働停止や減産をした影響165もあり、前年比2.4%増と20年通年の伸び(同2.8%増)も下回った。
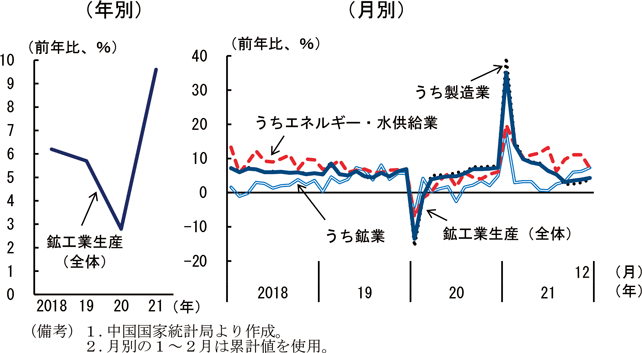
製造業の主要業種の生産をみると、コンピュータ・通信その他電子機器は、パソコン等の情報関連財の輸出増加等により、20年に引き続き前年比10%増程度の伸びを維持しており、電気機械は、巣籠り消費を背景とした家電の輸出増加もあり、おおむね2桁台の伸びとなっている(第2-2-19図)。このほか、医薬品も、国内外の防疫製品に対する旺盛な需要を受けた企業の生産拡大等を背景に、20年を大きく上回る高い伸びが続いている。他方、鉄金属加工業(鉄鋼等)は国内の生産抑制策166や高エネルギー消費産業への規制策167等を背景に伸びが低下し、下半期はマイナスで推移している。また、自動車は半導体不足168等が足かせとなり、6月に前年比で減少に転じて以降、マイナスで推移していたが、12月にプラスに転じた。
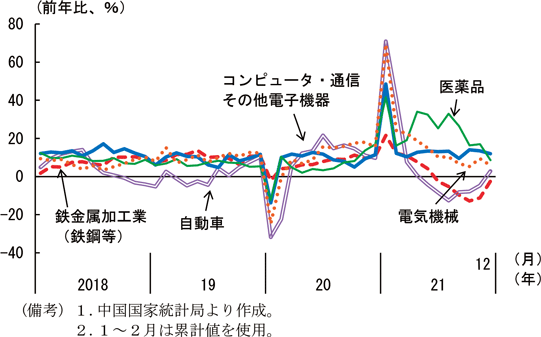
(4)固定資産投資
(固定資産投資は伸びが低下)
固定資産投資は、20年にいち早く持ち直しの動きがみられていたものの、21年7月以降伸びが低下し、12月は年初来累計で前年比4.9%増となっている(第2-2-20図)。主要業種別にみると、製造業投資は持ち直しの動きを続けているものの、20年に回復が早かった不動産投資、インフラ投資の伸びがやや低下している。
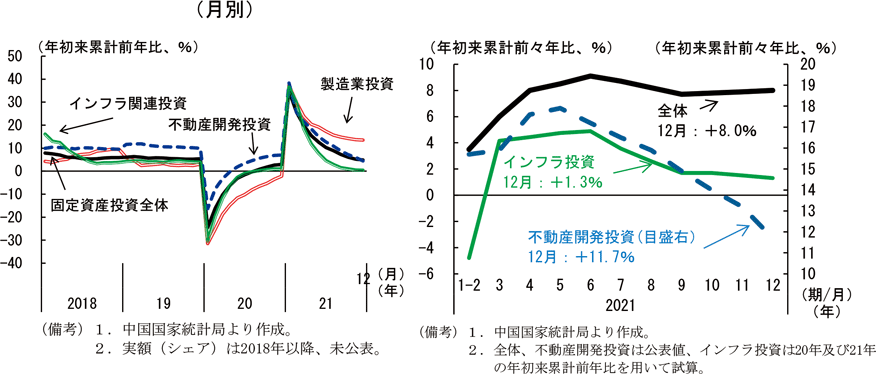
製造業投資は、感染症の影響により、20年はマイナス成長にとどまったものの、21年は持ち直しの動きが続いている。背景には、パソコン等への需要の増加に加え、20年に政府が「新型インフラ」169投資の加速等、同分野の振興に関連する政策方針や施策を示し170、21年に入っても同様の政策を推進していることがあると考えられる171。
インフラ投資は、21年は伸びが低下している。背景の1つとして地方特別債の発行が遅れたことがあるとみられる。20年は8月時点で既に全人代で設定された発行枠の95%に達したが、21年同月は50%にとどまった(第2-2-21図)。なお、政府は、7月30日の共産党中央政治局会議において地方債の発行ペース加速を年後半の経済運営方針として打ち出したほか、財政部も10月22日、21年の発行枠をできる限り11月末までに実施完了する方針を示した172。そのため、年後半にかけて発行は加速したものの、前年の水準にほぼ達したのは11月となり、インフラ投資の下支え効果の発現は遅れた。
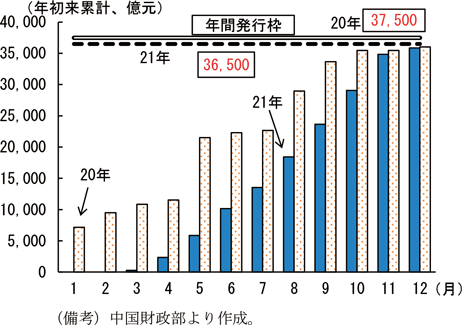
不動産開発投資は、21年1~12月には前年比4.4%増まで伸びが低下するなど増勢が鈍化している。関連指標として不動産販売面積をみると、7月にマイナスに転じ、12月には15.6%減となっている(第2-2-22図)。また、不動産販売価格については、前月比は21年に入りおおむね上昇基調で推移していたものの、1~3級都市でそれぞれ6月以降低下傾向となり、10月には2、3級都市でマイナスとなり11月に1級都市も前月比でマイナスに転じた。(第2-2-23図)。

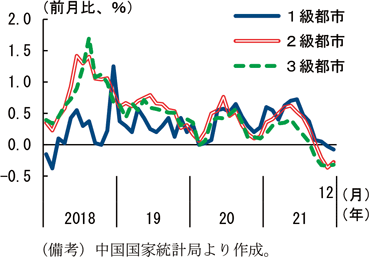
このような不動産開発投資の伸びの鈍化の背景には、20年半ば以降の政府による不動産市況過熱に対する抑制策がある。具体的には、まず、不動産企業に対し、20年8月20日に、住宅・都市農村建設部及び中国人民銀行が、主要不動産企業の資金監督、資金調達管理ルールの草案を示した。これは、不動産企業に対し、(1)資産負債比率70%超、(2)ネット負債比率100%超、(3)現預金対短期負債比率が1以下、の3つの基準(三条紅線)を設けるものである。上記基準に応じ借入規制(有利子負債の発行制限)が適用され、例えば、3つのレッドラインに全てに該当する企業は有利子負債を前年比で増加できなくなる。また、12月の中央経済工作会議では、21年の重点任務の1つに大都市の住宅問題の解決を挙げ、「住宅は住むためのものであり、投機のためのものではない」とし、不動産市場の過熱抑制策を進めていくこととした。その上で、銀行に対し、同月31日に中国人民銀行及び中国銀行保険監督管理委員会(銀保監会)は、21年1月から銀行の不動産融資比率に上限を設けることを発表した173。さらに、事業者に対し、21年3月に人民銀行、銀保監会等が共同で、事業性貸出の不動産市場への流入を抑制する通達を公布した。通達では、事業性貸出の期間や資金使途に対する審査や、事業性貸出の抵当物件の管理を強化するとしているほか、事業性貸出に対するモニタリングを厳格化し、投機資金流入を阻止する短期的な引締め措置を実施するなどとしている174。このほか、10月23日には一部の地域で5年間、土地使用権者及び建物所有者を対象とする不動産税を導入する方針が示された175。
こうした累次の規制や政策等を背景とし、21年には、恒大集団176を始めとする一部不動産企業の経営状況の悪化が浮き彫りとなった。関連産業への波及も懸念されており、今後の不動産市場・投資の低迷による経済への下押しに留意する必要がある。
なお、20年半ば以降、不動産市場の過熱抑制策が相次いで採られたことを背景に、21年初から金融機関の不動産貸出残高の伸びは不動産開発向けを中心に鈍化している(第2-2-24図)。
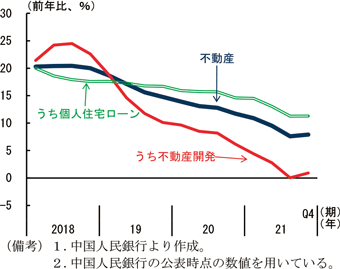
(5)物価
(消費者物価上昇率はおおむね横ばい)
21年の消費者物価上昇率(総合)をみると、3月から5月にかけてやや高まった後、緩やかな低下傾向となった。その後、10月から11月にかけて、豪雨や輸送コスト上昇の影響、年末に向けた消費需要の増加等で食品価格が上昇したことなどを背景に高まったが、12月には落ち着き、全体でみればおおむね横ばいで推移している(第2-2-25図)。なお、21年通年では、前年比0.9%増となり、全人代で設定された+3.0%前後の目標を下回った。こうした変動の背景をみると、食品価格の低下の影響がある。食品価格は、年後半はマイナス幅が拡大し、10月は前年比2.4%減となっている177。特に豚肉価格は9月には前年比46.9%減まで大きく落ち込んだ。これを受けて、政府は備蓄用豚肉の買入れを実施するなど供給・価格安定を図った178。他方で、食品以外は年初から上昇傾向にあり、特に交通・通信については、国際的な原油価格の上昇を背景に、自動車燃料価格は3月以来2桁増が続いている(第2-2-26図)。
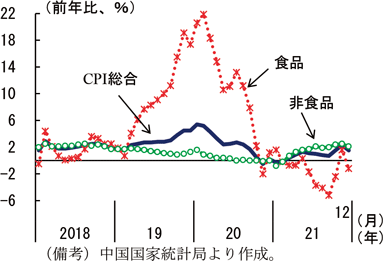
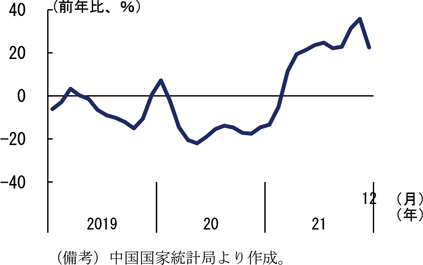
生産者物価上昇率は、年間を通して上昇傾向が続き、9月以降前年比2桁増の伸びを記録した(第2-2-27図)。これに対し、政府は、21年5月に、鋼材、アルミ等の業界団体等に対し、価格つり上げ行為等を防止するよう行政指導を実施するとともに、6~10月に銅、アルミニウム、亜鉛の備蓄放出を複数回実施して価格抑制を図っている179。財別にみると、国内の生産の回復や世界的な生産活動の再開の動き等を背景とした原材料価格上昇や、政府の高エネルギー消費産業への規制策の強化もあいまって、採掘財や原材料財を中心に大幅な上昇が続いたが、11月以降は低下し、頭打ちとなった180。
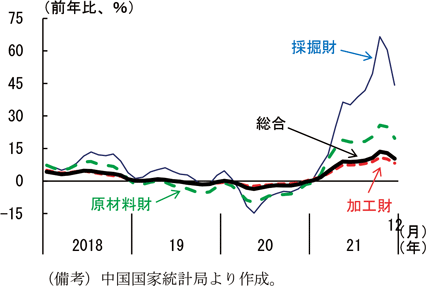
トピック3:中国における低炭素社会実現に向けた環境規制と新エネ自動車産業の発展の動向
中国政府は、このところ環境規制への取組を強化している。そこで、本トピックでは近時の環境規制の動向を概観しつつ、規制対象となっている石炭を中心とするエネルギー構造の現状をみていく。そして、低炭素社会実現に向けたグリーン経済の発展戦略として近年重視されている産業の1つである新エネルギー車産業の発展動向について整理する。
(1)環境規制の動向(両高対象業種への規制)と生産への影響
まず、最近の政策動向として、環境規制の基本的な枠組みについて、概観する。
21年3月の十四次五か年計画では、低炭素社会実現に向けた2つの定量的目標に言及している。1つ目は、「2030年のカーボンピークアウト」であり、これを着実に進めるための行動方針181を10月に制定した。2つ目は、「2060年のカーボンニュートラル」である。
十四次五か年計画では、これら二つの目標達成に向けた具体策として、エネルギーの「消費総量」とエネルギー使用効率を示す「消費強度」182のダブルコントロール(双控)という枠組みを設定している。前者については、化石エネルギーの消費抑制の重点化、特に石炭に対するコントロールを中心に関連施策を進めるほか、後者については、クリーンエネルギーと低炭素の安全かつ高効率な利用を推進し、工業、建設、交通等の分野で低炭素への転換を深化していくこととされている。また、数値目標としては、単位GDP当たりのエネルギー消費量及び二酸化炭素排出量を21年からの5年間でそれぞれ13.5%、18%削減する拘束性目標(必ず達成が求められる義務的目標)を設定し、低炭素社会への転換を強力に推進しようとしている。
21年12月、翌年の経済運営の基本方針を議論する中央経済工作会議において、カーボンピークアウト・カーボンニュートラルに向けた取組を強化する姿勢を改めて打ち出した。その上で、今後、「エネルギー消費全体」に対するダブルコントロールから「炭素」に対象を限定した排出総量と強度のダブルコントロールにできる限り早期に移行する旨が示された。ここで、再生可能エネルギーと原料用エネルギーについては、エネルギー消費総量規制に算入しない形に方針変更されたことに留意する必要がある。当該方針変更は、21年8月以降に電力供給不足の問題が発生したことなどを背景にキャンペーン式の一律の炭素削減運動が問題視された結果である旨の指摘がある。このように、政策の大きな方向性としては、カーボンピークアウトとカーボンニュートラル目標は維持しつつ、現実的な施策の推進が可能となるよう、対象範囲等について、若干の緩和もみられている。
次に、環境規制が具体的にどのような形で実施されたのか、それがどのように生産活動に影響を与えてきたのか、みていく。十四次五か年計画の数値目標を達成するため、21年8月12日に国家発展改革委員会は、21年上半期のエネルギーの「消費強度」と「消費総量」のダブルコントロールの達成状況を地方政府に通知した。本通知に基づき、21年上半期にエネルギー消費強度が上昇した地域は警告等級1級該当地域に分類され、年内の両高(高エネルギー消費・高汚染物質排出)プロジェクトの許認可審査が一時停止されることが発表された(表1)。
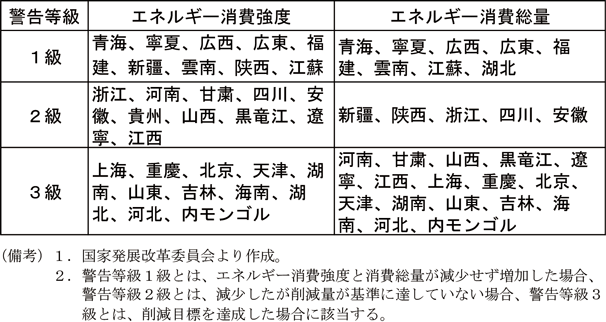
更に、9月16日に国家発展改革委員会は、各地域のエネルギー消費強度と総量の年間目標の策定と案の報告、両高プロジェクトの省エネ審査の管理制御の徹底、要求水準に適合しない両高プロジェクトに対する金融機関からの融資制限等を通知した。その後、例えば広東省では、9月24日に「両高プロジェクトの過度な発展の徹底的抑制のための実施方案」が通知され、その中では両高産業として石炭火力発電、石油化学、化学工業、鉄鋼、鉄金属、建材等の8業種が指定された。10月24日には国務院が、鉄鋼、建材(セメント、板ガラス)、非鉄金属(電解アルミニウム)等の生産能力の等量又は減量と、石炭火力発電、石油化学・石炭化学工業等の生産能力コントロールによる両高プロジェクトの過度な発展の断固停止等を内容とする意見を発表し、カーボンピークアウトとカーボンニュートラル目標実現に向けた取組を加速させている。なお、当該意見は、経済社会発展の中長期計画の中にカーボンピークアウトとカーボンニュートラル目標を位置付けることを明らかにし、経済発展とグリーン・低炭素との関係性を強めている。
このほか、10月28日に生態環境部ほか関係各部と関係省政府が連名で、地方政府及びエネルギー関連企業に対し、21~22年秋冬期の大気汚染に関する総合対策を通知した183。本対策では、21年10月から22年3月までの間、北京市、天津市、河北省、山西省、河南省等の65市を対象とし、PM2.5濃度や重度の大気汚染発生日数を16年同期比で低下させる数値目標が設定されている。対策の内容は、両高プロジェクトの過度の発展の抑制、鉄鋼業界の減産の実現、小規模な石炭燃焼ボイラーの淘汰、ディーゼルトラックの淘汰の加速等であり、進捗が思わしくない都市に対しては生態環境部が警告通知を発出し、政府の責任者を公開指導する旨が記されており、政府の強い決意がうかがえる。
このような環境規制は、両高産業の生産活動に実際に影響を与えていることが指標から読み取れる。高エネルギー消費・高汚染排出産業の生産動向をみると、両高規制が強化された21年夏以降、生産の伸びが顕著に低下している。業種別では特に鉄金属加工及び非鉄金属といった業種で伸びがマイナスになっている(図2)。生産品別にみても、粗鋼、鋼材、アルミ、セメント、板ガラスの生産量が前年比でマイナスに落ち込んでおり、政府の環境規制による影響がうかがえる(図3)。22年2~3月の北京冬季オリンピック・パラリンピックを控え、環境規制は当面強化されることが予想されるため、特に両高関連産業の生産動向については引き続き注視が必要である。なお、JETROの調査によれば、中国進出日系企業360社のうち直近1年間で環境保護に関し政府から指導を受けた企業は44.2%(159社)となっており、日系企業にも影響を与えていることが分かる184。
以上の環境規制の主な対象はエネルギーや炭素の消費であることを踏まえ、続いて、中国の石炭消費を始めとする現時点のエネルギー消費構造についてみることとする。
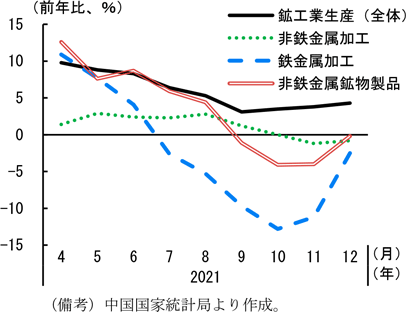
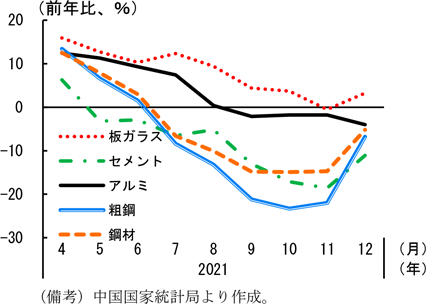
(2)エネルギー消費、電力の動向
エネルギー消費量について、エネルギー構成比率を概観すると、石炭は低下しているものの、20年でも依然として全体の約6割(56.8%)と高い割合を占めている(図4)。
石炭消費の主要分野は、電力生産用と産業用である。まず、電力生産について、電源別生産量をみると、石炭を多く消費する火力発電の割合は、低下傾向にあるものの20年で約7割(69.6%)と高水準で推移している(図5)。火力発電割合の低下に伴い、風力、原子力発電、太陽光発電の割合が増加傾向となっており、クリーンエネルギーの推進が徐々に進んでいる状況が見受けられる。次に、産業用については、石炭・コークス消費量の多いものとして、最多の電力・熱生産供給業(約2,018万トン)を別とすれば、鉄金属加工業や化学原料・製品業等で消費量が多くなっている(図6)。このため、これらの業種の石炭消費を減らすことが、十四次五か年計画の目標実現にあたり鍵となると考えられる。
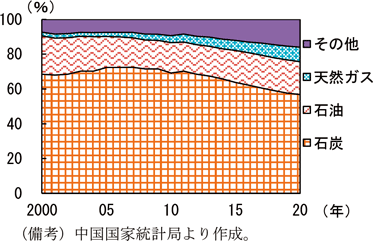
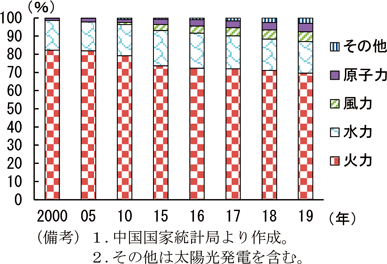
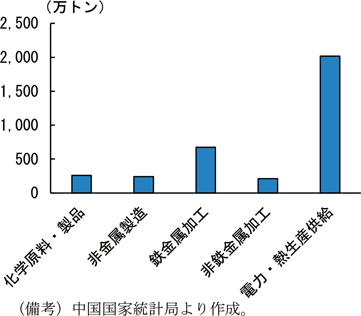
(3)新エネルギー車産業の発展と普及促進
中国政府は、高エネルギー消費や高炭素排出の現状を転換し、低炭素化を図るためには、交通分野、中でも都市公共交通や物流車両を始めとする車両の電動化の推進が重要であり、グリーン経済の発展にも貢献するものと位置付けている。このため、最後に、新エネルギー車産業の動向について、取り上げる。新エネルギー車は、電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド車(PHV)、燃料電池自動車(FCV)を指す。20年11月2日に、国務院が「新エネルギー自動車産業発展計画(21~35年)」185を発表し、25年までに新車販売台数に占める新エネルギー車の割合を20%前後に引き上げる目標を示した。また、35年までに新車販売の主流を電気自動車とし、公共分野で使用する車を全面的に電動化し、省エネ・排出削減水準の向上を促進するとしている。21年10月の国務院通知(前掲)でも、新エネルギー車産業の発展加速が言及されており、今後もグリーン成長に向け新エネルギー車産業の発展を推進するとみられる。
新エネルギー車の販売台数をみると、19年7月以降は、購入時の補助金が大きく削減された影響もあり、前年比で減少が続いていたが、20年7月に後述の販売支援策を背景に、増加に転じ、2~3桁台の伸びで推移している(図7)。21年の新エネルギー車のシェアは13.4%と前年から大幅に拡大しており、今後も増加傾向が続くことが見込まれる。
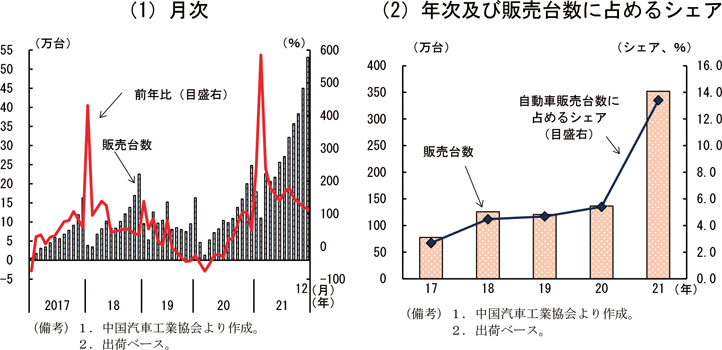
メーカー別の動向では、中国国内での新エネルギー車の販売台数は車載電池メーカーでもあるBYDが最大手となっており、その後に上汽GM五菱、テスラ等が続いている(図8)。また、近年設立された上海蔚来汽車NIO(ニオ)や小鵬汽車(Xpeng)等、新興メーカーも販売形態や開発で差別化を図ることにより販売台数を伸ばしている。
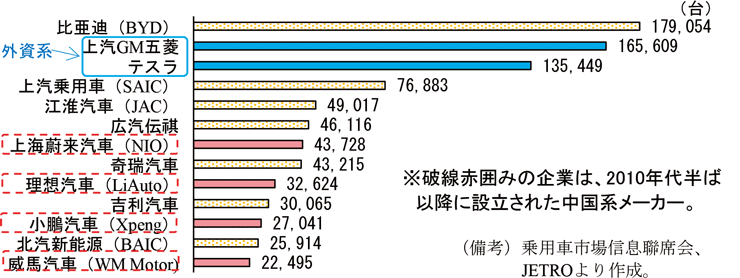
これまで新エネルギー車の普及のため、複数の施策が打ち出されてきたが、農村部においては、20年後半に実施されていた「新エネルギー車の農村への普及活動」に続き、21年は「新エネルギー車下郷」が実施されている。具体的には、販売に係る経費の支援や農村部での充電インフラの整備等が盛り込まれており、20年と比較して対象地域や対象企業が増えている。
新エネルギー車の購入に対する補助金は、一部メーカーに補助金への依存がみられることなどから、産業育成強化のため、20年で廃止する方針が打ち出されていたが、19年の販売台数が前年割れとなり、感染拡大により市場が下押しされる中、消費促進等のため車両購入税免除とともに22年まで延長された。ただし、21年は補助金を前年比で2割抑制するとしている。このほか、中国政府は、19年より各自動車メーカーに一定比率の新エネルギー車の生産又は輸入・販売を義務付ける制度を導入するなどして、新エネルギー車の普及を促進している。
以上を振り返ると、中国政府による脱炭素社会の実現に向けた政策は、当面の景気動向においては一部の業種などで生産の下押しにつながっていく可能性がある。他方、新エネルギー車の推進策は、中長期的には中国企業によるイノベーションの活発化を促し、グリーン経済の発展戦略の1つとしても中国経済の成長力強化につながる可能性がある。今後の脱炭素社会に向けた取組には多様なものがあるが、中国の経済成長に中期的にどのような影響を及ぼすか、注視していくことが求められる。
3.ヨーロッパ経済
ヨーロッパ経済は、21年初めより実施した感染拡大防止措置により経済活動が停滞した後、ワクチン接種の進展に伴う経済活動の再開により持ち直してきている。ここでは、21年1月以降のユーロ圏及び英国の経済の動向に焦点を当ててみていく。個別分野としては、景気回復を主導した個人消費、感染拡大(または活動制限)の影響を受けやすいサービス業事業者の景況感(PMI)に加え、今回の持ち直し局面の特徴の一つである世界的な供給制約に直面している生産、改善傾向が顕著な雇用、エネルギー価格高騰や供給制約等により押し上げられた物価について概観する。
欧州主要国及び英国では、21年春先以降、小売店・飲食店等の営業規制緩和や移動制限の解除等(第2-2-28図)を進めてきた。これに加えワクチン接種が進展したこともあり、第2四半期より個人消費が主導する形で経済が回復してきている(第2-2-29図、第2-2-30図)。
11月末以降は、オミクロン株を中心とした感染の再拡大による影響が懸念されている。多くの国ではワクチン未接種者を対象とした行動規制にとどまっており、22年1月半ば時点で、欧州の需要全体を大きく押し下げる動きはみられていない。
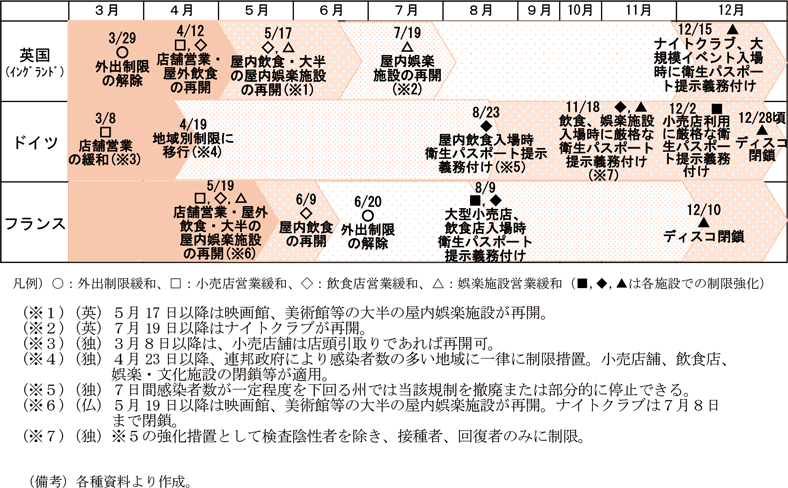
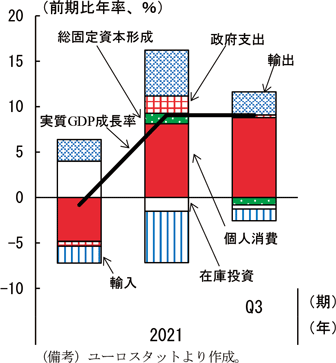
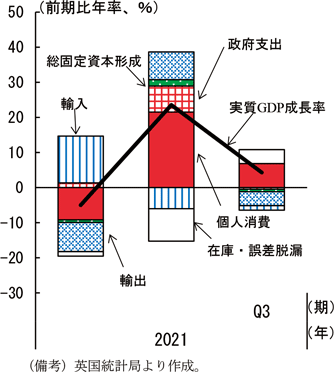
(1)個人消費
(個人消費は持ち直しているが、一服感)
夏以降の消費の回復のテンポを実質小売売上高(第2-2-31図)でみると、感染拡大が断続的に起こる中で、制限緩和等を反映し4~6月期に持ち直しの動きをみせた。7~9月期には、ワクチン接種の進展の下、欧州主要国では店舗利用時にワクチン接種証明書の提示を求める規制が導入され、その下で店舗営業の継続が可能であったことから、夏季消費の下支えとなった。この一方で、後述の供給制約による商品不足等186もあり、夏以降は一服感がみられている。
なお目的別187に消費をみると(第2-2-32図)、必需品である「食料品・光熱費」が21年初頭でコロナ前水準に回復した後、相対的に非日常消費とみられる「外食・宿泊・旅行・航空」が続く形で夏場に向け挽回需要により拡大したものの、その後は足踏みとなっている。「衣料品・車」のうち車については、世界的な半導体不足に起因する生産制約により消費が下押しされたものとみられる。
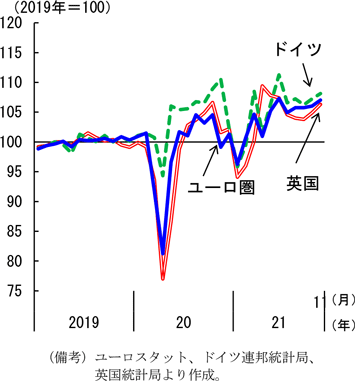
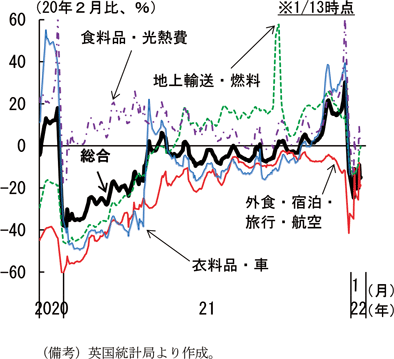
(2)サービス業景況感
(サービス業景況感は持ち直しのテンポが鈍化)
営業規制等活動制限の影響の大きかったサービス業について景況感(PMI)(第2-2-33図)から振り返ってみる。英国では、飲食業や主たる娯楽施設の営業が再開された5月に向けて、ユーロ圏に先行して景況感の改善幅が拡大していた。ただし、そのテンポは夏以降鈍化しており、要因として人員不足やサプライチェーンの混乱に起因するもののほか、印紙税控除額引上げ特例措置188の終了に伴う住宅不動産取引の縮小、EU離脱による貿易摩擦やインバウンド観光客の減少による影響等が報告されている。10月にやや改善しているが、これは同月に実施された入国制限の緩和により観光業等の需要の押上げが反映されたものとみられる。
ユーロ圏については、挽回需要を反映し夏季に拡大した後、供給制約がより深刻なドイツを中心に鈍化がみられる。ただし圏内でも濃淡があり、12月においてドイツでは感染拡大も重なり飲食・宿泊業を中心に低調であった一方で、フランスにおいては観光業にけん引されサービス業が堅調であった。
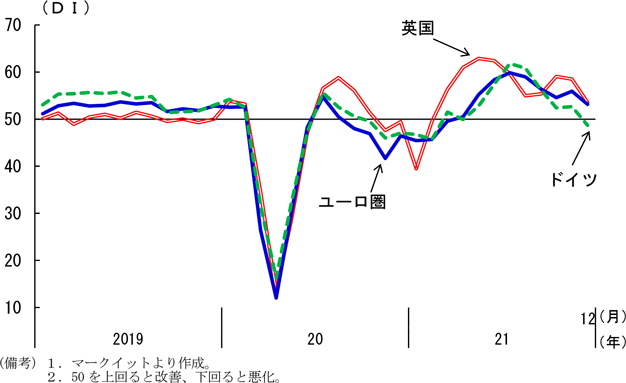
(3)生産
(生産は持ち直しの後、横ばい)
次に、世界的に原材料等の供給制約に直面している生産の動向についてみてみよう(第2-2-34図)。ユーロ圏、英国ともに個人消費に先行し20年第4四半期より資本財を中心として持ち直しの動きがみられた。その後は世界的な需要の急回復を受けた原材料・部品不足による供給制約を反映し、横ばいとなっている。第2-2-35図は、ユーロ圏の製造業企業に生産活動の制限となる主要因189を質問し、そのうち「材料・機器不足」を挙げた企業の割合を示したものであるが、21年に入ってから急激に上昇している。ドイツの製造業はユーロ圏全体の約4割を占めるが、同セクターにおいて供給不足がより大きな制約要因となっていることがみてとれる。英国においても、企業における原材料等の調達状況調査(第2-2-36図)の中で、製造業の約2割が「調達不可」もしくは「供給元変更又は代替策」と回答(21年秋時点)するなど、同様に供給制約に直面している。
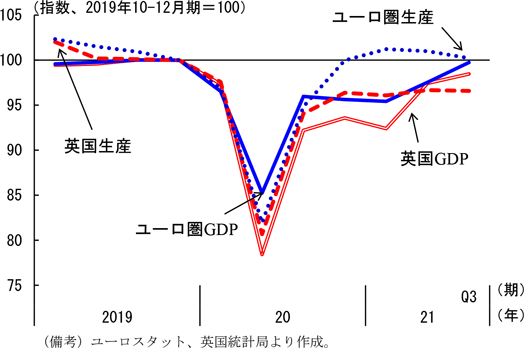
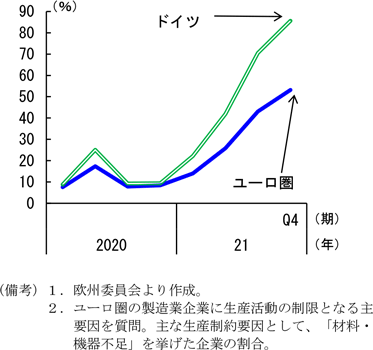
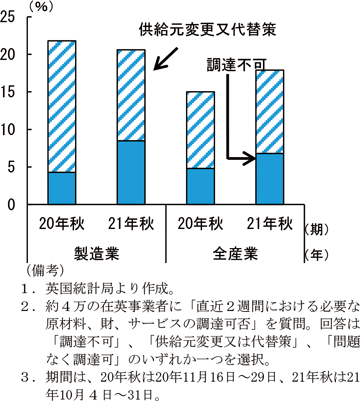
供給制約としては原材料、部品以外にも人員不足が指摘されている。英国においては、飲食・宿泊サービス等の対人サービスで、需要の回復を背景として夏頃には未充足の求人が増加しており、とりわけトラック(重量物運搬車(HGV))運転手の不足が問題視されている。ONSによれば、20年7月からの1年間に雇用されたHGV運転手は26万8千人と推計しており、これはコロナ前190の水準を5万2千人下回っている。他方で需要側をみると、HGV運転手の主たる就業先である運輸・倉庫業においては、経済活動再開に伴い求人を増加させており、21年7~9月期時点ではコロナ前を大きく上回る水準(5万2千人、前期比56%増、20年1~3月期対比49%増)に達している。
このようなロジスティクスにおける需給ひっ迫が供給制約をより深刻化させているものとみられ、また第2-2-37図をみると、輸出における制約要因ともなっている191。

(4)雇用
(雇用情勢は改善)
雇用情勢については、ユーロ圏、英国ともに全体として改善してきており192、失業率(第2-2-38図)をみると、ユーロ圏についてはコロナ前の水準まで回復している。リーマンショックでは、ユーロ圏の失業率が発生(08年9月)前の水準に回復するまでに10年以上要したことを踏まえれば、今般の雇用情勢の回復の早さは非常に顕著であるといえる。
他方で、BOEは、雇用維持スキーム193の利用率が、同制度が終了する21年9月末時点でも4.5%と高い水準にあり、さらに、これらの一時帰休者の多くが別の雇用主の下で副業を行い、また同制度で認められている既存の副業の範囲を拡大していた可能性があったとして、これらが今後の失業率の推移に対して押上げ要因となる可能性を示唆している194。
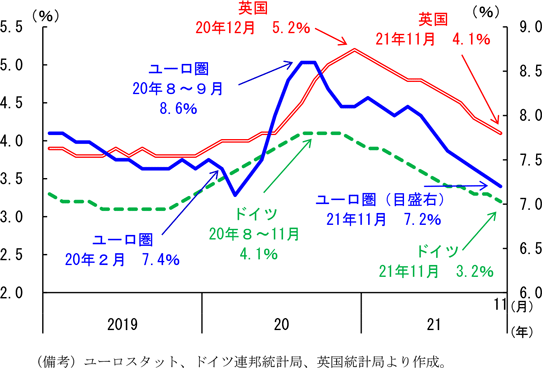
(5)物価
(物価上昇率は上昇)
消費者物価の動向(第2-2-39図)をみると、ユーロ圏、英国ともに物価上昇率が上昇傾向にある。両経済ともエネルギー価格の高騰が主たる押上げ要因となっており(特にユーロ圏において顕著だが、後述のコラムで扱う)、これに加えて前述の供給制約による影響が指摘されている。また20年には付加価値税(VAT)引下げ等の各種コロナ対策が実施され、その施行期間終了に伴う物価上昇率の押上げ効果(ベース効果195)も指摘されている。

トピック4:欧州におけるエネルギー価格上昇の背景
ユーロ圏では、21年初から消費者物価(以下「HICP」という。)が上昇を続けており、その背景として、(i)経済活動再開に伴う需要回復と供給制約、(ii)エネルギー価格の上昇、(iii)前年からの反動(ベース効果)等の要因が指摘196されている。物価上昇の要因を確認するため、HICPを寄与度分解してみると、夏以降の物価上昇の約半分程度がエネルギーにより押し上げられている(図1)。
通常、エネルギー価格の上昇は、国内経済の需給というより外的な影響を反映したものと位置付けられ、いわば一時的なものとして考えられることもある。しかし、欧州のエネルギー消費をめぐっては、脱炭素の動きによる影響も含む構造変化がみられる。以下では、今後のエネルギー価格上昇の持続性をみる観点から、最近変動の大きい天然ガスを中心として、エネルギー価格動向の背景を整理する。
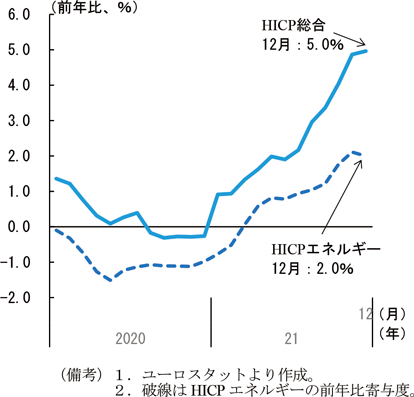
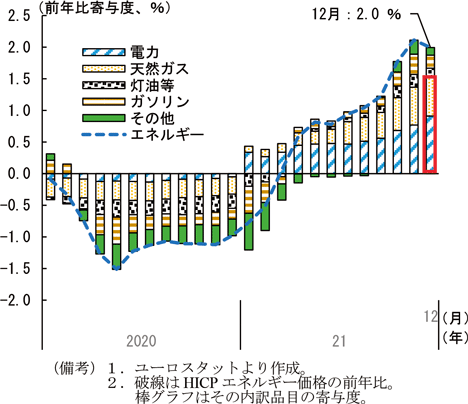
(1)HICPにおけるエネルギー価格の影響
エネルギー関連の品目による消費者物価への影響をみるために品目別に寄与度分解すると(図2)、電力料金が21年に入ってから上昇に転じ、その後、ガス料金が春先以降に上昇幅を拡大させており、足下では両者(図2の赤囲み部分)が、HICP全体(総合)の上昇に対するエネルギーの寄与(21年12月値では2.0%ポイント)のうち約8割に相当している197。
あわせてEU全体の電源構成の推移(図3)をみると、欧州委員会の政策の方向性を反映して再生可能エネルギーの割合が年々上昇しており、20年には化石燃料を上回っている198ものの、個別の電力源別では、ガスは依然として原子力に次いで2番目に高い割合となっている。
欧州エネルギー規制協力庁(ACER)199によれば、近年、ガス価格が電力卸売価格を設定する上での主要な要因となっている。また、各国で電力卸売価格を発電の限界費用200により決定(marginal pricing)しているため、燃料とするガス価格が高騰し安価な代替燃料が十分調達できない場合、電力卸売価格はガス燃料による発電コストにまで引き上げられ得るとされている。
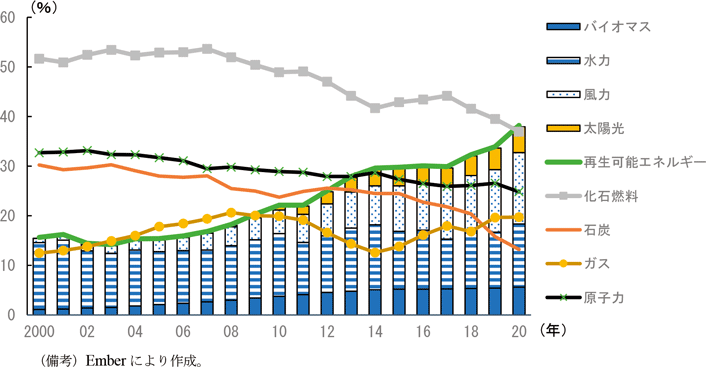
欧州におけるガス卸売価格の指標であるオランダのガスのスポット取引価格(以下「TTF」という。)をみると(図4)、21年春以降急上昇しており、10月に過去最高値を記録した後も高止まりを続けている。前述のとおり、電力卸売価格が発電の限界費用に密接にリンクしている点を踏まえれば、HICPにおける電力料金の夏以降の上昇については、このようなガス価格の高騰によるものとみられる201。
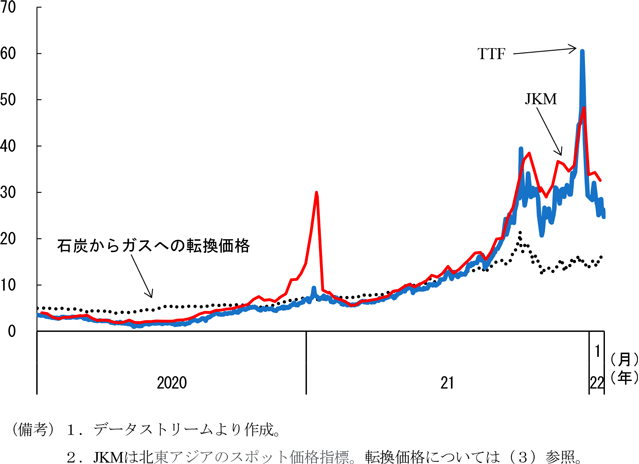
(2)欧州における天然ガス卸売価格体系の変化
欧州における天然ガスの卸売価格体系は、10年頃までは長期契約による石油価格にリンクした価格(石油インデックス)であった。その後、長期契約である石油インデックスは、世界的にガスが余剰状態にあっても価格硬直的であったことから、世界のガス市場の連結が進展する中で、10年代には市場における競争価格(スポット価格)への移行が進んだ202。
図5はガスの輸入価格について、100%石油インデックスと仮定した場合(青線)と実際の輸入価格(緑線)を、国際エネルギー機関(IEA)の試算結果に基づき比較したものである。過去10年間をみると、おおむね前者が後者を上回って(すなわち後者に対して割高で)推移しているが、21年に入ってからは逆転し実際の輸入価格が石油インデックスに比して大きく上昇している。また、棒グラフは、石油インデックスからスポット価格への移行により1年間で節約された輸入金額を示している。20年までは節約額はプラスで推移してきたが、21年に入りTTFにみられたスポット価格の上昇により輸入価格が対石油インデックスで割高となった結果、節約額は大幅なマイナスに転じている。
このように、欧州のガス卸売価格が21年に大きく上昇した背景には、近年スポット市場の利用が増加する中で、21年夏以降、スポット価格が高騰したことが挙げられる。
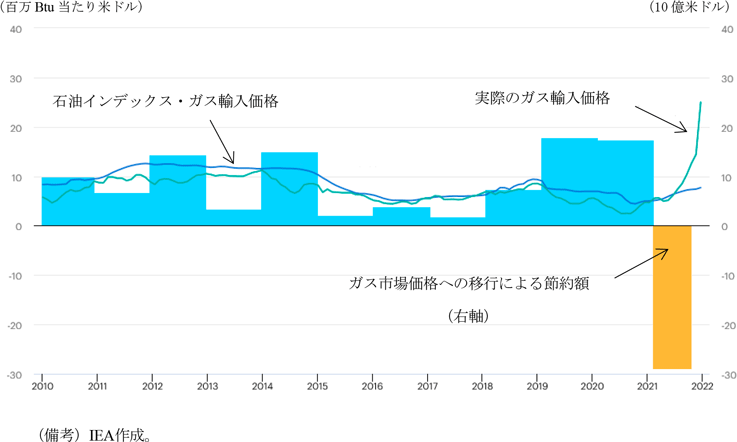
(3)欧州におけるガス価格高騰の背景
最後に、川上である現下の欧州でのガス・スポット価格高騰の背景として、(i)経済活動再開に伴うガス需給のひっ迫、(ii)天候条件203、(iii)欧州排出権取引(以下「EU-ETS」という。)価格の高騰、等による影響が指摘204されている。
このうち(i)については、世界の各市場でのガス価格の相関関係が強まっており、他地域での需給動向が欧州の市場価格に反映されやすくなっているとの見方205がある。21年春以降は、アジアでの価格上昇と比例的に欧州でも高騰している(図4)。他方で、21年のガス輸入の推移をみると、最大の供給先であるロシアのパイプラインによる追加供給が過去5年間と比して低調であったこともあり(図6)、需要増となる冬季が迫る中でも輸入が伸び悩み、年後半には需給のひっ迫が増幅している。
(ii)については、供給側要因としては欧州における風力不足による風力発電出力低下を補うためのガス火力発電量の増加、需要側としては、例年需要が減少する春以降、各国は冬季に減少する在庫を積み上げるが、21年4~5月が低温であったため在庫積上げが遅れた点や、東アジアでの寒波の影響等が指摘されている。
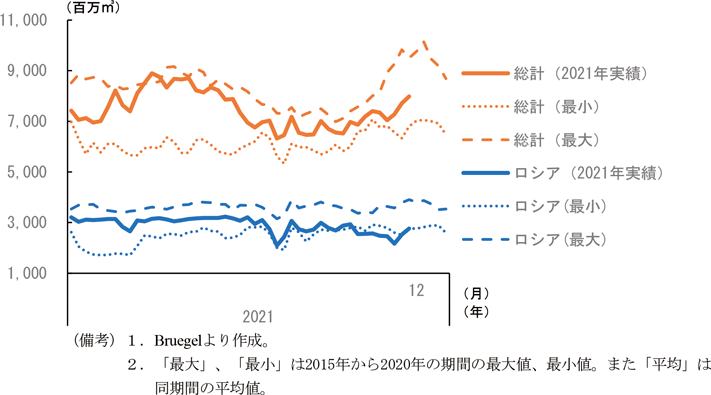
(iii)については、EU-ETSが21年よりフェーズ4の段階に入り温暖化ガス(以下「GHG」という。)排出量規制の強化206が図られたことにより、排出枠価格(EUA価格)が上昇したため(図7)、多くの排出権購入が必要となる石炭から、相対的に排出量の少ないガスへの発電用燃料の転換が促進され、ガス需要の増加を後押しした、との見方がある。
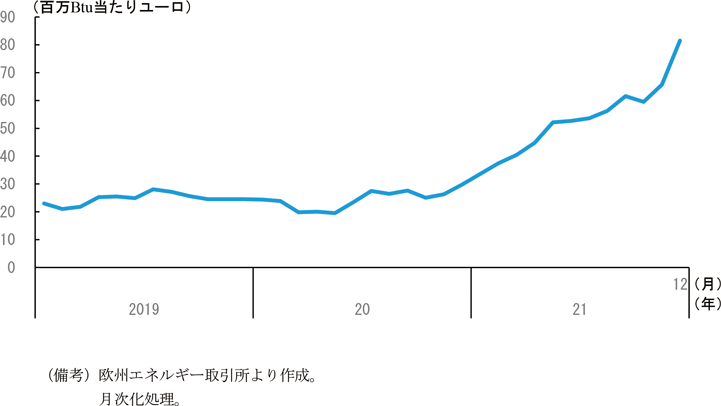
図4の石炭からガスへの燃料転換価格207の推移をみると、EUA価格やガス価格の値上がりを反映し、緩やかに上昇している。ガス価格は同転換価格を上回って推移しているが、これは石炭がガス(下回る場合はガスが石炭)に対し発電燃料として価格上はより有利となっている、すなわち、現在のガス価格高騰の下では、価格上は、かえって石炭への代替を促す格好になっていることを意味する。
このようにEUA価格の上昇は、短期的にはガス卸売価格を上昇させる面があるものの、中長期的には脱炭素化の進展により、GHG排出量のより少ない燃料源への転換が促進され、結果、ガス価格押下げの効果をもつものとみられる。
なおEUA価格動向のガス卸売価格への影響は、前述の(i)及び(ii)の要因から切り分けて把握することが難しいことから、一定の幅をもってみる必要があると考えられる。
これまでみてきたように、21年夏以降の欧州のエネルギー価格の大幅な上昇の背景には、電力卸売価格の設定方式や発電の燃料として用いられるガス価格の変動に加え、ガスの卸売価格体系の変化等、供給段階における様々な要因が影響していると考えられる。既述のように、こうした要因のうち、気候要因等は経済情勢とは独立の一時的な要因である可能性もあるが、脱炭素化の動きが中長期的なエネルギー価格の押上げ要因となっていることも考えられる。こうした構図は、脱炭素化に率先して取り組む欧州で先行して顕在化し、これに加えてロシアとの関係等地政学的な要因もエネルギー価格の押上げにつながっていると考えられるが、欧州以外の地域でも脱炭素化や燃料源の切替えの影響がみられていくことが予想される。世界経済において今後のエネルギー価格の動向や見通しを考える上で留意が必要であろう。
トピック5:ドイツ新政権が直面するメルケル時代から続く課題
21年12月8日、オラフ・ショルツ首相(ドイツ社会民主党(SPD)党首)率いるドイツ新政権が発足208した。昨秋の総選挙で、これまで政権を率いてきたキリスト教民主・社会同盟(CDU・CSU)が野党へ転落、第1党になったSPDが、緑の党、自由民主党(FDP)と共に3党による「信号連立」を形成させた(図1)。緑の党は政治信条的にはSPD(中道左派)に近く、FDPはCDU(中道右派)に近い(プロ・ビジネス、中道右派)ことから合意は難航することが予想されたが、3党は政策相違を乗り越え政権発足を優先させ、同年11月24日に連立協定の最終合意(表2)に至っている。
アンゲラ・メルケル氏は首相退陣とともに政界を引退したが、05年から16年に渡り4期に及ぶその長期政権においては、欧州債務問題、エネルギー安全保障そして難民の社会的包摂といった課題に直面した。本トピックでは、これらの課題について経済指標を参照しつつ振り返り、新政権の方向性を理解する上での手掛かりとする。
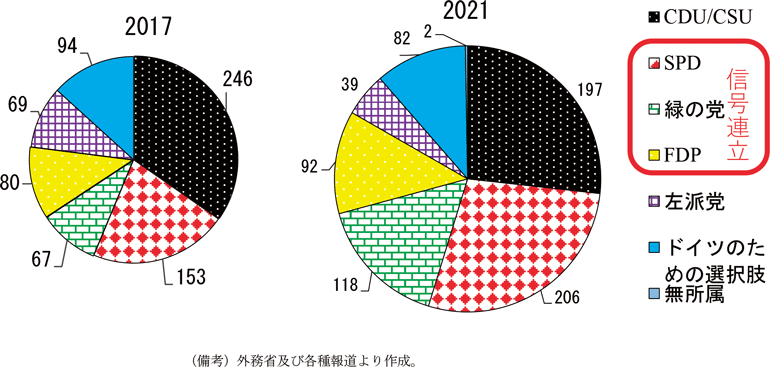
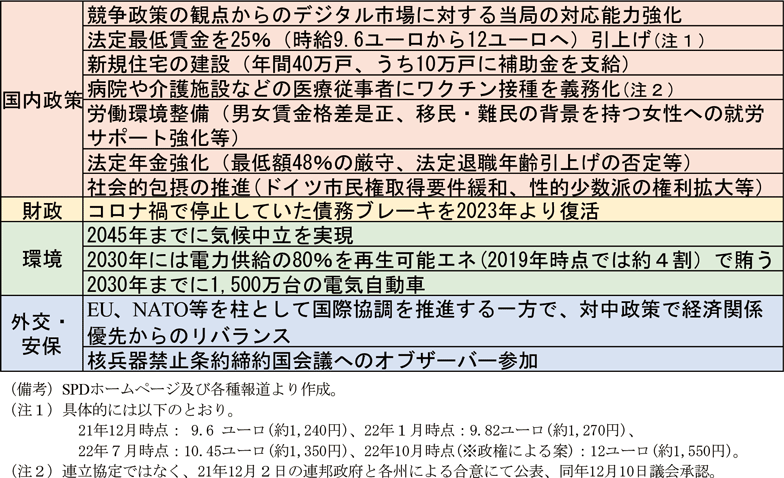
(1)欧州債務問題
EUでは、(i)単一金融市場の完成により銀行が域内で自国同様の活動が可能となり、(ii)99年1月のユーロ導入で為替リスクが消滅、(iii)EU第5次拡大209による域内向け海外直接投資(FDI)の増加等を踏まえ、2000年代を通じて西欧主要行は高利の南欧諸国への貸出を増加させ、国債を大規模に購入していた。その中でギリシャを始めとする南欧諸国の財政赤字・政府債務の膨張が2000年代末にかけて顕在化(図3)し、ソブリン・リスクに陥ったのが、欧州債務危機である。それまでEUでは「安定と成長の協定(以下「SGP」という。)」に基づく財政規律が求められ210、違反国に対しては過剰赤字手続(以下「EDP」という。)を勧告、そして一定期間内に是正措置が採られない場合、制裁が科せられることとされていた。ただし、実際の運営上発動までには裁量の余地があったため、一度も制裁が発動211されることなく形骸化していた。

このため、11~13年にかけてEUでは財政健全化・マクロ不均衡是正に向けた新たな改革が打ち出された。その1つがユーロ諸国の構造的財政赤字212を対GDP比0.5%以下に抑えること(「債務ブレーキ」ルール)を目的とした「安定・協調・ガバナンスに関する条約(以下「TSCG」という。)」である。TSCG はSGPと比して(i)自然災害等特別な事情を除き自動的に是正プロセスを適用(違反に対する制裁発動での裁量の余地を制限)、(ii)各国は同ルールを国内法(望ましくは憲法)で定める、などの強化が図られた。
ドイツは東西統一の後遺症から回復する中で財政健全化に取り組み、07年には財政収支が黒字に転じていた。ただし、その後のリーマンショックを契機とした戦後最大規模の追加景気対策213により大幅な財政赤字に陥り、EU経済・財務相理事会よりEDPを勧告された。対して、メルケル政権は09年には基本法(憲法)に均衡財政を義務付ける規定(構造的財政赤字を対GDP比0.35%以下とする債務ブレーキ)を設定し11年より適用を開始、大規模な歳出削減を断行し12年には財政黒字に回復させた。ドイツはこの先行的取組により、11年12月のEU首脳会議においてメルケル首相(当時)がTSCGを提案・主導するなど、同条約の制定(13年発効)に貢献した。
ただし20年に入ると、ほとんどの加盟国において、感染拡大から大規模の経済対策が打ち出され財政状況が悪化した。ドイツは14年以降公共投資の抑制等を通じて財政黒字を維持していたが、20年予算より前述の非常時に債務ブレーキ(構造的財政赤字を対GDP比0.35%以下)を停止する例外規定を発動、財政スタンスを一転させた。メルケル第4期政権(17年3月~21年12月:CDU・CSUとSDPの大連立)は、中小企業向け給付金やVATの一時的引下げを含む経済対策を実施し、その事業規模は約1.3兆ユーロ(約164兆円、対GDP比約40%)に達した。20年の財政収支は対GDP比4.3%の赤字となった。
EU全体としても、20年7月に欧州理事会において、「次世代のEU」と称する7,500億ユーロ規模(対GDP比4.6%)の復興基金214について合意に至った。復興基金は、加盟国共同の債券の発行により資金を調達するスキームであり、債務共有化をもたらすことから、その合意に向けた調整と交渉過程は難航した。特に、共同債の返済原資となるEU予算の拠出負担が相対的に重く、財政規律を重視するオランダ、オーストリア、スウェーデン、デンマーク(いわゆる倹約4か国)の反発を招き、20年4月、6月に開催された欧州理事会では合意に至らなかった。欧州委員会は同4か国に配慮し、当初案より補助金の割合を引き下げる対応を図った。ところが、同基金からの予算配分の条件として、不適切な使用防止の観点から「法の支配の原則」を導入する動きが出たことに対して、今度は、以前より同原則に関連してEUより指摘を受けていたハンガリーとポーランドが抵抗を示した。同基金の成立が21年に持ち越すとの観測もなされたが、EUの議長国であるドイツが妥協案を提示し、両国がこれを受け入れたことで、12月の欧州議会及びEU理事会において最終的に承認され、21年1月より執行されることが決定した。
(2)環境政策とエネルギー安全保障
メルケル第2期政権(09年10月~13年12月:CDU・CSUとFDPの連立)は当初、低炭素化と経済性を確保しつつ再生可能エネルギー(以下「再エネ」という。)拡大を進めるための「つなぎ」として原子力発電(以下「原発」という。)を活用することとし、原発稼働年数の延長を計画していた。しかし、11年3月の東日本大震災に伴う福島第一原発事故を機に、22年までに段階的に原発を閉鎖することを決定、ドイツの電源構成における原子力の割合は急速に低下した(図4)。再エネを推進しつつベースロード電源を確保するために、一時的に石炭火力の割合が上昇し、また、ロシアから輸入する天然ガスを燃料とした火力発電への依存を深めることとなった215。
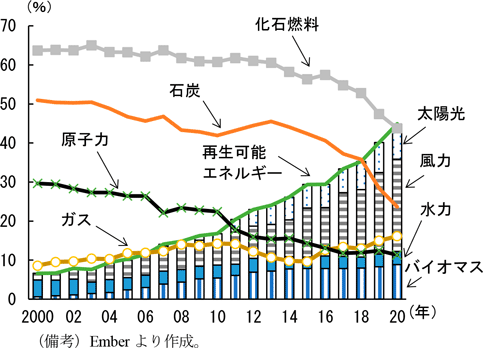
ドイツでは、2000年より再エネ法が施行され、太陽光発電を始めとする再エネによる電力の固定価格買取制度(FIT)を積極的に推進していた。同制度に後押しされ、再エネは拡大していったものの、(i)FIT買取価格引下げ216、(ii)中国企業の市場参入による供給過剰により、大手再エネ事業者の破産が相次いだ。同様に安価な中国製品に押されていたEUでは13年5月、欧州で販売される中国製ソーラーパネルに反ダンピング課税を導入することを提案したが、ドイツは、既に主要な輸出先となっていた中国への輸出に影響が及ぶことやソーラーパネル価格の高騰を懸念し、これに慎重な姿勢を示した。メルケル政権においては、対ロシアではウクライナ問題、対中国では人権問題等の政治問題で対峙する局面がありつつも、これらのエネルギー政策上の背景もあり、両国との経済関係は強化されていった(図5)。
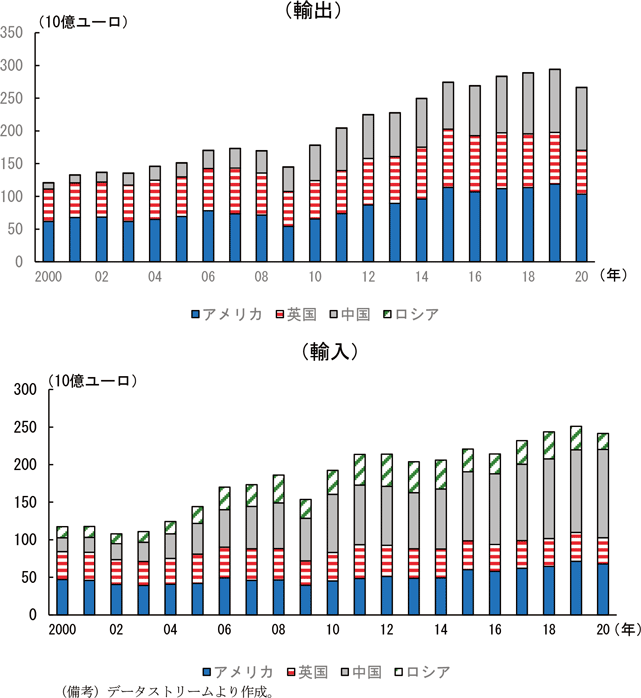
(3)難民の社会的包摂
EUでは10年代に入り、紛争や政情が不安定等の理由で北アフリカや中東等からEU域内に向かう難民の移動が増え始めた。15年4月の密航船転覆事故217により国際的保護を求める難民への人道支援策を求める声が高まり、欧州委員会は5月、イタリア、ギリシャに到達する大量の難民を加盟国に配分することを含む緊急措置をまとめ、欧州への難民の流入は15年夏から更に加速していった(図6)。ドイツは、当初、メルケル首相(第3期政権(13年12月~18年3月:CDU・CSUとSDPの大連立))が15年9月にダブリン協定218を破りハンガリーで滞留していた難民の受入れを決定するなど、EU主要国の中でも難民受入れにより積極的な姿勢をみせていた。しかし、その後もドイツを目指す難民が増加し100万人超が流入した結果、地方政府より収容負担の限界を訴える声が上がり、メルケル首相の寛容政策は連立与党内部からも批判を受けるようになり、全加盟国で受入れを分担すべき219と主張するようになった。
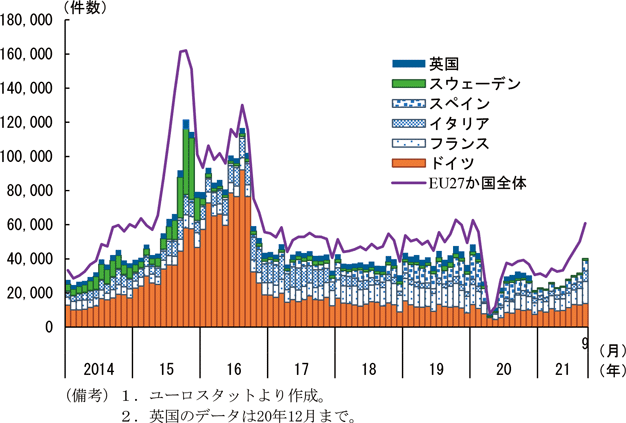
他方で、このようにして受け入れた難民をどのように社会に統合させ、労働市場への参加を促していくかが課題となっている220。ドイツにおける難民による職業訓練申込件数は増加したものの(16年:10,300件→18年:38,300件)、18年の受講件数は申込件数の36.5%にとどまっている。ドイツにおける、EU域外からの移民者と同国で生まれた者との労働参加率の差は16.3%ポイント(EU平均は9.4%ポイント)あり、EU内でも最も格差ある国の1つとなっている。また、女性についてみればこの格差は20.2%ポイント(EU平均は9.5%ポイント)と更に拡大する221,222。
(4)最後に
これまでみてきたように、メルケル政権ではドイツ一国のみならず欧州全体の転換点となるような局面において大きな役割を果たしてきた。これらの点は、新政権の政策内容(前掲表2)においても、景気動向を見据えての債務ブレーキの復活、ガス価格が高騰する中でノルド・ストリーム2223対応含むエネルギー安全保障と脱炭素化の両立、難民等社会的少数派の包摂と統合といった重要な課題となっており、新政権の今後の方向性を理解する上での補助線となるものと思われる。
ユーロ圏においては、ドイツにおける20年のVAT引下げ(20年7月1日~12月31日:19%であった税率を16%へ)期間の裏による押上げ効果。英国においては(i)20年8月の1か月間のみ実施された外食支援(酒類を除く飲食費の50%(一人当たり10ポンド(約1,400円)を上限)の割引を政府が負担。)、(ii)VATの引下げ(20年7月15日~21年9月30日:20%であった税率を5%へ)の終了に伴う押上げ効果があるとされている。ONSの分析によれば、(i)及び(ii)は各々20年8月の消費者物価上昇率総合を-0.4%ポイント、-0.2%ポイント押し下げたとしている。
この背景としては、(i)EUにおける家計向け小売電力料金の構成は20年平均で、エネルギーが占める割合は35%(他は、付加価値税等の公租公課が35%、送電コストが30%)である点(ACER, 2021b)、(ii)消費者はより安価な電力事業者への切替え(switching)によりエネルギー価格高騰の影響を軽減可能(域内でバラツキがあるものの、典型的なドイツの家庭は、市場で最も有利なオファーを選択した場合、年間の電力料金を最大約4割削減できるとしている)であるとしている点(European Commission, 2020b)、(iii)加盟国ごとに電源構成が異なり、例えば原子力主体であるフランスは燃料価格高騰の影響を受けにくい点、等が考えられる。

