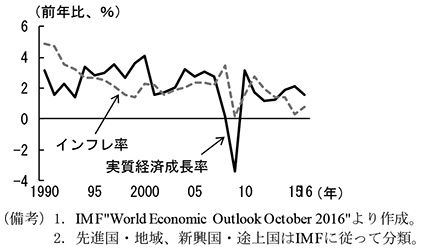第1章 先進国における低金利・低インフレ(第1節)
第1節 低金利・低インフレとは
世界金融危機以降、先進各国での回復のペースは緩やかなものとなっている1。インフレ率が中央銀行の目標水準に到達していない国も多く、各国中央銀行は緩和的な政策を継続している(第1-1-1図)。直近では一部の国で長期金利の上昇がみられる(第2章第5節参照)が、この節ではより長期的な観点から、低金利や低インフレの進展の背景を論じることにより、今後の政策の方向性について示唆を得る手掛かりとしたい(第1-1-2図)。
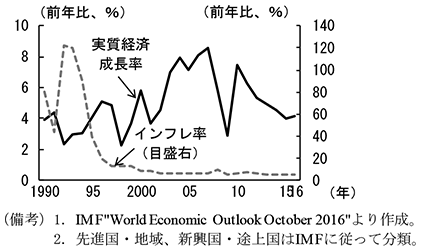
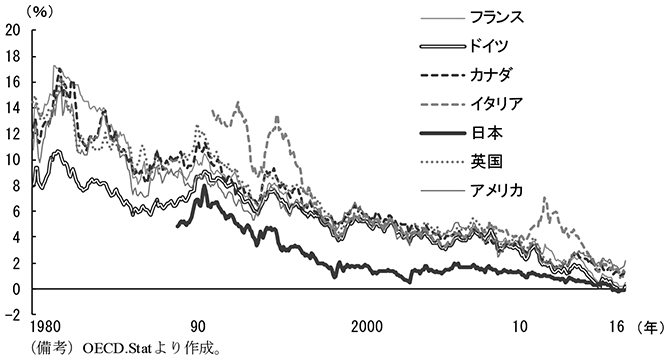
以下では、低金利・低インフレそれぞれの背景について整理する。
1.低金利の背景
先進国を中心とした緩和的な金融政策により、政策金利は歴史的な低水準で維持されているが、こうした短期の名目金利のみならず、長期金利も低下し低水準にとどまっている。長期金利の低下は1980年代以降のすう勢的なトレンドであることから、金融政策以外の要因も含めた複合的な影響によるものと考えられる。実質金利が低水準にとどまっていることに関する近年の国際的な議論の動向を振り返ると、(1)貯蓄の増加と投資の減少によって貯蓄・投資バランスが変化したこと、(2)国債を始めとした安全資産に対する需給がタイト化したことの2点が度々指摘されている3。以下では、それぞれの要因に関する議論の動向について整理する。
(貯蓄・投資バランスの変化)
低金利の背景として頻繁に指摘される要因の一つが、貯蓄の増加と投資の減少による貯蓄・投資バランスの変化である。実質利子率が高くなれば経済全体では貯蓄が増え、投資が減ることから貯蓄のGDP比は右上がり(貯蓄関数)、投資のGDP比は右下がり(投資関数)の関係にあると考えられ、経済全体の貯蓄は経済全体の投資と一致することから、両者の交点が均衡実質利子率に相当する。仮に何らかの事情で利子率の水準にかかわらず貯蓄意欲が上がり投資意欲が下がれば貯蓄関数は右方向にシフト、投資関数は左方向にシフトするが、貯蓄が投資を上回るようになり、両者を均衡させるために実質利子率は低下すると考えられる(第1-1-3図)。
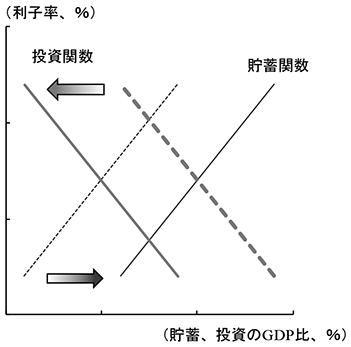
貯蓄が増加した理由については、平均貯蓄性向を押し上げる様々な要因を指摘できる。まず、分配面では、所得格差が拡大し富裕な資産家層が蓄えを増やした点が考えられる。リスクに対する選好の面では、世界金融危機時に将来所得の不確実性が高まったことに対応して、先進国で予備的動機から貯蓄率が上昇した4ことが指摘されている。これらの押し上げ要因に対し人口動態面では、ライフサイクル仮説に従えば、戦後ベビーブーマー世代が既に定年退職年齢を超えていることから、引退後に高齢化していくに伴って貯蓄の取崩しを行うため、高齢化の進展に伴い貯蓄性向にはマイナスに寄与する可能性がある5。
このほか、先進国で金利が低下した背景には、中国を始めとする新興国・途上国の資金が国際金融市場に流出したことによるものとの指摘もある。先進各国の国債の外国人保有比率をみると、90年以降総じて上昇傾向にある6(第1-1-4図)。この間、中国を始めとする新興国・途上国では国際金融市場への統合が進んでいたことから、新興国・途上国の資金が先進国の国債市場に流入し、長期金利を押し下げる方向に寄与した可能性がある。
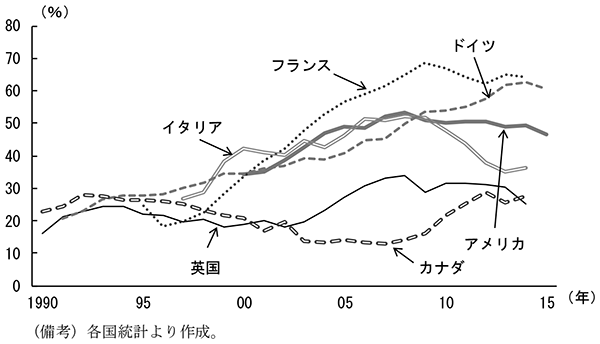
新興国・途上国で蓄えられた資金が国外に流出した背景としては、新興国・途上国における貯蓄率の上昇が考えられる。世界の貯蓄率をみると、先進国・地域がおおむね20%前後で安定的に推移しているのに対し、新興国・途上国では2000年以降急激に上昇している(第1-1-5図、第1-1-6図)。経済成長が顕著な新興国・途上国では、家計部門の所得も増加しているが、家計には過去からの習慣に従って消費行動を決める傾向があり、所得が増えてもその増加分をそのまま消費に充てることはしないと考えられることから7、所得の増加に伴って貯蓄率が上昇したものと考えられる8。また、世界全体の貯蓄に占める新興国・途上国の貯蓄シェアは2000年代に急上昇しており、新興国・途上国の経済成長に伴い、世界全体の貯蓄率を押し上げたと考えられる9。新興国・途上国は依然として高い経済成長率となっているものの、近年は以前と比較して国内に良質な投資プロジェクトが減少した結果、資金が国外に流出している可能性が考えられる。
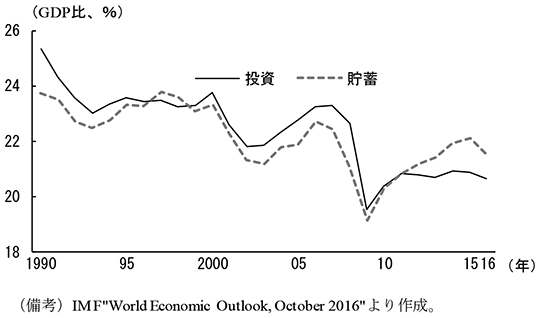
貯蓄・投資バランスが変化した要因としては、投資の減少も重要な点である。特に世界金融危機以降、先進国を中心に投資収益率が低下したことや、ICT関連を始めとした資本集約度の低い業種が台頭したことなどを背景に、先進国・地域では投資が低迷している(第1-1-5図、第1-1-6図、第1-1-8図)。また、資本財の相対価格をみると、1950年以降ほぼ一貫して低下を続けていることから、投資額を減少させる要因の一つとして指摘されている(第1-1-7図)。ほかにも、企業の先行き不透明感の高まりによる影響が指摘されている11。
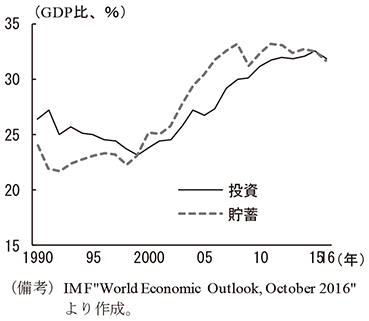
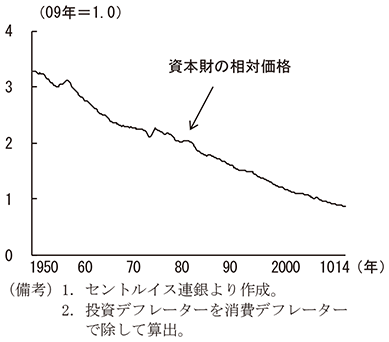
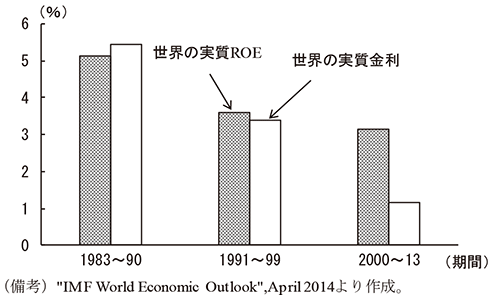
以上のような様々な要因で貯蓄関数、投資関数の双方がより低い実質利子率で均衡するようにシフトし、世界経済全体が貯蓄超過となった結果、均衡実質利子率が低下したものと考えられる。
(安全資産に対する需給のタイト化)
貯蓄・投資バランスの変化以外の要因としては、安全資産に対する需給がタイト化したことが考えられる。
供給面では、特に世界金融危機以降、国際金融市場での安全資産の供給制約の可能性が指摘できる。世界の国債発行残高をみると、新興国の国債発行残高は緩やかに増加しているものの、安全資産とされる先進国の国債発行残高は11年4~6月期頃から減少し始めている12(第1-1-9図)。この背景としては、世界金融危機時に各国が行った大規模な財政出動の反動の影響が挙げられる。
需要面では、投資家がリスク回避度を高め、リスク資産と比べて安全資産保有の選好を強めているとの見方がある。また、世界金融危機以降の一連の金融規制強化によって、金融機関の安全資産に対する需要が拡大したことも考えられる。他方、安全資産に対する需要の拡大とは対照的に、世界のマーケットに存在する安全資産が減少することによって、インフレ率の低下を通じた実質利子率の上昇が起きるとする議論も見られる13。
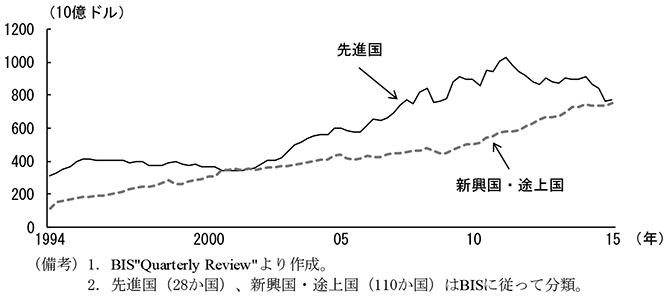
2.低インフレの背景
次に、先進国を中心とした低インフレの現状について述べる。低インフレの環境下では、(1)グローバル化が進み、インフレ率が他国のインフレ率と共振しやすくなったこと、(2)予想インフレ率がアンカーされなくなっていること等が度々指摘されている。
(グローバル化)
IMF(2016b)は、金融危機以降の国際的な低インフレの拡がりの最大の要因はグローバル化であると指摘している。同レポートは、低インフレがサービス部門より製造業、中でも貿易財で顕著であることから、アメリカ、中国、日本の製造業の低迷が輸入物価の低下を通じて貿易相手国にも低インフレのスピルオーバーをもたらしている、と分析している。また、BIS(Bank for International Settlements:国際決済銀行)は、サプライチェーンのグローバル化によって、一つの製品の価格が国内要因だけでは決まらなくなりつつあり、インフレ率は年々グローバル要因に左右されやすくなってきていると指摘している15。
(予想インフレ率のアンカー)
IMF(2016b)は、世界金融危機以降、人々の予想インフレ率がアンカー16されなくなり、現在のインフレ率が過去のインフレ率により大きく依存するようになったと分析している17(第1-1-10図)。後述するとおり、各国中央銀行はフォワードガイダンス政策を通じて予想インフレ率をアンカーすることによりマクロ経済の安定化を試みている。予想インフレ率はあまりアンカーされていないとの見方もあるものの、近年では、政策よりも原油価格等の外生的なショックによるインフレ率の低下が、適合的予想形成18によって予想インフレ率も押し下げる傾向が顕著であることも指摘されている19。
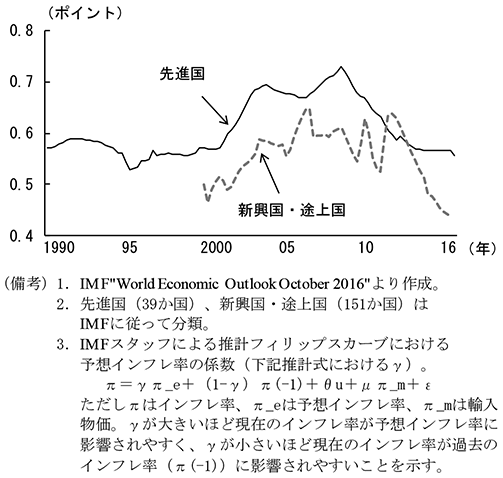
(その他の要因)
グローバル化や予想インフレ率のアンカーのほかにも、インフレ率が低下した要因については諸説が提示されている。09年、サンフランシスコ連銀イエレン総裁(当時)は、景気後退局面では経済の諸資源の稼働率が高くないため、物価や賃金の上昇圧力は極めて低いと指摘21したが、その後の景気回復局面でも労働市場の指標が改善するなか、賃金の伸びは比較的緩慢22であり、これが低インフレにつながっているとの見方もある23。
また、市中銀行が貸出を増やさなかったため、FRB(連邦準備制度理事会)やECB(欧州中央銀行)の追加緩和策があまりインフレ率の上昇につながらなかったとの指摘も見られる24。貨幣乗数の推移をみると、アメリカでは低水準にとどまっており、ユーロ圏では15年以降低下し続けている(第1-1-11図)。
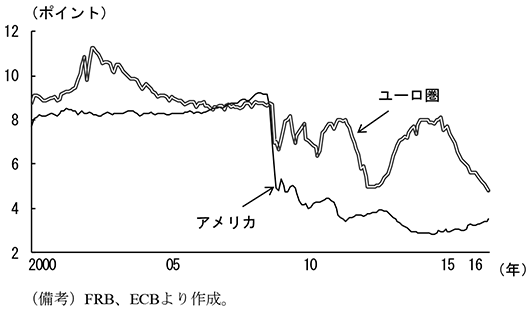
3.低金利と低インフレ
ここまで、低金利、低インフレの背景をそれぞれ見てきた。このような低インフレと低金利の両立に関する議論をサーベイし、両者が併存している現状をどう理解するべきか、金融政策面でどのような対応が必要とされているのかを考えるため、マクロ経済学者や金融政策の実務家による議論を整理する。
(自然利子率の低下と低インフレ)
インフレを加速も減速もさせない、景気中立的な均衡実質利子率は自然利子率と呼ばれる。言い換えれば、物価が低水準でほぼ安定している状況(低インフレ)で、持続的に潜在成長率並みの経済成長を実現するためには、中央銀行が実質利子率を自然利子率に一致させるような政策運営を行うことが必要となる25。このため、自然利子率の動向(足下の水準やトレンド等)は政策当局にとって極めて重要な情報となる。
金融政策が緩和的な効果をもたらすためには、市場における実質金利を自然利子率以下の水準に引き下げる必要がある。仮に自然利子率自体がゼロに近い低水準にあるとすれば、実質利子率をマイナス水準にまで下げない限り、需要を喚起する効果は小さい26。政策金利がゼロ金利制約下にある場合、短期の政策金利が自然利子率を上回ってしまうことから、伝統的な金融政策だけでは緩和的な状況を作り出すことができなくなる。仮に非負制約がないとしても、マイナスの政策金利をすぐに家計向けの預金金利等に反映できないことから、銀行の収益性を圧迫する可能性が高いこと、また市中銀行が大量の貨幣を管理するコスト等を考えるとマイナス金利には下限があると考えられており27、特に低インフレ下では実質金利を自然利子率以下に引き下げるのは困難となる。
自然利子率には様々な推計方法があり、アメリカを始め日本でも多くの試算結果が公表されている28。これらのうち、サンフランシスコ連銀が公表するアメリカの自然利子率29の推計結果が第1-1-12図であるが、90年代後半以降緩やかな低下を続けた後、近年ではマイナス水準になっている30。自然利子率は短期均衡下では景気循環を背景とした需要側のショックと、潜在成長率双方の変動の影響を受ける。したがって、上述したISバランスを変化させる要因に加えて、潜在成長率を変化させる技術革新等もその変動要因であり、低下した自然利子率を引き上げるには構造政策も含めた政策対応が必要と考えられる。
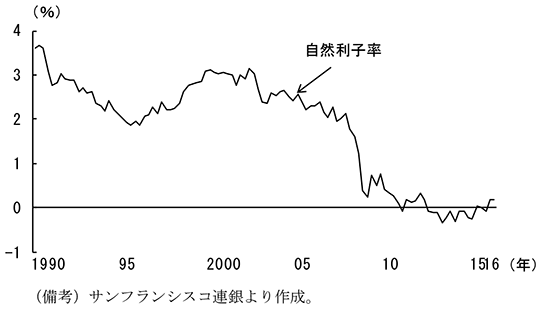
(低金利下で生じる低インフレの問題)
従来のマクロ経済学の議論31に基づいて政策金利とインフレ率の関係を考えると、名目金利の引下げは企業の借入増加につながることから、企業活動の活性化と労働市場の需給の引締まりを通じて賃金を引き上げ、賃金の上昇は価格に転嫁されていく32ため、結果としてインフレ率の上昇をもたらすことになる。一般に、インフレ率が低下した場合には名目政策金利の引下げで対応することが想定されるが、他方、先進各国の政策金利は世界金融危機以降、ゼロに近い水準で推移しており、前述の通り低インフレに対する金利面での政策対応が難しくなっている。
名目金利が低水準で安定してしまうと、中央銀行は、金融緩和が必要な時でも伝統的な手法での政策余地が極めて限定的となるため、需要を刺激することが困難になる。加えて、仮に名目金利が低い状況でデフレになれば実質金利は名目金利を上回り、経済の下押し圧力となる。セントルイス連銀のブラード総裁は、名目金利のゼロ下限制約下で政策ルールに基づく金融政策運営を行うと、ターゲットとする均衡(targeted equilibrium)ではなく意図せざる均衡(unintended steady state)においてゼロ金利かつデフレ状況になる可能性があり、後者の均衡では伝統的金融政策の範囲では政策当局はショックへの対応能力を失うため、問題となると指摘した33。
アメリカで金融政策の正常化の議論が登場してきた頃、経済学者の間では、低金利・低インフレのリスクを考えると、緩和策の行き過ぎのコストは不足のコストよりはるかに小さい、との見解が一般的であった34。FRBの政策目標である最大雇用、物価の安定のうち物価の安定については、インフレ率が多少目標を上回っても、失業率が十分下がるまでは利上げを踏みとどまるべきとする考え方が登場し、「高圧経済(high-pressure economy、平均を上回る経済成長率と低い失業率で特徴づけられる経済35)に向けた金融政策」等と称された。高圧経済のメリットについてHolzer et al. (2006)は、90年代末の低失業率の期間に、高卒未満の学歴の長期失業者にも就業機会が開けたことで、そうした人々が経験を積みスキルを蓄積できる機会が大幅に高まった、との見方を示した。インフレ率が多少オーバーシュートしても問題が起きにくい根拠としては、2000年代以降世界金融危機までの間は、中長期のインフレ予想がFRBのターゲットから大きく乖離したことがないことが指摘されている。なお、高圧経済を目指す政策について、FRBイエレン議長は16年10月の講演で、経済危機の損失の修復を図るための唯一の方策であると論じている。
これに対し、低金利・低インフレ状況には問題はなく、特段の政策対応は不要との指摘も一部にある。Cochrane (2016)は、政策金利がゼロになると、インフレ率も最終的には同じくゼロ近傍に近づき安定すると考え、長期では名目利子率の変化はインフレ率の変化と1対1で対応するとしている36。
こうした考え方に基づけば、インフレ率の低下に対して政策金利を引き下げると、結果として一層インフレ率を押し下げるため、最終的に名目金利がゼロ水準となる「低インフレ政策の罠」に陥るとの見方もある37。セントルイス銀行のブラード総裁はCochrane (2016)を引用し、08年末頃以降、G7諸国の政策金利はほぼゼロ水準で推移しているが、インフレ率は12年にピークに達した後、低下の一途をたどった事実と整合的であるとしている38。但し、この背後には原油を始めとする資源価格の動向も大きな影響を及ぼしていることには留意が必要であり、エネルギー価格などの影響を除いたコアCPIでみると、2000年以降ほぼ一貫して1%前後で推移していることから、Cochrane (2016)の考え方と整合的とは言い切れない(第1-1-13図)。
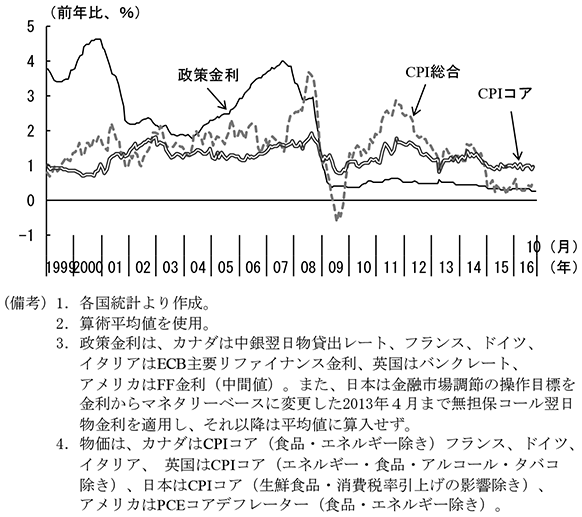
次節では、こうした低金利・低インフレが併存する環境において、政策当局が採るべき具体的な財政・金融政策の在り方に関する議論の動向を具体的に述べる。