財政・社会保障ワーキンググループ報告書 平成10年6月22日
- 目次
- 1.財政・社会保障の現状
- 2.財政構造改革等と世代会計
- (1) 世代会計について
- (2) 世代会計による試算
- 3.経済と調和のとれた社会保障制度の構築
- (1) 社会保障構造改革の必要性
- (2) 社会保障構造改革の視点
- (3) 公的年金制度改革の視点
- (4) 医療制度改革の視点
- (5) 社会保障制度の総合的見直し
経済審議会経済社会展望部会 財政・社会保障ワーキング・グループ委員
| (五十音順) | ||
| (座長) | 井堀 利宏 | 東京大学大学院経済学研究科・経済学部教授 |
| 橘木 俊詔 | 京都大学経済研究所教授 | |
| 田中 滋 | 慶応義塾大学大学院経営管理研究科教授 | |
| 堀 勝洋 | 上智大学法学部教授 | |
| 吉田 浩 | 東北大学大学院経済学研究科助教授 |
1.財政・社会保障の現状
我が国においては、現在相当の速度で少子高齢化が進展している。合計特殊出生率は1949年には4.32であったが、徐々に低下し1995年には1.42まで下がっており、今後も低い状態にとどまることが見込まれている。また、65歳以上の人口の総人口に占める割合は、1965年から1995年の間に8.2ポイント上昇し、14.5%になり、さらに1995年からの30年間で12.9ポイント上昇し、27.4%となると見込まれている。これは、21世紀には、我が国が世界に例を見ない超高齢化社会を迎えることを示すものであり、このことは、財政や社会保障制度に大きな影響を与えることが見込まれている。
我が国の社会保障制度は、これまでの経済成長の過程で大幅に拡充され、国民生活の安定に寄与してきたが、経済成長、人口構成及び生活の水準や様式といった社会保障制度の前提条件が、大きく変化してきたことにも拘わらず、従前と同様の制度であるため、社会保障制度の見直しが必要となっている。現に、高齢化の進展に伴い、社会保障給付は急速に拡大し、それに伴う財政支出も多大な額に及んでいる。今後、さらに超高齢化が進むことから、今後も一層大きな歳出圧力となることは必至である。また、我が国経済は二次にわたるオイルショックによる経済の低迷やバブル崩壊後の不況を、公共投資や減税等の対策によって乗り切ってきた。その結果、財政事情は相当に悪化してきたところである。
財政の現状を見ると、国の1998年度予算(補正後)においては、歳入面では公債依存度は26.3%であり、歳出面では国債費の割合が21.0%に及び政策的経費を大きく圧迫する状況となっている。また、国、地方をあわせた長期債務残高は1998年度末には 544兆円にのぼる見込みとなっている。主要先進国が財政赤字削減に積極的に取り組み債務残高を安定させてきている中、我が国の財政事情は最悪の危機的状況といえる。
現段階でこの財政赤字に起因する負担は顕在化していないものの、財政・社会保障の現状が放置された場合、高齢化等により社会保障基金は底を打ち、政府債務はファイナンス困難となるほど増大することが見込まれ、将来世代等にとって、現実の国民負担としてのしかかることが予想される。そして、高齢化に伴う国内貯蓄の減少から対外収支は赤字化し、純債務国に転落し、国民の実質所得の伸びも低下するという、いわば「破局」シナリオをたどることになると予想される。この「破局」シナリオを回避し、豊かで安心できる少子・高齢化社会への円滑な移行を図るためには、財政構造改革及び社会保障構造改革の実施が急務である。
現在、内閣の最重要課題として、財政構造改革、社会保障構造改革、経済構造改革等の「6つの改革」が一体的に推進されている。財政構造改革は昨年11月に成立、本年5月に一部改正された「財政構造改革の推進に関する特別措置法」により、2005年度までに国・地方の財政赤字対GDP比を3%以下とし、特例公債依存からの脱却を目指すこと等を目標に、歳出全般について聖域なき見直しが行われてきているところである。財政構造改革は、中長期的に国民負担率の上昇を抑えることや、公的部門の簡素合理化により、経済の活性化に資するものである。社会保障構造改革については1999年度の財政再計算に向けた年金制度改革の検討が開始されるなど、各方面において既に精力的な取組みがなされているところである。
現在の財政・社会保障構造を放置すると、いわゆる大きな政府が顕在化し、政府債務はさらに増大し、将来世代等にとってその負担は巨大なものとなり、「破局」のシナリオをたどることになる。この「破局」シナリオを回避するため、以下では、将来世代等の大きな負担という観点から、世代会計の手法により、2005年度を目途に、現在進められている財政構造改革等が世代の負担に及ぼす効果およびさらに社会保障構造改革が行われたとした場合の世代の負担に及ぼす効果を、また、大きな政府の顕在化という観点から、社会保障構造改革として、経済社会の変化を踏まえた年金・医療など具体的な社会保障制度のあり方を検討した。
2.構造改革と世代会計
(1) 世代会計について
世代の負担の問題を考えるにあたっては、家計の対政府の受益・負担構造を示す世代会計の手法がある。
世代会計の考え方は、
ア.従前は世代内の所得格差等が非常に大きかったが、高度成長以降、世代内よりも世代間の格差の拡大が問題になったこと
イ.高齢化が予想以上のスピードで進み、若い人が増えるという前提が崩れてきたことから、これから生まれてくる世代の負担が大きくなることが予想され、世代間の不公平が議論されるようになったこと
ウ.企業の投資行動や家計の消費行動に対し、1年間のフローである財政赤字よりも、将来も含めた政府との受払の現在価値である世代会計の方が影響が大きいと考えられること
などから提唱されてきたもので、具体的には、個人の生涯にわたる税・社会保険料等を通じた政府への拠出と政府サービスや社会保障給付等を通じた政府からの受給との関係を出生年齢階級毎に測定し、生涯を通じた純受益の割引現在価値を推計したものである。
この世代会計の手法により、将来に生まれてくる世代を含めた各世代に課せられる純受益(負担)の比較が可能となる。
(2) 世代会計による試算
世代会計はある時点の政府と家計の受払の姿が一定の(1世帯当たりのGDPの)成長率、利子率等のもとでそのまま将来も続くとの前提による推計であり、あくまで一つの仮定例として、その結果については幅をもってみる必要がある。また、世代間の公平性については、その時代、時代における生活水準、所得水準や価値観などにより、考え方に違いもある。さらに、私的な移転(養育・教育費、住宅等相続財産等)の存在を考えると、単に政府との受払のみで世代間の公平性全てを論ずることはできないことは言うまでもない。
しかしながら、巨額に膨らむ政府債務の存在が、将来への不安感をもたらしている現在、このような世代会計の手法は、世代間の公平性を中心とした経済社会問題を考えるひとつの検討材料になるものと考えられる。
財政構造改革等の経済に及ぼす効果としては、
- 財政構造改革は、政府債務の縮小等により将来世代等に先送りされる負担を減少させるとともに、国民負担率の上昇を抑えることや、公的部門の簡素合理化により、中長期的に経済を活性化させ、成長率を高める要因となること
- また、あわせて規制緩和を中心とした経済構造改革が推進されることは、新規産業の創出および魅力ある事業環境の整備により、良質な雇用機会の確保を含めた産業の活力ある発展をもたらし、成長率を高める要因になること
などが考えられ、財政構造改革等が行われない場合と行われた場合とでは、成長率に差が出るものと考えられる。(試算の前提として、2005年度以降、財政構造改革等が行われない場合は1%、財政構造改革等が行われた場合は3%と仮定する。)
このような財政構造改革等の経済に及ぼす効果も踏まえつつ、世代会計の手法により財政構造改革等が行われない場合および財政構造改革等が行われた場合、加えて社会保障構造改革が行われた場合の1世帯あたり生涯の受益・負担構造について試算を行う。(試算の方法については補論参照)
【1】 財政構造改革等が行われない場合
従前の政府の収支構造として1995年度時点をもとに、世代会計の試算を行う。
その試算結果をみると、49歳以下(将来世代を含む)では負担が受益を上回り、50歳以上では受益が負担を上回る。
図表1 財政構造改革等が行われない場合の世代会計の試算
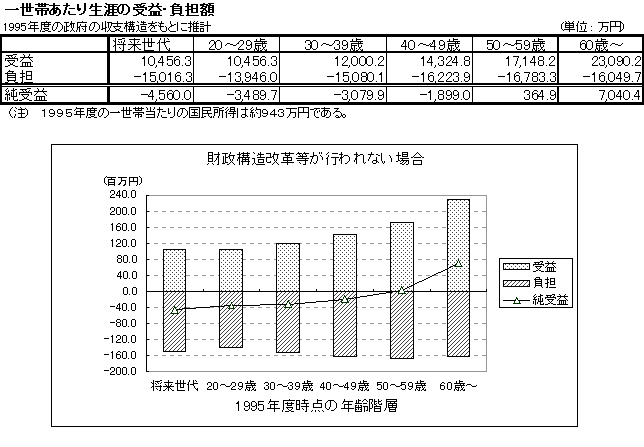
【2】 財政構造改革等が行われた場合
財政構造改革等が実現した後の姿として、2005年度時点において国・地方の財政赤字の対GDP比3%が達成されることをもとに、同様の方法により推計する。(各世代は1995年の時点と同一世代としている。)
その試算結果をみると、【1】の場合と同様49歳以下(将来世代を含む)では負担が受益を上回り、50歳以上では受益が負担を上回る。
図表2 財政構造改革等が行われた場合の世代会計の試算
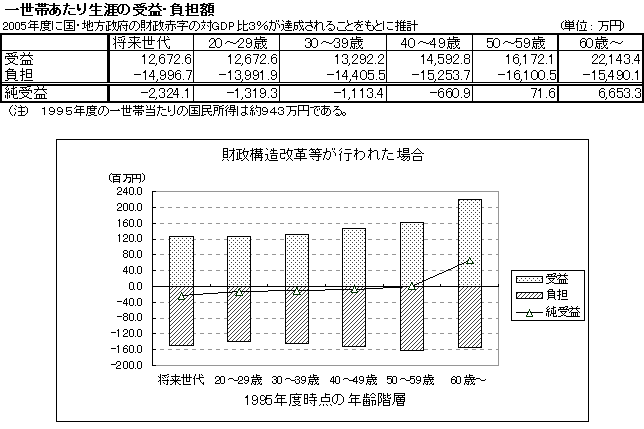
【2】財政構造改革等が行われた場合には、【1】 財政構造改革等が行われない場合と比べると、50歳以上の世代では純受益額が減少し、49歳以下の世代(将来世代を含む)では純負担額が減少する。
図表3 財政構造改革等による世代毎純受益への効果
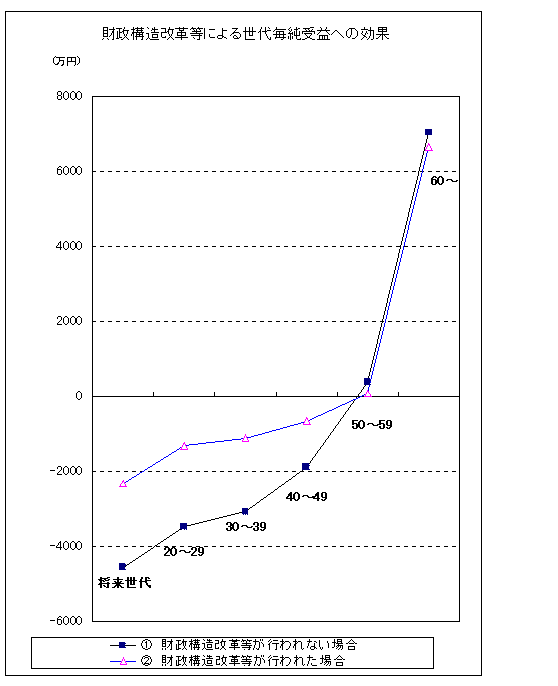
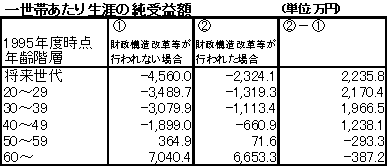
【3】 【2】に加え社会保障構造改革が行われた場合
【2】のケースに加えて社会保障構造改革により高齢者の年金給付を25%削減(高齢世代の年金給付期間が60歳から80歳(世代会計の手法においては、80歳までの生存を前提としている)までの20年間から65歳から80歳までの15年間となると想定)した場合について、同様の方法により推計する。(各世代は1995年の時点と同一世代としている。)
その試算結果を見ると、59歳以下(将来世代を含む)では負担が受益を上回り、60歳以上では受益が負担を上回る。
図表4 財政構造改革等に加え社会保障構造改革が行われた場合の世代会計の試算
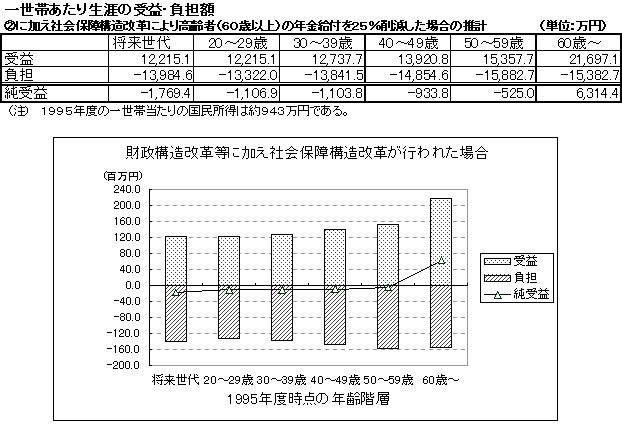
【3】 財政構造改革等に加え社会保障構造改革が行われた場合には、【2】 財政構造改革等が行われた場合に比べると、40歳以上の世代では純受益が減少あるいは純負担が増加し、39歳以下の世代(将来世代を含む)では純負担が減少する。
さらに、【3】 財政構造改革等に加え社会保障構造改革が行われた場合を【1】 財政構造改革等が行われない場合と比べると、50歳以上の世代では純受益が減少し、49歳以下の世代(将来世代を含む)では純負担が減少する。
図表5 改革(財政構造改革等に加え社会保障構造改革が行われた場合)による世代毎純受益への効果
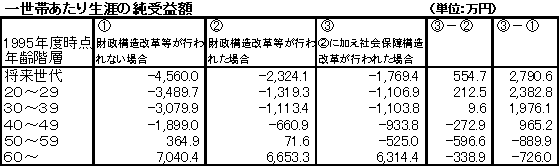
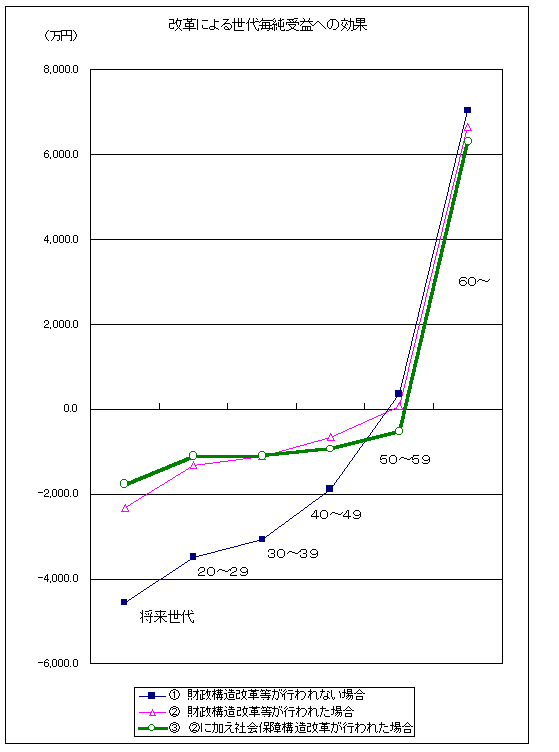
以上の試算から、改革が実現することにより、若年世代、将来世代の負担超の部分が 縮小するなど、世代間の公平性に関し、改善することが見込まれる。このように改革により、世代間の公平性実現に向けた動きが現れることは、将来に対する不安感を除去することでもあり、経済社会の活性化を促すことにつながるものと考えられる。
3.経済と調和のとれた社会保障制度の構築
(1) 社会保障構造改革の必要性
前述の世代会計の試算結果から、改革が実現することにより、若年世代、将来世代の負担超の部分が縮小するなど、世代間の公平性に関し改善することが見込まれ、改革の重要性が確認された。特に、社会保障制度は、国民の連帯による世代間扶養の理念に基づき所得保障や医療保障等を行うという機能を有する。構造改革が進展しない場合には、少子・高齢化の進展や年金制度の成熟化等に伴い将来世代に相当の負担を強いることとなるだけでなく、世代間の給付と負担の不均衡が大きなものとなれば、制度に対する若い世代の理解を得られなくなり維持不可能となるおそれもある。(図表6)
したがって、今後の経済社会の状況変化を踏まえつつ、同一の時代における現役世代と高齢世代の間の公平性を図る必要がある。また、今後生れてくる世代も含めた出生年齢階級間の問題については、各世代を取り巻く生活水準等が異なるほか、後世代は前世代が生み出した技術等を引き継いで生産活動を行う場合があること、私的部門における後世代への移転が存在することなどから、単に政府を通ずる受益と負担のみをもって比較することは妥当ではないが、社会保障制度に対する国民の信頼を維持するためには、出来る限り出生年齢階級間の公平も確保していくことが望ましい。
(2) 社会保障構造改革の視点
社会保障制度は、これまで経済成長の過程で大幅に拡充され、国民生活の安定に寄与してきた。例えば、公的年金は、労働所得のない老後生活の糧となり、医療保障は、生命・健康の保持や労働能力の回復に寄与してきた。このように、社会保障制度が国民生活ひいては経済社会や政治の安定に寄与してきた役割を無視することはできないが、一方で、経済成長、人口構成及び生活の水準や様式といった社会保障制度の前提条件は、制度の拡大期とは大きく変化してきたことも事実であり、こうした変化に対応した社会保障制度の見直しが必要となっている。
したがって、社会保障構造改革を進めるに当たっては、経済社会の変化を踏まえ、次の3つの視点を考慮することが重要である。
1 経済と調和のとれた制度の構築
社会保障給付費は、対国民所得比で1970年度には 5.8%であったが、95年度には17.1%まで拡大しており、少子・高齢化の進展等により一層の拡大が見込まれている。また、これとともに社会保障に係る公的負担も上昇するものと考えられる。例えば、国立社会保障・人口問題研究所「平成7年度社会保障給付費」によれば、社会保障負担の国民所得に対する相対的な規模は95年度現在で13.3%であるが、社会保障制度を内生化したマクロ経済モデルを用いて推計すると、現行の社会保障制度を維持した場合には、2025年度時点で約24%に達するものと見込まれている。(図表7)
社会保障制度は国民経済から大きな影響を受けるだけではなく、国民経済にも大きな影響を与えると考えられる。所得保障や各種サービスの提供を行う社会保障制度は、安定した購買力を国民に付与したり、新たな産業や労働需要を創出することにより、経済の発展に寄与するという積極的な役割を果たす面がある。例えば、介護保険制度が創設されることより介護サービス需要が顕在化し、21世紀の新規産業分野としてシルバービジネスの成長が期待できるだけでなく、従来家庭において高齢者を介護に従事していた者が解放され、就業を選択することもできるようになり高齢化社会における労働力不足を補うことにもなる。
しかし、今後の本格的な少子・高齢化に伴い、経済全体に占める社会保障の財政規模は大きなものとなり、その給付と負担の両面で経済パフォーマンスに影響を与える可能性もあり、さらに、経済パフォーマンスの変化が、社会保障の給付と負担の水準にも影響を及ぼすものと考えられる。また、社会保障の制度設計の在り方も経済パフォーマンスに影響を与えるものと考えられる。例えば、財政方式の在り方は一定の条件の下でマクロの貯蓄率や資本蓄積に影響を与え、所得と給付の関係は労働者の働く意欲に影響を与え、これらを通じて経済パフォーマンスが左右されることも考えられる。
したがって、構造改革を検討する際には、制度改革を経済と独立に検討するのではなく、制度改革とマクロ経済とのフィードバック関係を考慮した上で、社会保障制度は、経済及び財政状況と整合性のとれた、経済パフォーマンスをできるだけ阻害しないものとすることが必要である。
2 ライフスタイルの選択に対して中立的な制度設計
社会保障制度において皆保険・皆年金体制が確立した昭和30代に比べ、今日では高齢者や女性を含めた国民のライフスタイルは大きく変貌した。
当時は、相対的に自営業者の比率が高いため、高齢期を迎えても継続して就業する者が現在よりも多かったが、雇用者は60歳を過ぎれば退職し、老後生活を送ることが一般的であった。しかも、老後生活は主として家族により支えられ、決して余裕のあるものではなかった。また、女性は一般的に結婚により退職し、専業主婦として夫を支え家族の面倒をみるものと考えられていた。
しかし、高齢期の就業意識についてみると、総理府「長寿社会に関する意識調査」(1986年、1991年)によれば、「できるだけ長く仕事をしたい」とする者の割合が1986年の44.7%から91年の54.9%に上昇しているなど、就業意識は高まっている。また、高齢者が世帯主となっている世帯の経済状態についても、厚生省「平成6年国民生活基礎調査」等によれば、世帯間で大きな所得格差があるものの世帯人員1人当たり平均所得では他の年齢層とほとんど変わらず、1世帯当たり貯蓄残高では他の年齢層と比べて高い水準にあるなど、それ以外の世帯に比べて遜色がない。なお、高齢者以外の世帯の平均世帯人員数は高齢者世帯のそれを上回っており、世帯員共通の経費を節約できることに留意すべきである。このような高齢者のライフスタイルの変化、平均寿命の伸長からみると、高齢者を年齢により一律に退職者や弱者とみなす制度は、今日では高齢者の就業のインセンティブを弱めていると考えられる。(図表8)
また、女性の就業状況についてみると、総務庁「労働力調査年報」によれば、雇用者に占める女性の割合が1975年の 32.0%から94年の 38.8%へと高まっているほか、女性の就業意識についても、総理府「男女共同参画に関する世論調査」等によれば、「子供ができてもずっと職業を続ける方がよい」と考えている女性の割合が急速に増加するなど、女性の就業意識は高まっている。このように女性のライフスタイルが変化し共働き世帯比率が増加するなど社会環境が変化する中で、国民年金の第3号被保険者制度は、現在の女性の家庭における役割(育児、介護等)や就労環境等の条件を考慮し、所得が一定水準以下となっている被扶養配偶者について世帯単位で保険料を拠出する制度であるが、女性の就労時間に対して好ましくない影響を与えかねず、個人の自由なライフスタイルの選択の妨げになっているという指摘がある。(図表9)
したがって、高齢者を画一的にとらえる仕組みを弾力化することにより年齢中立的(エイジ・フリー)な制度とするほか、男女双方が共同で家庭における役割を担っていくとともに、女性の就労環境が整備されていくに伴って、将来的には世帯単位でとらえる制度の見直しが検討されてよい。これにより、個人のもつ能力や意欲を十分に発揮できるようにするとともに、公的負担を軽減していくこともできる。
3 社会保障の機能の明確化
財政及び経済の構造改革が行われた将来の社会は、個人の自己責任原則に立脚したものになろうとしている。しかし、市場経済の原理に基づき個人が自己責任と自立性をもって行動し、リスクとリターンを自己管理することを前提とした社会になっても、例えば、構造改革の推進等による労働力需給のミスマッチに伴い、構造的・摩擦的失業が増大する可能性があるなど、自分の意思や力では対応できないような生活を脅かす大きなリスク(貧困、失業、疾病、障害等)を負う可能性がある。
そこで、社会全体として、それらのリスクに対応しようとするものが社会保障である。自己責任に基づいた社会においては、社会保障が確保されてはじめて個人が自らの能力を発揮でき、経済社会が安定し、発展することができる。また、個人は公的な給付と負担を織り込んで将来にわたる生活設計を立てている。将来の不透明な経済社会の変動期にあっては、どこまでを社会保障により対応するかを明確にすることにより、国民の生活に対する不安を払拭することが必要である。
なお、セイフティ・ネットとしての社会保障の機能の具体的内容や水準については、社会保障に対する国民の認識や歴史的沿革、人口動向や経済社会状況等の要素に左右され、様々なとらえ方があり、時代によって異なり得る。
(3) 公的年金制度改革の視点
1 公的年金制度の現状
公的年金は、国民の老後生活の基本部分を支えるという役割を担うものとされている。現行の厚生年金の給付水準をみると、平均月額賃金を支給されている片働き世帯で夫婦双方が40年間制度に加入した場合の老齢厚生年金と老齢基礎年金は合わせて23.1万円(1994年度価格)である。これは、各々1994年度現在のグロスの平均標準報酬の約68%、直接税・社会保険料を除くネットの平均標準報酬の約80%、ボーナスを考慮した総報酬の約62%に相当する。
現行の給付水準を維持する場合、既に述べたように少子・高齢化の進展等を背景として保険料を大幅に引き上げる必要があり、将来の現役世代にとって過大な負担となるものと考えられる。また、給付水準が世代間でほとんど変わらない中で保険料負担は後の世代ほど高くなることから、世代間の格差が問題となる。このとき、家庭内で行われていた扶養負担が代替的に低下していることや、少子化により1人当たり相続額が大きくなること、さらには現役世代の高い生涯所得が高齢世代の貢献により築かれた経済成長によりもたらされたことにも留意すべきであるが、公的年金制度の強制性等に鑑みれば、それは必ずしも、将来の世代の理解が得られないような公的年金制度における世代間の格差を、将来に向かっても維持してもよいということにはならない。
2 経済パフォーマンスへの影響の経路
公的年金制度改革が長期的な経済パフォーマンスに影響を与える経路は大きく2つに分けられる。1つは資本蓄積を通じた影響であり、給付水準及び財政方式が関係するものである。もう1つは労働供給を通じた影響であり、給付水準、負担水準、支給開始年齢及び第3号被保険者制度の在り方等が関係するものである。
ア.財政方式及び財源が資本蓄積に与える効果
(積立方式と賦課方式)
財政方式としては、将来の給付に必要な保険料をあらかじめ積み立てていく「積立方式」と給付に必要な費用をその時々の現役加入者からの保険料で賄う「賦課方式」に大別される。現行の公的年金の財政方式は修正積立方式と呼ばれ、保険料の水準については負担能力等が考慮されており、被保険者本人の将来の給付水準に見合った保険料は徴収されてこなかったこと等から賦課方式の要素が強い。
財政方式が資本蓄積に与える影響を考える場合、個人の貯蓄行動についてどのような前提を置くかによって結論が異なる。仮に、現役時代には生涯の残余期間をたえず考慮して消費パターンを決定し、退職後に貯蓄総額を消費と遺産に振り分けるという「遺産動機を含んだライフサイクル仮説」を満たすような、長期的な視野をもった個人を前提とすると、近年の我が国のように、概して労働人口成長率と賃金上昇率の和(経済成長率)が利子率を下回る場合が多い状況においては、公的年金を賦課方式よりも積立方式で運営する方が、マクロの貯蓄率を高めて資本蓄積を促進し長期的な成長率を高める。ただし、積立方式への移行がマクロの貯蓄率を高めることは、利子率の低下をもたらし、積立方式の方が有利であると判断した初期の状況が変わってしまうのではないかという見方もある。そこで、制度の移行に伴う利子率等の変化を内生化し、かつ海外との資本移動も考慮した「二国間世代重複モデル」を用いて修正積立方式から積立方式への移行をシミュレーションしたところ、移行した場合の方が貯蓄率や成長率が高いという結果となった。(図表10・図表11)
当然のことながら、前述の結果はどのような仮定を設けるかによって変わり得るものであり、幅をもってみる必要がある。例えば、老後の生活に備えて予め貯蓄をすることのない近視眼的な個人を前提とすれば、公的年金を廃止して民間の積立方式による制度に任せるとすると、マクロの貯蓄率は低下する可能性もある。また、財政方式の選択に当たっては、その他の特徴も考慮する必要がある。おおよその傾向として、積立方式は、世代間の再分配がなく、人口構成の変化に対し中立的であるが、インフレや利子率等の経済変動の影響を受けやすく給付の実質価値を維持することが困難であるという特徴を有する。一方、賦課方式は、世代間の再分配が行われ、少子・高齢化の状況下では世代間の負担の格差が生ずるが、インフレや利子率等の経済変動の影響に対し給付の実質価値を維持しやすいという特徴を有する。
(積立方式への移行を巡る問題)
修正積立方式から積立方式に移行する方法には、保険料引上げスケジュールの前倒しや給付水準の引下げ等により給付債務に対する積立金の比率を高めて積立要素を拡大する方法と、公的年金の一部の財政方式を積立方式に移行する方法が考えられる。後者については、さらに、財政方式を積立方式に移行した部分について、公的年金として運営する場合と、民営化(公的年金の該当部分を縮減)する場合に分けられる。積立方式を選択する場合には、現実には次のような問題がある。
積立方式に移行する場合、過去期間に生じた年金の債務負担が顕在化するため、後世代の負担となるもの(厚生年金の2階部分全体では 350兆円(平成11年度末)に達する)を、追加的に主として移行期の世代が負うという「二重の負担」の問題が解決される必要がある。この解決方法の1つとして、数十年にわたり段階的に移行し、負担を軽減していくことが考えられるが、いずれにせよ二重の負担を負う世代が、その負担を受忍できる程度として同意できるか否かにかかっている。(図表12)
また、積立方式に移行して民営化する場合には、老後の生活に備えて予め貯蓄をすることのない近視眼的な個人を前提とすれば、マクロの貯蓄率は低下する可能性もあるほか、積立金の規模が拡大する場合には、金融・証券市場で運用する資金量が大きくなり、金利等を通じて経済に与える影響を考慮する必要がある。
さらに、企業年金の役割を拡大するかたちで公的年金の一部を民営化する場合、加入について強制性がなくなることから、財政基盤の不安定な中小企業等においては導入されない恐れがある。このため、例えば、民営化された年金の導入を促進するための税制等の措置を採ったり、導入できない保険者のために公的年金を一部残したりする等の対策を別途検討する必要がある。
(財源を巡る問題)
公的年金の財源は、現行では基本的には社会保険方式によっているが、税方式に切り替える考え方もある。個人の生涯の税負担が等しいという前提の下で、社会保険方式(労働所得に課税)、支出税方式(消費を課税ベースとした直接税)及び所得税方式(労働所得と利子所得に同率に課税)という3つの方式が経済パフォーマンスに与える影響をみると、1人当たり産出量が最も高いのは支出税方式、その次は社会保険方式であり、最も低いのは所得税方式であることが示されている。所得税方式が社会保険方式よりも低い産出量となるのは、所得税方式では利子に課税されることから、社会保険方式と比較して将来時点の労働所得や年金給付が割高に評価されて総資産の現在価値が上昇し、消費が増大する分だけ貯蓄が減少して資本蓄積が阻害されるためである。また、支出税方式が社会保険方式より高い産出量を実現できるのは、いずれの方式も生涯消費を課税ベースとする点では同じであるが、支出税方式では引退期間中にも課税されるため、負担が勤労期間に集中する社会保険方式と比べて貯蓄が増大し、資本蓄積を促すためである。このほか、税方式による場合、拠出に関わらずに給付を行うことから、未納・未加入による無年金者等をなくすことができる。
しかし、社会保険方式には、拠出と負担の関係が明確で保険料と給付の均衡を確保しやすく、拠出についての国民の合意を得やすいという長所がある。一方、税方式は、財政方式が賦課方式となるため、世代間の格差を拡大するほか、保険料を納めてきた者との間で不公平が生ずるという無視できない欠点がある。また、現実的には保険料収入に相当する巨額の税財源を今確保できるのかといった問題や、一般財源を用いる他施策との競合や景気変動に伴う税収の変動などのため長期的な財源としての安定性に欠けるという欠点もある。
イ.公的年金制度が労働供給に与える効果
(支給開始年齢及び在職老齢年金制度)
まず、支給開始年齢や在職老齢年金制度が高齢者の労働供給にどのような影響を与えているかについてみてみる。
現行の老齢基礎年金及び老齢厚生年金の支給開始年齢は65歳であり、60歳~64歳の間は特別支給の老齢厚生年金が支給されている。この特別支給の老齢厚生年金については、退職して厚生年金から脱退すれば全額支給されるが、在職して厚生年金に加入していればその賃金額の増加に応じて賃金と年金の合計額が増額される仕組みとなっている。具体的には、在職中は2割の年金の支給停止となり、年金月額の8割と賃金の合計額が22万円までは8割の年金と賃金が併給されるが、これを超えて合計額が34万円となるまでは賃金の増加2に対し年金額1が停止され、さらに34万円を超えると賃金が増加した分だけ年金は支給停止される。(図表13)
労働省「平成8年高齢者就業実態調査」により、高齢者男性の年金の受給状況と就業率の関係をみると、年金を受給していない者の就業率は受給している者のそれと比較して、60歳~64歳で30%ポイント弱、65歳~69歳で16%ポイント強だけ大きくなっている。また、経済企画庁経済研究所「高齢化の経済分析」によれば、就業行動に対して公的年金受給額は有意にマイナスの影響を与えている。これらの結果から考えると、年金給付は就業率を低下させている可能性があると言える。就業希望者がまだ相当いる年齢階層について一定の年齢を超えた者を全て就労能力を喪失した者とみなす制度設計は、個人のもつ能力や意欲を年齢に関わらず発揮することを妨げているという点から問題となるだけでなく、労働供給を阻害するという意味においても問題がある。(図表14・図表15)
したがって、労働供給をできるだけ阻害しないよう、定年年齢等と支給開始年齢との接続に配慮しつつ、高齢者の雇用環境の整備状況及び平均寿命の伸びに応じた支給開始年齢の引上げや60歳代前半の特別支給の老齢厚生年金の廃止について、検討する必要がある。なお、60歳代後半の在職中の年金給付については、稼得収入があること、少子・高齢化の進展の中で年金制度を支える人をできるだけ増やす必要があることなどから、保険料の納付を求めるとともに、在職老齢年金制度の導入を検討すべきである。
(第3号被保険者制度)
次に、第3号被保険者制度が女性の労働供給にどのような影響を与えるかについてみる。
第3号被保険者制度とは、女性の年金権を確立することを目的として、1985年の改正により導入されたものであり、被用者の被扶養配偶者は、被用者が納める厚生年金等の保険料により独自に基礎年金を受けることができるというものである。社会保険である公的年金においては、負担能力がある者に負担を求め、必要性を考慮して給付を行うという考えに立って所得再分配が行われており、所得のない専業主婦に必要な費用は被用者全体で負担する仕組みになっているわけである。しかし、被扶養配偶者であるためには、労働時間が通常の就労者の4分の3未満で、かつ年収が 130万未満であることが必要であり、この条件を満たさない就労者は保険料納付義務が生ずることから、有配偶のパートタイム労働者は、年収が 130万円未満となるよう就労調整を行うなど、労働供給が阻害されているのではないかという指摘がある。
労働省「平成7年パートタイム労働者総合実態調査報告」により、パートタイム労働者の平均年間賃金額をみると、110万円以上130万円未満である者の割合は 3.7%であり、130万円以上140万円未満である者の割合( 2.8%)と大きな差はみられず、社会保険の被扶養配偶者の適用基準を理由として実際に就労調整が行われている可能性は低い。しかし、同報告により、パートタイム労働者の年収調整の状況とその理由をみると、30.0%が「就労調整をする」としており、そのうち40.1%が「健康保険の加入義務が生じる」ことを理由としており、厚生年金と健康保険の被扶養適用基準額が同じ130万円である ことに鑑みれば、少なくとも意識の面では就労調整の理由の1つとなっていると考えられる。また、90万円以上100万円未満である者の割合(20.9%)と比べて、100万円以上110万円未満である者の割合(7.7%)が相当に小さいことから考えて、税制や企業の配偶者手当の基準額である100万円の近辺で既に就労調整が行われており、それよりも高い130万円の近辺では顕在化していないだけであるという可能性もある。(図表16)
そこで、労働供給を阻害しないという観点に立てば、第3号被保険者本人からも定額の保険料を徴収することが考えられる。しかし、専業主婦のように所得のない者に負担を求めることは適切でないという考えがあるほか、女性の年金額が現実には相当低い水準となっていることも考え合わせると、現状では所得の低い者にまで負担を求めていけば無年金・低年金の高齢女性が発生することが予想されるなど、公的年金の所得保障機能を低下させるという可能性がある。
したがって、まず、育児環境の整備、介護施策の充実、男女の就労条件の均等化など女性の働きやすい環境を整備していく必要がある。その上で、ライフスタイルの多様化に応じて、就労女性との負担の公平性や有配偶者の労働供給の促進という観点からも第3号被保険者制度について検討していく必要がある。
ウ.公的年金制度の規模の縮小による効果
公的年金制度の規模の縮小がマクロ経済に与える影響は、長期的な視野をもつ個人を前提とすれば、積立方式に移行することに等しくなると考えられる。したがって、公的年金の規模を縮小することは、一定の前提の下で資本蓄積の経路を通じてマクロ経済に望ましい影響をもたらす。さらに、公的年金の規模の縮小が成長率を高める場合には、一層の年金財政の改善を可能にし、保険料負担の軽減、成長率の上昇という良循環をもたらすことも考えられる。
公的年金の規模の縮小に当たっては、給付水準の見直し、スライド制の見直し、支給開始年齢の引上げ、部分年金の廃止等の様々な方法が考えられるが、いかなる方法を採用するかに応じて、労働供給の経路を通じたマクロ経済への影響は異なると考えられる。
そこで、マクロ経済モデルを用いて、給付水準の段階的引下げ及び特別支給の老齢厚生年金報酬比例部分の支給開始年齢引上げにより公的年金の規模を縮小した場合の効果をみる。現在、就労と年金の接続の観点から特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分については、定額部分と異なり2001年度(女性については2006年度。以下同じ)以降も60歳から支給することとされているが、今後労働力人口の減少が見込まれる中で高齢者の本格的な就業を促進するために、報酬比例部分の支給開始年齢も引き上げていくべきであるという考え方がある。この考え方に基づき、特別支給の老齢厚生年金報酬比例部分の支給開始年齢を定額部分と同様に65歳に段階的に引き上げるとした上で、2025年時点の全受給者の平均年金額の(平均賃金に対する)水準が、今後新たな改革を行わないとした場合よりも10%程度低下するよう平均年金額を2001年から段階的に引き下げることとする。
これとともに、年金制度の改革のみを切り離して考えるのではなく、医療等の他の社会保障制度の改革や、経済構造改革の効果も含めた総合的な視点で考える。すなわち、経済構造改革等が進展し、女性や高齢者の労働力率の上昇や技術進歩率の上昇等が実現することとする。
この改革による影響をみると、次のとおりである。
・ 2025年度時点の社会保障負担対国民所得比率は、改革を行った場合は約16%(96年度は13.2%)に留まるが、改革を行わなかった場合はそれよりも約8%ポイント高まる。
・ 将来世代が生涯を通じて受け取るネットの年金額(年金受取額-年金保険料負担額)の生涯賃金に対する比率をみると、今後の長期的な賃金上昇率と労働力伸び率の和が金利水準にほぼ等しい状況において、改革を行わない場合には支払超過となるが、改革を行った場合には受取超過となる。
・ 既に年金を受給している者に関しては、原則として、改革により抑制されるのは年金額の伸びであり、現在受給している年金額が引き下げられるわけではない。また、将来的には、物価の上昇に応じた引上げが想定されており、年金額は現状より上昇する。さらに、年金制度の成熟化に伴って加入期間が伸びることにより、年金額が上昇するといった要因もある。このほか、経済成長による賃金上昇を勘案するのであれば、これも年金額の上昇要因となり得る。
(具体的な計数でみると、モデル年金の水準は2025年度時点で 500万円強となっている。この増加分は物価上昇分、賃金上昇分などから構成されている。)(図表17)
なお、数値については、技術進歩率や労働供給の弾力性等の前提の置き方により変わり得るものであり、幅をもってみる必要がある。
当然のことながら、ここで示された改革は1つの手法に過ぎず、公的年金の規模を縮小するためにどのような手法を採るかは国民の合意によるべきである。いずれにしても公的年金の規模を縮小することは、経済パフォーマンスを改善し、社会保障制度運営の安定性を高める可能性があるものと考えられる。
3 公的年金制度改革の視点
最終的にどのような制度を選択するかは、国民の選択に委ねられるべき問題である。年金制度は約60年の長期にわたる制度であり、その間に給付水準が頻繁に変動するようでは、老後の生活設計に大きな影響を及ぼすとともに、制度に対する信頼を失うこととなる。また、年金制度は長期的な経済パフォーマンスに影響を与える要素でもある。
したがって、制度改革に当たっては、過去の財政再計算の前提や問題点、制度改革と経済パフォーマンスの関係等について、国民に十分な情報提供を行った上で、長期的な視点に立って合意を形成していくことが必要である。
(4) 医療制度改革の視点
1 医療制度の現状
医療制度は、所得水準に関わらず誰でも公平に医療を受けられるようにするという役割を担っている。しかし、近年、国民所得の伸びが毎年1%台にとどまっているのに対し、国民医療費は平均6%の伸び率で増加しており、将来的にも、高い経済成長が期待できない中で、人口構成の高齢化、医療技術の高度化などにより医療費は相対的に高い水準で伸びるものと考えられる。特に、老人1人当たりの医療費はそれ以外の者の5倍に相当し高齢化の進展とともに8%程度で増加しており、現行制度のままでは2025年時点には老人医療費は国民医療費のおよそ5割に達することが見込まれている。また、我が国の薬剤費比率は、薬剤使用量の増大や相対的に高価な新薬への移行等により、累次の薬価引下げにも関わらず国際的にみても高い水準にあり、薬価基準制度の根本的な見直しが課題となっている。このような経済基調と国民医療費の構造的な不均衡は、医療保険財政を悪化させており、医療保険制度を維持できなくなる事態も懸念されている。また、医療費の増大に伴い保険料負担も上昇し、過大な負担となるものと考えられる。(図表18)
さらに、現在の老人医療費の大部分は現役世代の負担となっているが、高齢化の進展等により老人医療費が増大する中で、現役世代の負担は一層増大することが見込まれる。このため、医療資源の非効率な使用をもたらしているいわゆる「社会的入院」等について、介護施策の充実等により解消を図っていく一方、高齢世代と現役世代の負担の公平性等の観点から、老人医療費の費用負担の仕組みを見直すことが必要となっている。
2 競争原理を活用するための適切な管理
(医療サービスの特性)
一般的にサービスは市場競争に委ねることにより効率的な供給や配分が達成されるが、医療サービスについては「全ての国民が比較的安価な自己負担で自由に医療サービスを受けることできる」という目的を達成する必要があることなどから、社会保険制度を通じた費用保障が行われてきた。しかし、行われた診療行為のそれぞれについて費用を償還する従来の出来高払い方式のもとでは、医療提供主体間で競争を通じた効率化のインセンティブが働きにくく、非効率な資源配分が生じると考えられる。
また、医療サービスは、市場競争では医療提供者と患者との間の情報の非対称性等が要因となって、過剰供給が生ずる可能性がある。すなわち、患者は医療について十分な知識がないため、自分の健康状態や治療の必要性等を十分知り得ない上、医療提供者は医療行為の効果がある限りはサービスを提供しつづける傾向があるため、社会的に最も望ましい供給水準と比較して過剰となる傾向がある。
このため、従来より政府が保険医療機関の指定等の保険者機能の一部を一元的に担い、医師数や病床数等の供給量や診療報酬等の価格を管理することにより医療費が抑制されてきたところである。
(医療制度の効率化)
前述のように我が国の医療制度は、医療費の増大に伴う医療保険財政の悪化や世代間の負担の格差という問題を抱えており、国民医療費の伸びと経済成長との均衡を図る必要がある。そのためには、我が国の医療制度の非競争的な状況を踏まえると、供給及び需要の両側面において従来よりもより医療資源を無駄なく活用できる競争原理を基本とした効率的な制度を構築することが重要であると考えられる。
具体的には、
・ 医療機関や医師等の資源をより適切に配分するため、医療機関の役割を明確化するとともに、専門医制を確立し、それに対応して診療報酬制度を多様化する
・ 診療報酬について効率化のインセンティブをより働かせるため、出来高払い制度に代えて包括払い制度を拡大していく
・ 患者の選択を通じた医療機関や医師等の間の競争を促進するため、患者への情報提供を推進するとともに、患者の情報能力や評価能力を高めるために保険者の機能を強化する
などが挙げられる。これらは、医療保険制度及び医療提供体制に広くまたがる問題であり、医療機関の機能、診療報酬制度、保険者機能、政府規制などについて個別に検討するだけではなく、各制度の補完的な関係等を十分に踏まえながら、総体として検討していくことが必要である。
(医療提供体制の機能分化とそれに対応した診療報酬体系)
現行の医療提供体制及び診療報酬体系は、疾病の状況等に対応した医療の質の違いが十分に反映された仕組みとなっていないため、患者が病状に合った適切な医療機関を選択することが容易でないなど資源配分上の無駄が生じている。例えば、外来患者の大病院への集中やはしご受診、医療機関における高額医療機器への過剰投資などの問題である。
したがって、患者の疾病の状況に応じて適切な医療機関への流れができるよう、地域医療支援病院、特定機能病院、地域医療を担う病院及び診療所の機能を明確化するとともに、専門医制を確立することが必要がある。例えば、診療所や地域医療を担う病院をかかりつけ医機能に重点を置いた医療機関と位置づける一方、二次医療圏単位では、病床や高額医療機器の共同利用など通じて地域医療を支援する病院(地域医療支援病院)を整備し、相互の機能分担と連携を強化する。また、特定機能病院は高度な医療に特化する。次に、診療報酬体系においては、例えば外来について、地域医療支援病院及び特定機能病院は専門的機能を、地域医療を担う病院及び診療所はかかりつけ医機能をそれぞれ重点的に評価するなど、機能の違いを診療報酬体系に反映させていく必要がある。また、医師の経験や技術水準に関係なくほぼ一律に定められていた診療報酬体系を、医師の専門性、医療技術の難易度、患者の重症度などに応じたものにしていくことも必要である。
一方、従来は行われた医療行為に対応した「出来高払い」が一般的であったが、サービス供給の効率化に対するインセンティブを高めるため、「包括払い」を患者の病状が比較的安定している慢性疾患の場合に拡大していくことが必要である。さらに、慢性疾患以外についても、標準化できる疾病について順次DRG(Diagnosis Related Groups(診断群別疾病分類):統計的に有意な入院日数差を示す手術・措置と診断のグループ)のような診断群別の包括払いを検討することも必要である。なお、包括払いはサービス提供の効率化に資する一方で、医療提供者主体が財政リスクを負担するため、必要な医療サービスの量的減少や品質低下をまねく可能性もある。このため行政機関や保険者が中心となって医療の質の確保に関する監督機関を設けることなどの工夫を合わせて検討する必要がある。
(情報提供の推進と保険者機能の強化)
患者が自らの判断で医療機関を選択することを通じて医療機関相互に競争原理が機能し、適切な医療が受けられるようになるための基礎的な条件として、患者が診療について十分情報提供を受けた上で医療に関する技術評価や個別医療機関の評価を行う能力を持つことが必要である。
まず、医療従事者は診療ごとの患者への治療方法に関する情報開示を行い、適切な説明と患者の理解に基づく医療を定着させるとともに、カルテやレセプト情報を患者に提供することが求められる。また、患者による医療機関の選択に資するため、医師の専門等医療機関の機能に関する事項の広告を認めていくことが必要である。次に、個人には情報能力及び評価能力に限りがあるので、保険者は、医療機関の施設や技術水準等に関する情報提供を行ったり、医療機関の質を評価し公表することによって患者の選択能力を高めていくことが求められる。また、現在第三者機関において診療の質や患者の満足等の項目について病院機能の評価事業が行われているところであるが、その一層の充実を図り、評価結果を公表することも考えられる。政府は、保険者の活動を支援するための基盤を整備する役割を担っており、技術評価に関する調査研究体制を整備するとともに、技術評価の基礎となるデータベースを整備し、保険者、医師及び市民に広く提供していくことが求められる。(図表19)
さらに、現在の国民皆保険制度のもとで医療機関間の競争を促進していくためには、保険者は、被保険者のエージェントとして医療機関を評価し選別する機能を持ち、そのような評価を含めた情報を被保険者や医療機関に提供するだけでなく、それらに基づいて医療機関を選定することも検討すべきである。その前提として、都道府県知事が一括して保険医療機関を指定する現在の仕組みを、保険者が医療機関を選択できるシステムに改めることが必要となる。ただし、保険者による選択は、患者の選択をサポートする観点から行われるべきであって、例えば、財政的理由から患者の医療へのアクセスを制限することがないよう、両者の整合性を確保していく必要がある。
3 介護施策の充実
高齢者介護の問題は、老後の最大の不安要因であり、介護を社会全体で支える仕組みとして介護保険制度が創設されたところである。
これまで、急増する要介護高齢者のニーズに対して介護サービスの供給が追いつかず、医療サービスで対応せざるを得なかった結果、いわゆる「社会的入院」(急性期の治療が終了しても介護ニーズがあることなどが原因で、退院することなく一般病院のベッドを使用すること)が生じていた。これは、要介護者が生活施設としては決して快適とは言えない環境で暮らすことを余儀なくされているという点で問題となるだけでなく、医療資源の効率的な利用の観点からも問題となっている。介護保険制度の創設により社会的入院が解消されれば、要介護者は住み慣れた自宅や生活環境の良い介護施設において生活できることとなり、また、医療の側からみても、医師、病床等の医療資源を治療機能に特化し効率化を図ることができる。また、介護保険制度では、虚弱の高齢者に対する給付も対象になっており、高齢者が要介護状態に陥るのを事前に予防し、結果的に高齢者の医療や介護に係る費用の負担を軽減することもできる。
さらに、国民経済全体からみると、介護保険制度は、前述のとおり、新規産業分野としてシルバービジネスの成長を促し、介護従事者を介護労働から解放することにより労働供給を増大させる可能性があるなど、中長期的な経済にも好ましい影響を与えるであろう。
介護保険制度が2000年度から円滑に実施されるためには、それを裏付ける介護施設やホームヘルパー等のサービスの供給基盤が整備されることが必要である。そのためには、まず、2000年度の法の施行までに、全国の地方自治体が介護需要を踏まえて94年に作成した老人保健福祉計画の集大成である「新ゴールドプラン」を着実に達成することが重要である。従来の補助金の枠組みでは困難な場合には、補助金の弾力的運用により既存施設を活用するなどの方策も視野に入れながら進めていくことも必要である。次に、介護保険法の施行後には、市町村は地域の介護ニーズを調査した上で、新たなサービス基盤の整備目標を定めることとしており、これをベースとして計画的に整備を進めていくこととなる。これと並行して、民間事業者の参入が促進され、サービス供給基盤の拡充においても民間部門の創意と工夫が活かされることが期待される。こうした総合的な基盤の整備により、老後の介護の不安に応えられる体制が実現していくものと考えられる。
(5) 社会保障制度の総合的見直し
(社会保障全体としての効率化・公平化)
社会保障制度を構成する年金、医療、介護等の各制度は、それぞれ固有の目的を達成するために、それぞれの制度ごとに発展してきた経緯があり、制度間で給付や負担の調整が十分に行われていないという問題がある。したがって、社会保障制度を改革するに当たっては、年金、医療、介護等の各制度を個別に検討するだけでなく、社会保障制度全体としてすき間や無駄、重複が生じていないか、また、そのコストが経済・財政と整合性のとれたものとなっているかという観点から、社会保障制度を総合的に見直すことにより、効率化と公平化を図る必要がある。
例えば、現行制度では、年金受給者であっても社会福祉施設に入所している間は負担能力に応じて食費等生活に必要な経費を負担しているが、費用徴収の在り方について見直す必要がないか、また、要介護高齢者が介護施設を利用する場合に、社会福祉施設と保健・医療施設の間で利用者負担金に格差が生じているため、必ずしもその目的に沿った利用がなされていないのではないか、などの問題が挙げられる。
また、社会保障構造改革に当たって、年金を基盤にした経済的に自立した高齢者像を前提として、高齢者にも医療及び介護において相当の自己負担を求める方向でいくのか、年金水準を切り下げ、医療及び介護の自己負担を軽減していくのかといった、各制度間の整合性を図ることも必要である。
(社会保障制度と他施策との連携)
社会保障施策と他施策との連携を図ることによりニーズを充足し、社会保障の効率化を図ることができる。
例えば、介護サービスのような将来的に供給不足が予想されるサービスの基盤を整備するに当たり、都市・住宅のバリア・フリー化と一体的に推進することにより限られた財源の中でより多くのサービスを供給することができる。また、リバース・モーゲージの普及を図ることにより、平均的に高水準に達している高齢者の土地、金融資産等のストックを老後の生活保障に有効に活用する道を開くことができる。

