堺屋太一経済企画庁長官講演「日本経済の今日と明日は」於:イェール大学(米国コネチカット州ニューヘブン)、 2000年5月
注)実際の講演は本稿を要約した形で行われた。

本日ここで「日本経済の今日と明日は」について話す機会を与えられたことは、私の大きな歓びとするところです。というのは、この場所が積学の府、イェール大学だというだけではなく、今こそ日本経済の現状と将来を、米国のそして世界の人々に語らねばならない時代に当たっている、と考えるからです。
I.日本経済の「今日」
森新内閣は小渕内閣の積極経済政策を継続する
周知の如く、「人柄の小渕」といわれて国民に親しまれた小渕恵三首相は、4月2日病に倒れ、小渕内閣は終了した。発足以来615日、約1年8ヶ月、小渕内閣は不況と戦い続け、快勝とまではいかないものの、劣勢から優勢へと盛り返した。景気の本格的な自律的回復を目前にして、また自ら主催する予定の沖縄サミットを真近にして不意の重病に倒れたのは、小渕首相もさぞ無念であろうと思う。
しかし、小渕首相を継いで内閣首班となった森喜朗氏は、全閣僚を留任させ、小渕内閣の内外政策を継承することを確認している。特に経済政策においては、景気の回復と経済構造の改革を強力に推進して行くことを所信表明でもはっきりと述べている。私自身も小渕内閣から継続して経済政策を担当する大臣として、これまでの経済政策の継続発展に努める決意である。
2000年に入ってからの日本経済は、われわれの予想していた通り自律回復の動きが拡まっている。(図1)
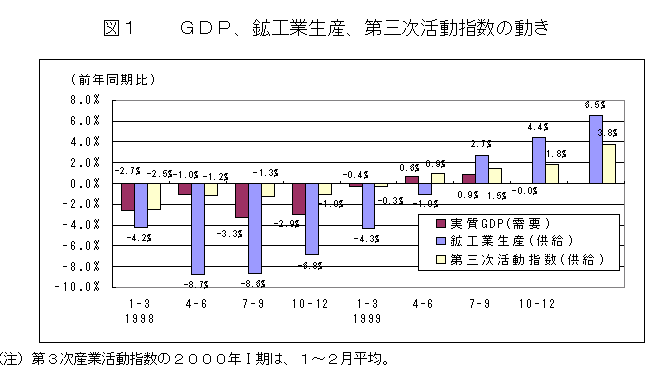
まず需要面を見れば、消費は99年10~12月期に大きく落ち込んだが、2000年1~3月には回復、閏年効果を除いても前年同期を上回るようになった。特に新車登録台数やパソコンを中心とする家電の伸びが目に付く。住宅建設も好調を維持しているし、貿易はアジア向けを中心に大幅に伸びている。何よりも心強いのは、長い間減少を続けていた設備投資が昨年10~12月期から反転上昇に転じたことだ。設備投資の先行指標といえる機械受注(船舶、電力を除く民需)は、10~12月期には9四半期ぶりに前年同期を上回った。2000年1~3月期にもこの傾向は続いている。日本でもIT関連を中心とする新時代に向けた投資拡大の気運がようやく現れ出した。
需要面以上に顕著に拡大しているのは、生産面だ。鉱工業生産は98年度には前年より7.1%も縮小したが、99年7~9月期からは前年同期を上回り、2000年に入ってからは6%程度前年水準を越えるようになっている。在庫調整が完了した上、日本経済の先行き好調の予想とアジア向けを中心とした輸出の拡大のためである。また第3次産業活動指数も99年4~6月期から前年同期を上回るようになり、2000年に入ってからは一段と好調になっている。
企業の経営も改善に向かっており、全企業経常利益は99年度下半期には前期に比べて16.8%増の見込みである。また全企業の売上高利益率は98年度の1.97%に対して99年度には2.31%、2000年度には2.61%へと上昇する見込みである。
しかし、すべての指標が明るいわけではない、雇用情勢は依然厳しく3月末の完全失業率は4.9%、日本としては戦後最悪である。もっともここにも明るい兆しはある。99年12月から有効求人数や求人広告件数が増加すると共に、所定外労働時間も増加している。経済企画庁が行っている組織的聞取り調査の一つ「景気ウォッチャー」からの報告によれば、派遣業では既に人手不足感も出ているという。失業率が景気動向に後遅するのに対して、所定外労働時間や派遣業は先行する。この点を考慮すれば、雇用の面でも回復して来ている、と見ることができる。
私は日本経済は長い不況を脱し、ようやく離陸の状況に入ったと見ている。しかし、それはまだ滑走路から少しばかり浮揚したに過ぎず、安定した飛行態勢に入るまでにはなおかなりの日時を要するだろう。それまでの間は、財政と金融面での積極的な支援が必要と考えている。
ここで重要なことは、単に景気を回復させるだけでなく、日本経済の構造改革と経済社会の組織および機能の変革を進めなければならないことだ。つまり規格大量生産型にでき上がった日本の社会を多様な知恵の時代にふさわしい形に変えることである。それは恰も鈍重な大型飛行船を、運動性の高いジェット機に造り変えるような手間と費用と勇気の必要な作業である。日本政府がこの2年間に積み上げた巨額の公的債務もそのためには避けられないコストであった。そしてそれが完成すれば十分に処理し得るものでもある。
では、なぜ日本経済はこれほど深く長い不況に喘がねばならなかったのか。それに対して小渕内閣は何をして来たのか、そしてまた、これから森内閣は何をしようとしているのか、詳しく申し上げたいと思う。
(2)98年危機の凄まじさ
1年9ヶ月前の98年7月末、小渕内閣の発足した時、日本経済はデフレスパイラルの入口に立っていた。多くの金融機関は膨大な不良債権を抱え、自己資本比率の改善のために貸出しを大幅に減少しなければならない状況だった。これによって、一般企業への資金供給は減少し、設備投資が激減、雇用の危機も迫りつつあった。中でも問題なのは、大企業からの発注や支払いが減少した中小企業の中には、経営そのものは健全でありながら資金繰りの行き詰まりから倒産する企業が続出し出したことだ。日本経済は、経済の血液ともいうべき資金の循環が、心臓に当る金融機関の機能悪化によって枯死しようとしていたのである。
それだけではない、日本経済の各部門に深刻な問題があった。流通大手や建設大手の中にも土地や株式の値下がりで債務超過に陥っていた企業がいくつもあった。大手製造業の多くも過剰設備と過剰負債と過剰雇用を抱え、需要の減少や販売価格の下落で赤字経営になっていた。街の商店街もホテルやレストランも売上の減少に苦しんでいた。加えて前年(97年)7月からはじまったアジア通貨危機によって、日本の輸出は減少、アジアへの投資も壊滅的な打撃を受けた。
こうした状況を反映して株価は急落、小渕内閣発足から72日目の98年10月9日には日経平均が12,879円にまで低下した。前年同日に比べて約4,500円、25%の下落である。また、日本円に対する信頼も損なわれ円の対米ドル為替レートは98年8月には1ドル147円21銭になった。95年4月の天井1ドル80円34銭に比べると3年4ヶ月間に45%の低下である。このため経営者は自社の生き残りのために規模の縮小と投資の抑制に走り、国民は将来不安に脅えて消費を抑制して貯蓄に走り、系列発注先と金融機関に見放された中小企業の経営者の中には自ら命を絶つ者さえ出る有様だった。
98年秋、私は「今、日本経済はデフレ・スパイラルの入口を通り過ぎようとしている」と表現した。不況の渦にはまり込む危険があった。小渕内閣が大胆かつ迅速に対策を購じなければ「日本発世界不況」が生じた可能性も十分あったわけである。
(3)「三重の不況」-短期循環の下り坂
戦後50年、急成長と大発展を続けて来た日本経済が、これほどに悲惨な状況に陥ったのは何故か、そこには「三重の不況」が存在したからである。
まずその第1は、短期循環における下向段階に入っていたことだ。90年のバブル景気の崩壊から大下降に入った日本経済も、94年からは緩やかな回復に転じ、95年、96年は好調に推移した。阪神大震災の復興需要、携帯電話などの新商品の普及、そして95年4月以降の円安ドル高などが日本経済に有利に働いた。このため日本のGDPは、95年度3.0%、96年度4.4%という高い伸びを示した。株価も上昇し、日経平均は96年4月には2万2千円台にまで上昇、95年の最安値に比べると56%の上昇となった。
こうした状況を見て、当時の橋本内閣は、日本経済の回復を信じ、財政再建の好機と判断した。橋本内閣が気忙しく財政再建に着手し、消費税の引き上げや医療保険負担の増大などで国民経済に約9兆円の負担増を求めた。
しかし、95・96年の景気上昇は、短期要因によるもので、構造改革は進んでいなかった。このため、97年1~3月頃を頂点として景気は急速に悪化、7月からはアジア危機による打撃も加わった。97年11月には大手銀行の一角を占めた北海道拓殖銀行や4大証券の一つであった山一証券などが破錠するに至って、金融システムに対する不安が一挙に拡がってしまった。
これに対して政府は、97年12月には30兆円の金融再生スキームを作り、特別減税を実施したりした。当時は、この程度の糊塗策で日本経済の再生が可能と考える浅い見方が一般的だったのである。
(4)成長から成熟へ――大波動転換の後遺症
第2の不況は、80年代末のバブル景気崩壊の後遺症が処理されずに残っていたことで引き起こされた「バランスシート不況」だが、その実態は成長経済から成熟経済への転換で生じた構造不況である。
1980年代の日本は、規格大量生産型の近代工業分野では、巨大な生産力と強力な国際競争力を誇っていた。しかし、このために日本は、産業経済を規格大量生産型にしただけではなく、教育においても規格大量生産の現場で働くのに適した辛抱強く協調性の強い人材を育成する制度を作り上げた。
80年代の日本では生産(供給)が伸びるほど需要は伸びず、貯蓄が貯り、貿易黒字が累積して、猛烈な円高となった。
過剰となった資金の一部は外国にも流れたが、大部分は国内の株式と土地に向かった。このため、88年・89年には株価と地価が暴騰、いたるところに株成金・土地成金ができた。最高だった89年末の東京証券取引所一部上場株式時価総額は611兆円に達していた。また、90年末の日本国の土地資産総額は2,365兆円、面積が25倍ある米国国土総額の3.3倍に達していた。
しかし、こうした土地と株の値上がりは長期的な採算性の裏付けの無いバブル現象だった。
一国の経済が成長期から成熟期に換わる時、バブルが発生し易い。成長が貯蓄を生み、財蓄が投資になってさらなる成長を促し、それが所得の増加と財蓄の拡大をもたらすという成長循環の中で、投資対象が減少すると貯蓄だけが高水準を続け、資金過剰が生じるからである。
80年代末の日本経済も正にその通りだった。この種のバブルははじけるまで膨らみ、膨らみ切ったところで不愉快な終り方をするものだ。日本の場合もその通りになった。株価は89年12月末の日経平均3万8,915円を頂上として劇的に下降、92年10月には頂上値の1/3になった。土地価格は、それより一年ほど遅れたが、東京圏や大阪圏ではほぼ同じくらいの比率で下落した。
この結果、株式や土地を大量に購入していた建設会社や流通大手は巨大な値下り損を抱え込んだ。また、土地を担保に融資していた金融機関も膨大な不良債権を背負うことになった。
もし、日本の経営者と政治家、官僚に優れた先見性と強い勇気があれば、93年までに金融機関に公的資金を注入して、不良債権の処理を行うべきであった。しかし、当時の日本では選挙法の改正が優先された。経営者や官僚は不良債権処理を断行する勇気を欠き、再び株価や地価が上昇することを祈るばかりだった。結局、90年代前半に処理されたのは住宅金融専門会社といわれる銀行などの出資会社と少数の小規模金融機関だけである。
98年に小渕内閣が発足した時点では、金融機関をはじめ、多数の企業が膨大な不良資産を抱えたままであり、その処理のため、新たな投資や新規事業には手を出せない状況だった。
前述の金融機関の不良債権が資金循環を阻害する「心臓病」だとすれば、各種企業に溜まった評価損は、経済が成長から成熟に転換する時に生じた贅肉とコレステロールのようなものだ。日本経済を再生するためには、この贅肉を削ぎ、コレステロールを排出する苦しいトレーニングが必要だった。
(5)規格大量生産型社会の拘束
しかし、日本経済の当面する最も重大な問題は、規格大量生産型社会の組織的発想的束縛である。
明治維新以来100年余、日本は規格大量生産型の近代工業の育成に努めてきた。戦後これが結実、80年代の日本は人類史上でも最も完璧な規格大量生産型を完成することができた。日本の一人当り国民総生産は1987年にアメリカを抜き、人口1000万人以上の国では最高になった。失業率は3%を越えることがなく、貧富の格差は小さく、国際収支は70年代後半から黒字基調となり、為替レートの上昇にも拘らず、輸出は増え続けた。
それだけではない。経済の成長と工業化の進展に伴って人口の都市集中は進んだが、治安は良好で犯罪は減少した。社会福祉は充実し所得格差は縮小したのに、国民の向学心と勤勉さは失われなかった。そして80年代には公害防止や都市整備も急速に進んだ。80年代の日本は、「近代工業社会の理想」に最も近づいた国、といえるだろう。
日本がそうなり得たのは、そのための社会体制があったからだ。その第一は、官僚主導による産業育成だ。欧米に比べて遅れて近代工業化に乗り出した日本は、外国から優れた技術や制度を導入、官僚の主導のもとに民間企業に普及した。特に重要な役割を果たしたのは金融制度だ。1930年代から日本では全金融機関が政府の規制下におかれる一方、すべての金融機関が破綻することのないような保護が与えられていた。これは「護送船団方式」と呼ばれる。また、日本には個人預貯金総額の約30%を占める巨大な郵便貯金制度があり、その資金は官僚によって配分できるようになっていた。
こうした金融システムは、国民の資金を官僚主導で規格大量生産型社会の確立に注ぎ込む効果があった。また、破綻することのない金融機関は、大胆で長期的な金融を行うことができた。1960年代から、日本では大手銀行を中心とした企業系列ができ、各系列毎に総合商社、ゼネコン、自動車や電機メーカーなどを育成した。そしてそのそれぞれの企業がまた下請け、孫請けなどの系列を形成した。ここでは長期取引きによる信用が重んじられ、元請大企業から下請けの中小企業へと人事交流(天下り)や資本参加が行われていた。日本の産業組織には官僚主導で作られた「横」の業界協調と、金融機関や大手企業を中核とした「縦」の系列ができあがっていたのである。
日本の雇用慣行が終身雇用・年功序列となったのも、これと関係がある。金融的な支えによって大手企業が倒れることは滅多にないという条件と、系列の中での天下り人事が終身雇用を可能にしたのである。また、日本の企業経営が配当率を低く抑えて内部留保を厚くする先行投資型財務体質となったのも、系列の中で株式持合いが多く、相互に低配当を許容するようになっていたからである。
日本を優れた規格大量生産社会に育てる過程では、情報発進の東京一極集中や教育の没個性化も大きな意味を持っていた。情報発進を東京一極に集中した結果、全国に同じ情報が流れ、同じ規格の商品が大量に販売できた。また、小中学校の段階では通学区域によって特定の学校に強制入学させる制度によって、個性よりも協調性を、創造性よりも辛抱強さと模倣性を重視する教育を行った。
要するに、日本は規格大量生産型の社会を完成するために多くの制度と組織を作り上げた。ところが、80年代末、日本がそれに成功した時、人類文明の流れは規格大量生産から多様な知恵の時代へと変りつつあった。いわば日本の目指すゴールは空虚なものとなり、文明の進路からはずれていたのである。98年当時、日本の陥っていた深刻な不況の根底には、発展方向の喪失があった。このため日本は、新規創業の少ない、投資対象としても魅力の乏しい窮屈な国となっていたのである。
日本経済は心臓を病み、贅肉過多でコレステロールが溜まる体質的欠陥を持っていただけでなく、確立した組織が束縛となり、習得した機能が役立たなくなっていた。
日本経済の再生に立ち向かう小渕内閣には、こうした規格大量生産型社会のパラダイムを解消し、新しい多様な知恵の時代にふさわしいものに組み替えるという巨大な作業が課せられていたわけである。
II.経済再生の戦術と戦略
さて、以上のような「三重の不況」に見舞われていた日本経済の再生のために、小渕内閣は3段階の戦略を考えた。
第1段階は、直面するデフレスパイラルへの落ち込みを防止する緊急経済対策、第2段階は、その成果を受けて構造的な改革に着手しつつ自律的回復を推進する経済新生対策、そして第3段階は経済社会のパラダイムを根本から改革して新しい多様な知恵の時代にふさわしい経済社会を形成する新発展政策である。
(1)大胆な金融改革―日本社会の深部に関わる問題
まず第一は、98年のうちに採られたデフレスパイラルを回避するための緊急経済対策であり、その目標は99年度を「はっきりとしたプラス成長」にすることである。
この主な内容は、3つの分野から成り立っている。①金融再生、②中小企業等の倒産防止、③需要拡大である。
金融再生に関しては、これまでの「護送船団方式」を排し、市場競争による淘汰と発展の原則を適用することにした。つまり、債務超過の不良機関は破綻させる一方、それ以外の機関を再生強化するため公的資金を注入する、というものだ。このために政府は、98年10月、総額60兆円(2000年度予算における追加10兆円を加えれば70兆円)の金融再生スキームを設けた(図2)。破綻金融機関の預金者保護17兆円(2000年度で10兆円追加して27兆円)、破綻金融機関の処理に18兆円、そして健全金融機関の自己資本強化のための注入資金が25兆円である。
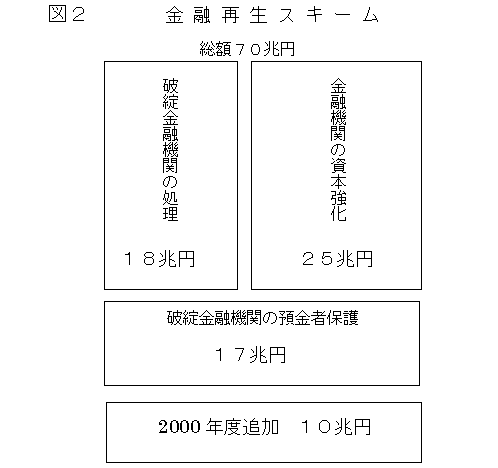
政府はこの方針に従って、これまでに日本長期信用銀行、日本債券信用銀行をはじめ十数の中小金融機関を破綻処理する一方、大手銀行等21行に約7兆9千億円の公的資金の注入を行った。
これは、緊急対策であると同時に、日本の経済社会の深部に関わる重大な改革でもある。
これに対する民間金融機関の反応は政府の予想以上に大きく、主要銀行の間では統合提携が急速に進んでいる。3年前には20行を数えた日本の大手金融機関は、大型地方銀行を志向する大和銀行を除いて4つのグループに再編され、それぞれ100兆円内外の資金量を持つことになるだろう。
このことは当然、大手銀行を中心とした「縦」の系列の解消にも連なる。99年度中に売却された持合い株の総額は10兆円以上と見られ、企業の下請け系列も緩みつつある。最近は、部品の発注をネットビジネスにする企業も現れ、系列外からの受発注が増加している。
このことは、日本のサラリーマンの生態にも大きな変化を与えている。企業の負担で官僚や取引先の社員を接待する社用族が急減、日本特有の高価な料亭やクラブを困らせている。日本文化の変化につながる可能性さえある大変化だ。
(2)中小企業政策の転換
小渕内閣の緊急政策の第二は、中小零細企業の倒産防止と新規創業の育成である。
日本にはかねてから中小企業借り入れ保証制度があったが、これに政府は、98年10月より新たに5000万円を限度とする無担保の公的保障を行う20兆円(2000年度の追加によって30兆円)の枠を設けた。景気の後退と担保土地価格の急落で、健全な中小企業でも必要な運転資金を引き上げられるケースが多かったからである。この制度によって98年12月から約1年、中小企業の倒産が激減、デフレスパイラルに日本経済が陥るのを防止する効果が大きかった。
政府はまた、中小企業政策の抜本的な改正も行った。新しい中小企業基本法は、中小企業の多様性に着目、新規創業やベンチャービジネスを、金融、情報、人材の供給の各面から支援することを主眼としている。
(3)需要拡大政策――公共事業と大減税
小渕内閣が不況との戦いの中で採った第3の緊急政策は需要の拡大、とりわけ公共事業の追加と大幅減税である。
もともと日本経済の中で公共事業の比率は高い。1998年度の実績では、GDPに占める公共事業(IG)の比率は約8%、アメリカの約2.5倍にも当る。だから政府支出による需要の拡大といえば、まず第1に公共事業だ。公的支出一単位当たりの需要創出の乗数効果も高いからだ。
小渕内閣もこの手法を採り、98年12月には大型補正予算を編成して3.8兆円の公共事業費を追加した。この大部分は地方自治体への補助金となり、地方自治体の補助裏負担が追加される。従って、98年度第2次補正予算によって追加された公共事業の総額は8.1兆円に達し、実質GDPを1.9%程度押し上げる効果をもつと考えられていた。
これと併せて、小渕内閣は99年度から大幅な減税を行った。個人の所得課税では、4兆円規模の恒久的減税を行った。これによって個人の所得に課せられる最高税率(国税、地方税を含めて)は65%から50%へと引き下げられた。また法人の所得に課される税率(同上)も実効税率を国際水準並みの約40%に引き下げ、約2兆円の減税を行った。
所得に課す税率を最高50%にしたことは、競争の結果としての可処分所得の格差を認める方向に動き出したことを意味する。
景気対策として特筆されるものは、総額2兆円に達する政策減税である。その中には住宅取得のために借入れたローン残高の一定割合を税額控除するものや、一定の電子機器の取得費用を即時償却できるものが含まれている。
以上のように99年度から実施された減税の総額は約9兆円に達したのである。
(4)99年度見通しは+0.5% ― はっきりしたプラス成長に
政府の大胆かつ迅速な経済政策と並行して行われたのが、日本銀行による金融緩和政策である。特に99年2月からは「ゼロ金利政策」を採り、コールレートは実質ゼロ金利となる0.02%にまで引き下げられ、10年ものの国債流通利回りもおおむね2%以下で推移している。
われわれ経済企画庁は、これらの対策によって、99年度の日本経済は「はっきりしたプラス成長」になるものと確信していた。98年末にわれわれが行った経済見通しでは、99年度の経済成長率は0.5%だった。
当時、これを信じる者は少なかった。翌年度の経済成長率を予測した日本国内の40余の調査機関のほとんどがマイナス成長を予測(平均▲0.6%)、プラス成長を主張したのはたった一つ、それも0.2%である。また、IMF、OECD等の国際機関もすべて日本経済は引き続きマイナスと予測していた。
しかし、政府の迅速かつ大胆な対策が効果を発揮し、99年前半には、予想以上に需要が盛り上がったため、99年夏から秋にかけて急に楽観論が拡がり、日本国内の民間調査機関や国際機関の多くは、1%台のプラス成長を予測するようになった。これに対して経済企画庁はいたって慎重で、99年11月の見通し改訂でも0.6%に改めただけである。99年10~12月期には12月支給のボーナスが低い水準になることから消費が落ち込み、需要全体が停滞すると見られていたからだ。10~12月期は予想通りだったが、2000年1月~3月期には、はっきりと回復の動きが現れている。
その反面、長い間減少を続けて来た民間設備投資は10~12月期に前期比4.6%(前年同期比3.1%)の大きな伸びを見た。日本の企業も情報技術をはじめとする新規投資に積極的になり出したことを示している。
III.経済新生対策と2000年度予測
さて今年、2000年度の日本経済の目標は何か。それは経済再生の第2段階、経済新生対策に示されている。政府は2000年度を自律的な景気回復を確実にする年と位置付け、実質1.0%の着実な成長を見込んでいる。これはやや控え目な数字だが、99年度が前半好調、後半停滞だったことを考えるとけっこう高い上昇となる(図3)。特に2000年度には緊急経済政策で着手した金融改革、新しい中小企業政策、需要拡大政策を一段と推進すると共に、構造改革の実現を目指している。
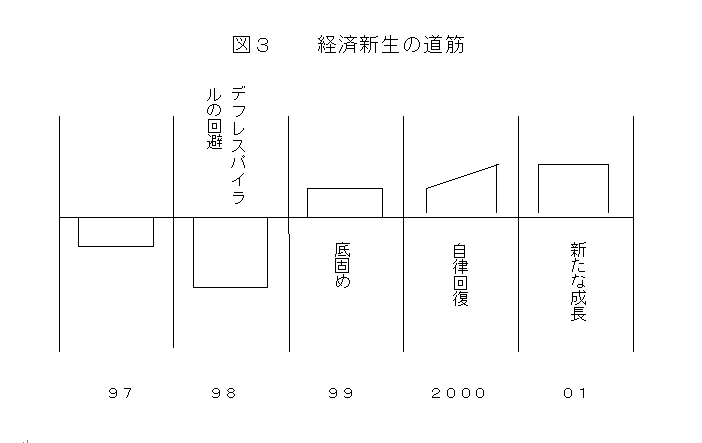
金融改革では金融の自由化、金融業界への市場原理の導入を断行したことで、日本の主要金融機関の間に大規模な統合合併がはじまっていることは既に述べた。これと並行して証券市場の改革も進んでおり、東京証券市場にはマザーズが昨年11月に設立され、大阪にはナスダック・ジャパンが6月末に設立される予定である。これによって中小企業やベンチャービジネスも資金調達がやり易くなるだろう。
新しい中小企業政策も確実に進行している。99年末からは企業の選別が進む反面、情報産業、ソフト産業、介護産業での創業は増加している。
第2段階への移行で、大きく変ったのは公共事業だ。経済新生対策では多様な知恵の時代にふさわしいインフラストラクチャーの整備に重点が移された。2000年度予算においても、公共事業関係費は前年度同額の9兆4千億円(国・地方を合わせたIGベースでは約40兆円)としたが、そのうち2兆600億円は、情報、高齢化、環境、都市の新基盤整備の重点4項目に当てられている。
この中には、2001年までに全公立学校等をインターネットで繋ぎ、2003年までに電子政府を完成させる情報革新、交通機関のバリアフリー化、混合型都市の形成する「歩いて暮らせる街造り」および遺伝子解析事業などが含まれている。
また、2001年を新千年紀のゲートイヤーと位置付け、インターネットの上で大規模な博覧会を開催する「インターネット博覧会」の開催も計画されており、私自身が担当大臣となっている。これには日本の全府県と主要都市が参加するほか、多数の企業、主要団体もネット上にバーチャル・パビリオンを設置することになっている。
規格大量生産型の工業社会を完成した日本は、情報技術においても、機器の開発生産では優れた能力を持っているが、ソフトウェア開発とコンテンツ創作ではアメリカよりずっと遅れている。インターネット博覧会は、全国各地で新しいコンテンツを創造する組織と人材を開発し、日本の経済に新しい活力を、日本人の暮らしに新しい楽しみを加えることになるだろう。
経済新生対策によって大規模な国際的研究活動がはじめられる。それは、活力ある高齢化社会と持続可能な循環型社会の基本構想を解き明かす国際研究プロジェクトである。この2つの研究プロジェクトは、経済企画庁の経済研究所が担当する。
活力ある高齢社会の研究では、「70才まで働くことの選べる社会」を創造するための産業構造、雇用制度、勤労環境、使用機器および税制・年金などのあり方を解明する必要があると考えられている。
また、持続可能な循環型社会の研究では、資源回収に当たる静脈産業の労働生産性を飛躍的に高めることが必要だ。われわれは、それに必要な技術開発と施設の配置、技能労働者の養成、および奉仕的参加のシステムを確立しなければならない。
IV.日本経済の明日
日本経済は今、急速に立ち直りつつある。99年度の実績は政府経済見通しの実績見込み(プラス0.6%)の近辺になるだろう。そして2000年度の1.0%成長も達成される可能性が極めて高い。日本経済が新たな発展軌道に乗ると期待されているのは、2001年度からであり、自然成長率と見られる2%以上の成長となるだろう。
日本経済にとって重要なのは、量的な成長率ではなく、構造改革と組織機能の飛躍的転換である。新しい森内閣は、この完成を目指して、引き続き積極的な経済政策を続ける決意である。
(1)爆発する情報革命
では、日本経済の新たな発展軌道とは何か。そしてそのあとの日本経済の「明日」はどんなものか。
まず第1に挙げるべきは、目下進行中の情報革命である。今、日本では携帯型の情報機器が爆発的に増加している。今年中には携帯電話が5千万台を超え、固定電話を上回るだろう。さらにiモードと呼ばれる大型画面とインターネット接続機能を持つ携帯機器が猛烈な勢いで普及しつつある。
また、家電のデジタル化も急速で、ソニーの売り出したゲーム機、プレイステーションIIは3万円台の価格で通信機能からDVDプレーヤー機能までを備えている。日本の電機メーカー各社はこの種の便利で安価な情報機器を次々に発売する予定だ。これによって、今後1年間でも日本の情報環境は著しく改善するに違いない。
(2)構造改革 ― 職縁社会からの離脱
第2に、日本が急がねばならないことは、経済の構造改革、とりわけ経済の仕組みの組替えである。金融システムの大改革によって、大手金融機関を中核とする「縦」の系列が揺らぎ出していることは前述した。来年中に大手金融機関の統合合併が現実のものとなれば、この傾向は猛烈に進むだろう。
同時に、大手メーカーやゼネコンを頂点とする元請け下請け受発注の企業系列も急速に消滅しつつある。金融系列から離れたメーカーやゼネコンは、価格面での厳しい競争に直面するので、より迅速でより安価な部品調達を必要とするからである。
また、戦後の日本社会の最大の特色であった終身雇用も崩れつつある。かつては、正社員を定年前に解雇することなど絶対にないと信じられていた巨大企業が、99年には次々とリストラ計画を発表、それを日本社会も受け入れた。この結果、今、日本では人々の考え方が変わりつつある。日本のサラリーマンのほとんどは家庭よりも、地域社会よりも、宗教や趣味よりも、職場への帰属意識に燃えて来た。それを私は「職縁社会」(職場の縁でつながる社会)と呼んでいる。しかし、この仕組みが、今、緩もうとしている。それは日本における倫理観と美意識の変更、つまりパラダイム・チェンジにつながるだろう。
(3)多様な知恵の時代にふさわしい発想を
私は、1985年に「知価革命」を著し、遠からず規格大量生産の時代は終わり、「知恵の値打ち」が企業利益と経済成長の主要な源泉となるだろう、と予想した。この予想は日本ではなく、米国において的中した。私が「知価革命」を書いていた頃、米国は経済危機と社会不安に陥っていた。金融機関の破綻、製造業の不振、失業の増加、社会不安、そして財政と国際収支の双子の赤字の増加などである。しかし米国は、この間に金融、運輸の規制撤廃などにより、自由な競争によって新しい金融取引やソフトウェア産業など知価創造的な産業を興すことによって、今日の長期繁栄を築き上げた。
90年代の日本は、先に挙げた80年代の米国に起きた不幸の中の最後のもの(国際収支の赤字)を除く全てを経験している。しかも日本の場合、規格大量生産型の社会を究める仕組みが整然とした制度と組織によって作られている。これには、戦後の高度経済成長という成功体験の支えもある。だが、われわれはそれから脱しなければならない。そのためには少なくとも3つのことが必要である。すなわち①行政機構の大改革、②生活観の変革、③人間評価の変更である。
新しい森内閣は、この三つに果敢に挑うとしている。
行政改革は、97年末に橋本内閣によって基本方針が定められ、99年に小渕内閣によって法制化された。2001年1月より、中央行政機関が大改造、省庁の数は21から13に減らされる。この改革の主目的は総理大臣の権限を強化し、各省庁の官僚によって分割されていた予算と行政に対する指導力を高めることである。
森内閣はこの方針を堅持し、行政機構の変革を実現すると共に、これを実効あるものとするだろう。
このことは、日本社会に深く根付いてきた官僚主導・業界協調体制を根絶させることになるはずである。
第2の生活観の変更の中で重要なことは、先を憂うるよりも今を楽しむ暮し方を実現することである。日本の伝統文化の中には「先に心配して、あとで楽しむ」悲観的警戒的な生活態度を好しとする教えがある。この教えが広く実行されるようになったのは、戦後の高度成長の中で、大企業は常に有利であり、財産価格は必ず上昇するという現実があったからだ。少年時代に苦しい受験勉強に励んだ者は一流大学から一流企業に入り、社会の中流上層部の暮しが生涯約束されていた。節約と貯金に努めて、早目に住宅や土地を買った者は、その値上り益を享受できた。こうしたことが、今を楽しまず先を憂うる人生観・生活観を生み出した。経済が成熟段階に達し、人口構造が高齢化した今も、日本の貯蓄率が高いのはこのためである。
日本の老人は豊かで財産も預金も多い。それなのになお、80才にして年金の一部を貯蓄する者が多い。日本経済の真の再生のためには、日本人が生活を楽しむ習慣を身につけなければならない。その意味では、90年代に起った土地価格の下落による先行投資の損失と、大企業のリストラによる終身雇用の揺ぎは一定の教育効果を持つだろう。
第3の人間評価の変更もこれと深く関わっている。日本ではビル・ゲーツ氏やウェーレン・バフェット氏のような創業者よりも、官庁や巨大企業の官僚的人事機構の階段を昇り詰めた人のほうが尊敬されるところがある。日本での学校でほめられるのは、教科書をよく覚えて試験に合格する生徒であり、芸術界で尊ばれるのは先人の技法を忠実に模倣する流派である。日本では、独創は「我流」と呼ばれて軽蔑され、個性は「くせがある」として嫌われる。これも規格大量生産型の社会を築くために欧米の先進技術を模倣したことから生れた人間評価であり、戦後の教育の中で固定化されたものである。日本の経済が新しい発展段階に入り、新規創業の多い状況になるためには、こうした人間評価をも改めなければならない。
日本政府は、この欠点を改めるために、抜本的な教育改革を目指して、教育改革国民会議を発足させた。森首相は特に教育に詳しい政治家であり、教育改革の実行が期待されている。
(4)財政再建は全社会的変改の中で
最後に、日本の財政について一言触れておきたい。
現在、日本の国および地方自治体の財政は危機的状況にある。99年度の国の財政は2回の補正まで加えれば約42兆円の赤字、公債依存度が43.4%である。2000年度はやや軽減しているとはいえ、国の財政赤字がGDPの7.8%にも当る。また国および地方自治体を併せた長期債務残高は2000年度末で645兆円に達すると見られる。これはGDPの約130%に当る。
現在の日本は極端な低金利で、10年ものの国債利回りが1.8%内外だから利払いは少なくて済むが、金利が国際水準になれば大変な負担になることは明らかだ。こうした数字から日本の財政再建のためには、いずれ日本経済を決定的な不況に導びきかねないほど大増税と歳出の大幅減が必要だと主張する者が多い。
しかしこのような決定論的考え方は間違っている。現在の日本経済は「三重の不況」にあり、税収は異常に少ない。特に法人の所得にかかる税(法人税・事業税)は、企業経営の低迷を反映して大幅に減少している。また金利の低下は公債利払いを軽くする一方で、金利所得から得られる税収をも減少させている。645兆円の長期債務残高のある一方では、日本には1,330兆円の個人金融資産がある。要するに長期にわたる財政問題を、現在(98~99年)の不況と構造不適合にある日本の現状を前提として論じるべきではない。景気回復と構造改革とパラダイム・チェンジを果たした後の日本経済の姿を見てから論じるべきなのである。
米国も80年代には財政赤字に苦心した。それが今では財政が黒字となり、その使い方をめぐって議論が起こっている。80年代に(いや92年の時点でも)米国の財政がこれほど短期間に黒字になると予想したものはいなかったであろう。経済の構造改革に成功したからこそ、財政も黒字になったのである。
小渕前首相は「二兎を追う者、一兎も得ず」という古い諺を繰り返した。これに対しても、「景気回復を追いかけて歳出を拡大、財政の健全性を放棄している」と非難する者もいた。しかし、この非難は当っていない。景気の回復、経済の再生と財政再建という二羽の兎は別々の方向に走っているのではなく、同じ方向にいる。ここはまず、景気回復・経済再生という手前の大きな兎をしっかりと捕らえてから、その先を走る財政再建の兎を追うべきである。経済再生を中途で放棄し、増税や歳出抑制に走るならば、どちらも成功しない。森内閣はこの方針を受け継ぎ2000年度においても経済再生を第一とした積極的財政政策を採る。これには、経済の状況に応じてあらゆる手段を可能としておかねばならない。
われわれは、日本経済の再生、そして日本社会そのものの新生に覚悟を決めて邁進しているのである。

