第2節 日本の財政リスク
第1節では、金融市場の国際連動性が高水準にあることとその背景を確認した。リーマンショック以降、各国の財政収支が悪化する中、ギリシャ、アイルランド、ポルトガルでは財政リスクが顕在化し、各国への財政リスクの伝播が注目されている。我が国でも、2011年入り後、日本国債が格下げを受ける等、我が国財政の持続可能性に対して、懐疑的な議論が高まってきている。しかしながら、我が国の国債利回りは低位で安定して推移し、財政リスクは顕在化していない。
第2節では、欧州政府債務危機や過去に財政破綻(国債のデフォルト)を経験した国のケーススタディを通じて、財政リスクがどのような状況において顕在化したかを探る。更に、我が国で財政リスクが顕在化しない背景を、日本国債の保有構造等を通じて分析する。
1 財政リスク顕在化のケーススタディ
欧州政府債務危機や財政破綻国のケーススタディを通じて、財政リスク顕在化の条件を探る。
(欧州政府債務危機の経緯と金融市場の反応)
まず、欧州政府債務危機を巡る金融市場の動向とその経緯を整理する(第3-2-1図(1))。
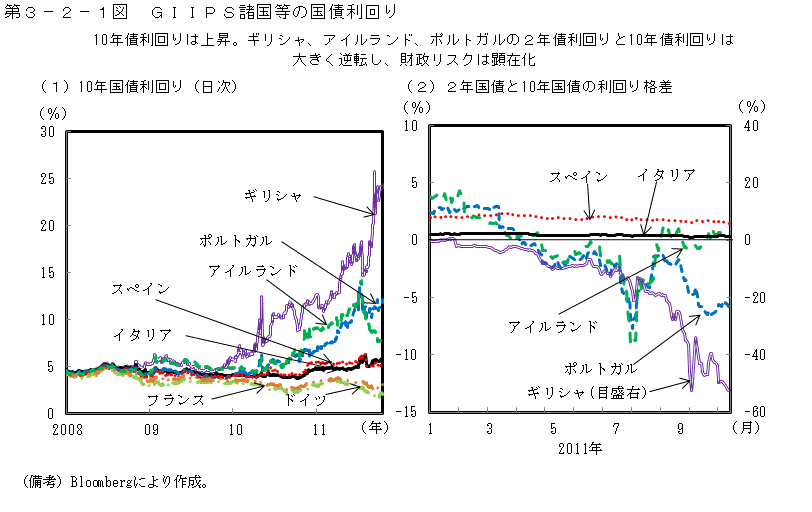
リーマンショック後、ギリシャ、アイルランド、イタリア、ポルトガル、スペイン各国(以下、GIIPS諸国という)では、①景気低迷による税収の減少と、②不良債権の増加等によって自己資本の毀損を受けた金融機関への公的資金注入などから急速に財政収支赤字が拡大し、政府債務残高が増加した。更に、2009年 11月のドバイ・ショックにより、中東諸国向け与信を多く持つヨーロッパの銀行の更なるバランスシートの悪化懸念から、GIIPS諸国の財政収支赤字の拡大が一段と意識された。
そうした中、2009年 10月に国家財政の粉飾決算(財政収支の大幅赤字修正)が明るみに出ていたギリシャの財政リスクが特に意識され、2009年 12月以降、ギリシャ国債は、各格付会社による格下げ41を受けて、利回りが上昇した。
その後、ギリシャ政府は、2010年4月 23日に短期国債の利回り上昇により資金調達が難しくなったことから、EUとIMFに金融支援を要請した。しかし、2010年5月6日には、「ECB(欧州中央銀行)はユーロ圏国債買入に消極的」との報道を受けたギリシャのデフォルト懸念の高まりから、長期国債利回りも更に上昇した。このとき、NYダウは一時 998ドル下落し、リーマンショックの再来が意識された(ギリシャショック)。2010年5月10日には、欧州金融安定基金(EFSF:The European Financial Stability Facility)設立の発表とECBによるユーロ圏国債買入等が決定されたことから、金融市場はいったん落ち着きを取り戻したが、その後も、ギリシャ国債の利回りは上昇し続けた。
この間、アイルランド国債とポルトガル国債は、リーマンショック後の銀行の不良債権問題から、金融機関に対する巨額の追加支援等による2009年の財政収支悪化(アイルランド:対GDP比▲14.6%、ポルトガル:対GDP比▲9.3%)が意識される中、格付け会社による相次ぐ格下げ42を受けて、利回りが上昇した。アイルランド政府は 2010年 11月に、ポルトガル政府は2011年4月に、各々EUとIMFに金融支援を要請した。
2011年7月 21日に発表されたユーロ圏首脳会議によるギリシャ支援の合意案が各国議会の承認を得られないとの思惑等を背景に、8月には、ギリシャ国債がデフォルトした際のヨーロッパの銀行のバランスシート悪化懸念などから、周辺国の財政悪化が再び意識され、アイルランド国債、ポルトガル国債に加えて、政府債務残高の大きいスペイン国債とイタリア国債、更にフランス国債の利回りもやや上昇した。
こうした中、ギリシャ国債、アイルランド国債、ポルトガル国債では、財政リスクが顕在化し、デフォルトが強く意識され、2年債の利回りが10年債の利回りを大きく上回る事態にもなった(第3-2-1図(2))。
(リーマンショック後の経常収支赤字の縮小と財政収支赤字の拡大)
このように財政リスクが顕在化し、デフォルトが強く意識されたギリシャ、アイルランド、ポルトガルを中心に、リーマンショック後のGIIPS諸国の財政状況等を分析し、財政リスクが顕在化した背景を整理する。
財政面では、リーマンショック後の景気対策や金融機関支援による財政支出拡大と、景気悪化による税収の落ち込み等から、財政収支赤字は、ギリシャ、アイルランド、ポルトガルを中心に大幅に拡大し、政府債務残高は増加した。例えば、ギリシャでは、2004年のアテネオリンピックにかかわる財政支出等から、政府債務残高は高水準で推移していたこともあって、2010年までに対GDP比で143%まで上昇した(OECD加盟国中2位)。アイルランドとスペインでは、「安定成長協定(Stability and Growth Pact)43」を満たす等、厳格な財政規律の管理から、2007年までに政府債務残高44は減少していたが、アイルランドでは2007年の25%から2010年の96%に、スペインでも2007年の36%から2010年の60%にまで急激に増加した(第3-2-2図(1)(2))。
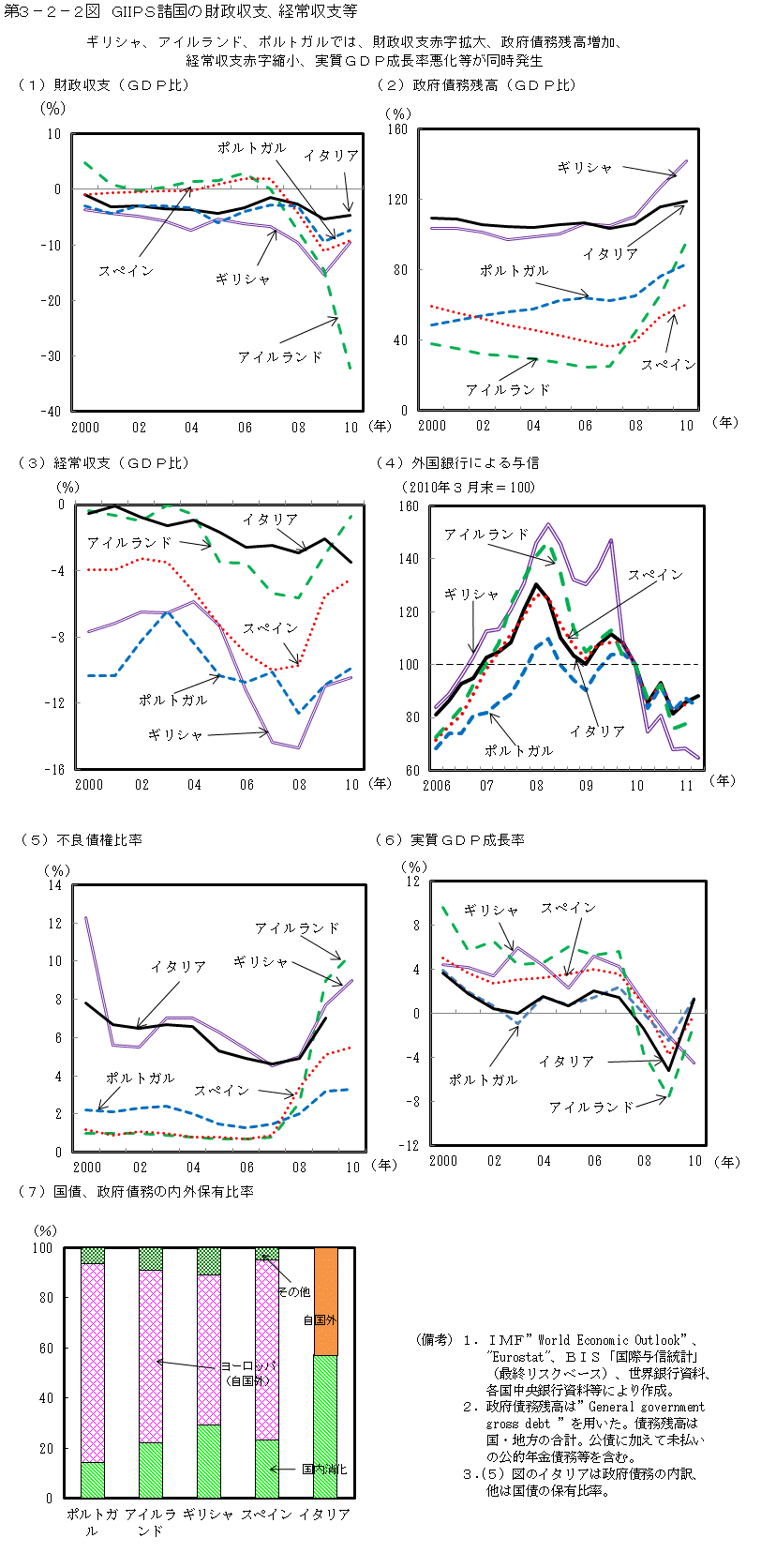
こうした財政収支赤字の拡大と政府債務残高の増加の背景には、リーマンショック後に、外国資本が流出し、実体経済が悪化したことも大きな要因である(第3-2-2図(3)(4))。
リーマンショック以前は、ギリシャ、アイルランド、ポルトガル、スペインの経常収支赤字は、99年のEUの通貨統合によるヨーロッパ域内での資本移動の容易さを受けた外国資本の流入から、高水準で推移していた。特に、①ギリシャでは、アテネオリンピック後に好景気が続いていたことや、②アイルランドでは、ヨーロッパ域内での資金調達が容易なことを背景に、主要行が資金調達を増やしたこと(主要行の総資産はアイルランドのGDPの約9倍に達した)から、外国銀行による与信が大きく増加していた。こうした資本移動は、本来は国際的な資金の効率的再配分を助けるものであるが、ここでの問題は、外国資本の流入による資産価格バブルがアイルランド、スペインを中心に生じており、資金が必ずしも効率的に利用されていなかったことにある。
実際、リーマンショック後に、外国銀行による与信が急激に減少しているように、信用収縮(デレバレッジ)から外国資本が流出し、経常収支赤字は急激に縮小した。特に、ギリシャでは、2008年9月まで外国銀行等による外国資本の流入が高水準で続いていたことから、落差は大きかったと考えられる。
また、この外国資本の急激な流出は、実体経済の悪化を加速させた。リーマンショック以前は、外国資本の流入による資産価格バブルがアイルランド、スペインを中心にみられていたが、リーマンショック後の外国資本の流出を受け、資産価格は大幅に下落した(バブル崩壊)。こうした外国資本の急激な流出の背景には、2000年代前半からリーマンショックまでの間、世界的に金融市場のボラティリティが低下し、主要な金融商品の収益率が低下する中、外国銀行等が「searchforyield(利回りの追及)」の風潮の基で相対的に高い収益率を求めて、GIIPS諸国に半ば投機的に投資していたこともあったと考えられる。
資産価格バブルの崩壊は、不良債権の増加ももたらし、実体経済の悪化(実質GDP成長率の急激な低下)等を通じて財政収支を悪化させ、財政リスクを高めていったと考えられる(第3-2-2図(5)(6))。
更に、この間の国債の内外保有比率をみると、ギリシャ、アイルランド、ポルトガル、スペインの外国保有比率は70~80%と高くなっている。このことも、財政リスクが意識される局面で外国投資家が売却したことによって、ギリシャ、アイルランド、ポルトガルの財政リスクが顕在化するのを加速させることになった45(第3-2-2図(7))。
こうしたGIIPS諸国のケーススタディからは、リーマンショックのような大きな金融危機により、外国資本が流出し、経常収支赤字が急速に縮小する中、実体経済の悪化と金融機関のバランスシートの毀損等から財政収支赤字が拡大、政府債務残高が増加し、財政リスクが顕在化するという構図が示唆される。また、その際、危機以前の資本流入が非効率な投資等に結び付いていた点も事態を悪化させた要因になったと考えられる。
(近年の財政破綻事例)
98年にロシアが727億ドルのデフォルトを、また、2003年にアルゼンチンが823億ドルのデフォルトを起こす等、83年以降、12か国でデフォルトが発生している46。GIIPS諸国の財政リスク顕在化のケーススタディと同様に、近年の財政破綻事例として、ロシアとアルゼンチンについて、経常収支赤字縮小と実体経済の悪化、財政収支赤字拡大、政府債務残高増加等がどのように財政破綻を招いたかを確認する(第3-2-3表)。
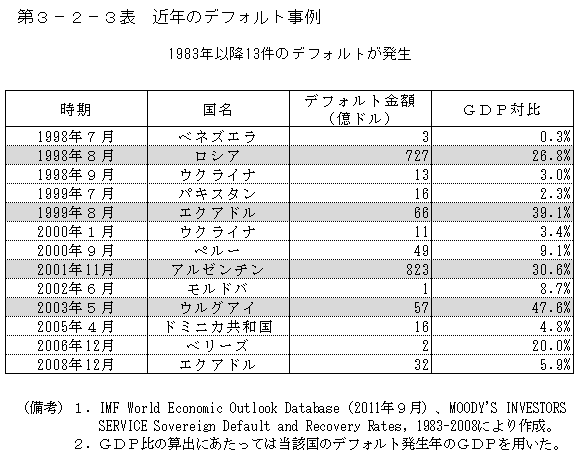
ロシアでは、92年の市場経済移行後、高インフレ、高失業率等から実質GDP成長率はマイナスが続いていたが、97年に原油価格の上昇を受けて一時的に実質GDP成長率はプラスに転化した。この間、成長期待もあって、外国銀行による与信が急激に増加しているように、外国資本が急激に流入していた(第3-2-4図(3)(4)(5))。
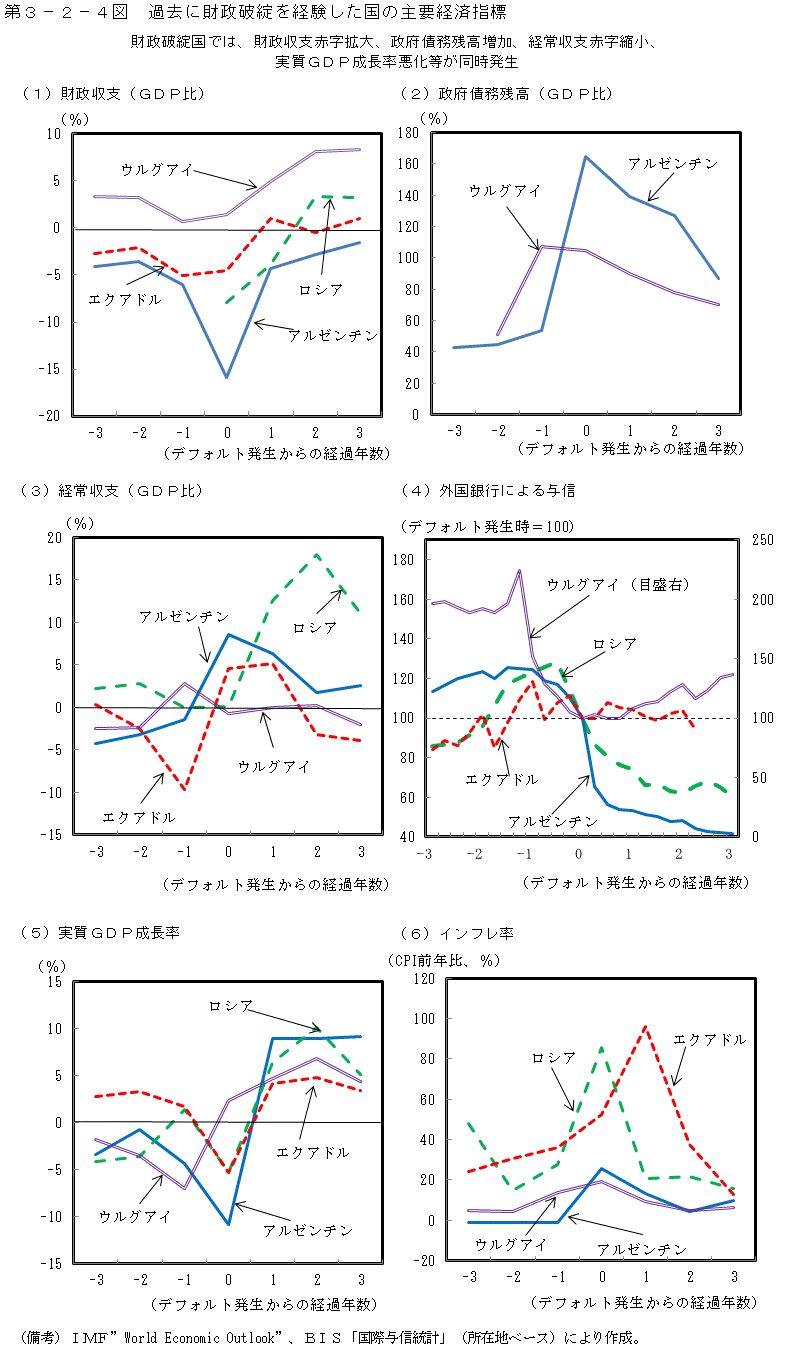
しかし、98年のアジア通貨危機による世界経済の悪化を受けて、外貨取得源である原油価格が下落した上、信用収縮から外国資本の急激な流出が生じたため、景気後退と金融危機が同時に発生した(銀行の約半分の720行が支払不能になった)。その結果、財政収支赤字が急激に拡大し、政府債務残高も増加した(第3-2-4図(1)(2))。
ロシア政府は、外国資本の流出を阻止するために、公定歩合を 100%超に引上げたものの効果はなく、98年8月にデフォルトに至った。
なお、デフォルト後は、ルーブルの切り下げ(1ドル=6ルーブル→1ドル=28ルーブル)と原油価格の回復による輸出の増加から景気は回復し、実質GDP成長率は再びプラスに転化した。他方、ルーブル切り下げを受け、ハイパーインフレが生じることになった(第3-2-4図(6))。
また、アルゼンチンでは、高インフレを抑えるため91年からドルペッグを採用した。アジアに端を発する通貨危機を受けて99年に隣国ブラジルがレアルを切り下げたため、対レアルでの競争力低下から輸出が減少し、景気は低迷した。更に、アジア通貨危機の余波により外国資本が流出したことも重なり、実質GDP成長率は99年に▲3.4%とマイナスに転化した。景気の悪化を受けて、税収は減少、財政収支は大幅に悪化した上、政府債務残高対GDP比は165%まで上昇した。
こうした中、アルゼンチン政府は、2001年 11月に対外債務、対内債務のデフォルトを宣言し、ペソ切り下げと預金封鎖を同時に実施した(預金封鎖は2002年12月まで継続)。
なお、デフォルト後は、ペソ切り下げ(1ドル=1ペソ→1ドル=4ペソ)を受けて、輸出が回復し、実質GDP成長率はプラスに転化した。他方、ペソ切り下げを受け、ハイパーインフレが生じた。
ここで、対GDP比でみたデフォルト額が大きいウルグアイ、エクアドルも含めて指標の推移をみる(デフォルト時を0とする)と、財政破綻前には、資本流出が生じ、外国銀行による与信は減少している。その結果、経常収支赤字は急激に縮小し、実質GDP成長率も低下している。同時に、財政収支赤字は拡大し、政府債務残高は増加している。更に、為替切下げにより実質的に外貨建て対外債務の負担も増加している。
このようにGIIPS諸国のケースと、おおむね似通った動きを示していることが確認できる。
(財政リスク顕在化への経路)
こうした財政リスク顕在化のケーススタディから以下の経路により、財政リスクは顕在化すると整理できる(第3-2-5図)。
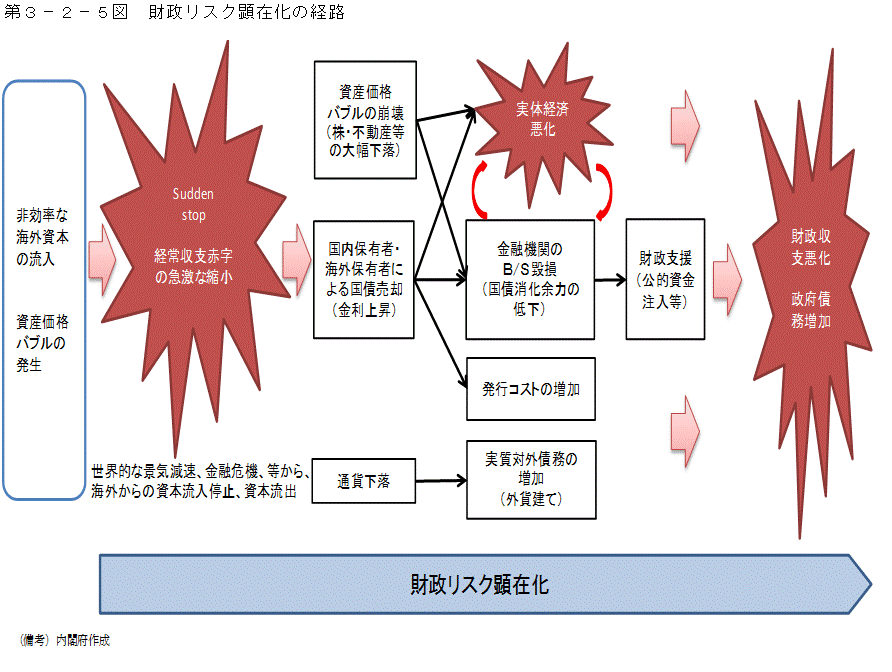
世界的な景気減速や金融危機等から、外国からの資本流入が停止したり、資本流出が生じ(「suddenstop」という)、経常収支赤字が急激に縮小する。同時に、実体経済の悪化(実質GDP成長率の低下)や金融機関のバランスシートの毀損により財政収支赤字が拡大、政府債務残高が増加し、財政破綻の危険性が高まる。
市場参加者はこうしたメカニズムを考慮して、財政リスクをみていると考えられる。
2 日本国債における財政リスク顕在化の可能性
我が国においても財政リスクが顕在化する可能性がないかを、過去2回の格下げ局面の状況と、日本国債の保有構造を通じて検証する。
(日本国債における格下げ局面)
我が国において、財政の持続可能性が議論され、日本国債の格下げが生じた時期は、①98~2002年47と、②2011年入り後の2回あった(第3-2-6図)。
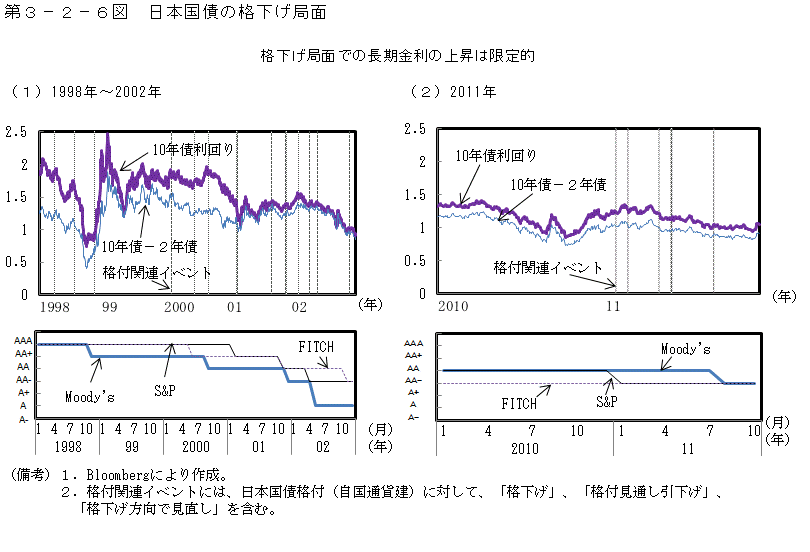
前者の時期には、97年の山一証券破綻を端緒とする金融危機や、98年のアジア通貨危機等から、景気は一段と悪化(97~98年と 2001年に景気後退した)し、相次ぐ財政出動から財政収支赤字は拡大、政府債務残高は増加していた。各格付け会社による格下げの主な理由としては、①景気の低迷、②財政収支の悪化、③政府債務残高の増加、④金融セクターの脆弱性が指摘されていた。
後者の時期には、2008年のリーマンショックによる景気後退を受けた大規模な景気対策から、財政収支赤字は拡大、政府債務残高は増加した。更に、2011年3月の東日本大震災を受けて、一段と財政は悪化するとみられている。ムーディーズの格下げ(2011年 8月 24日、Aa2→Aa3)の理由として、高水準の政府債務残高に加えて、震災の経済への影響(地震・原発問題に対する歳出の増加懸念)が指摘されていた。
しかしながら、両期間ともに、国債利回りの上昇は限定的であり、財政リスクが顕在化することはなかった。
(財政リスクを巡る状況)
格下げのあった時期をみると、財政面では、度重なる景気対策による支出の増加と景気低迷による税収の減少、公的資金注入等から、財政収支赤字は拡大し(97年▲5.8%→99年▲8.2%、2008年▲3.3%→2010年▲8.5%)、政府債務残高も増加、2010年には政府債務残高対GDP比は200%まで上昇している(97年100.5%→99年127.0%、2008年174.1%→2010年199.7%)。実体経済面では、前者の時期には、バブル崩壊後の長引く不況の中、不良債権率はそれぞれマイナスとなった(98年▲2.1%、99年▲0.1%、2008年▲1.2%、2009年▲6.3%)。財政面と実体経済面では、財政リスクが顕在化してもおかしくない状況であったと考えられる。
他方、経常収支をみると、経常収支黒字であり(経常収支対GDP比は99年2.6%、2010年3.6%)、外国資本は急激に流出していない。実際、外国銀行による与信にも変化はみられない(第3-2-7図(1))。
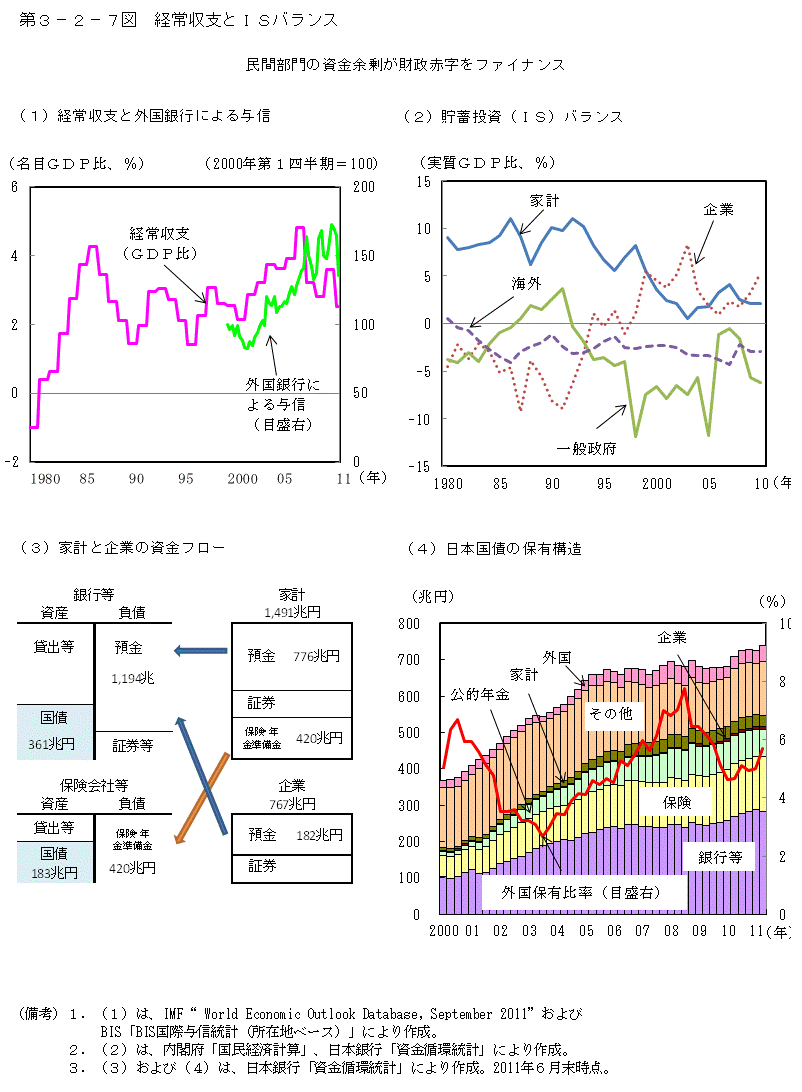
2011年6月の日本国債(短期証券を含む)の保有構造をみると、銀行等(都市銀行、地方銀行、信用金庫、信用組合等)が40.0%と最も多く保有し、保険会社(生命保険会社、損害保険会社等)が16.7%、公的年金が8.1%と続いている。日本国債は国内投資家により安定的に消化され、保有主体の構成比率は安定している。他方、外国投資家等による外国保有比率は7.4%と低く、この点で財政リスク顕在化国とは大きく異なる(第3-2-7図(4))。
財政状況の悪化にもかかわらず日本において財政リスクが顕在化しなかったのは、基本的に、国内の貯蓄超過によって財政赤字が消化されてきたことによると考えられるが、こうした国内資金が経済情勢や制度的要因により日本国債の保有に向かうインセンティブがあることも無視できない。
貯蓄投資(IS)バランスをみると、我が国では、民間部門(家計と企業)の資金余剰が、財政収支赤字をファイナンスしてきたことが分かる。この間、家計の貯蓄超過は、バブル崩壊以降の所得環境の悪化や高齢化による貯蓄率の低下を反映して減少傾向にある一方、企業の貯蓄超過は、期待成長率の低下を受けた設備投資の減少や労働分配率の低下から、増加している(第3-2-7図(2))。
こうした家計や企業の資金余剰は、銀行や保険会社等を通じて日本国債に投資されている。銀行や保険会社等により日本国債が選好される理由として、まず、経済が低迷する中で、企業向け貸出や株式等が有しているリスクが回避され、安全資産である国債への逃避的行動が生じていることが挙げられる。また、金融政策における時間軸効果から国債価格が暴落しないことを見越して、積極的に長期国債に投資できる環境にあることも挙げられる(銀行等では、デフレ脱却後は、ボラティリティ上昇により金利リスク量が増えるため、デュレーションを短くし、長期国債を売却する可能性があるが、その分を短中期国債にシフトするだけで、全体の保有量は変化しないと考えられる)。更に、次項で詳しく分析するように、リスク管理を強化する制度的変更の影響により国債保有が促進されている面がある(第3-2-7図(3))。
なお、我が国の財政リスク顕在化が抑えられている他の要因として、我が国経済がデフレ下にある中で、ゼロ金利政策が導入された99年以降、国債利回りは一貫して低水準にあることにより利払費の増加が抑えられてきたことが、財政状況の悪化を緩和する効果をもったことも指摘できる。加えて、我が国の租税負担率は、22%とOECD加盟国対比で低いと見なされ、租税負担率の引上げ余地が大きいと見なされている48ことも指摘できる。これらのことも、金融機関等による日本国債の保有を促したと考えられる。
このように、我が国は、財政と実体経済の状況が悪化しているために格下げを受けたが、経常収支黒字であり、外国資本の急激な流出が生じているわけではなく、日本国債の外国保有比率も低いことから、ケーススタディでみたような資本流入の急激な逆転に端を発する財政リスクの顕在化はなかったと考えられる。
以下では、日本国債の主たる保有者である銀行等、生命保険会社、公的年金について、バランスシート、有価証券投資における国債の位置づけ等を踏まえながら、近年の国債保有動向を確認する。
(銀行等の国債保有)
銀行等の国債保有残高は一貫して増加している(2006年度 241.7兆円→2010年度 287.9兆円)。この背景には、①銀行等のバランスシート上の調達、運用構造において、預金が増加する一方、貸出が低迷し、その結果、有価証券が増加していること、②リスク管理の強化を求める自己資本比率規制(2007年よりバーゼルIIへ移行)等の制度変更の影響により、国債投資に偏重していること等が指摘されている。以下、各々について確認する。
預金は、個人預金と企業(法人)預金がともに増加している(2006年度1,085兆円→2010年度1,160兆円)。個人預金については、リーマンショック後の金融市場の低迷を受けた株式や投信等の損失から、リスク選好が後退していることや、安全資産である個人向け国債の利回りが低水準にあること(2005~2006年頃に大量発行された個人向け国債の償還資金が預金に滞留している)等から、他の金融商品に投資されていた資金が預金へ流入している。また、企業預金については、期待成長率の低下による設備投資意欲の低下等から余剰資金が預金へ流入している。
他方、銀行等の本業である貸出は、長引く景気低迷を映じて企業の資金需要が弱いことから全く伸びていない(2006年度604兆円→2010年度606兆円)。その結果、預貸ギャップは拡大し、有価証券が増加している(第3-2-8図(1))。
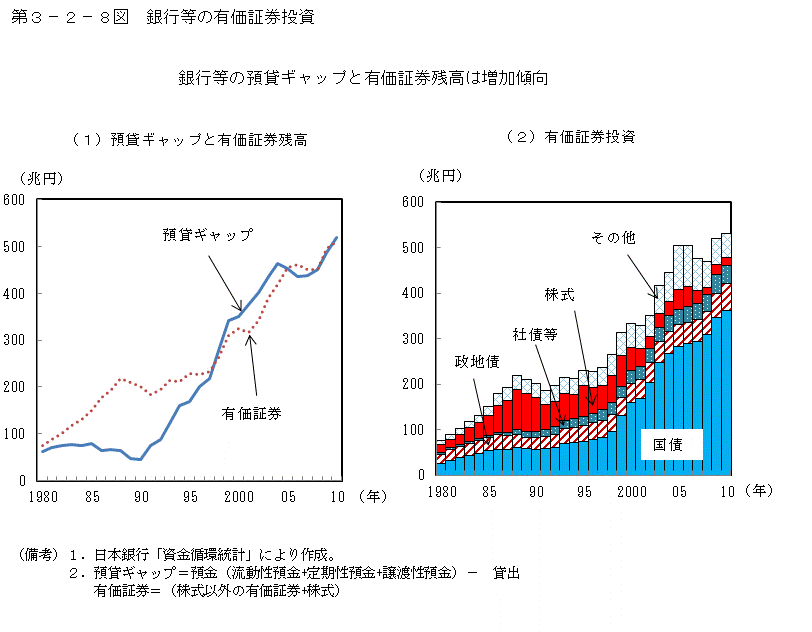
有価証券の内訳では、国債の割合が最も多く、68%(2010年度)を占めている。この背景には、①600兆円近くの余剰資金を、国債以外の債券で運用することは難しいこと(地方債70兆円、政府保証債35兆円、財投機関債28兆円、社債71兆円<2011年9月の発行残高>)、②自己資本比率規制上、国債のリスクウェイトが0%に設定(標準的手法)49されていること、③信用リスク管理上、国債はリスクフリー(デフォルト確率0%)と認識されていること、④流動性リスク管理上、国債は市場流動性が高く、換金可能資産(すぐに現金化可能な資産50)として認識されていること、⑤2000年の時価会計導入に伴い、相対的にボラティリティが高い株式等の金融商品への投資インセンティブが低下していること、などがある(第3-2-8図(2))。
更に、近年では、有価証券に占める国債保有割合は、2006年度57.3%から2010年度68.0%まで上昇している。この背景には、①リーマンショック時の仕組債51やクレジット商品等での運用の失敗を受けて、安全資産とされる国債への投資が一段と増加していること、②導入予定の新たな自己資本比率規制(バーゼルIII)においては、流動性リスク管理が強化される(流動性カバレッジ比率、安定調達比率)ことや、持合い株相当の負債性調達(金融機関向け出資)が自己資本から控除されること52(バーゼルIIでは自己資本に算入可能)、③導入が検討されている国際会計基準(IFRS)では、「その他保有目的」で保有していた株式等の一部について、評価損が損益計算書に反映されること、などがある。このように、預金が増加し、貸出が伸び悩む中で、リスク管理強化を目的とした制度変更等の影響から、有価証券の中で国債が選好されてきた。
先行きについても、①個人預金は、高齢化の進展による預金の取り崩しから、減少が意識されるものの、②期待成長率の低下による設備投資の抑制などから、企業預金は高水準で推移し、貸出は伸び悩むことが意識されるため、預貸ギャップは高水準で推移することから、銀行等による国債保有は継続する、との見方が多い。もっとも、我が国の期待成長率の上昇を見込めない中で、企業が外国での設備投資を活発化させ、企業預金は減少するとの見方もある。そのため、銀行等による国債保有残高は減少する可能性も否定できない。
コラム3-2 銀行による国債保有残高の増加と10年債利回りの低下
本論でみたように、貸出の低迷や、リスク管理の強化を目的とした自己資本比率規制や企業会計等の制度変更などから、銀行は国債保有を近年増加させている。こうした中、銀行による近年の国債保有の増加が、債券市場への影響を強めており、10年債利回りを大きく低下させているとの指摘がある。
一般的には、国債需要が増加すると利回りは低下するため、国債保有残高と利回りの間に観測される関係は負の相関を持つと考えられるが、個別の投資家でみると、10年債の市場流動性は非常に高い一方、その投資額は微小であることから、個別の投資家による価格への影響はほとんどない、と考えられている。
しかし、銀行の国債保有残高と 10年債利回りの関係においては、係数が統計的に有意となり、1%の国債保有残高の増加に対して 10年債利回りは▲0.4bps低下する関係がみられる。この背景には、大手銀行による投資年限は5年以下の短中期ゾーン中心の運用であるが、近年の大手銀行の国債保有残高の急激な増加によりその投資額が大きくなっている(価格への影響が大きい)ことから、イールドカーブ全体を下押ししている(10年債利回りは低下)ことや長期国債への投資額が相応に増えていることなどがある(コラム3-2(1)図)。
この他、近年では、地域銀行が、貸出利鞘の縮小に伴う収益性の低下をカバーすることなどを目的に、相対的に高い利回りの長期国債への投資を積極化していることも、10年債利回りの低下に寄与しているとの指摘もある。この背景には、金利リスク量の判定基準であるアウトライヤー比率53(過大な金利リスクテイクを避けるためにバーゼルIIで導入された。アウトライヤー比率が 20%を超えた銀行をアウトライヤー銀行と称する54)が、コア預金内部モデル55の導入(地域銀行の7割が導入)により、大きく水準を切り下げ、各地域銀行の長期国債の保有余地を増やしたことが指摘されている56(コラム3-2(2)図)。
以上のことから、銀行による国債保有残高の増加が、近年では、10年債利回りを低水準に抑えてきたと考えられる。
ただし、先行きについては、リスク管理の強化を目的とした制度変更等による他の投資資産から国債へのシフトには限りがある中、預金の減少や貸出の増加が生じた場合には、国債保有残高は減少する可能性がある。加えて、積極的に長期国債に投資した地域銀行の平均投資年限は、約4年と、大手銀行の平均投資年限の約1年を大きく上回っており、地域銀行による長期国債へのシフトにも限りがある(コア預金内部モデルを導入した一部地域銀行でも、アウトライヤー比率が20%に近くなっている)。これらのことは、10 年債利回りの上昇の可能性もあることを示唆している。
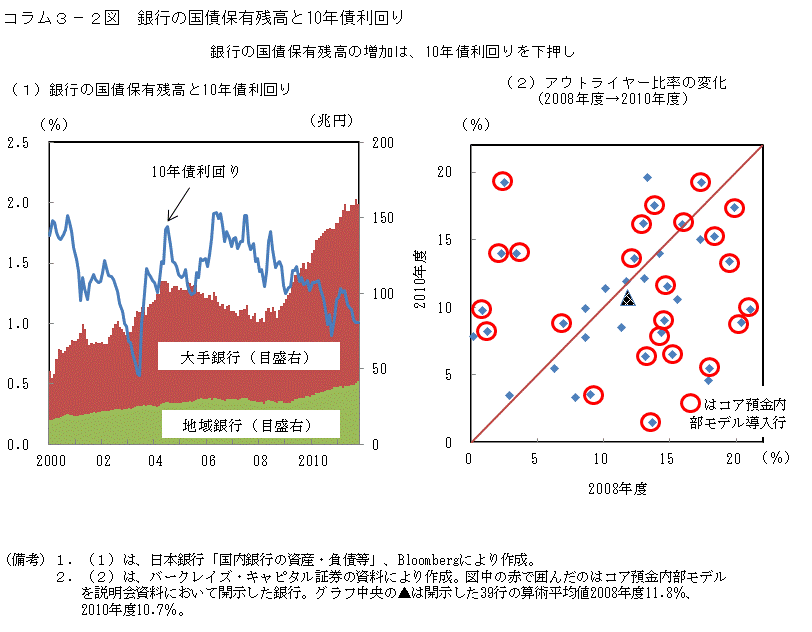
(生命保険会社の国債保有)
生命保険会社の国債保有残高は一貫して増加している(2006年度 106.4兆円→2010年度 121.8兆円)。この背景には、①生命保険会社のバランスシート上の調達・運用構造において、責任準備金57が高水準にある中で、貸出が減少し、有価証券が増加していること、②リスク管理強化を目的とした金融監督上の基準であるソルベンシーマージン比率規制等の制度変更により、国債投資に偏重していること等があると指摘されている。以下、各々について確認する。
生命保険会社のバランスシートの負債サイドをみると、生命保険と個人年金の責任準備金は、やや減少しているものの、高水準にある(2006年度254兆円→2010年度248兆円)。この背景には、個人年金保険の契約額が、①2002年の銀行窓口販売開始により認知度が高まったこと、②公的年金への不信感、③独身世帯の増加等から、増加している一方、生命保険の契約額は、高齢化や景気低迷による保険金額の見直し等から、減少していることがある(第3-2-9図(1))。
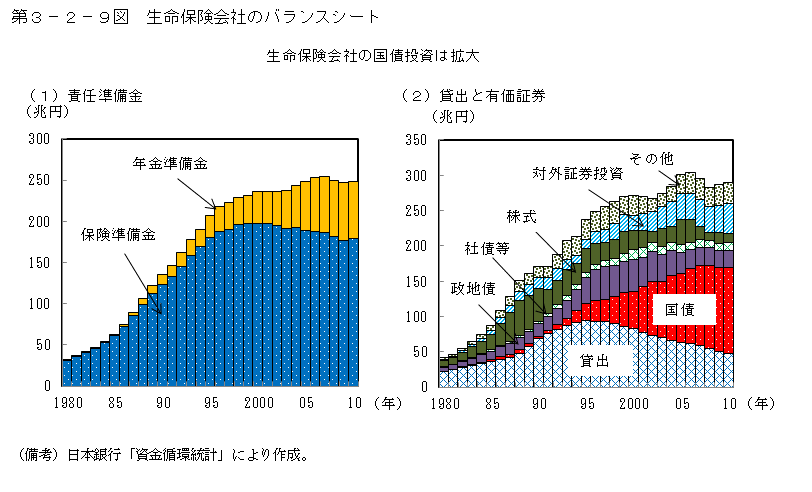
他方、資産サイドをみると、貸出は、①企業の資金需要の低迷や、②バブル崩壊後に生命保険会社のバランスシートが毀損したことを受けて、生命保険会社は信用リスク管理を強化したこと等から、減少している。その結果、有価証券が増加している(第3-2-9図(2))。
有価証券の内訳では、国債の割合が最も大きく、65.4%(2010年度)を占めている。この背景には、①バブル崩壊後の株式等での損失から、安全資産である国債中心の運用にシフトしたこと、②2000年の時価会計導入による価格変動リスクに対する見直し(リスク調整後収益率を考慮)から、株式運用が見直されたこと、等がある。
近年の傾向をみると、有価証券に占める国債保有割合は、2006年度54.5%から2010年度65.4%まで上昇している。この背景には、①2012年3月からのソルベンシーマージン比率規制強化に伴い、株式の保有リスク量の掛目が10%から20%に拡大されるため、リスク量の削減を目的に株式売却を進めていること(特に、金融機関や企業との持合い解消による政策投資株の売却がみられる)、②新しいソルベンシーマージン比率規制(一般的にソルベンシーIIといわれている)で経済価値ベースによる負債サイドの評価が導入される予定であるため、資産サイドのデュレーション長期化を企図58して、長期・超長期国債を中心に増加させていること等がある。
このように、責任準備金が高水準にある一方、貸出が伸び悩む中で、リスク管理強化を目的にした保険会社に対する各種制度変更等から、有価証券の中で国債が選好されてきた。
先行きについては、①個人年金保険の伸びが頭打ちとなることが見込まれる上、高齢化等により、生命保険の一段の減少が見込まれることから、責任準備金の減少が予想されること、②負債サイドと資産サイドのデュレーションのミスマッチによる長期・超長期国債へのシフトが頭打ちとなると予想されること59等から、中長期的には国債保有残高は減少していくとの見方が多い。
(公的年金の国債保有)
公的年金の国債保有残高は、高水準で推移している(2006年度67.1兆円→2010年度72.4兆円)。しかしながら、公的年金積立金(国民年金と厚生年金の積立金)を運用している年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の運用資産が、高齢化を映じた給付額の増加から取り崩され、減少傾向にある(2006年度138.9兆円→2010年度121.2兆円)ことから、国債保有残高も2008年度84.4兆円をピークに減少傾向にある(第3-2-10図(1))。
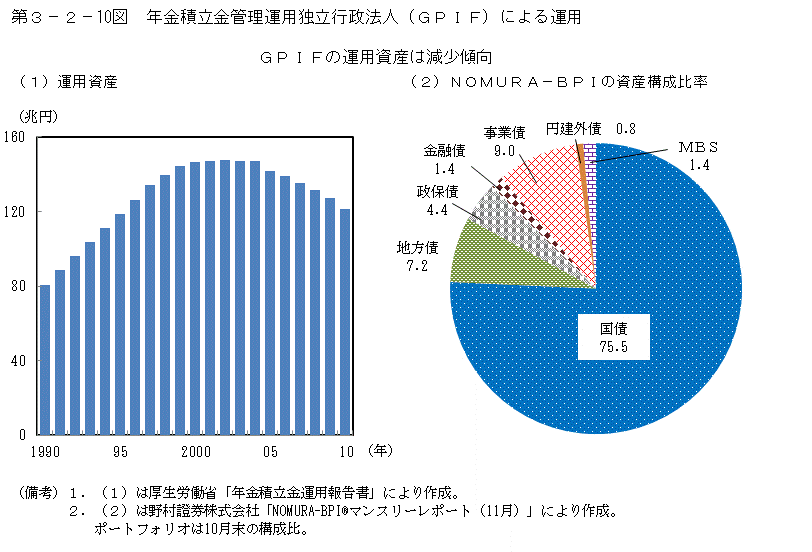
GPIFの運用方針について確認すると、運用資産の内訳は、厚生労働大臣が定める中期目標において「長期的な観点からのポートフォリオを定め、これに基づき管理を行うこと」とされ、国内債券が67%、国内株式が11%、外国債券が8%、外国株式が9%、短期資産が5%と定められている。国内債券は、2001~2007年度にかけて旧資金運用部資金の移行に伴い引受けた財投債(運用資産の15%に相当)と、市場運用分(運用資産の52%に相当)で構成される。国内債券の市場運用分は、NOMURA-BPIによりインデックス運用をしている。NOMURA-BPIは、国内債券市場の時価総額に応じて構成され、国債は76%を占める60。このため、GPIFの運用資産に占める日本国債の割合は、65%程度と試算される(第3-2-10図(2))。
先行きについては、給付年齢の引上げが議論されているが、高齢化を映じた給付額の増加から運用資産の減少は続くとの見方が多く、国債保有残高の一段の減少が見込まれている。
(第2節まとめ)
財政リスク顕在化国と財政破綻国のケーススタディを通じて、財政リスクが顕在化したのは、資本流入の逆転とそれによる経常収支赤字の急激な縮小、実質GDP成長率悪化、財政収支赤字拡大、政府債務残高増加等の同時発生によることが示唆された。
我が国の財政リスク顕在化の可能性については、経常収支黒字であり、外国資本の急激な流出が生じているわけではなく、また、日本国債の外国投資家保有比率も低いことから、資本流入の逆転による財政リスク顕在化の可能性は低いと考えられる。財政状況の悪化にかかわらず日本において財政リスクが顕在化しなかったのは、基本的に、国内における貯蓄超過によると考えられるが、そうした国内資金が経済情勢や制度的要因等により日本国債の保有に向かうインセンティブがあることも無視できない。
しかしながら、高齢化に伴い個人預金や生命保険、公的年金積立金の減少を見込む向きもあり、日本国債のこうした良好な需給環境が続いていくとは限らない。実際に、生命保険会社の責任準備金は頭打ちとなり、公的年金積立金は高齢化による給付額の増加から運用額は減少している。また、今後の経済・金融情勢によっては、投資家の資産選択が急激に国債から他のリスク資産へシフトする可能性があることは注視すべきである。
2011年8月以降の欧州政府債務危機で、GIIPS諸国は財政、金融、実体経済の間の悪循環に苦しめられている。財政の持続可能性に対する信認が失われ、国債利回りが高騰し、国債価格が下落することから、銀行のバランスシートが毀損し、銀行等による信用収縮が生じる。その場合、企業の設備投資の抑制等、実体経済は悪化する。更に、財政面では、利払い費が増加し、また、銀行への公的資金注入等を行おうとすると、財政収支赤字の更なる拡大が生じる。政府が国債に対する信認を回復すべく緊縮財政や増税等による財政健全化を図ると、実体経済は悪化し、税収が思うように伸びないため、国債に対する信認の回復につながらない。これらは相互に連関しており、実体経済はスパイラル的に悪化していくと考えられる。
我が国において財政リスクを顕在化させないためには、財政健全化に向けた取組を、金融市場の信認を確保しながら確実に行うことが必要となる。

