第1章 第2節 史上最長の景気拡大を続けるアメリカ経済
| 第1章 世界経済の現況 | 第2章 知識・技能の向上と労働市場 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 |
| 概観 | アメリカ | 欧州 | アジア | 金融・商品 | IT | アメリカ | 欧州 | アジア |
第2節 史上最長の景気拡大を続けるアメリカ経済
1 アメリカ:回避された景気過熱
1991年3月に始まったアメリカの景気拡大は、2000年2月に史上最長となり、4月には10年目に突入した。その後も、個人消費など一部に減速をみせながらも拡大を続けている。この1年を振り返ると、99年末から2000年初頭にかけて高い成長からくる景気過熱感がみられたこと、2000年半ば以降にみられた減速によって過熱感が薄れつつあることが大きな特徴といえる。
99年末は、長期的な投資ブームに加えて耐久財を中心に個人消費が非常に好調であった。2000年に入っても、株高等の影響により個人消費の伸びが一層高まるとともに、暖冬で住宅建設のテンポが落ちず、Y2K対策で年内は手控えられていた民間設備投資が大幅に増加するなど一時的な要因もあって需要は力強く拡大し、労働需給のひっ迫が続く中でインフレ懸念が高まった。2000年半ばにかけては、Fed(Federal Reserve System:連邦準備制度)の金融引締め政策の効果が現れだしたことや株価調整の影響などにより、耐久財消費や住宅着工など一部に減速がみられ始め、2000年半ばを過ぎると、住宅投資の鈍化がはっきりするとともに、生産も伸びが鈍化した。このため、景気が安定成長ペースに移行するというソフトランディング期待が高まっている。しかしながら、雇用増も、以前に比べて穏やかになったとはいえ、依然として労働需給のひっ迫は続いており、インフレ懸念は払拭されたわけではない。
以下では、この1年の景気動向を俯瞰した後、アメリカ経済のソフトランディング実現の障害となり得るインフレリスクについて検討する。
(1)この1年間の景気動向
1)需要項目別の動向
(根強い消費者マインド)
個人消費は、この1年でみると、5.3%増と高い伸びを示した。特に、自動車の購入については、自動車ローン金利が上昇していたにもかかわらず、2000年1~3月期まで非常に高い伸びを続けていた。しかし、2000年4~6月期には、金利上昇の影響が浸透してきたことに加え、株価調整の影響もあり、自動車を中心とする耐久財消費が減少するなど、過熱ぎみであった個人消費に鈍化がみられるようになった。4月には小売売上が前月比マイナスとなった。その後、株価が持ち直したことなどから、個人消費の伸びは以前ほどではないが再び高まっている(第1-2-1図)。
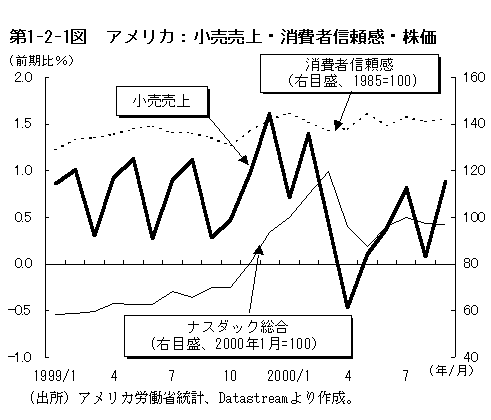
9月中旬以降株価は調整局面に入っているが、将来所得への強い期待を反映して、消費者マインドは高水準のまま推移している。消費者信用残高が増加を続け、消費者信用残高の可処分所得に占める比率は、2000年4~6月期には21%台と逓増傾向にあるにもかかわらず、資産も増加しているため、これまでのところ実物資産を含む家計の資産と負債の比率でみた家計のバランスシートは悪化していない。家計貯蓄率は、株価の高騰による資産効果や、エネルギー価格の上昇がエネルギー関連の消費を押上げたことの影響により、所得の伸び以上に消費が伸びたことから低下基調で推移しており、2000年8月にはマイナス0.4%と過去最低を更新した。
(高水準ながらも鈍化傾向を示した住宅投資)
住宅投資の鈍化傾向は個人消費よりも明確である。この1年でみると、民間住宅投資の伸びは1.2%減となった。モーゲージ金利の歴史的な低水準による98年の住宅ブームの後、99年1~3月期以降は金利が上昇を続けたに関わらず、住宅価格の先高期待もあって住宅投資は高水準を維持した。モーゲージ金利が、借入意欲を大きく減退させるといわれる8%台にまで上昇した2000年初頭にも、暖冬などの一時的要因の影響で住宅投資のテンポは落ちなかった。しかし、そうした一時的要因がはく落した3月頃には、金利上昇の影響が現れ始めた。住宅投資の先行指標であるNAHB指数(1)や住宅許可件数が減少に転じ、一戸建てを中心に新規住宅着工件数も減少基調となるなど、次第に鈍化傾向が鮮明になっている(第1-2-2図)。長期金利低下の影響で、モーゲージ金利の上昇に歯止めがかかっていることにより、住宅着工の減速のペースは多少抑えられてきたが、7~9月期には住宅投資が前期比年率9.2%減となり、減速傾向が強まった。
(IT関連を中心に好調が続く民間設備投資)
個人消費や住宅投資の伸びに鈍化がみられた反面、民間設備投資は非常に好調であった。Y2K問題への対策からIT関連投資が手控えられたと考えられる99年10~12月期でも前期比年率9.6%増と高い伸びとなった。それ以降2000年1~3月期、4~6月期と、株価調整や金利上昇の影響も少なく、同二桁台で伸びた後も、7~9月期に同6.9%増と増加を続けている。内訳をみると、機械設備及びソフトウェア、中でもIT関連の投資の寄与が大きく、99年以降ほぼ一貫して、民間設備投資の伸びに対するIT関連投資の寄与は2/3以上を占めている。一方、構築物への投資は、産業構造の変化などから96年以降伸びが鈍化を始め99年1~3月期から3期連続でマイナスとなっていたが、暖冬の影響等により、99年10~12月期以降は増加に転じている(第1-2-3図)。
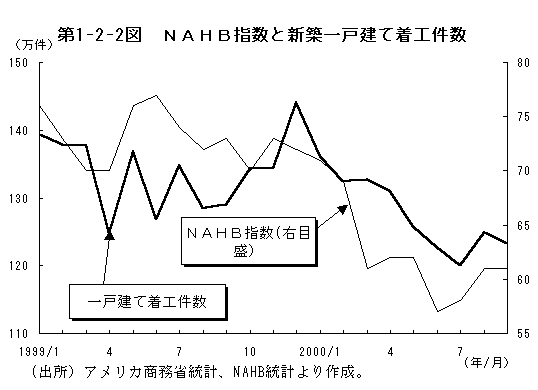
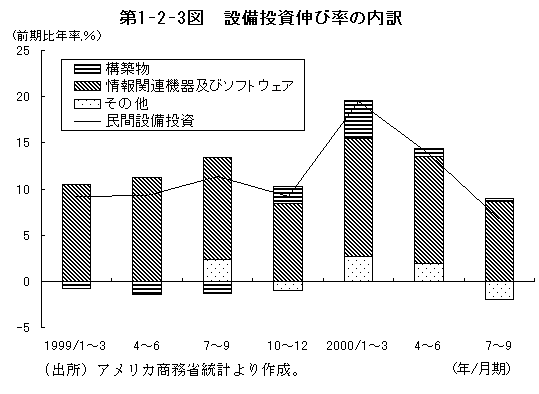
(支出増にもかかわらず拡大した財政収支黒字)
政府支出は、2000年7~9月期までの1年で2.1%増となった。特に99年10~12月期には、Y2K対策もあり、連邦政府、地方政府ともに投資支出が大幅に増加し、前期比年率20.1%となっている。その反動から連邦政府の投資は2000年1~3月期にやや減少したが、地方政府は投資・消費ともに高い伸びを続けた。
財政収支は、歳出抑制、好景気による税収の増加や歳入確保努力により、98会計年度(2)に、29年ぶりに黒字に転じ、99年度には約1,244億ドル、2000年度には約2,370億ドルと黒字幅が拡大した。こうした財政収支の改善を背景に、2000年1月、2000年中に300億ドルの国債の買い戻しを行う計画が発表された。
(拡大を続ける経常収支赤字)
外需は、海外経済が好調なことから輸出が拡大しているものの、力強い内需の拡大から輸入がそれを上回るペースで増加しているため、実質GDP成長率に対してマイナスの寄与が続いている(2000年7~9月期前期比年率寄与度▲0.3%)。経常収支赤字は、貿易収支赤字の拡大を受けて、97年4~6月期以降、毎期、過去最高を更新し続けている。現在の経常収支赤字が80年代の赤字と異なる点は、財政赤字を伴わず、赤字の大部分が民間部門の投資に吸収されている点である。貿易収支赤字の拡大は、主に内需の好調を反映した輸入超過によるものであり、99年後半以降は、原油価格の上昇が輸入額を押し上げている。
経常収支とは逆に、資本収支は一貫して黒字となっている(詳しくは第1章第5節参照)。この背景には、アメリカ国内の株高やドル高等の優れた投資環境に惹き付けられて海外からの資本流入が増加していることがある。
2)雇用と物価の動向
(ひっ迫続く労働市場)
労働市場はひっ迫した状態が続いている。失業率は、2000年に入り下げ止まっているものの、4.0%前後という極めて低い水準となっている。2000年4月、9月には3.9%と、1970年1月以来(30年ぶり)の低失業率を記録した。雇用者数の推移をみると、2000年1~3月期は月平均で32.4万人増と大幅に増加し、4~6月期も同21.3万人増と堅調に増加を続けたが、7~9月期は同4.0万人増と伸びが緩やかになった(98年月平均25.1万人、99年同22.9万人)。この動きには政府の臨時雇用の影響(3)が含まれているため、政府部門を除く民間非農業事業所雇用者数の推移でみると、2000年1~3月期の同24.4万人増に対して、4~6月期、7~9月期は12.8万人増、15.4万人増と伸びにやや鈍化がみられるが、労働需給のひっ迫を緩和するほどには至っていない。
(総じて安定している物価)
物価の動向をみると、原油価格上昇の影響で99年10~12月期から輸入価格が急速に上昇したものの、エネルギー価格を除けば、総じて安定している(詳しくは後述)。
インフレの動向を的確に把握するには、消費者物価指数や、生産者物価指数以外にも、GDPデフレータ、個人消費(PCE)デフレータ、輸入物価等の指標を幅広くみる必要がある。FRBは、その点を強調した上で、2000年2月以降、物価見通しの指標をCPIからPCEデフレータに変更している(4)。PCEデフレータの動きをみると、エネルギー価格や医療費の上昇をうけ、99年前年比1.8%上昇の後、2000年1~3月期前年同期比2.5%、4~6月期同2.4%、7~9月期同2.5%と上昇傾向にある。しかし、PCEデフレータのうち食料品とエネルギー価格を除くコアは、2000年1~3月期前年同期比1.6%、4~6月期同1.6%、7~9月期同1.7%と、このところやや上昇傾向にあるものの安定している(第1-2-4図)。生産者物価指数、消費者物価指数もこれまでのところ同様に原油価格の高騰による影響がみられるものの、コアは比較的安定している。
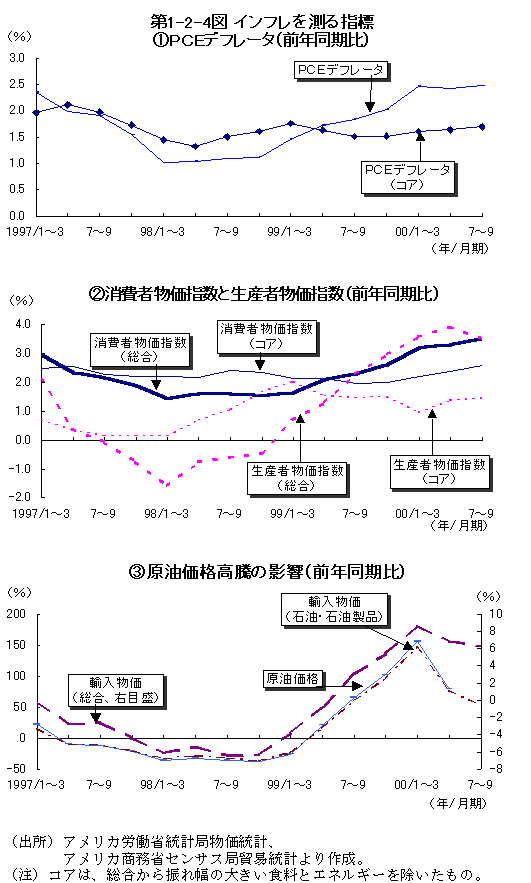
3)金融市場、株式市場の動向
(金融政策の動き)
金融政策についてみると、短期の政策金利であるFFレート(Federal Funds Rate:フェデラル・ファンド・レート)の誘導目標水準が、99年6月のFOMC(連邦公開市場委員会:Federal Open Market Committee)で、将来のインフレを未然に防止する目的で0.25%ポイント引き上げられたのを始めとして、2000年5月まで6回にわたり計1.75%ポイント引き上げられて6.50%となっている。公定歩合も8月以降、5回にわたって引き上げられて、6.00%となっている。引上げ幅は、両者とも毎回0.25%ポイントずつであったが、2000年5月のFOMCでは0.5%ポイント引き上げられた。
2000年2月のFOMCからは、従来公表していた次回のFOMC時までの金融政策姿勢を表す「バイアス」について、金融市場の無用な混乱を引き起こしているという理由から公表を取り止め、代わりに、物価の安定と景気拡大の維持という長期的な2つの政策目標を追求していく上で、現存する今後の「リスク」に対するFOMCの見方を毎回公表するようになっている。リスクの見通しは、新しく導入された2月以降、「インフレ方向」を維持している(10月時点)。
また、99年後半から2000年初めにかけて、Y2K問題に起因する金融市場の不安に対処するために金融市場には十分な流動性が供給されていた。
(金融市場の動き)
長期金利(5)は、2000年1月中旬以降、利上げによるインフレ抑制期待と財政収支黒字を背景とした国債の満期前買戻しの進展から低下している。一方、短期金利は企業の旺盛な資金需要によって上昇傾向で推移しており、その結果、2000年3月末以降は長短金利が逆転している。社債金利は、99年を通して上昇基調であったが、2000年に入り、国債利回りの低下の影響を受け、横ばいとなっている。
(調整局面を迎えた株式市場)
99年後半から2000年初めにかけて株価は上昇を続けた。しかし、3月の消費者物価指数が予想を上回る高い上昇率となったことを受けて、懸念されていたインフレが顕在化したとして、ニューヨーク株式市場でダウ・ジョーンズ工業株30種平均(以下ダウ平均)が前日比617.78ドル安、ナスダック総合指数(以下ナスダック指数)が同355.49ポイント安と、ともに史上最大の下げ幅を記録した。ダウ平均はすぐに回復したが、ナスダック指数は、ハイテク企業の業績の先行き不透明感やネットバブルに対する不安感などを受けて、5月中旬まで下落を続けた。この株式市場の動揺は、企業の資金調達に影響を及ぼした。縮小傾向にあった社債と国債のスプレッドは、2000年3~5月に急速に拡大し、社債の発行が激減した。新規株式公開(IPO)も、ナスダック指数の下落が目立った4、5月には減少したが、その後は社債発行とは異なり回復している(第1-2-5図)。
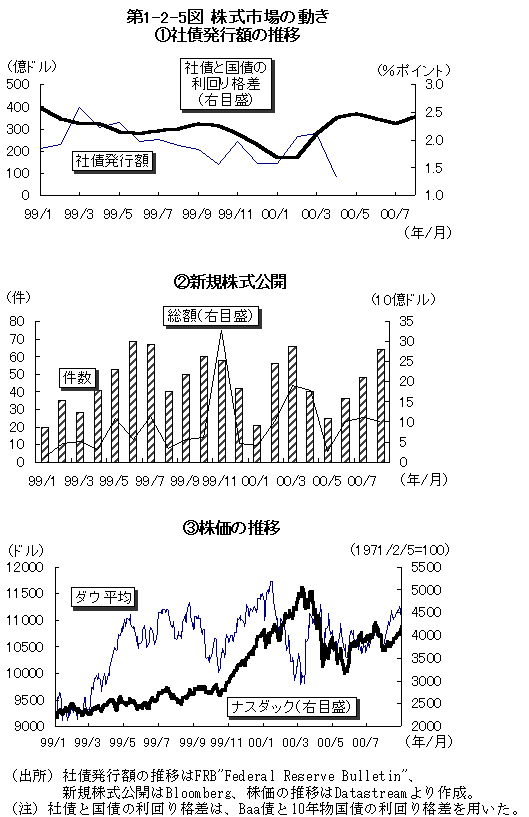
6月以降、株価は、インフレ懸念が後退したことなどから、7月末の一時期を除きおおむね上昇基調で推移した。しかし、9月中旬に入ると、主にコンピュータ、インターネット関連などハイテク企業の株価が大幅に下落し、10月中旬にはダウ平均が10,000ドルを割り、ナスダック指数が年初来最安値を更新するなど再び調整局面を迎えた。その背景には、景気の減速に加えて、原油価格の高騰によるコスト上昇、ユーロ安がもたらす欧州市場における売上高減少などから、7~9月期の業績見通しの下方修正が相次いで発表されたことがあった。
(金融制度関連の動き)
99年11月、十年来、米国議会で議論の対象になっていたグラス・スティーガル法(6)のうち、銀行業と証券業の分離を規定した条項を撤廃し、金融制度改革法(通称:グラム・リーチ・ブライリー法)が成立した。これによって、銀行、証券、保険などのあらゆる金融業務を一つの経営体として営むことが可能になった。また、毎年2月と7月に、FRB議長が経済見通し、政策目標、実現状況を議会に報告するように求めたハンフリー・ホーキンズ法(完全雇用均衡成長法、1978年)が、2000年5月で期限切れとなったが、7月の議会証言で、今後も慣習的にほぼ同形態で議会証言を継続することになった。
(2)インフレリスクの抑制とソフトランディングの実現
今回の景気拡大局面では、高い経済成長が続く中、労働需給のひっ迫はみられるものの、柔軟な労働市場の下での賃金上昇圧力の抑制、労働生産性の向上や、輸入品増加に伴う価格競争の激化など構造的な要因を背景に、物価の安定が続いている(第1-2-6図)。しかし、99年末から2000年初めにかけて需要が大幅に拡大し、また、99年来の原油価格上昇の影響が徐々に表れ、足下ではエネルギー価格だけでなくコアの消費者物価にまで上昇が及んでくるなど、インフレ懸念が高まった。Fedによる金融引締め等により、これまでのところインフレ顕在化は防がれているが、インフレ懸念は払拭されたとはいえない。そこで、以下では、インフレに関連する様々な要因の動向を整理することにより、インフレリスクを抑え、持続可能な成長を実現するための課題について改めて考えてみたい。
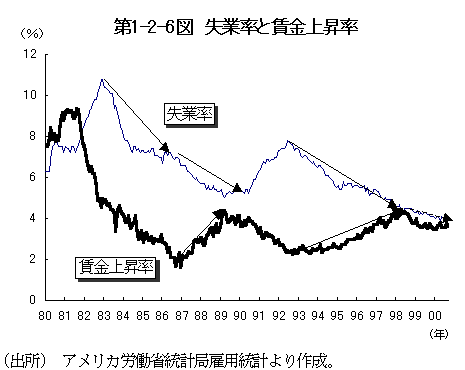
1)物価安定の構造的要因
(労働生産性の向上)
90年代後半からの労働生産性の向上は、供給能力を高め、単位労働コストを低下させることにより物価の上昇を抑える要因となっている。2000年アメリカ大統領経済報告によれば、95年から99年の労働生産性上昇率は年平均2.9%であり、1973年からの平均より1.47%ポイント加速している。労働生産性の向上に、構造的な要因と景気変動要因がそれぞれどの程度寄与しているかについては様々な議論があるが(7)、グリーンスパンFRB議長が議会証言などにおいて労働生産性の向上を構造的な要因として指摘したように、この傾向は持続するという見方が一般的である。実際、2000年に入ってからも、非農業部門の労働生産性は、1~3月期前期比年率1.9%、4~6月期同5.3%と高い伸びを示している。また、先にみたように、個人消費や住宅投資に減速がみられる一方で、IT関連投資を中心に民間設備投資の好調は続いている。このことは、資本装備率の上昇を通じて将来の労働生産性の向上をもたらすと期待される。
(労働市場の柔軟性)
アメリカの労働市場の柔軟性が高まったことも重要な要因である(詳しくは第2章参照)。アウトソーシングや情報化の進展の下で、雇用ニーズに対応した労働力の供給が可能になったことにより、労働のミスマッチが小さくなっている。労働市場の柔軟性の向上は、NAIRU(Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment:インフレを加速させない失業率)を低下させ、低失業率の中で低インフレを実現する要因と考えられる。労働市場を取り巻く環境は、インターネットの発達により近年ますます柔軟性を増していることから、今後もインフレの抑制に大きな役割を果たすであろう。
こうした労働市場の柔軟性が、労働者の賃金上昇期待を抑制する心理的圧力として働いている可能性もある。労働需給のひっ迫にもかかわらず、時間当たり賃金(民間非農業)は、99年前年比3.6%の後、2000年1~3月前年同期比3.6%、4~6月同3.6%と落着いた動きを示している。この背景には、労働者がこれまでの低い賃金上昇率に馴れていることや、レイオフ等に関する雇用不安を抱えているため高賃金を要求しにくいこともあると考えられる。大規模ストライキ件数(1,000人規模以上)をみると、99年は17件と98年の34件から半減し、47年の統計開始以来の最低値を記録した(第1-2-7図)。2000年に入ってからも、1~3月期に発生した大規模ストライキは3件と低水準で推移している。
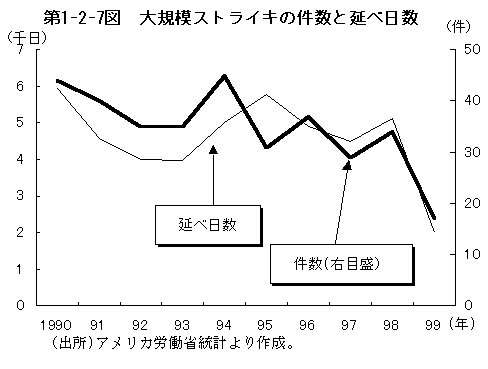
しかし、賃金が安定している別の理由として、賃金以外の福利厚生の充実が賃金を代替してきたことも考えられる。後述するように、賃金以外の医療費やボーナス等から成る諸手当はこのところ伸びが高まってきている。今後も労働需給のひっ迫が続けば、これらの諸手当を含む雇用コストが増大し、生産者物価を押し上げ、インフレを引き起こす可能性も考えられる。
(企業の価格転嫁能力の低下)
企業の側では、国内市場において新規参入企業や海外からの輸入の増加による価格競争にさらされているため、コストの上昇を価格に転嫁しにくいことが、インフレを抑制する方向に働いている。全米購買部協会(NAPM: National Association of Purchasing Management)が毎月発表している景況指数(8)のうち商品価格の推移をみると、製造業では2000年に入って上昇傾向を示したものの、3月を境に落ち着いてきている。同協会が99年12月及び2000年5月に行った調査によると、「価格転嫁不可能」、「殆ど不可能」という回答が製造業においては8割、非製造業においても6~7割を占めている(第1-2-8図)。
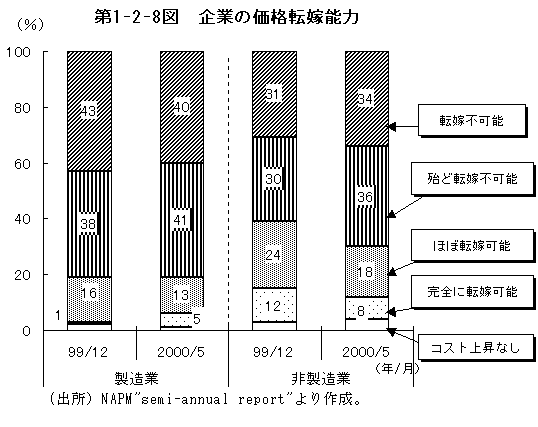
2)インフレ懸念抑制の必要性
構造的な要因が物価上昇圧力を緩和してきたことが景気拡大を長期化させてきたと考えられるが、99年末から2000年初めにかけての需要の力強い伸びはインフレ懸念を増大させた。足下をみると、減速がみられるとはいえ、労働市場のひっ迫は依然続いており、加えて原油価格の上昇の影響がコアにまで及んでくるなど、今後ともインフレ加速に対する警戒を続ける必要がある。
(労働市場のひっ迫)
労働市場をみると、雇用増が緩やかになったものの、失業率は歴史的な低水準で推移している。グリーンスパンFRB議長が労働需給の指標として「労働者のプール」(9)の推移に注目していることはよく知られているが、これは近年縮小してきており、労働市場が依然としてひっ迫していることが分かる(第1-2-9図)。深刻な労働力不足が、企業の供給能力の伸びを制約するおそれがある。ことに専門的な技術を身につけた優秀な労働力が必要なハイテク業界においては大きな問題となっている。アメリカ政府はこの対策として、一時的に就業・サービス・訓練に従事する外国人のうち特殊技能者(10)を対象に発給されるH1-Bビザ(特殊技能者を対象とする短期就労査証)の発行数を11.5万人(1年間)から2000年10月より3年間、1年につき19.5万人に引き上げた。
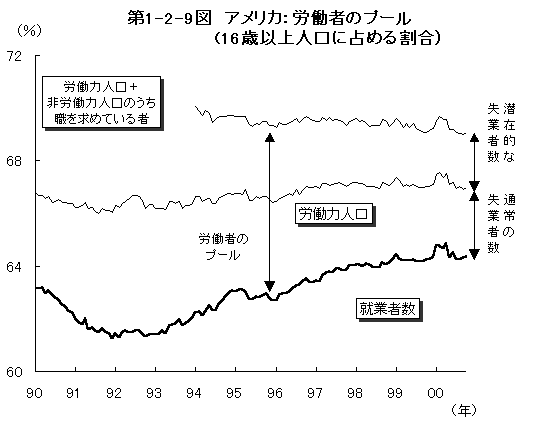
賃金上昇の動きをみると、現在のところ、賃金自体の伸びは比較的安定しているが、医療コストやボーナスなど雇用主側にかかる全ての費用を含む雇用コスト指数(ECI:Employment Cost Index)は、医療コストを中心として諸手当(11)が増加したため、2000年1~3月期に跳ね上がった(第1-2-10図)。
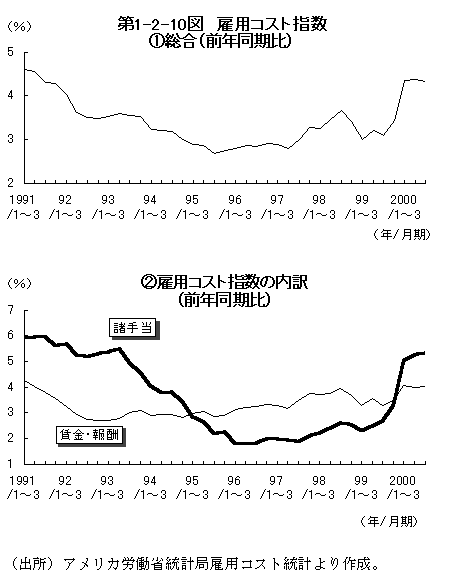
マネージドケアの普及により医療負担が低下したこと、株価の上昇による確定給付型年金の積立て額の縮小が可能となったこと等、昨年まで諸手当の伸びを大幅に抑えていた要因がなくなっている。また、労働市場のひっ迫が続く中、企業側が賃金を上げずに労働者を確保しようと様々な特典を付けることにより、諸手当の伸びが高まっている。労働生産性の上昇等の構造的な要因が雇用コストの上昇を相殺することにより、労働市場のひっ迫が物価上昇につながりにくい構造になっていると考えられるが、このまま雇用コストが上昇し、企業収益を圧迫するようになれば、これまで抑えられていた価格への転嫁が進み、インフレの顕在化に結びつく可能性もある。
(原油価格の高騰)
原油価格の高騰を受け、2000年初め頃から、企業側に値上げの圧力がかかり、航空運賃等には実際に燃料コストの価格転嫁がみられた。しかし、このような動きはこれまでのところあまり広がっていない。これは、企業が価格転嫁することを難しいと考えているためである。消費者物価、生産者物価それぞれの上昇率をコスト要因による推計値と比較してみると、ここのところ実績値が推計値を下回っており、乖離幅は拡大傾向にある。これは、原油価格の上昇分などの価格転嫁が進んでいないため物価上昇が抑えられていることを示唆している(第1-2-11図)。しかし、このまま原油高が続けば、価格転嫁の動きが広がりインフレにつながる可能性があることには注意が必要である。
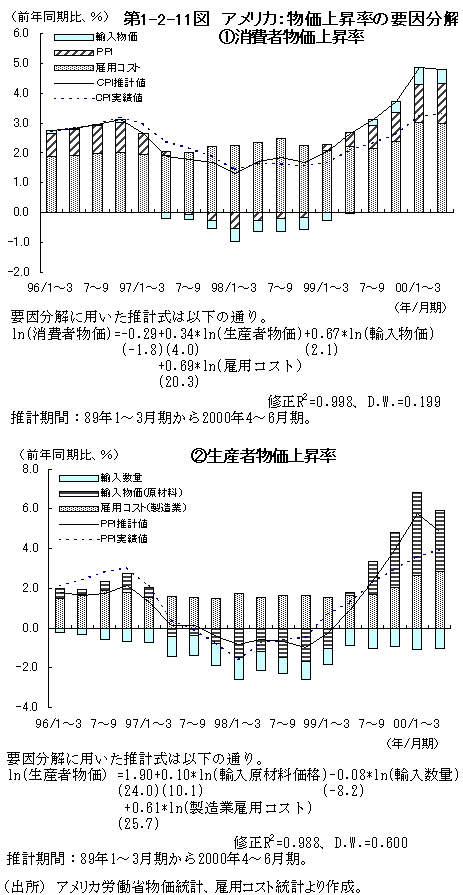
3)マクロ経済政策運営
(政策金利引上げ)
こうしたインフレ懸念に対応するため、政策当局は早い段階から段階的な金利引上げを行ってきた。中央銀行の金融政策運営を説明する代表的なルールにいわゆるテイラー・ルールがある。これは、インフレ率の目標値からのかい離と実質GDP成長率のトレンドからのかい離に反応して政策金利を変更すると考えるものである。すなわち、今次局面では、インフレが顕在化していない段階でも需給のひっ迫に応じて金利を引き上げると想定される。このルールに照らし、99年以降のFFレートの実績値をみてみると、水準はやや低いが推計値とほぼ一致した動きを示しており、理論上の動きとほぼ整合的なタイミングで利上げがなされてきたことがわかる(12)(第1-2-12図)。
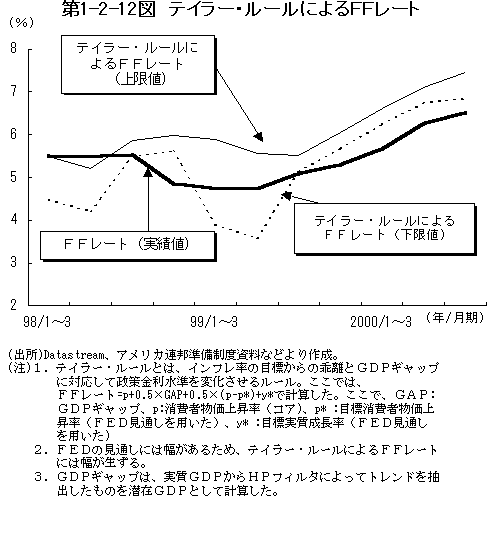
金融引締めはモーゲージ金利や自動車ローン金利を上昇させ、ある程度のラグはあるものの、住宅投資や耐久財消費を鈍化させる。しかし、今回の引締め局面では、金利の上昇はすぐにみられたが、2000年に入るまで実体経済への影響がほとんどみられなかった。これは、金利引上げのインフレ抑制効果を好感して株式市場が活況を続け、金利引上げの効果を相殺したことによるものと考えられる。
しかし、2000年4~6月期には、個人消費と住宅投資を中心に伸び率が低下し、特に株価が大幅に下げた後は、これらの需要の鈍化傾向が確実なものとなっていることから、金融政策の効果が現れてきたといえる。
(新大統領下での財政政策)
財政政策をみると、92年度以降、軍事費を中心とした支出削減の取組が功を奏して財政収支の改善が進み、これに景気拡大による税収増や歳入確保努力が加わって、98年度に黒字に転じた後、黒字幅が拡大している。規律ある財政政策は、長期金利の低下を通じて民間部門の投資や消費を支えるとともに、期待インフレ率の低下をもたらし、安定的な成長に寄与してきた。
2000年7月のCBO(Congressional Budget Office:議会予算局)の予測によれば、2001~2010会計年度の10年間で約4.6兆ドルの大幅な財政収支黒字が見込まれている。2000年大統領選挙では、この財政収支黒字の使途について、減税や歳出拡大の規模・内容などが大きな争点となった。共和党及び民主党の両大統領候補ともに、選挙公約の中で、程度の差はあるものの、従来に比べて拡張的とみられる財政政策を提案しているが、景気を刺激しインフレリスクを高めるおそれがあるため、新政権においても財政規律の重視が望まれる。
4) ソフトランディング実現への課題
以上みてきたように、構造的な要因に加え、景気拡大のテンポが低下していることから、インフレリスク顕在化は抑制されており、ソフトランディングの期待が高まっている。しかし、足下をみると、労働需給のひっ迫や原油価格の高止まりなど、インフレに対する懸念材料も依然として残っている。今後は、適切な金融政策、財政政策運営の下で、需要の伸びを持続可能なペースに維持しながら、インフレリスクを緩和していくことが重要である。景気が再び加速すれば、労働需給のひっ迫を背景とする賃金上昇圧力からインフレが起り、金融が引き締められる中で金利上昇と株価の下落により景気が急速に減速するハードランディングの可能性がある。また、これまでの金融引締めの累積効果が景気をオーバーキルすることのないよう留意が必要である。さらに、景気が減速する中で、投資家のアメリカ経済の好調さに対する確信が失われれば、高水準にある株価の調整や大幅な流入超過にある海外資金の流出を招くことにより景気のさらなる減速をもたらすことも考えられる。アメリカ経済が急減速すれば、現在の好調なアメリカの内需に依存度を高めている世界各国・地域への打撃も深刻なものとなる。アメリカ経済の持続可能な景気拡大の実現は世界経済にとっても重要な課題であり、そのためにはインフレの抑制が不可欠である。現在みられている需要の鈍化は、インフレ抑制の鍵となっており、実体経済が労働市場のひっ迫を緩和する程度にまで減速し、最終的に持続可能な景気拡大ペースに落ちつくかどうか、金融、財政当局の政策を含め、今後の動向を注視していく必要がある。
- 1 全米住宅建設業者協会(National Association of Home-builders, NAHB)が月に1度実施する業界サーベイで、来店する客数の多寡(buyer traffic)を指数化したもの。
- 2 98会計年度は、97年10月~98年9月。
- 3 政府部門の雇用者数は、国勢調査(センサス2000)のために大規模な臨時雇用が行われ、2000年4~6月期は大幅に拡大したが、センサス関連の臨時雇用が終了した5月をピークにその後は大幅に減少した。
- 4 理由としては、CPIに比べてPCEデフレータが(1)連鎖方式を導入しているため上方バイアスが少なく、(2)より広範囲の品目をカバーし、(3)時系列的な整合性・比較可能性が高い点で優れているためとしている。
- 5 アメリカの長期金利の指標となる長期国債の指標銘柄は、30年債から10年債へと移ってきており、Wall Street Journal 、Financial Times、日経新聞などの主要各紙が指標銘柄を10年債に変更するとともに、社債発行や住宅ローンの金利設定の際の参考金利に10年債利回りが使われる例が増加している。
- 6 1933年銀行法(略称)の通称。1929年の株式市場の暴落とそれに続く大恐慌を受けて成立した。この法律によって、中央銀行の強化、セイフティ・ネットの充実、競争制限、業務規制が図られた。
- 7 平成11年度年次世界経済報告では、民間非農業の労働生産性上昇率年率1.94%(96~98年)のうち景気変動要因は0.30%程度としている。
- 8 全米購買部協会(NAPM:National Association of Purchasing Management)は、4万人を上回る米国企業の調達担当役員によって構成され、企業経営に役立つ調査・研究、教育などを行うことを目的とする非営利の団体である。毎月、会員の調達担当役員に対するアンケート結果をもとに、新規受注、生産、入荷遅延、在庫、雇用、商品価格、輸出の7分野の今後の見通しについて指数化し、公表している。
- 9 将来、職に就く意思はあるものの、現在就職活動をしていないために失業者としてカウントされていない潜在的な失業者数と雇用統計の発表ベースの失業者数をたし合わせ、可能な労働供給余力の最大値を示したもの。この潜在的な失業者数は、16~64歳で、調査期間中就職活動をしていないため、非労働人口として発表されている。
- 10 米公認大学の学士号、またはそれ以上の学歴を有することなどの条件が課せられ、滞在は6年間を限度としている。
- 11 退職金や医療保険、雇用保険等、雇用主が人を雇うにあたって負担する賃金報酬以外のコスト。
- 12 ここで計算に用いたFedの物価上昇率の見通しは、2000年2月以降はCPI上昇率からPCEデフレータの上昇率(前年同期比)に変更されている。そのため、CPI上昇率とPCEデフレータ上昇率の乖離により、2月以降の推計値が高めに出ていることに注意が必要である。
2 カナダ:内需を中心に堅調に景気拡大
カナダ経済は、95年以降の低金利政策が功を奏し、個人消費や民間投資などの内需を中心に97年以降拡大している。実質GDP成長率をみると、99年7~9月期前期比年率6.5%増、10~12月期同5.1%増、2000年1~3月期同5.1%増、4~6月期同4.7%増と高い成長率が続いている。2000年に入ってからの景気動向を需要項目別にみると、個人消費は1~3月期前期比年率3.4%、4~6月期同3.6%となった。民間投資(1~3月期前期比年率15.4%、4~6月期同19.5%)は、設備投資、住宅投資がともに高い伸びを示し、景気拡大のけん引役となった。物価は、消費者物価上昇率(前年同期比)は、99年後半からエネルギー価格の上昇などによりやや上昇しているが、コア・インフレ率は、カナダ中央銀行の目標レンジ(1~3%)の下限に近い値で安定している。失業率は、景気拡大に伴う雇用増から低下してきており、99年末から6%台に低下し、76年3月以来の低水準となっている(第1-2-13図)。
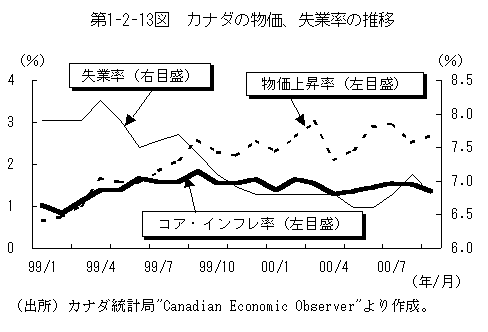
カナダ・ドルは、2000年に入ってから弱含んでいるが、通貨の減価は、インフレ圧力にはなっていない。また、金利も99年初から同年末にかけて上昇基調で推移したが、2000年に入って低下しており、長期金利(10年国債)は1~3月期平均で6.28%、4~6月期同6.00%、7~9月期同5.79%となっている(第1-2-14図)。
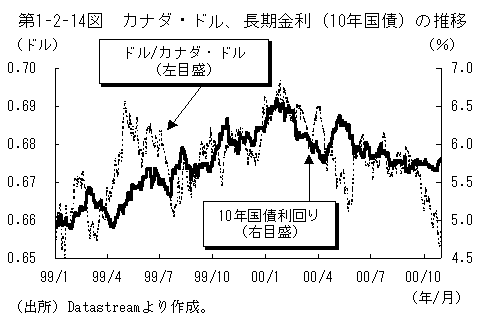
カナダの代表的株価指数であるTSE300指数は、2000年9月末で99年初と比べると1.6倍となっているが、株価が調整局面を迎え、株式による資産効果が薄れると、これまでの経済成長の柱となっていた個人消費の動向に影響を与えることが懸念されている。実際、93年以降低下してきている家計貯蓄率は、依然として低下しており、アメリカと同様、株高による資産効果およびそれに伴う信用(負債)増加によって、所得の伸び以上に消費が伸びているものと考えられる(第1-2-15図)。
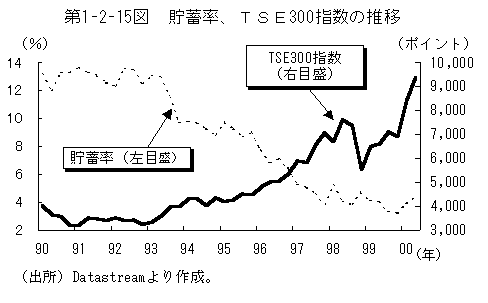
(強まるアメリカ経済との結合度)
カナダの貿易動向を見ると、輸出・輸入ともに拡大傾向にあり、特に、アメリカの需要増による輸出の増加が顕著である。カナダは、従来から対米貿易依存度が高かったが、対米輸出が全体に占める割合は、90年の73.4%から99年で85.8%、米国からの輸入は同69.2%から76.3%と90年代に一層高まっている。取引額(名目ベース)も90年から99年で輸出は2.8倍、輸入は2.6倍と大きく増加している(第1-2-16図)。
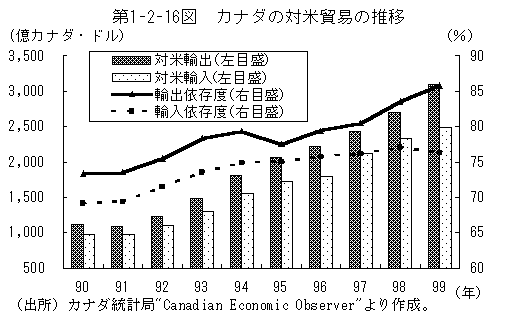
99年の直接投資をみると、カナダから米国への直接投資は797.2億ドル(前年比7.5%増)、逆に米国からカナダへの直接投資は1,117.1億ドル(前年比9.7%増)、となっている。対米証券(債券、株式)投資も、好調な米国経済を背景に増加しており、99年に米国債への投資が縮小して一時減少したものの、今年に入って株式投資を中心に再び増加している(第1-2-17図)。
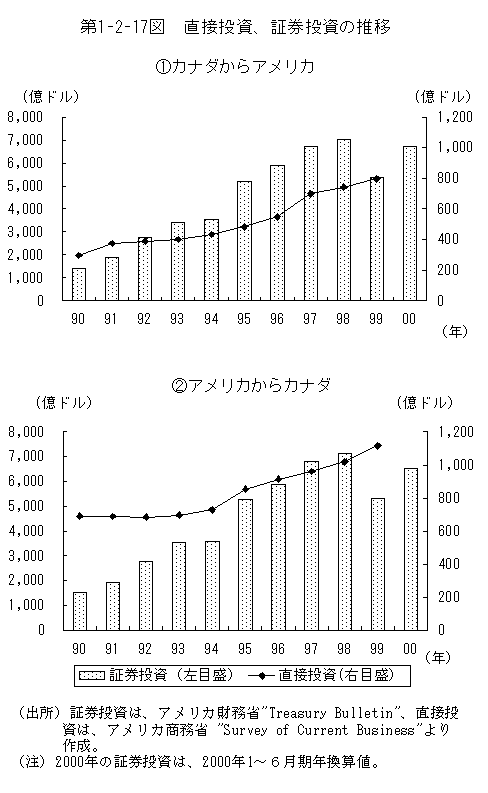
このように、アメリカ経済との結合度がますます強まっているカナダは、金融政策も米国と歩調を合わせる必要性が高まってきている。実際、ここ1年のカナダの金融政策を見てみると、米国の金利引上げに追随するような形で、2000年2月、3月、5月に公定歩合を引き上げ、米国と水準を合わせている(2000年10月末現在で、公定歩合6.00%)。
(財政の健全化)
カナダは、90年代に入り、景気の後退と失業及び医療保険を中心とした社会保障支出の膨張、公債利払い費の増大などにより、巨額の財政赤字に苦しんでいたが、現クレイティエン政権が発足(93年11月)してから財政健全化への取組を本格的にスタートさせた。その結果、94年度(94年4月~95年3月)から財政が好転し始め、97年度に28年ぶりに連邦政府の財政が黒字化し、その後も99年度まで3年連続で財政黒字を実現している(第1-2-18図)。また、2000年2月28日発表の予算案によれば、引き続き2000~01年度も財政黒字を見込んでいる。
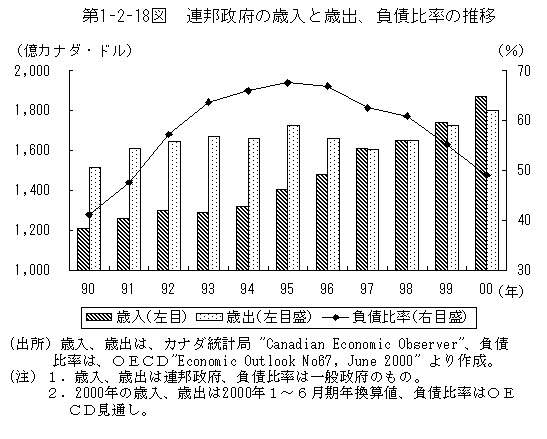
財政黒字化の要因としては、歳出の削減と税収の増加との2つが挙げられる。歳出の削減については、94年度の予算作成以来、各省庁の徹底した経費の削減、州や企業に対する補助金制度の見直し、連邦職員の削減などを中心としたプログラムを実施した。具体的には、各省における将来の支出に優先順位を設定し、それに従って首相の強い指示のもとに内閣が中心となって調整し、削減の年次目標を示して実行した(第1-2-19表)。これにより、92年度に過去最高の51.1%であった歳出のGDP比が、99年度には40.2%にまで減少した。
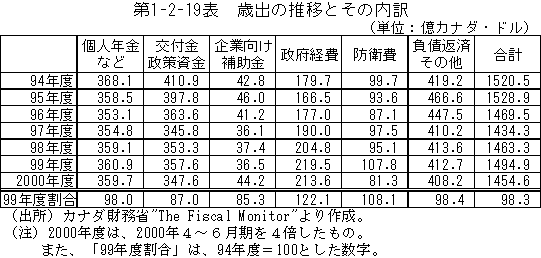
一方、税収は、GST(Goods and Services Tax)導入、所得税付加税及び法人税付加税の導入等の税制改正が行われたこと、低金利や規制緩和・撤廃などの政策が経済を活性化させたこと、好調な米国経済の追い風があったことなどから、94年度以降年々増加し、全体では99年度には、対94年度比で1.4倍、個人所得税は同1.4倍、法人直接税は同1.9倍に増加した(第1-2-20表)。
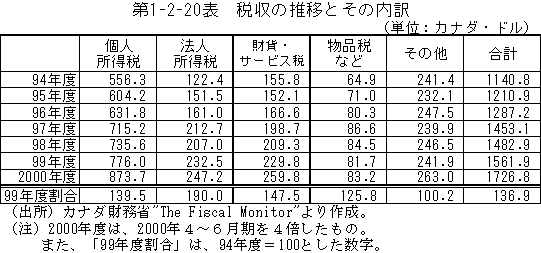
3 中南米:大統領選挙年も景気拡大が続くメキシコ
(1) メキシコ:大統領選挙年のジンクスを破り景気拡大が続く
2000年7月2日に行われた大統領選挙では、野党PAN(国民行動党)候補のビセンテ・フォックスが勝利し、71年ぶりの与野党政権交代が実現することになった。76年以降、大統領選挙の年には経済危機が起こるとのジンクスがあり、94年12月の通貨危機も政権交代に伴う政治混乱がその原因の一つであったが、今回は経済危機なき政権交代が行われるとみられている。
フォックス候補の勝利が明らかになった7月3日には、民主的な選挙が行われたことを市場が歓迎して株価が6.1%と大幅に値上がりし、為替レートもペソ高となった。メキシコ政府は、混乱防止策として昨年から設定されているIMFなどからの資金借入枠の期限を来年まで延長するとともに、総額を27億ドル拡大して264億ドルとした。また、7月10日には2000~2001年の国際金融機関及び各国の輸出入銀行からの融資枠を設定するとともに、2000~2003年に対外債務を67億ドル近く削減することを盛り込んだ「財政強化計画」を発表し、今回の政権交代では経済混乱が起こらないことを国際社会にアピールした。メキシコの公的対外債務残高の推移を見ると、95年をピークに低下傾向にあり99年はGDP比19.1%となった(第1-2-21図)。3月にはムーディーズがメキシコ外貨建長期国債を投資適格とし、大統領選後に起債されたグローバル債の発行利回りの米国債に対する上乗せ幅が2.41ポイントと現政権下で発行されたドル建債としては最低となるなど、メキシコの対外的な信用は改善している。
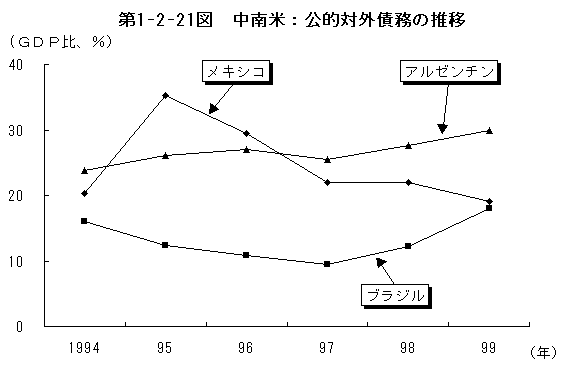
GDP成長率は98年4.8%、99年3.7%とブラジルの通貨危機の影響で鈍化したものの、2000年は1~3月期が前年同期比7.9%、4~6月期が同7.6%と主に耐久財消費による内需主導の拡大を続けている(第1-2-22図)。物価についてみると、消費者物価上昇率は99年以降は低下してきており、99年10~12月期が前年同期比13.7%、2000年1~3月期が同10.6%、4~6月期が同9.5%、7~9月期は同9.0%となっている。
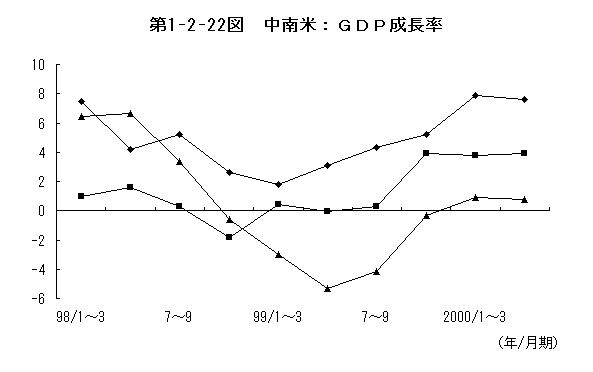
貿易先を相手国別にみると、輸出の88%、輸入の74%をアメリカが占めている(99年)。このようなアメリカへの過度の依存を解消する目的もあるEUとの自由貿易協定が7月に発効となった。これによりメキシコは2003年までにEUからの輸入の50%以上を対象に関税免除、2007年までには一部を除いて関税の全廃を行う。EU側は2003年までにメキシコからの全輸入に対し関税を撤廃する。ちなみにEUは輸出の4%、輸入の9%を占めている(99年)。貿易動向をみると、輸出は原油価格の高騰から、99年10~12月期が前年同期比21.5%、2000年1~3月期が同27.2%、4~6月期は同22.2%、7~9月期は同21.7%と増加している。輸入は99年10~12月期が前年同期比で19.4%増加し、2000年1~3月期が同25.9%、4~6月期が同22.6%、7~9月期も引き続き同24.0%の増加となった。貿易収支赤字は99年10~12月期は24億ドル、2000年1~3月期11億ドル、4~6月期13億ドル、7~9月期20億ドルとなっている。
メキシコは2000年11月に欧州自由貿易連合(スイス、ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタイン)との自由貿易協定交渉を終了した。2001年7月の本協定の発効によりメキシコは31か国との間に11の自由貿易協定を有することになる。シンガポールとは2000年7月より自由貿易協定締結に向けて交渉を開始しており、日本、韓国にも交渉を呼びかけている。このように積極的に各国と自由貿易協定を結んでいる背景の一つには、アメリカ経済への過度の依存からの脱却、もう一つには、自由貿易協定先進国としての地位を確立し世界貿易のハブを目指すという考えがある。これらの自由貿易協定による外国投資受入の増加も期待されている。外国直接投資受入額は98年は113億ドル、99年は118億ドルであり、2000年1~6月期は67億ドルとなっている(第1-2-23図(1))。
(2) ブラジル:変動相場制への移行後、予想以上の回復
98年のロシア金融危機の影響が残るなか、99年1月、ミナス州政府が連邦債務のモラトリアムを宣言したことによって信用不安が高まり、レアルの切下げ圧力が強まった。これに対し、ブラジル中央銀行は変動幅の拡大を決定、事実上の変動相場制へ移行した。対ドルレートは99年1月の1か月間に約70%減価し2.05レアル/ドルとなったが、3月には指標金利であるSELIC金利(国債を担保とした翌日物金利)目標値を年率45%に引き上げたことにより1.718レアル/ドルとなり、その後は安定的に推移した。金利も99年4~6月期以降徐々に引き下げられ、2000年7月には16.5%と94年7月の新レアル導入以来最低となった。
この利下げの背景には物価の安定がある。消費者物価上昇率は、99年10~12月期が前年同期比8.4%、2000年1~3月期が同7.9%、4~6月期が同6.6%、7~9月期が7.6%と低下傾向にある。
99年3月のIMFの見通しでは▲3.5~4.0%と大幅なマイナスになるとみられていた99年のGDP成長率は1.1%のプラス成長となり、その後も2000年1~3月期は前年同期比3.8%、4~6月期は同3.9%と、順調に回復している(前掲第1-2-22図)。鉱工業生産も99年第4四半期からプラスに転じ99年10~12月期が前年同期比5.5%増、2000年1~3月期は7.9%増、4~6月期には同5.8%増となった。他方、失業率は高水準で推移しており99年10~12月期は7.0%、2000年1~3月期は8.0%、4~6月期は7.7%となった。
貿易面についてみると、輸出(ドルベース)は99年10~12月期にはプラスに転じ前年同期比11.3%、2000年1~3月期は同19.9%、4~6月期は同13.7%、7~9月期も引き続き同21.2%の増加となった。輸入は2000年1~3月期が前年同期比で10.7%増加し、4~6月期は同4.3%、7~9月期は同20.5%の増加となった。輸入の伸びが拡大したことから2000年7~9月期の貿易収支は1億ドルの赤字となった。
ブラジル政府は2000年5月末にIMFとの協定を修正した。これによると、2000年における財政のプライマリー収支の目標は対GDP比3.25%の黒字となっている。99年は目標値である対GDP比3.1%を達成、311億レアルの黒字となった。しかし、高金利や通貨切下げの影響から利払い費が1,272億レアルと98年の726億レアルから急増したため、名目ベースでは99年は対GDP比10.0%の赤字となった。2000年は改善傾向にあり、推計では1~8月期は同3.2%の赤字となっている。99年の外国直接投資受入額は327億ドルとなり、この年の経常収支赤字244億ドルを完全にファイナンスしているが、このうち31億ドルは民営化によるものであった(第1-2-23図(2))。ブラジルは91~99年の間に719億ドルの民営化を行っており、2000年はIMFとの協定で150億ドル近くの民営化が見込まれている。
このところブラジルを中心に南米地域の経済統合に向けた動きが盛んになっている。ブラジル政府は2000年4月、アルゼンチンとともにメルコスル(1)再建に向けた宣言を発し、6月30日にはメルコスル内で2006年から域内貿易を自由化する新自動車協定に合意した。また、8月31日に初めて開催された南米サミットでは、メルコスルとアンデス共同体(2)によって遅くとも2002年1月までに自由貿易圏を成立させること等を盛り込んだブラジリア宣言が採択された。
(3) アルゼンチン:景気は低迷している
アルゼンチン経済は、96年以降プラス成長を続けていたが、98年のロシア金融危機、ブラジルの通貨不安、一次産品の国際市況の低迷等から景気が減速した。さらに、99年1月にはブラジルが変動相場制に移行、レアルの大幅な切下げとなったため、アルゼンチン製品の価格競争力が低下し輸出が減少したことから、99年のGDP成長率は▲3.2%のマイナス成長となった(前掲第1-2-22図)。2000年1~3月期は前年同期比0.9%と6四半期ぶりにプラス成長となり、4~6月期も同0.8%とやや回復傾向がみられるものの、IMF支援のもと緊縮財政政策がとられており、景気回復への動きは鈍いものとなっている。
99年12月に就任したデラルア新政権は2000年2月、IMFに「経済政策に関する覚書」を提出し、このなかでドル兌換制を維持しながら構造改革を進め国際競争力の強化を図ることを表明した。この経済政策が評価され、3月にはIMFと約72億ドルのスタンバイ・クレジット供与について合意に達した。さらに、5月にも経済調整策を発表し、9億3,800万ペソの歳出の削減、社会構造改革、投資の促進を掲げている。
輸出競争力の低下からブラジルへの外国企業移転問題が生じたため、4月に資本財輸入税の減免、輸出払戻金の引き上げなど7項目からなる投資・輸出振興策を発表した。貿易収支は97年から赤字となっていたが、99年は輸出、輸入ともに減少し、赤字額は8億ドルに縮小した。経常収支も99年は123億ドルと前年比15%減となった。直接投資受入額は98年は65億ドルだったが、99年は232億ドルと大幅に増加した(第1-2-23図(3))。このうちスペインのレプソル社の旧石油公社(YPF)買収が150億ドルを超える。
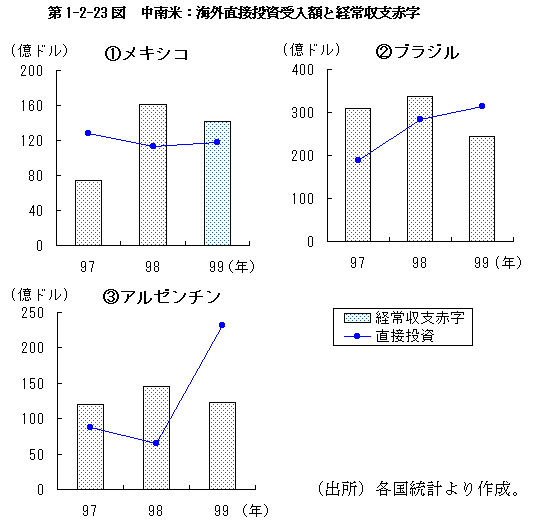
ブラジルの変動相場制移行により当初はアルゼンチン・ペソの切下げも予想されたが、2000年6月にマチネア経済相のドル化を示唆する発言があったものの、現在まで1ペソ=1米ドルの兌換制を維持している。固定相場制への移行以来、物価は安定していたが、消費者物価上昇率は、99年が前年比▲1.2%、2000年1~3月期が前年同期比▲1.3%、4~6月期が同▲1.1%、7~9月期が同▲0.8%とデフレ傾向にある。
脚注
- 1 ブラジル、アルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイによって91年に発足した関税同盟。96年にチリ、97年にボリビアが準加盟。
- 2 69年にコロンビア、ペルー、ボリビア、エクアドル、チリによって設立。73年にベネズエラが加入、76年にチリが脱退。
| 第1章 世界経済の現況 | 第2章 知識・技能の向上と労働市場 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 |
| 概観 | アメリカ | 欧州 | アジア | 金融・商品 | IT | アメリカ | 欧州 | アジア |

